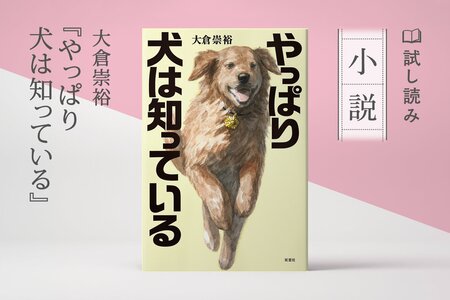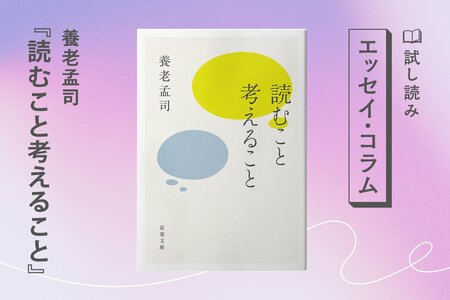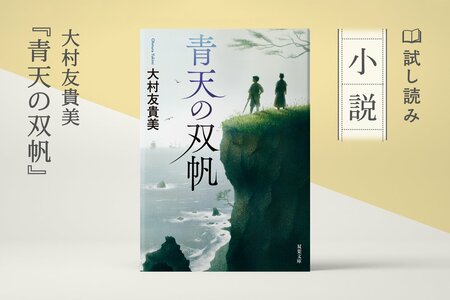前置きが長くなったが、結局のところ、ガッチガチの研究者でなければ、どんなアプローチで考古学に触れたっていいということ。好きなように学んだところで、考古学という学問の価値は何一つ損なわれるところはない。むしろ、専門家が考古学の魅力をもっと丁寧に噛み砕いて伝えていくことができれば、面白さだけではなく、先人たちが蓄積してきた学問としての奥深さが伝わっていくのではないかと思う。私が考古学を専攻した当時は、インディ・ジョーンズやキートンに憧れている同期がたくさんいたし、その中には現在、考古学者として活躍している連中が何人もいるのだ。
ということで、本書では考古学の基礎をなるべくわかりやすく、そして面白おかしく紹介していきたい。
そうは言うものの、正直、自信はあまりない。ノンフィクションを書く際に一番難易度が高いと感じるのは、基礎の説明やシステムの解説である。どうすればわかりやすく伝えられるのか。これができなければ絶対に面白おかしくはならない。さらには、ここに考古学特有のロマンチックが止まる現象が加わってしまうので、さらにハードルは上がる。そこで、自分にできる範囲での噛み砕きに注力するため、厳密な学問の基礎というよりも、私が考古の現場で経験してきたエピソードを中心に、考古学の基礎的な部分をお伝えしようと思っている。
さらには、その考古学の面白さを実地的に紹介するため、旅行エッセイのテイストを交えて伝えることを試みようと思う。そこには、考古学者としてだけでなく、長年の裏社会取材やバックパッカーとしての経験を生かしていきたい。これは、私にしか書けない“新しい考古学の本”だ。
「考古学×裏社会×旅」
目指すはMASTERキートンのような冒険譚であり、教養が身につく読み物である。「そんなのお前に書けるのか?」「そもそもお前の青春期みたいなものが面白いのか?」という声も聞こえてきそうだが、しばらくお付き合いいただけたら幸いである。
ちなみに、目下の目標は、どこかの研究機関に海外調査に連れて行ってもらうことでもあるので、その辺りを明記しておきたい。だって、書いておいたら実現するかもしれないじゃない!?
序章 旅の始まり
「考古学、やっちゃいなよ」
考古学者への道をドロップアウトして十数年。それだけの長い月日が経った頃、ジャーナリストを生業にしていた私に転機が訪れた。
「國學院大學学術資料センター共同研究員」
母校にいる先輩たちの厚意により、この肩書きを名乗れることになったのだ。この肩書きを得るためには、大学に書類を提出して厳しい審査を通過しなければならない。通常なら、一介のジャーナリスト風情が簡単に名乗れるものではないはずだ。しかし、私が宮城県出身で東日本大震災に関する著作を手がけていたこともあって、被災地・石巻市の金華山にある山岳信仰遺跡に関する調査を始めていた國學院大學に、研究員として協力を求められる運びになったのだ。かなり奇跡に近い話なのだが、そのおかげで、一応は考古学者と名乗ってもいいようになったというわけだ。実際、共同研究員の身分で学者として研究活動をされている人は多かったりするくらいだから、これはこれで“考古学者”と自称しても支障はない。
正直、それだけでも十分だったのだが、事態が動いたのは(大げさか)、その就任から3年が経過した2018年。私の考古学者人生に、さらなる転機が訪れた。意外な人物から連絡が入ったのだ。
「考古学の連載、やっちゃいなよ」
電話の主は、双葉社の編集Sさん。院友(國學院大學では同窓生をそのように呼ぶ)で、
文学部史学科の先輩でもある人物だ。そのSさんが軽い感じで、『TABILISTA』という旅のwebマガジン(現在は休止中)でのコラムの連載を持ちかけてくれた。
ちょうどその頃、文化庁の文化審議会が「北海道・北東北の縄文遺跡群」を2020年登録のユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の世界文化遺産推薦候補に選定したというニュースが流れたこと(同遺跡群は、その後2021年の推薦に回され、同年7月に登録)や、評論家の山田五郎さんも「岡本太郎以来の縄文ブームが来ている」とラジオで言っていたのを聞いて、心がざわついていた時期だった。
(マジかよ!)
物書きの端くれとして、“ムーブメント=ネタになる”という意識が働く。
(このブームに乗りたい!)
だが、こう見えても(どう見えるのかは不明だ)、ジャーナリストとしてのキャリアは考古学者のそれ以上に長く、簡単に「やります!」と即答できるほど若くはない。特に、危険地帯のルポでそれなりに知名度が上がってきたばかりの私にとって、それ以外のテーマの執筆は、失敗した時のダメージがでかすぎる。
おまけに、考古学をネタにするならブームが来ている縄文時代を語るのは必須だろうが、そもそも私は縄文のことをよく知らない(基礎的な勉強ぐらいはしているので、まったくの素人ではない。超基本の加曽利Bぐらいはわかる)。専門は古墳時代から古代にかけての分野だったために、縄文はまるで門外漢なのだ。嫌でも慎重な返答にならざるを得ない。
(う~ん。困った。)
「考古学ってタイトル、頭につけるとコケるような気がするんですよね。考古学じゃない、むしろジャーナリスト目線でなら……」
「もちろん、丸山くんの得意なやり方でいいのさ」
「う~ん、それなら」
この時点でおわかりだろうが、私は編集者からの押しに弱い。そんな性格ゆえに、ゴーストライターをやったり、ゴンザレス名義以外にもペンネームを使い分けたりしながら無理して、これまで30冊以上の本を量産してきた。だがこの著作数は誇れるものではない。ただ単に、頼まれたら断れないだけというものもある。
「わかりました。それなら『旅』をメインにしちゃいましょう。旅のコラムなんだし。それに、考古“学”つっても、どうせ俺の“学”なんて大したことないですから。ジャーナリスト目線の『考古ルポ』ってことでいいですか?」
「ソレでいいよ。てゆーか、ジャーナリストなんだから、むしろソレで!」
あっさりと連載開始が決まってしまった。だが、いざ始めるとなると、自虐的に言った“学”のなさが不安でしかない。実際、私の考古学の実績や知識など本当にたかが知れている。というか、基礎知識すらほとんど忘れてしまっているのに気づいてしまったのだ。
それから私の短くも濃密な苦悩の日々が始まった。どう書けばいいのだろうか。学生時代に読んだ基本書を眺めてみたり、大学の先輩や同級生と話し合ったり(そのまま酒を飲んで、だいたい忘れた)、いろんなことを試してみた結果、次のコンセプトが固まった。
「考古学者崩れの丸山ゴンザレスが立派な研究員となるべく様々な遺跡を巡り、研究者に話を聞いていく“リハビリ考古旅”」
まあこんな程度の軽いノリで始まったコラムである。ちょちょっとどこかへ旅をして半年程度でまとめるつもりだった。しかし、いざ始めると、これがかなりしんどい! 考古学の魅力を伝えるためにどうすればいいのかを一冊にするまでに2年以上も試行錯誤することになるとは、この時はまったく予想もしていなかった──。
この続きは、書籍にてお楽しみください