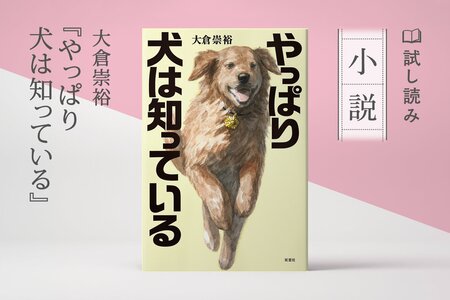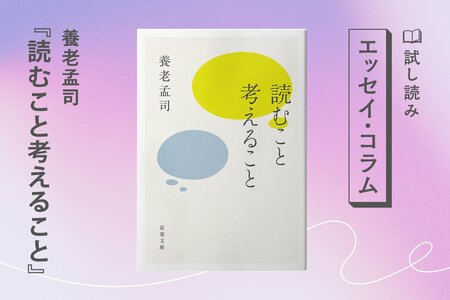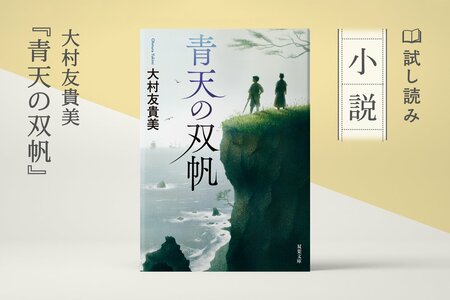はじめに
海外のスラムや麻薬問題を取材するジャーナリストで、趣味はバックパックを担いだ一人旅と格闘技、筋トレ。そんなプロフィールからどんな人物像を想像するだろうか。おそらく強面のタフガイといったものだろう。
当たらずといえども遠からず。
TBS系列のテレビ番組『クレイジージャーニー』にたびたび出演したことでパブリックイメージが固定されてしまった観はあるが、私が体育会系あがりの中年男であることは間違いではない。
そんな私にとって、この“ガテン系ジャーナリスト”というスタイルのルーツとなっているのが、何を隠そう「考古学」である。本当に隠していないのだが、ファン層にすら認知されていないのが現実だ。「学生時代に考古学を専攻していて修士号を持っている」と言うと、大抵の人が驚く。
修士号を取得するには、大学院(博士前期課程)で2年間学んで論文を提出し、その論文の審査をパスしなければならない。だが学問の道には、さらに先があり、大学院の博士後期課程に進んで着実に研究を重ね、博士論文をクリアすると博士号を取得できる。そこに辿り着くまでの道のりは非常に長く、30代で取得できるなら若いほうで、40代、50代になってやっと取得する人も珍しくはない。
基本的にはそこまでしないと「考古学者」と名乗れない。別にそういう厳密な決まりがあるわけではないのだが、実際のところ、考古学の世界では後期課程まで進んでいないと「考古学者」とは名乗りにくい。私自身も、学者と名乗るためには修士号だけでは不十分だと思っている。
だが、考古学者となるには別のアプローチもある。私の考古学の師匠である吉田恵二先生は、大学院に行っていない。したがって博士論文も提出しておらず、学位は生涯、学士(4年制の大学で取れる学位)のままだった。それでも研究機関や大学に所属して研鑽を積み、考古学の世界ではそれなりの権威といえる私の母校・國學院大學の教授にまで上り詰めた。そうやって確固たる実績を作ることができれば、博士号がなくても立派な考古学者である。
そうなると、いよいよ修士号しか持っていない上に何の実績もない私は、非常に中途半端。ジャーナリストを名乗る一方で、何とか考古学に絡めた肩書きをつけたかった私は、「考古学者崩れ」などと自称してきた。
もともと好きで始めた考古学。最初はフィクションの世界の考古学者に憧れた。ハリソン・フォード主演の映画『インディ・ジョーンズ』や、浦沢直樹先生の漫画『MASTERキートン』など、アラフォー世代にはお馴染みの作品だ。リアルタイムで触れたのは小学生から中学生の頃。多感な時期だけに影響されやすかった。
しかし、やがて現実を知るタイミングが訪れる。進路を決める頃になれば、大学で専攻できる「考古学」が、それらの作品に出てくる「考古学」とは違うということに大半の人は気がつく。フィクションと現実との乖離はあまりにも大きい。だが私は、この両者がそれほどかけ離れたものだとは感じなかった。
学問とは、自分の内に溜め込んだ知識を効率良く知恵に変換する手段だと、私は思っている(こういう言い回しをしてしまうのは、無駄に論文を読んできたため……ではなく、生来のものなのかもしれない。師匠からも「君の言い回しは難解だね」と何度か言われたことがある)。つまりどういうことかというと、学問というのは頭を良く見せるための装置で、中身はただの趣味であるということだ。答えが簡単に出ないものを調べて考えることで、趣味に没頭しながらハードな脳トレになり、おまけに箔がつく。そういった意味では子供の頃から好きだった考古学は自分に最も適した学問と思い、その道を目指した。
準備ができたら、あとは勝手に考古学で遊べばいい──そう思っていた。だから、大学での考古学徒(専攻生は自分たちのことをこのように呼ぶ)ライフは、すこぶる楽しいものだった。大学の4年間が過ぎて大学院へ進学すれば、このまま考古学者への道が1本で繋がっていると思っていた。
だが、私はその道半ばで断念した。詳しくは本編で綴ろうと思うが、その理由は単純。生活できなかったからだ。就職しないと生きていけない。そんな状況に直面したのだ。
そこで私は、言論や報道を生業とする道を選んだ。端くれではあったが考古学者として培った経験を、他の形で生かせる仕事に就こう──そう思ったのだ。
しかし、いざジャーナリストとして出版業界に軸を置いた活動をしていると、この業界には「残念な法則」があることに気づく。それは「考古学をテーマにした本は、特に売れない」ということだ。今さら説明するまでもないが、「出版不況」といわれるようになって久しい。だが、そんな厳しい状況の中で、考古学の本は特に売れないジャンルだと思う。その理由は明らか(あくまで個人的な見解ではあるが)。
それは、「ロマンチックが止まってしまう」からだ。
先述した『MASTERキートン』や、同じく漫画の『スプリガン』など、考古学関連のテーマでヒットした本もなくはない。だが、『MASTERキートン』は考古学者が主人公ではあっても考古学自体がメインテーマではないし、『スプリガン』は古代遺跡やオーパーツ(「OOPARTS=out-of-place artifacts」。それが発見された場所や出土した地層の時代とはそぐわない物品)が登場するものの、戦闘員が主人公のアクション漫画だ。オーパーツや超古代文明などを扱ったオカルト系をメインに扱った雑誌なら、『ムー』などは一部で堅調な人気を博しているが、これを考古学関連の本と言っていいのかは微妙だ。ちなみに『インディ・ジョーンズ』シリーズは世界的にヒットしたが、そもそも本ではない。
考古学をメインテーマにして話題になった著作物といえば、ジャーナリストの立花隆氏が旧石器捏造事件、いわゆる“神の手”事件(民間の考古学研究家が自分で埋めた石器を自分で発掘して、それを新発見だと偽っていたのが毎日新聞のスクープによって発覚した事件)を追った『緊急取材・立花隆、「旧石器発掘ねつ造」事件を追う』(2001年、朝日新聞社)くらいだろう。しかし、これもまた、ジャンルとしては考古学ではなく、事件モノのノンフィクションだ。
考古学がテーマに組み込まれた作品で人気があるものには共通点がある。それは、専門家である考古学者が執筆していないということだ。それはイコール「学問的に厳密じゃない」ということ。つまり、考古学という響きには人を惹きつける神秘的なイメージがあるが、実際の考古学は、それを打ち消してしまう現実主義的な要素があるのだと思う。
たとえば『スプリガン』では、富士山の溶岩に沈んだ超古代文明が登場するのだが、考古学的にはそんなことはあり得ない。それは、私が考古学を学んだだけでなく、富士の樹海を自分の足で歩いた経験があるだけに、実感を持って言える。
「富士山麓に超古代文明ってあったんですか?」
こんな質問をされたなら、私はこんなふうに返事をするだろう。
「超古代文明とかあり得ないです。遺跡のように見えるものは、溶岩の堆積と風化のもたらす錯覚でしょう。百歩譲って噴火による被害を考慮しても、周辺に関連施設の発掘事例が何もない以上、溶岩の下に都市が埋もれてしまったとも考えづらい」
面白みに欠け、幻想を盛り上げることもなく完全にロマンチックが止まる。考古学をかじった者の返事としては正しいはずだが、正しいのと面白いのは違う。
だが、この学問の特色でもある「厳密な正しさ」を追求する姿勢こそが、考古学を普及させる際の足枷になっているのではないかと、私は思う。専門家なら、面白さを重視する姿勢には異論があるだろう。もちろん厳密に正しさを追求するからこそ学問としての面白さや魅力があるというのは間違いない。ただ、それでは本気で学者を目指す人しか考古学の面白さを享受できなくなってしまうのではないか。私の中では、そうした懸念がどうしても拭えない。
さらに重ねて言わせてもらえば、プロではないアマチュアなら楽しみを優先していいと思うのだ。超古代史のような“歴史マニアやオーパーツ好きの人が、中途半端な考古学の知識で趣味的に都合のいい解釈をするのは良くない”という風潮が、プロの考古学者には根強くある。
確かにその通りなのだが、学術と趣味とでは、そもそも目指しているところが違う。それならそうと割り切って、否定するのではなく考古学の面白さを多くの人に知ってもらうために利用すればいいのではないか。知られないよりは知られたほうがいいと、かつて考古学どっぷりの世界からドロップアウトした私なんかは思ってしまうのだ。
「MASTERゴンザレスのクレイジー考古学 増補改訂版」は全2回で連日公開予定