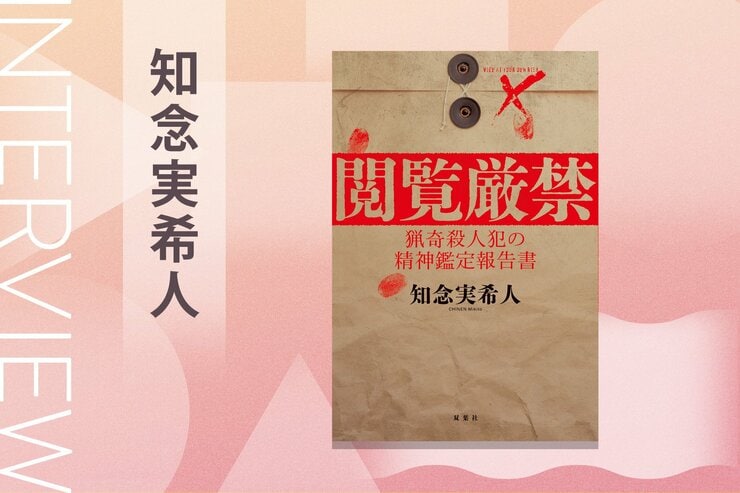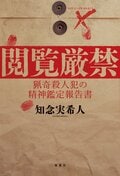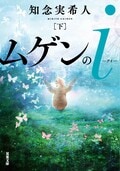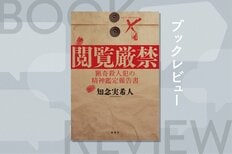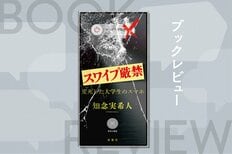知念実希人さんがホラー小説『スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ』と『閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書』を2か月連続刊行した。都市伝説の謎を追う大学生が恐怖に見舞われる『スワイプ厳禁』と、精神科医へのインタビューが殺人事件の恐るべき真相をあぶりだす『閲覧厳禁』。独立した作品でありながら、重要な部分がリンクし、ひとつの大きなストーリーを形作る2冊は、それぞれ読者を物語に引きずり込むような画期的な〝仕掛け〟がある。ホラーブームの目玉となりそうな野心的な作品について、知念さんにうかがった。
取材・文=朝宮運河 写真=種子貴之
本の冒頭に「警告」を載せているんですが、あれは脅しではないんです。
──ラストにはそうだったのかという衝撃の展開があり、しかもスマホ型であることが絶大な効果をあげている。『スワイプ厳禁』は単体でも十分怖いホラーですが、9月発売の『閲覧厳禁』と続けて読むと、また違った感想が浮かんできます。
知念実希人(以下=知念):『閲覧厳禁』を読むと、『スワイプ厳禁』の事件や関係者のその後が分かるという作りになっています。『スワイプ厳禁』だけでも面白いものになっている自信がありますが、真相が気になった人はぜひ『閲覧厳禁』まで読んでみてください。
──東京都内で発生した大量殺人。その犯人の精神鑑定を担当した医師・上原香澄に対するロングインタビューを掲載したのが『閲覧厳禁』。130ページほどの『スワイプ厳禁』に比べて、『閲覧厳禁』は約300ページとボリューミーですが、会話で話が進んでいくので読みやすいですね。
知念:小説をあまり読み慣れていない人は、地の文から状況を思い浮かべるのが大変なんです。『閲覧厳禁』は香澄とインタビュアーの会話でできていますから、地の文の多い本が苦手という人でも読みやすいと思います。会話のやり取りによってリアリティや緊迫感が生まれたり、何かが起こっているという不穏な雰囲気を演出できたり、という効果もありました。
──殺人事件現場の見取り図、犯人がライター時代に書いた記事、犯人が残した怪文書、〈ドウメキの街〉の地図など、事件にかかわる資料が多数掲載されています。実録を装ったフィクション、いわゆるモキュメンタリーの手法ですね。
知念:もともとあった読者を当事者にするというアイデアが、モキュメンタリーホラーにうまくはまりました。流行のモキュメンタリーは身近な怖さを感じられて楽しいんですが、読書に慣れていない人には、理解するのが難しいだろうなという作品もあります。『閲覧厳禁』ではちょっと分かりにくい状況は画像を掲載して、読者が迷子にならないように工夫しました。事件現場の見取り図とか、廃病院の間取り図とか、事件の真相につながるヒントをちりばめて、謎解きに参加する楽しさも味わえるように作っています。
──『スワイプ厳禁』もそうですが、ページをめくると怖い画像が目に飛び込んできて、思わずぎょっとする、という〝意地悪〟な作りでもありますよね。
知念:そういうギミックも含めて、直感的に楽しめる作品になっていると思います。
──インタビューが進むにつれて、大量殺人事件と都市伝説〈ドウメキの瞳〉の関係が徐々に浮かび上がり、クライマックスでは驚愕の真相が明らかに。まさかこんな方向に展開するとは、思ってもみませんでした。
知念:モキュメンタリーを書く方はたくさんいるので、先行作とは差別化を図らないといけない。僕が好きなホラーは『リング』にしても『パラサイト・イヴ』にしても、荒唐無稽なストーリーを理系の知識が支えているので、今回もそういうホラーを目指しました。そしてやっぱりミステリー作家なので、意外性のある展開も加えたい。モキュメンタリーの怖さとどんでん返しを融合させた作品って、これまであまり書かれていないと思います。
──そこまででも怖いのに、ラストには恐怖の駄目押しがある。読んでしまったことを思わず後悔するような、幕切れが用意されています。
知念:虚構と現実の地続き感を演出するモキュメンタリーからさらに一歩進んで、本当の意味で読者が事件の当事者になってしまうような仕掛けを作りました。本の冒頭に読むのを途中でやめてもいいですと「警告」を載せているんですが、あれは脅しではないんですね。読まないでとは言いませんが(笑)、覚悟して読んでもらえれば。
──これはできれば2冊連続、リアルタイムで読むべきですね。
知念:せっかくホラーが盛り上がっているので、僕も作品で貢献したいと思います。ホラーやミステリーに興味があっても、何となく読書にハードルの高さを感じている人は少なくないはず。その突破口になれればいいですよね。ホラー小説やミステリー小説って面白いんだなと感じてもらえたら嬉しいですし、この2冊をきっかけに、読書が趣味という人が増えたら本望です。