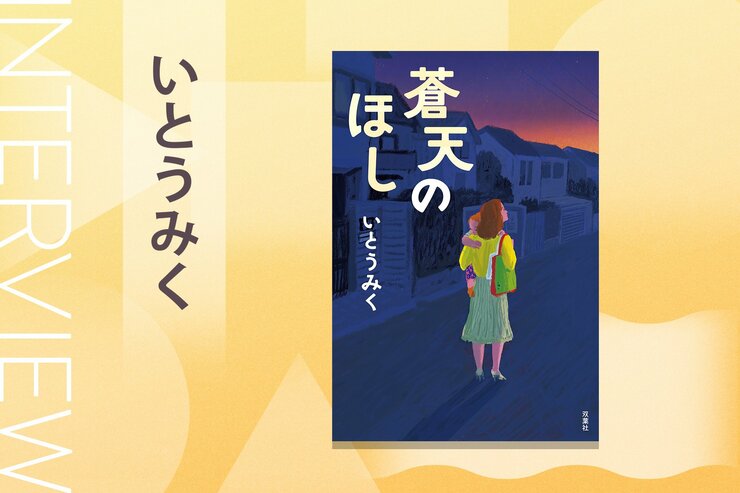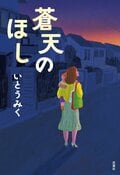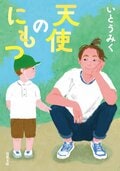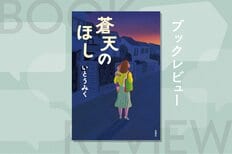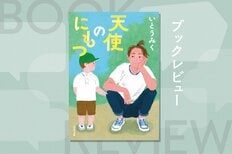近年、野間児童文芸賞、河合隼雄物語賞、坪田譲治文学賞などを立て続けに受賞し、その実力が高く評価されているいとうみくさん。そんないとうさんがこのたび発表したのは、夜間保育園を舞台にした5編からなる連作短編集『蒼天のほし』。執筆の動機や各話に込めた想いなどを伺いました。
こうあるべき、みたいな呪縛にがんじがらめになって頑張ってしまう母親たち
──第一章で描かれるのは、未婚のまま出産した母親と四歳の一人娘という親子です。母親の玲奈は高収入を求めてホステスとして働き始めますが、どうしても朝起きられないため娘の萌を保育園に通わせられず、夜の勤務時間中は一人で留守番させています。たまたま同じアパートに住む風汰から、すずめ夜間保育園の利用を勧められた玲奈ですが、「認可外の、ベビーホテル……」と言って最初は難色を示します。
いとう:過去に起きたいろいろな事故を思い浮かべてしまって、ベビーホテルってあまりいい印象ではないのかなと。実際に、ベビーベッドに寝かせっぱなしなど、これは問題あるでしょ……というような預かり方をしているところもあると思います。とはいえ、「たいよう保育園」のように、子どもと親のために丁寧で手厚い保育を行っているところもあります。ですので、きちんと自分の目で見て、確かめることが必要なんでしょうね。すずめ夜間保育園の園長が、まずは見学に来てくださいと言ったのはその通りだと思います。
──第二章では、新米保育士である風汰が保育園で直面する様々なことが描かれます。たとえば女児の母親から、おむつ替えは風汰ではなく女性の保育士にやってほしいと言われてしまいます。ショックを受けた風汰に対して、逢沢園長がかけた言葉が印象的でした。
いとう:「どうでもいいことかなって思ったのよ」という部分ですか? わたし、園長のあのことばとても気に入っているんです。言われた風汰がショックを受けるのはすごくわかるし、わたしが風汰の立場だったら、やはり「はぁ?」とかムッとしちゃうかも、と思います。でも、本質を考えると、その部分はそんなに深刻に考えることではないような気がするんです。ただ、そう思うのはなかなかできることではない。やっぱり逢沢園長の保育観、根の張り方があってこそ発せられた、あのことばだと思います。
──風汰を悩ませるのが、子どもの様子を保護者に知らせるための連絡帳です。でも、先輩保育士の坂寄千温や園長からのアドバイスを受けて書いてみたところ、「ママがね、ふうたせんせーのれんらくちょうがおもしろいってわらってた」と園児から言われるようになります。まさに、風汰の成長ですね。
いとう:そうですね。風汰も少しずつ成長しています。風汰のいいところって、素直さかなと。ですから自分でなにかに気づくと、真剣に悩むし、考えるし。風汰の根幹には楽観性であるとか向日性があるのだと思います。
──我が子を育てる「親」の立場としての保育士を描いたのが第三章です。風汰の指導役ともいえる坂寄千温ですが、実は離婚して、息子の浩介とは二歳の時から離れて暮らしています。小学五年生になった浩介が突然、千温が勤めている「すずめ夜間保育園」を訪れます。保育士の「親」としての苦悩は忘れられがちな視点だと思いました。
いとう:ありがとうございます。わたしもこの章は気に入っています。ひとりの人間の中にはいろいろな立場があるし、いくつもの顔があって、生きてきた歴史の上にいまの千温がいるんですよね。人は重層的で多面的ですが、逆の言い方をすると、千温は保育士という一面を千温自身が前面に意識することで、母親である自分の脆さや女性としての弱さをガードできているともいえると思うんです。それがいいとか悪いとかいうことではなくて。
──夜中の十一時に、卒園児のめぐみが泣きながら「すずめ夜間保育園」に電話をかけてくるシーンから始まる第四章。シングルマザーの母親が二日間、家に帰ってきません。この章では「いい母親」を「呪いのことば」と表していて、思わず胸がハッとしました。連載時、もっとも読者の反響があったのがこの章です。
いとう:そうなんですか!? それだけ親って難しいんでしょうね。頑張りすぎてぷっつりと切れてしまうってのは、そんなに珍しいことではないのかなと思います。真面目な人であればあるほど、母親はこうあるべき、母親ならこうするべき、みたいな呪縛にがんじがらめになって頑張ってしまう。あ、これは現代にだけいえることではなくて、近代の母親たちが陥りがちなことでもあるのではないでしょうか。仕事も子育ても家事も頑張る。頑張れる自分でありたいというか。
でも、子どもだった頃の自分を振り返ると、自分をちゃんと見てくれて、自分が大切にされていることを感じるほうが重要だったんじゃないかな……。なんて言いましたが、子育て真っ最中の人はそんなことを考えてなどいられない、というのもわかります。毎日必死ですから、どうしても頑張りすぎてしまう。頼ってもいい場や弱音を吐ける人は、なにも家族や親族、友だちに限りません。逆にいまだと、そっちを求めようとすると夢物語になってしまうかもしれません。そういった受け皿になってくれているのが地域の福祉なのかもしれません。保育園もその一つだと思います。
──そして最終章、タイトルはずばり「すずめ夜間保育園」。この夜間保育園を開いた逢沢鈴音の幼少期の経験が、今は園長として子どもたちを預かる使命感に強く反映されているように感じました。執筆当初から、鈴音のこのようなバックグラウンドは構想されていたのでしょうか。
いとう:いえ、とくに構想していたわけではありません。ただ、小さな認可外の夜間保育園を運営している園長ですから、なにか夜間保育を必要としている子どもと親に対して思い入れはあるのだろうな、ということは考えていました。ですので、鈴音という名前も途中で、あ、この「すずめ保育園」の園名は、園長の名前が元になっているんだと気がついて、逢沢園長の名前を鈴音にしました。わたし、書きながら物語を展開させていくので、かなり行きつ戻りつしながら書くんです。面倒でとても非効率的な書き方だと思います(笑)。
夜間保育を必要としている子供たちをかわいそうな子にしてはいけない
──物語のラストで、夜に親がいない環境に置かれている子どものことを「明るい場所からは見えないこともあるのではないだろうか。まるで蒼天の星のように」と書き表していますね。本作のタイトルへと帰結する、なんて心に残るフレーズなのだろうと思いました。
いとう:嬉しいです。ありがとうございます。この作品を書きながら……というより取材させていただいている段階から、夜間保育を必要としている親子がいるのに、いろいろなことを言って社会は目をそらしている現実がまだまだあると感じていました。夜間保育を否定的に言うことは簡単ですし、そう言った意見はめちゃくちゃ正論なんです。でも、現実にいるよ、と。そして、そうした夜間保育を必要としている子どもたちは、決してかわいそうな子どもではない。というより、かわいそうな子にしてはいけないと思いました。そんな想いで、夜間保育園を舞台にした人間模様を描きました。
──いとうさんは、これまで主に児童文学のジャンルで活躍されてきました。前作の『天使のにもつ』は青少年読書感想文全国コンクール課題図書(2020年中学校の部)に選出されています。本作は、大人の読者に向けて書かれたと思いますが、 執筆にあたり何か意識したことはありますか?
いとう:正直あまりないんです。いえ、最初はちょっと意識しました。でも結局メインの登場人物が大人というくらいで……。あ、もちろん大人をメインに書けることで世界は広がったと思います。ただ、児童文学というのは、「子どもの読み物」ではなく、「子どもから読める読み物」だと、わたしは思っています。なので、言ってみればわたしが書く物語はどれも児童文学なのかな、と思います。
──核家族化が進み、共働きの家庭が増え、女性の働き方も多様化しています。ますます夜間保育園の役割は重要になると思います。本作の執筆を終えた今、この社会の流れをいとうさんはどのように受け止めていますか?
いとう:夜間保育園がどんどん増えればいい、とは思っていません。夜間保育は、預けられている子どもも、預けている親も、預かっている保育士にとっても負担は大きいと思います。ですが、必要としている親子はしっかりと支えていく。そういった受け皿を社会がきちんと作って、必要な親子につなげられるといいなと思っています。
──最後に、読者の方々にメッセージをお願いします。
いとう:もうたくさんお話ししてしまったのでとくにはないのですが (笑)、とにかく、夜間保育園を舞台にした五つの物語をお楽しみいただけたら嬉しいです! どうぞよろしくお願いいたします。