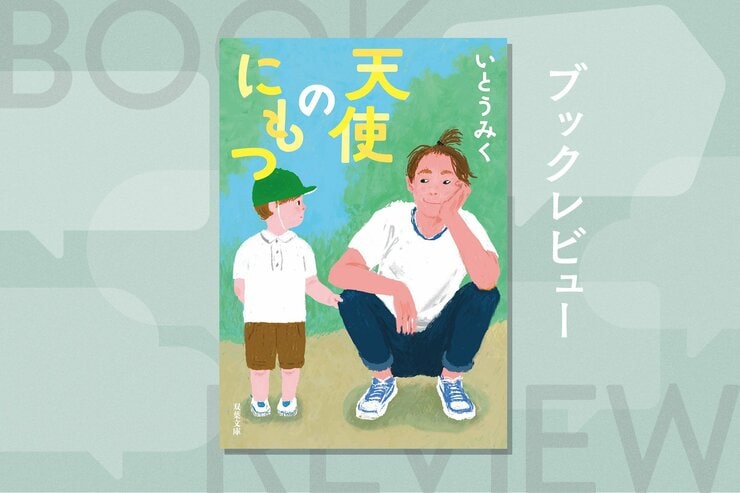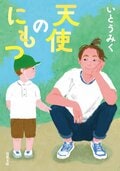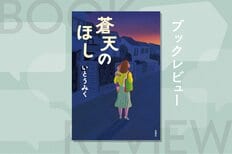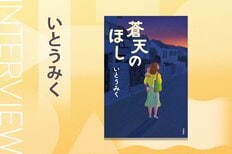中学二年生の風汰が職場体験先として選んだのは、保育園。「子どもとあそんでいればいいってこと?」と気楽に選んだわけだけど、もちろん楽な仕事のはずはなく……。園児や先輩保育士と過ごした5日間を時にコミカルに、時にちょっと切なく描いた物語。著者のいとうみくさんと同じく、児童文学も手掛ける作家、椰月美智子さんによる解説を全文公開します!
■『天使のにもつ』いとうみく /椰月美智子 [評]
読んでいて、ひどく懐かしい気持ちになった。息子たちが保育園に通っていた頃を思い出したのだ。あの匂い。色。音。声。小さな布団。小さなズック。先生たちの笑顔。
あんなにあたたかい場所に子どもを預けていたというのに、自分はといえば、時間に追われるように、ただただ慌ただしく日々を過ごしていた。きっと、おそらく、多くの母親たちが同じような状況だったのではないだろうか。
本書は、中学二年生の風汰が、授業の一環で5日間の職場体験場所を決めるところからはじまる。風汰が選んだのは、エンジェル保育園。その小ささにびっくりし、用務員だと思っていたおばちゃんは園長先生だった。
その日、風汰は段ボール箱のなかに捨てられていた子犬を見つける。そのままにしておけず、団地の駐輪場の小屋で、同じ団地のまーくんセンパイの協力のもと、子犬をかくまうことにする。
エンジェル保育園で、風汰は4歳児クラス、きりん組の担当となり、園児や担任の先生たちと一緒に5日間を過ごす。
風汰は、きりん組にしおんというちょっと気になる男の子を見つける。しおんは他の子たちと違って、叩いてきたり、いきなり飛び乗ってきたり、カンチョーなんてこともしないで、目が合うと恥ずかしそうにそっと手を握ってきたりする。
物語は、風汰の保育園での職場体験と、小屋での子犬とのふれあい、しおんとの関わりの三筋で進んでいく。
風汰の職場体験では、保育園のリアルな日常が綴られている。朝の送り時のドタバタ、給食、絵本読み、お昼寝、お散歩、おやつ、園庭遊び。
風汰は、言葉遣いや行動が不器用ながらも、戸惑いつつ、正直な心で子どもたちにぶつかっていく。
発熱した我が子のお迎えに、すぐに来られない母親。子どもが引っかかれたと怒鳴り込んでくる父親。そのつど、風汰は中学生らしいまっすぐさで怒ったり呆れたりするが、あの時代を経験した自分は、つい保護者寄りの目線になってしまう。
あの頃の慌ただしい日々、追われる仕事、生かさなければいけない子どもたち、次々と起こる些細だけれど見過ごせない問題の数々。とにかく、どこをとってもバタバタの毎日だった。子どもを保育園に送り届けるだけで精一杯で、先生の側から子どもたちを見る想像力もなかったが、作中で園長先生が、
「子どもがどうしたらその子らしく、幸せに生活することができるか。その子の持っている力を引き出すことができるか。正しい成長や発達を遂げることができるか、とかね。そういうことを考えて保育しているの」
と言う場面があり、しばし感じ入ってしまう。
また、お昼寝の時間に一人、事務室で絵本を読んでもらっているしおんについて、風汰は、VIPっすね、と笑うが、
「平等って全員に同じことをしてあげることじゃないと思うの。一人ひとり、その子にとって本当に必要なことをしてあげる。それでいいと思うのよ」
という言葉も園長は残す。ありがたい、と今さら、頭を垂れるばかりである。
風汰と子犬のチビとの関わりでは、まーくんセンパイのやさしさもさることながら、同級生たちとのやりとりがいい。
ペットショップに職場体験に行っている女子2人。犬を飼いたいというので、風汰はチビをやると言ったが、柏崎にトイプードルかティーカッププードルじゃないと嫌だと断られる。風汰は頭に来て怒鳴り、柏崎を泣かせてしまう。
その翌日、チビの小屋に行くと、チビの様子がおかしい。風汰は慌てて動物病院に行くも休みだった。そこで偶然、柏崎に会う。柏崎はぐったりしているチビを心配する。
「心配って、なにいい人ぶってんだよ。おまえ、捨て犬はやだって。捨て犬で病気の犬なんて」
「ばっかじゃないの! それとこれとは関係ないじゃん。あたしは飼いたい犬がいるの。ずっと飼いたいって思ってた犬なの。あこがれてるの! だからほかの犬じゃダメ。そういうのダメなの? いけないことなの!? だけどあたしが飼いたいっていうのと、これは話が別じゃん。目の前で具合の悪そうな犬がいたら心配するに決まってるでしょ! いい人ぶったりなんてしてないし、だいたい風汰にいいかっこう見せたって、なんの得にもなんないもん」
柏崎の言葉に、風汰は妙に納得する。昨日は一足飛びに感情優先で怒ってしまったが、きちんと相手から話を聞くと、まるで違う結論にたどり着くものだ。中学生とは、そういうことをたくさん知ることができる貴重な時期でもある。
結局、風汰は柏崎に案内され、チビを動物病院に連れていくことができたのだった。
風汰は、しおんが母親から虐待されているのではないかとうっすらと疑っている。
夜のお弁当屋さんで偶然会ったとき、しおんの母は店内にいるのに、しおんだけが雨が降る外で待っていた。保育園の給食の時間、他の園児たちは自分の箸を持ってきているのに、しおんだけは割り箸だ。また別の日、夜のマンションでしおんが一人で、入口につながる3段の階段を、上っては飛び降りることを繰り返していた。
土曜日、職場体験は休みだが、風汰はいてもたってもいられずに保育園を訪れる。しおんは登園していたが、先生に気になっていることはなにかとたずねられ、
「……オレわかんねーけど、虐待とかそういうの。そうじゃなくて、そういうんじゃなくて。でも、大事にされてんのかなって、ちゃんとあいつ」
と、風汰は気持ちを吐露する。
風汰は、自分が母から愛されていることを知っている。だから、どこの母親もそうだと思っている。
保育園で、しおんは絶対に土に触れようとしない。それはお母さんが汚れることを嫌うからだ。しおんはお母さんに嫌われることはしたくないのだ。先生は、いつか絶対、泥んこになって遊べるようにさせたいと、風汰に伝える。
しおんのお母さんが、本当に虐待をしていたのかどうかはわからない。保育園での朝、いってらっしゃい、と手を振ってお母さんを見送るしおんを、お母さんは振り返らない。風汰はしおんと手をつないでお母さんを追いかけ、
「いってらっしゃーい! いってらっしゃーい! しおん君のお母さん!」
と、大きな声でお母さんを見送るのだった。
5日間の職場体験での風汰の成長が小説のテーマのように思えるが、特筆すべき著しい成長があったとは思わない。もちろん、中学生が新しい場所に出向き、これまでしたことのない体験をするわけだから成長はあるだろう。
けれどその成長は、あくまでも中学生が日々を過ごすなかでの、年齢相応の成長に過ぎない。
あるのは、たくさんの「気付き」だ。風汰は5日間、小さなたくさんの「気付き」のなかで生きていく。しかし風汰は、その「気付き」に気付かない。当たり前だ。いちいち「気付き」に思いを寄せる中学生はそうそういないだろう。
風汰の感情は伝わってくるが、風汰が具体的にどう思っているのか、なにを考えているかの説明は描かれていない。
それは中学生男子の特徴かもしれない(自身の息子を育てての感想です)。口数が少なく、なかなか言葉にしないくせに、心のなかでは、豊富な思いや気持ちが、あふれんばかりにぱんぱんに詰まっているのだ。
物語は、まるで長回しの映画のように、風汰の5日間のそのままを綴ってゆく。彼の思いは、読んでいるわたしたちにゆだねられている。答えは読者の心のうちにある。
本書『天使のにもつ』の続編、『蒼天のほし』が刊行予定だ。中学生だった風汰が保育士になっているそうで、風汰の成長ぶりがたのしみである。