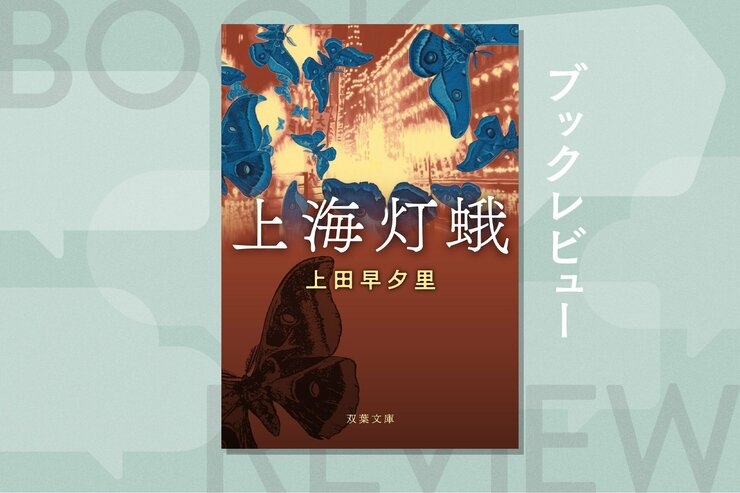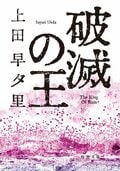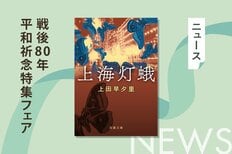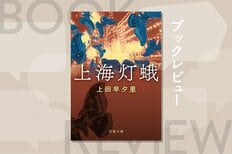日中の対立が深まり、軍靴の響き絶えない1930年代の上海。日本の寒村を飛び出してこの地に渡ってきた青年・吾郷次郎は、偶然の出会いから裏社会の闇へと足を踏み入れていく──。歴史の奔流に翻弄される人間の業を鋭く描き出した本作『上海灯蛾』の読みどころを、書評家・細谷正充さんのレビューでご紹介します。
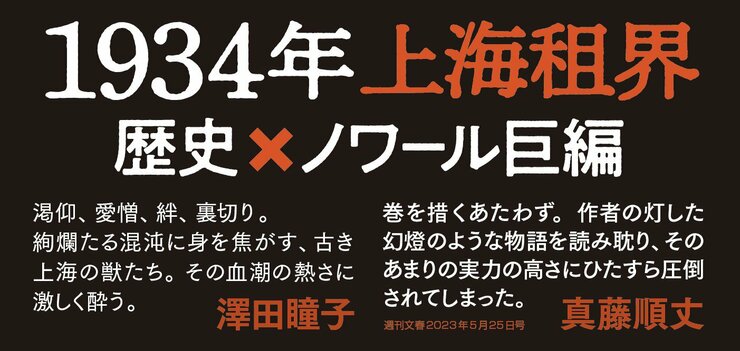
■『上海灯蛾』上田早夕里 /細谷正充[評]
阿片戦争で敗北した清は、イギリスとの間に1842年に南京条約を結んだ。これにより上海が開港し、租界(外国人居留地)が造られる。当初は、イギリス、アメリカ、フランスが租界を設定したが、後にフランス租界と、日本を含む複数の国による共同租界へと再編された。独自の発展を遂げた上海租界は、野望を抱く者たち、祖国からはみ出した者たち、各国政府の思惑を秘めた者たちが入り乱れるようになる。一方で貧富の差は激しく、多くの軋轢が生まれた。まさに“魔都”と呼ばれるに相応しい、妖しい混沌に満ちた場所だったのだ。
こうした戦前から戦中にかけての上海租界は、創作者の意欲を刺激するらしく、昔から数多くの作品の舞台になってきた。かつて上海租界という妖しい輝きに群がった人々のように、創作者もその“灯”に魅了されたのだ。そのひとりに本書の作者の上田早夕里がいる。
火星を舞台にしたSFハードボイルド『火星ダークバラード』で、2003年に第4回小松左京賞を受賞した作者だが、その作風は幅広い。第32回日本SF大賞を受賞した黙示録的海洋SF『華竜の宮』を代表とするSF作品の他に、パティシエ小説や、お菓子を題材にしたミステリー、妖怪と人間が共存する町を舞台にした妖怪ハードボイルド、室町時代の播磨の法師陰陽師の兄弟を主人公にした連作時代小説……。このように拡大し続ける作品群の中に“上海三部作”もあるのだ。
おっと、三部作と書いてしまったが、先駆けとなる短篇が存在している。2013年発行の「SF宝石」に掲載され、その後、短篇集『夢みる葦笛』に収録された「上海フランス租界祁斉路三二〇号」だ。上海自然科学研究所に赴任した日本人科学者を主人公にした、歴史改変SFである。『破滅の王』の構想を練っているときに、習作として執筆したそうだ。そして、『破滅の王』『ヘーゼルの密使』『上海灯蛾』の三部作が誕生したのである。なお、双葉社文芸総合サイト「COLORFUL」に掲載されたインタビューで作者は、
「三部作に共通する要素は、“科学と戦争”です。第1作の『破滅の王』は、細菌兵器と上海自然科学研究所ですから、ストレートに科学の話ですよね。2作目の『ヘーゼルの密使』は日中和平工作の話でしたが、作中には通訳や石油開発の話が出てきます。通訳や翻訳は人文科学、石油開発は工業関係ですから、これもまた科学に関する物語です。この2作で、政府や軍部に直接関与できた高学歴の人たちを書いたので、3作目の『上海灯蛾』は庶民を描くことにしました。阿片は医薬品として研究と販売が始まり、のちには各国軍部の戦費調達にも使われていきます。ですからこれも“科学と戦争”を巡る物語なのです」
と語っている。作品理解のためには重要な言葉だ。阿片・青幇・関東軍について作者は綿密に調べたのだろう(個人的には、日本人でありながら阿片王といわれた里見甫が、ちらっと登場するのが嬉しい)。ストーリーの背景には、近代史の膨大な事実がある。とはいえ、あまり構えて読む必要はない。本書は魅力的な悪党の一代記でもあるのだから。
『上海灯蛾』は、「小説推理」2021年3月号から翌22年7月号にかけて連載。2023年3月に双葉社から単行本で刊行された。物語の序章は、1945年8月9日の上海。中年男の遺体が黄浦江に沈められる。
この場面が終わると、時間は1934年の上海租界へと遡る。25歳のときに租界で雑貨屋を始めた吾郷次郎の店に、天津租界から来たという原田ユキヱが訪れた。「芳香異体」という香水のようないい匂いを放つ女だ。熱河省産だという阿片煙膏を持ち込んだユキヱは、これを売ってほしいと依頼する。しかも在庫は、もっとあるとのこと。知り合いの中国人の薬屋を通じて、中国の秘密結社“青幇”の末端に属する楊直と対面した次郎。楊直に阿り、配下のような存在になる。やがて青幇の小組織の長・郭景文の無茶な要求も乗り切った。その後、やはりユキヱの持ち込んだ高品質の阿片の種で、芥子畑を作ることになる。黄基龍という中国名を名乗り、楊直の部下の何忠夫と一緒に山奥で働く次郎。3年後、『最』と名付けた阿片により大金を獲得した彼は、戻ってきた上海租界で浮かれ騒ぐ。だが、時代は戦争へと向かっていた。
主人公の吾郷次郎は悪党である。兵庫の寒村を飛び出し、曲折を経て上海租界に流れてきた彼は、大金を手に入れて面白おかしく暮らすことを夢見ていた。それが実現したのは阿片の力だ。阿片がどれほど人間を破滅させるかはいうまでもなく、その意味で次郎は極悪人というしかない。また後半で、ある人物を殺してしまうのだが、これに関しても言い訳無用である。
それでも次郎は魅力的だ。「おれだって大金はほしい。だが、人としての道理にはそむけない」といい、自らの命を賭けられる人間だからだろう。最初は打算で楊直を「大哥と呼んでいた次郎だが、後には本当の義兄弟の絆を結ぶようになる。欲望に忠実すぎる彼は、それゆえに束縛を嫌い、すべてから自由であろうとする。日中の民族間で憎しみが高まり、関東軍の謀略によって人々の命が踏みにじられる時代だからこそ、自由を求める次郎が、ヒーローのように見えてくるのである。
一方、次郎の周囲にいる人々は、さまざまなものに捉われている。次郎と強い絆を持つようになる楊直だが、中国人であることと、青幇の軛からは逃れられない。それはラスト近くの、ある人物との会話でも明らかであろう。さらに妻子を惨殺されたことで、復讐に取り憑かれる。この事件によって本書のミステリー色が強まっていき、ただでさえ面白い物語のリーダビリティが、さらにアップしているのだ。
次郎を阿片の道に誘った原田ユキヱは、まさにファム・ファタールである。しかし彼女の行動も、過去に捉われたものであることが、やがて判明する。要所々々で現れるユキヱの行動も、自由とは無縁なものであった。
他にも、日本人を憎む何忠夫など、何事かに捉われた人は何人かいるが、もっとも注目したいのは伊沢穣である。日本人の父とロシア人の母の間に生まれた彼は、上海租界のダンスホールで働いているときに次郎と出会い、援助を受ける。その後、満州の建国大学に入学するが、関東軍に見込まれ、軍関係者の推薦があって入れる暁明学院大学に移される。そして大学を卒業すると関東軍の命を受け、阿片の件で次郎たちと敵対するようになるのである。
といっても穣は、嫌々、行動しているわけではない。子供の頃から差別の原因となったロシア人の血を厭う彼は、関東軍によって日本人と認められたと思い、喜んで命に従うのだ。差別されてきたからこそ、差別する側になる。このような問題は、現代でも偏在する。だから、日本人であることにこだわる穣との対比により、次郎の自由がより印象づけられるのである。
それにしても次郎の持つ、ノンシャランとした明るさは何なのだろう。時代もテーマも重いので、それを中和するための明るさなのか。だが、同じく「COLORFUL」のインタビューで作者は、
「彼らを書くうえで意識したのは、奇妙な明るさです。犯罪関係のノンフィクションを読んでいると、奇妙に明るい犯罪者がいることに気づくんですよね。『自分が悪事を働いていることはわかっているから、警察に逮捕されたら素直に裁きを受けるつもりだ。でも、それまでは金儲けさせてもらう』と彼らはいうんです。人間の罪深さを表現するためにも、そういう部分は意識的に描きました」
と語っている。なるほど、人間の罪深さを直視した結果が、人物の明るさになったのか。そういえば『夢みる葦笛』の文庫の解説を担当したSF評論家の牧眞司は、作者のSF作品のほぼすべてにおいて、さまざまにかたちを変えて提起される問いが、「人間を人間たらしめているのは何か?」だといっている。私も同意する。そして“科学と戦争”を共通する要素とした三部作も、この問いが根底に横たわっているといっていい。阿片に群がる人々の物語を楽しみながら、作者の問いを真摯に考えたいのである。
ところで“Shanghai(上海)”は、土地の名前を意味する名詞の他に、かつては動詞としても使われていた。上海への船員補充のために男が誘拐されることが相次ぎ、それが転じて「強制する。強いる」という意味を持つようになったという。牧逸馬(『丹下左善』で知られる林不忘の別ペンネーム)の短篇「上海された男」で扱われているので、興味のある人は読んでみるといいだろう。
別に強制されたわけではないが、上田早夕里の上海三部作を思うたびに、物語という船に乗せられ、上海に連れていかれたという気持ちになる。でも、これほど楽しいことはない。今後も、もし作者が上海を舞台にした作品を書いてくれるなら、いつでも“上海された読者”になる用意はできているのである。