湊かなえさんの29作目となる新刊『暁星』。ご本人が「一番好きだと断言できる作品です」と語る本書は、読み手の価値観を揺さぶり、新しい夜明けをもたらす物語です。
そんな湊かなえさんの最高傑作について「小説推理」2026年1月号に掲載された書評家・千街晶之さんのレビューで『暁星』の読みどころをご紹介します。

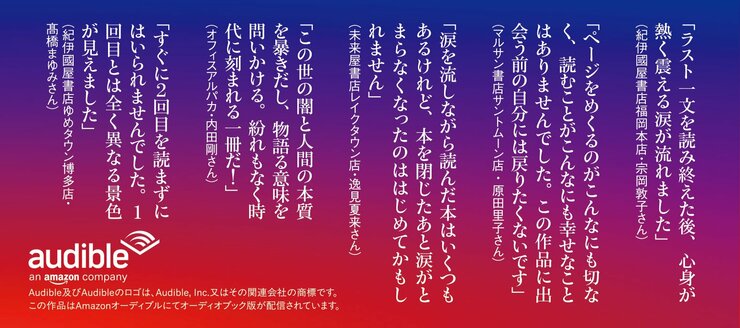
■『暁星』湊かなえ /千街晶之 [評]
「真実」と「創作」ふたつの物語が描き出す「事件の真相」とは!?
明け方の空に輝く金星は「明けの明星」と呼ばれ、その美しさから女神に譬えられることが多いが、キリスト教においては堕天使ルシファーを意味し、日本神話で金星の神格化とされる天津甕星は、天津神に最後まで服従しなかったことで知られる。湊かなえの新刊の『暁星』というタイトルは、絶対的な力を持つ存在への叛逆という不穏なニュアンスを帯びている。
本書は発端からしてスキャンダラスだ。文部科学大臣が衆人環視の場で刺殺され、犯人は母親が信者として献金していた宗教団体「愛光教会」への怨みを動機として口にした──と来れば、実際に起きたあの事件を想起しないのは難しい。果たして著者の狙いは奈辺にあるのか、少々不安な気持ちで読みはじめた。
本書の前半「暁闇」は、週刊誌に掲載された犯人の手記が中心となっており、その合間にSNS上の読者からの反応などが挟み込まれている。犯人は一見、大臣暗殺に至るまでの経緯(作家である父親が愛光教会が背後にいる文学賞に落選した後に自殺したことや、弟の死にまつわる怨みなど)を赤裸々に語っているかに思える。だが、著者の小説の愛読者なら、衝撃的な告白ほど裏に何かを秘めている場合が多いことを知っている筈だ。
後半「金星」は、犯人の手記というノンフィクション仕立てから一転し、ある人物が執筆した小説となっている。そのフィクションの世界で語られるのは、前半で伏せられていた真実であり、宗教二世ならではの苦しみであり、真実が何故小説のかたちで発表されなければならなかったのかという理由である。
ひとは往々にして、ノンフィクション=真実、フィクション=創作であると考える。しかし、フィクションのかたちでしか伝え得ない真実もあるのではないか。本書はそんな問いを突きつける。そして最後まで読み終えたあと、「暁闇」の終章に戻ることで物語は完結する。二つのパートの書き手が苦しみの中で求めたもの、守りたかったものを読者に考えさせながら。





















