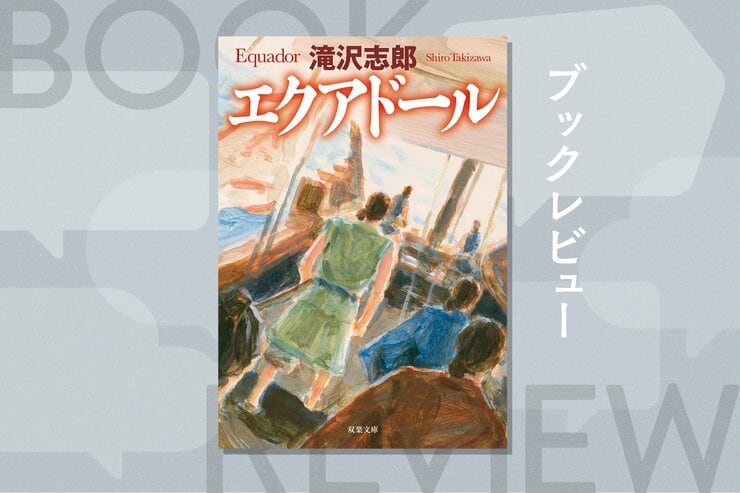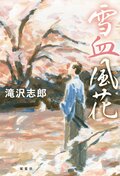島とそこに住む大切な人たちを守るため琉球人たちは旅に出る──。「大航海時代」を舞台に命をかけた船旅を通し、旅先で出会った言葉も風習も違う人たちとの交流、そして国同士の争いに巻き込まれながら成長していく若者の姿を描く滝沢志郎の歴史小説『エクアドール』。その魅力を琉球史に精通する上里隆史さんが解説する。
■『エクアドール』滝沢志郎 /上里隆史 [評]
本書の時代は16世紀、1540年代の琉球をめぐる海域アジアが舞台である。「海域アジア」とは陸上の「国」単位を集合させた地域の概念とは異なる。国境を越えた海を中心に、その沿岸部も含めた「海域」という視点で日本海や黄海、東シナ海、南シナ海をはじめとした東南アジアの内海を一つの世界と見立てたものである。そのなかでは「国」という権力体だけではなく、海上民や海賊、貿易・航海に携わる「民」が主たるプレイヤーであり、海をはさんだ陸同士の交流や闘争、海上と陸上の相互作用を含んだ歴史を「海域史」と呼び、歴史研究の新たな潮流として定着しつつある(桃木至朗編『海域アジア史研究入門』)。
15世紀初頭に成立した琉球王国は中国明朝との朝貢関係を基軸に日本、朝鮮、東南アジア各地へ貿易船を派遣し、中継貿易で栄えた。だが朝貢貿易は16世紀には衰退期に入りかかっていた。明への派遣回数は15世紀中頃から16世紀にかけて減少、1474年の福州での琉球使節による住民殺害事件を契機に二年一貢に制限された。明より無償提供されていた大型海船は1450年代には停止され、1520年代には小型船の自前での建造に変わっていく。こうした対外貿易の不振が1470年のクーデターによる新王朝樹立(第二尚氏)と1500年の八重山征服をはじめとした周辺離島への軍事侵攻による支配強化へとつながったのではないかとの見方もある(ただし朝貢以外の全体で見れば依然として貿易は活発ではとの反論もあるが)。
また16世紀に入ると周辺の国際環境も激変していった。本書で描かれている「倭寇的状況」がそれである。明の国力衰退とともに海禁政策は有名無実化し、海域世界では民間商人たちの非合法活動が活発化していった。「後期倭寇」として知られる彼らは中国出身者がその大半を占めていたと言われ、そのほか日本人や朝鮮人、ポルトガル人などで構成されていた。また彼らの所属や民族は曖昧な場合も多く、その実態は「武装した多国籍商業集団」であった。明の公権力は彼らを一緒くたに「倭寇(日本の海賊)」と認識し排除をはかったのである。
中国海商たちは1540年代以降、続々と日本の九州各地に押し寄せ拠点を築き、それらは後に「唐人町」の地名として痕跡が残る。日本来航の背景には中国で急増した銀需要と石見銀山の大増産、いわゆる「シルバーラッシュ」があった。中国大陸での密貿易の一大拠点として発展したのは浙江省寧波近くの沿岸にある双嶼である。本書に登場する王直や許棟らはまさにこの地で活動する倭寇の頭目であった。「倭寇王」とも称された王直は日本やシャムなど東南アジアを往来して巨万の富を築き、日本の平戸にも拠点を持った人物で戦国大名とも親交を持ち、「大明人五峰先生」と呼ばれた一流の教養人でもあった。種子島の鉄砲伝来に関わっていたのも彼である。物語の中での王直はこうした史実を反映したキャラクターとなっている。
「倭寇的状況」の荒波は琉球へも押し寄せていた。1541年、福建漳州商人の陳貴が那覇に渡航し、広東潮州府潮陽の船と取引をめぐるトラブルで殺傷事件が起こっている(陳貴事件)。陳貴を招いたのは琉球の長史(久米村の高官)、蔡廷美であった。公的な朝貢貿易に限定されない交易が那覇で行われていたことを示すが、交易の一方でこうした武装海商への備えが急務となっていたのがこの時代である。
本書では倭寇対策のための切り札としてポルトガル伝来の新兵器・仏朗機砲の調達をはかり、眞五羅たち一行は東南アジアへと旅立つことになっている。史実では1554年に那覇港口に砲台の屋良座森グスク、続いて16世紀中に三重グスクが築造されたが、そこに設置する大砲はどこから調達したかは不明である。1609年には島津軍船の那覇港への侵入を「大石火矢」また「銃」で阻止したと記録にあるので大砲を調達したことは確実なのだが、歴史研究ではそこには踏み込めない。『エクアドール』ではこうした史実と史実の隙間を埋めるピースを巧みにストーリーに組み込んでいる。
元倭寇で「琉球人」ではないはずの眞五羅がなぜ琉球使節の「南蛮才府」として参加しているのか。この設定は当時の琉球の交易スタイルを忠実に再現している。そもそも琉球の中継貿易の実態は琉球の地元民だけが行ったのではなく、久米村をはじめとした那覇在住の外来者たちが実務を担っていた(本書では梁元宝らが該当する)。国際的な交易のハブだった那覇は外来者や地元民が雑居する状態で、琉球王府は必要な人材を民族や出身にこだわらず採用していた。
さらに那覇港に一時滞在する商人たちに王府の外交業務そのものをアウトソーシングする事例もあり、私的な商人の船団に少数の琉球使節が便乗して交易する場合もあった。たとえば1500年の朝鮮への琉球使節団は総勢470人、4隻の大船団だったが、正副使含めた琉球人はわずか22人で残りは全て「倭人」だった(『朝鮮燕山君日記』)。また時代は下るが1601年、那覇を出航し中国沿岸で略奪行為を行った熊普達らが明軍に拿捕される事件が起こるが(熊普達事件)、構成員は琉球人や日本人、中国人の混成メンバーだっただけでなく、熊普達は琉球の「官舎」職にあり、かつて中国派遣の正規の使節も務めた人物であった。那覇にいた倭寇的な民間人を王府は正式な貿易船スタッフとして登用しており、彼らは時として「倭寇」としての顔を覗かせていたことがわかる。このように眞五羅たち琉球使節の構成はかなり当時の実態に近い姿である。
眞五羅の生い立ちも当時の海域世界ではかなり一般的なものである。彼に近いケースだと15世紀の「対馬の賊首」早田六郎次郎の子、平茂続の母は朝鮮慶尚道の出身だった例などがある。六郎次郎は那覇に渡航し、朝鮮への琉球使節船を護送する任務にも就いていて琉球とも関わりの深い人物であった。
弥次郎は実在の人物で日本最初のキリスト教徒として知られる。薩摩出身の彼は元倭寇で若い頃に殺人を犯しポルトガル船でマラッカに逃亡、イエズス会のフランシスコ・ザビエルのもとで洗礼を受け、ザビエルとともに日本へ帰国して布教活動に従事した。二人はともに国境や所属を越えて自在に活動する海域世界の民を象徴的するような存在として登場している。
この二人に三重グスク築造を主導した王農大親、「ほら吹きピント」と呼ばれ『東洋遍歴記』を著したメンデス・ピント、そして王直らの実在の人物も加わり仏朗機砲を求めて旅は続いていく。まるでドラゴンクエストのようなRPGゲームを彷彿とさせるような冒険小説であり、琉球史・海域史研究に少しばかりふれた私からすると、このメンバーは「ドリームチーム」が結成されたかのようで心躍る。しかも全くの荒唐無稽なフィクションではなく、史実を矛盾なくつないだ「もしかしたらありえた」展開なのである。
1511年、ポルトガルの攻撃によりマラッカ王国は滅亡、以降マラッカ周辺の情勢は後継のジョホール王国、イスラム勢力のアチェ王国をはじめとして拠点が多極化し混沌としていく。琉球はマラッカの滅亡後はポルトガルと交流を持つことはなく、代替としてスンダ(ジャワ島)やパタニ(マレー半島)へと交易相手を移したことがわかっている(『歴代宝案』)。琉球人は現地では「レキオ」として畏怖される存在であり、ポルトガル人も高い関心を持ってその情報を記している(トメ・ピレス『東方諸国記』など)。
作中ではもしこの時期、歴史の記録に残らないかたちで琉球人が直接マラッカでポルトガル人たちと取引することになったら……という「歴史のIF」が実現している。琉球の外交文書集『歴代宝案』にこの派遣文書が存在しないのは、ポルトガルのマラッカ総督が朝貢国間の関係でなく、さらに世あすたべ(三司官)の敵礼関係を反映した別種の文書であったから、という解釈も成り立ち、歴史研究の立場からつい想像をふくらませてしまう。作中にはこうしたリアルと見違えてしまうような細かで緻密な歴史的設定も随所に散りばめられている。
交易が盛んだった15~16世紀の琉球に関する史料は少なく、当時の東南アジアで具体的にどのような交易をおこなったのか、琉球から東南アジアへの経由地、航海中、倭寇などの海賊に襲撃された際に行われた戦闘など、詳しいことはよくわかっていない。しかし本書では史料の空白を補うような躍動する人々の動きや世界が見えてくる。歴史の情景をありありとよみがえらせたと言うこともできよう。
この時期の琉球は中継貿易が陰りを見せ、海域世界における民間海商の活動の影響で従来の交易国家としての地位が揺らぎ始めていく時代であった。倭寇対策のための砲台築造と大砲調達は、こうした海域世界の変化の影響を受けた琉球側の対応といえる。この後、1567年の明の漳州における海禁解除、1570年シャム交易の途絶と琉球はさらに激流に吞まれていく。眞五羅たち一行の冒険はこうした荒波から落日の小国を守るささやかな抵抗であったのかもしれない。
沖縄は周辺の大国や国際環境に常に翻弄されてきた歴史を持つ。琉球処分や沖縄戦、戦後の基地問題……現代でもそれは基本的に変わらない。だが沖縄の人々はそれらの抗いがたい力に対してしたたかに、しなやかに向かい合ってきた。『エクアドール』の世界と現代の沖縄とは地続きの世界なのだ。18世紀琉球の大政治家・蔡温の言葉をこう取り上げている。「琉球の国力は小さい。その小さな国力で、唐(清朝)と大和(日本)にさまざまな義務を負っている。その義務は、国力に見合わぬほど重いものである。」と(『琉球王国を導いた宰相 蔡温の言葉(佐藤亮 著/ボーダーインク刊)』)。弱小国をいかに経営していくかが琉球の国家経営の大前提であったと述べる。直面する困難に挑む眞五羅たちの姿からは、時代を超えて沖縄の課題と闘った人々の姿が重なって見えてくるのである。