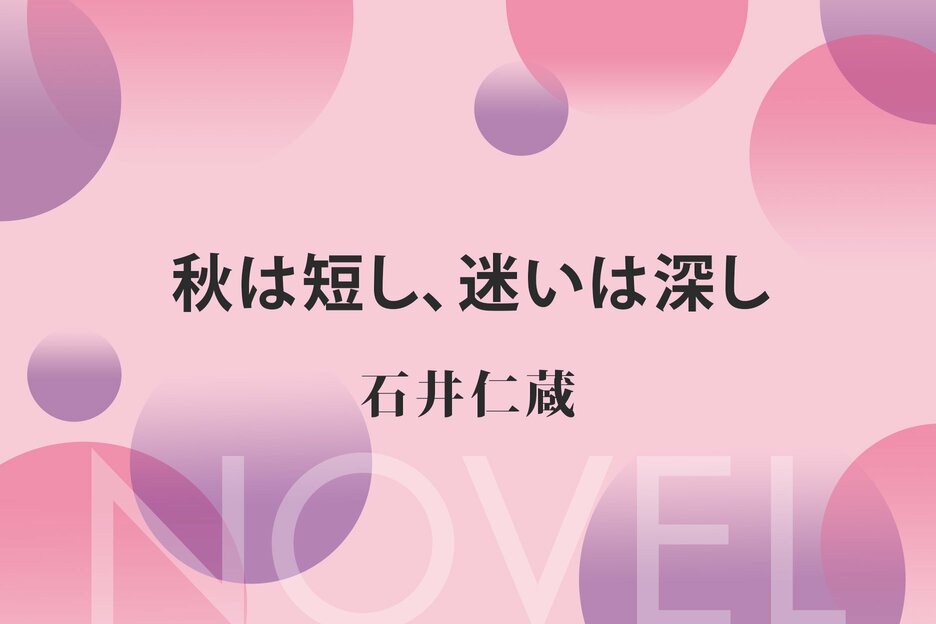塾を辞めたい、と息子が言っている。
楠島くんのお母さんから連絡を受けたその日のうちに、わたしと森野谷先生は面談をセッティングした。昨日の失踪騒ぎはあっけない形で解決した。楠島くんは十時半頃にふらっと家に帰ってきたらしく、行き先を尋ねれば「二つ先の駅の本屋で立ち読みをしていた」と答えたそうだ。一件落着、と思ったのはつかの間で、わたしたちは翌日、退塾の相談を受けたのだった。
「辞めるって選択肢は、ないから」
席に着いて間もないうちに、森野谷先生は容赦なく言い切った。正面に座る楠島くんは伏し目がちな格好でじっと固まり、お母さんは息子の反応を窺うように口を結んでいた。
「五月から俺も糸内先生も、3L1で君を受け持ってきた。ほかの子とは別枠の時間も確保して、勉強を見てきたわけだよね。個別指導に通う子が毎月のお金を払って過ごす分の時間を、君は無料で手に入れてきた。なのに出てくる言葉が、塾を辞めますでは、さすがに身勝手じゃないかな。最後まで通うのは君自身が負うべき責任だよ、最低限の」
わたしには考えられない、考えたくもない説得方法だ。これでは彼が潰れてしまう。息苦しさを感じつつも、話の主導権を奪うのは気が引けて、ひとまずは黙って様子を見る。
「通うのを前提にして、今後について検討しよう。志望校が問題なら、まずはそれを晴らそう。そこでもやもやしてるから、辞める辞めないみたいな、意味のないことに頭が行くんだ。志望校について率直なところを聞かせてくれ。楠島くんの気持ちが何より大事だと思ってるから俺は」
この人に向いている仕事は塾講師以外にもきっとある。真っ当な道なら弁護士、道を踏み外せば詐欺師。もともとの論点を忘れさせて、都合のいい方向に誘いこむのだ。顔色ひとつ変えずに、見せかけの優しい言葉を与えながら。
「えっと、んん、僕は、城見か、緑塚か、迷ってるっていうか」
「緑塚ってこの前から言ってるけど」
お母さんが口を挟む。「まともな理由ないじゃないの」
「ある。あるけど聞いてくれない」
「じゃあ今、先生たちに話してごらん。だいたいあなたさ、今のクラスに移るときだってさ、お母さん言わせてもらうけどさ……」
話してごらん、と促しておきながら結局は、お母さんのほうがべらべらと喋り始めた。保護者が喋りすぎるのは子どもにとってよくない、とはっきり思う。一人っ子の楠島くんは、何も言わないうちからご両親にあれこれと決められ、自らの意思を発する習慣を持てずに来たのではないだろうか。
言いたいことがあったら言っていいんだよ、と俯く楠島くんに言いたくなる。でも、それは酷なアドバイスかもしれない。何かを伝えても、二人の大人が十倍にして返してくるのだ。塾を休んだのは彼なりの自己主張だったのかもしれないし、とにかく逃げ出したくなったのかもしれない。塾を辞めたいと思うのも自然なことだ。
辞めたっていいよ、と言いたくなって、すぐに思い直す。
駄目だ。それではこちらの責任を放棄するだけだ。彼を助けられない。
お母さんの熱心なお喋りに少しうんざりしたところで、楠島くんは意外なことを口にした。そもそも緑塚を見に行ったこともないでしょ、と切り捨てるお母さんに、あるよ、と彼は答えたのだ。お母さんは戸惑ったように一瞬言葉を失い、いつ、と短く尋ねた。
「昨日、見てきた、夜に」
わたしたち三人は一様に目を見合わせる。誰かその件について聞いていましたか、と無言で尋ね合い、いいえ自分は知りませんでしたよ、と目線で答えを交換し合う。
「なんで言わなかったの」
「別に言わなくていいと思った」
ほんとこの子は、とお母さんは額をこすり、大げさにため息をついてみせる。
「無断で塾休んで何やってるの、だいたい夜に行ったって仕方ないでしょ」
なるほどそのとおり、仕方ない。そしてこれ以上話を続けても、同じくらいに仕方がない。門の閉じられた暗い校舎を眺めても学校の様子がわからないように、閉ざされた子どもの気持ちもわからない。城見を目指します、と形だけ言わせて決着することに意味があると、二人は本当に思っているのだろうか。
ひとつの考えが、ふと頭に浮かんだ。
「ちょっとすみません」
わたしはスマホを取り出した。「調べたいことがありまして」
正門前の歩道を彩る銀杏並木の葉はまだ緑色。
湿り気の薄れた涼しさが街を覆い、秋晴れの空はつい見とれてしまうほど爽やかな青で、わたしはこの季節の晴天を仰ぎ見るたびに「世界は美しい」などと大げさで陳腐な言葉を頭に浮かべてしまう。地上へと目を移せば、日差しに祝福された樹木の姿が愛おしい。歩道を曲がって敷地へと足を進める人たちの顔は明らかに浮かれていたり、そわそわした風にほころんでいたり、緊張した風にこわばっていたり。来校する人々を迎える高校生たちが羨ましいなあと思いながら、正門の奥の風景をしみじみと眺める。ありし日をふと思い出す。
「高校のとき、バレー部だったんですけど、バスケ部の二年生に好きな人がいたんですよ。一個上で、背が高くて格好良い男の子で。それでどうしても話したくて、文化祭の日に声掛けたんですね、その人がクラスの出店で店番やってるときに。話しただけで舞い上がって内容覚えてないんですけど、わたし、趣味でちっちゃいぬいぐるみ付きのキーホルダーをつくってたから、それを渡したんです。鞄に付けてくれたら嬉しいなって思って。ありがとうって受け取ってもらえて、どきどきしてたら何日後かですよ、その人がバレー部にいたわたしの同級生の子と付き合ってるってわかったんです。前から付き合ってたって。わたし、バカみたいじゃないですか。その子からどういうつもりなのって詰められたりして、もう最悪でしたよ」
「長々と何の話だ」
「今日の文化祭でも、青春の悲喜こもごもがあるんだろうなって話ですよ」
「相手の恋愛事情を充分にリサーチしてなかったわけだな。一人で燃え上がって、肝心な部分が見えてなかったと」
「あのですね、人の甘酸っぱい思い出をいちいち分析しなくていいんですよ」
「甘酸っぱさより、苦々しさが際立つな」
どうしてこの人と一緒に回らなければならないのだ、とげんなりしつつ、聞こえよがしにため息をついてやった。当の森野谷先生はいっこうに気にしない様子でスマホに目を落とし、待ち合わせの時間過ぎてるし、と独り言のようにつぶやいた。
わたしたちが待ちかねている相手は、楠島くんだ。
ぴりつきまくった先日の三者面談で、わたしはひとつの提案をした。
緑塚高校の文化祭に行ってみたらどうですかと。
楠島くんが目にかすかな光を宿らせる一方、お母さんは渋い表情を浮かべた。わたしは城見高校の見学も併せて案に乗せた。緑塚の一週間後には、城見の文化祭がある。両方を見比べて、どちらにするかの結論を出せばいいと話して、なんとか承諾をもらった。
「わたしだけで大丈夫だったんですけどね」
「この前も言ったじゃん。緑塚に誘導したら困るって」
楠島くん一人ではすっぽかす恐れもある、ひいてはお母さんが同行する、という話になりかけたところで、一緒に行くのは嫌だと楠島くんがごねた。結果、わたしが付き添うことになった。「監視役」を自称する森野谷先生もくっついてきた。
「お、やっと来たわ」
森野谷先生がばたばたと手を振る。わたしたちを見つけると、楠島くんは小走りでやってきた。黒い学ラン姿で、ちょっぴり気恥ずかしそうに頭を下げた。
「よろしくお願いします」
「好きに見て回ってね、わたしたちは気にしないで」
正門の受付で、来場者のQRコードを提示する。防犯の意味もあって、校外の人間は公式サイトからの事前登録が必須だった。ところが。
「あ、どうすれば、えっと、ええと、あの」
楠島くんは自分のスマホを持ったままうろたえていた。登録してません、と情けない声を出し、スマホを見つめて固まる。
「おい何だよ、しっかりしろよ」
たしなめる森野谷先生の一方で、受付の職員の方が助け船を出してくれた。生徒手帳はあるかと尋ね、楠島くんは鞄から慌ただしく紺色の手帳を取り出して事なきを得た。
「よく持ってたな。俺の中学、そんなのなかった気がする」
ないわけないですよ、とわたしはすかさずつっこむ。無事に正門に入ると、校内は見事に浮かれていた。在校生の子たちが声高らかにチラシを配り、何時からどこどこでこれこれの催しがありますと、競うように来場者を誘う。数日遅れのハロウィンのように、猫の着ぐるみやアニメキャラクターのコスプレではしゃぐ子たちに目を奪われる一方、ブレザー姿の生徒が瑞々しく映った。深緑のブレザーにグレーのスカートないしはズボン。セーラー服だった高校時代、近隣の高校に通うブレザー姿を羨みながら眺めていたものだ。ブレザーのほうが、なんとなく映えて見えたのだ。
「楠島くん、思ったんだけど」
わたしは振り向いて言った。「一人で回ってみたら?」
未知の世界の楽しさ、面白さ、美しさ。新しい刺激をたっぷり味わうには、大人は邪魔だ。こんな風にわたしたちの後ろをとことこついてきても、新たな扉は開けない。誰かに導かれるべきではない。
「俺がついて行くよ、糸内先生はフリーでオッケーだから」
「そうじゃなくって」
見学の道中、森野谷先生がごちょごちょと口を挟むのを避けたい。それも理由のひとつだった。こいつのことは引き受けた、存分に味わってきなよという思いで、わたしは森野谷先生を引き剥がす。楠島くんに一時の別れを告げる。一時間後をめどに、昇降口で合流しようと決めた。
「もしかして、俺とデートしたかった?」
「じつはそーなんですよー、ばれちゃいましたかー」
平板な声で答えた。楠島くんはこちらを気にするように振り返りながら、校舎へと歩き出し、わたしは手を振った。呆れ笑いをこぼすような鼻息が耳元に降ってきた。
「糸内さん、俺のこと嫌いでしょ」
実はそうなんですよ、ばれちゃいましたか。とげとげしい返事が喉から出かかって、かろうじて呑み込む。吐き出せば苛立ちが膨れそうだ。嫌い、というよりも、わかり合えないというほうがしっくり来る。
「もっと生徒に寄り添ってあげたらって、思うときはあります」
外でずっと突っ立っていてもしょうがないと、わたしたちも校舎に入る。来訪者用の玄関で、靴をスリッパに履き替えた。
「たとえば?」
「退塾の話が出たときも、こんだけ世話してやったんだからやめるな、みたいな言い方だったじゃないですか」
「おかげでやめなかったじゃん」
昇降口からは左右に廊下が延びていて、正面には二階へ続く広い階段があった。行き先を探るように首を動かしながら、森野谷先生は答えた。「あいつにがっつり寄り添えばよかったのか? やめたい気持ちを尊重するよって」
「そうじゃないけど」
「強引に押し込むほうがいいケースもあるんだよ。対話より圧力が重要だって、朝のニュースでも政治家が力説してたぜ」
ワイシャツにネクタイ姿の在校生が周囲を歩き回り、中学生と思しき子どもや保護者の姿も多い。楠島くんがどこに向かったのかはわからない。探し出して様子を観察しようかと一瞬考え、自分が彼の立場なら嫌だろうなと思い直す。
「考えをしっかり受け止めてあげるのが大事だと思うんです。上から押さえ込んだら、道を選ぼうとする気力を奪っちゃいますよ」
教員時代の経験を打ち明けようかと一瞬迷って、やめる。どちらが先を行くでもなく、わたしたちは二階に向かって階段を上がった。先の壁には「ようこそ緑塚へ」と、カラフルな文字で書かれた特大のポスターがあり、そばにはクラスや部活動の催しを示す張り紙がびっしりと並んでいた。
「間違った道に進もうとしていても、受け止めろと?」
迂闊な答えをして揚げ足を取られたくはない。どう切り返せばと迷ううちに、彼は続けた。「判断力のない子どもの志望校選びで、思いどおりにさせるなんてのは無責任だ」
「じゃあ、大人の言うことを聞いておけばいいんですか。自主性のない人間になっちゃうとは思いませんか?」
「決めつけるなよ。先々のことなんて俺たちが立ち入る領域じゃない。糸内さんも本当は、自分の思いどおりにさせたいんだよ。自主性のある子どもになってほしいってのは君の勝手な望みだ。親は別に望んでない」
「子どもは親の人形じゃないですよ」
「君の人形でもないけどな」
誰もそんなこと、と言いかけたとき、通りすがりの職員の方と目が合い、ふと我に返る。来訪者を歓迎するポスターの前で、言い争いを続けるのは正しくない。
学生の頃に繁華街のクリスマスツリーの前で彼氏と口論になり、そのままぎくしゃくして、年明けに別れたのを思い出す。好きなロックバンドがメジャー志向で行くべきか、独自の音楽性を追求するべきかで揉めたのだ。バンドのメンバーが揉めることでしょそれ、と友達には笑われたが、当時のわたしたちには真剣な問題だった。
「これからどこ行きます?」
「グラウンドのほう行ってみるか。運動部がいろいろやってるみたいだ」
「わたし、教室のほう見たいんですよね。クラスの感じとか知りたいですし」
「だったら、別行動だね」
返事も待たずに、彼は階段を降りていった。その背中を眺めながら、そういえばあのバンドも結局解散しちゃったな、と寂しい記憶が蘇った。
中学ではなく、高校に勤めていたら今も教員の仕事を続けていただろうか、なんてことをぼんやりと考えて、教室の並ぶ廊下をひとしきり歩き回る。小中学生とふだん接している人間には新鮮な空間だ。塾の生徒たちよりも世慣れた振る舞いで、大学生に比べれば幼く、大人とも子どもともつかない曖昧な年頃。そんな彼らの姿は見ていて飽きない。おばけ屋敷やらマジックやら男女混成のメイドカフェやらが並ぶ教室に、入ってみたいと思いつつも恥ずかしい。楠島くんはちゃんと楽しめているかなと気になって、はっとする。何をやっているんだ。森野谷先生が彼を捕まえてネガティブな印象を植え付けていたらどうするんだ。そう思い至ったものの、いざその場にぶつかったら議論がぶり返しそうな気もして、会うのが少し気まずい。どうしようかな、と悩みながら歩いた先に、美術室があった。
楠島くんのような子はもしかしたら、黙々とキャンバスに向き合うことで自身を表現できるんじゃないかと、勝手な想像をしながら部屋に踏み入る。
美術室はとても静かだった。にぎやかな教室棟を離れると余計にその静けさが際立ち、心地よくもあった。室内の四方に白い板の壁が設えられ、作品が展示されたさまはさながら、美術館の展示スペースを模したようなつくりだ。鑑賞する生徒や大人に紛れ、絵画や彫刻を眺めているとき、一枚の絵に目を引かれた。
青空を背景に一輪のひまわりが描かれた大きな油絵。色使いが鮮やかで、この一枚があるだけで部屋全体が明るさを増すようにすら感じられた。面白いのは、作者の凝らした趣向だ。黄色い花びらに囲われた丸い部分に、目と口だけのイラスト風の笑顔があり、「満面の笑み」のお手本みたいな溌剌さを放っている。細やかな色彩の油絵と、ポップなイラストタッチが調和した作品だった。
絵画の下に掲示された作者名に何気なく目をやって、わたしはふと固まった。
「あの、すいません」
息を呑む。声を掛けてきたのは、緑塚の制服を着た女の子。
知り合いが一人もいないこの高校で、知った顔に出会った。
「津木さん?」
問いかけが口からこぼれた。すると相手はわたしを指さしながら、「ですよね? ですよね?」とはしゃぐように笑顔を見せた。「お久しぶりです!」と頭を下げた。
三年三組、津木凛々菜。記憶の中にいる中学生の彼女。
一年一組、津木凛々菜。目の前にいる高校生の彼女。
同じ顔の二人は、違う顔をしていた。
去年より顔立ちが大人びたのは当たり前としても、表情にはかつてのような曇りがない。ふっくらとした頬は艶やかで、切れ長の目は光を帯びている。
「津木さん!」
感激の声は思いがけず大きく跳ねた。周囲の視線に慌てて口を押さえた。皆さん鑑賞中なので、と情けなくも彼女に注意を受けたわたしは、我ながらせわしない動きでぺこぺこと周りに会釈をした。気を引き締めようと、はっと息を吐く。
「緑塚に進んだんだ? ごめん、あのあと中学校やめたから知らなくて、ずっと気になってたんだけど、連絡したら負担になるかなとかあれこれ考えちゃって」
駄目だ。落ち着かない。学校に通えなくなって、すべてのエネルギーを失ったように見えた彼女が、いきなり立派な高校生となって目の前に現れたのだ。話をしたい。あの頃のことを謝りたい。と思いつつ、自分をしゃきっとさせる。元担任らしく、冷静に、頼もしく。
「美術部入ったんだ?」
「そうなんです。不登校の頃に、一日中家にいて気が塞いじゃうから、イラストとか描いてたんですよ。そしたら結構はまっちゃって」
「名前見てほんとびっくりした。すごいよ、この絵。すごく、なんていうか、ああ、ごめん、美術にぜんぜん詳しくなくて、語彙力が」
語彙力どころか、言葉を続けることさえできなくなった。不登校、という単語で記憶が蘇る。けれどすぐ目の前には弾けた笑顔のひまわりがある。
絵に付けられたタイトルは「Cheerful & beautiful!」
喉が詰まった。鼻の奥が熱くなった。視界が曇った。目元が湿った。
「どうしたんですかっ? 大丈夫ですか?」
「ごめん」照れくささに涙を拭う。精一杯笑う。「感動しちゃって」
感動。違う。もっと複雑な感情。でも残念。語彙力がない。津木さんは苦笑い。
「そこまで反応されちゃうと逆に恥ずかしいですよ」
「だよね、ごめんね」
謝ってばっかりだ。彼女を困らせてはいけないと呼吸を整え、周囲に目線を向けた。
その先に、よく見る顔があった。
す、と音もなく、仕事モードの切り替えスイッチがオンになる。
手招きして彼を呼び寄せる。
おずおずと近づいてきた楠島くんを、わたしは津木さんに紹介した。細かな事情は明かさずに、彼が高校の志望先について迷っていることを伝えた。文化祭の感想を津木さんに尋ねられた楠島くんは「楽しいです」と月並みな一言で返す。どんな催しがあったとか、こんなイベントに驚いたとか、人との会話ではそういう付け足しをするものなのだよと言いたくなるけれど、問われてから喋る彼のクセを変えなくちゃいけないなあとも考えて、わたしは津木さんと目を見合わせながら、間を埋めるように微笑みを交わす。
「そっかあ」と津木さんが口を開いた。
「緑塚はねえ、面白い人多いよ。先生は変な人が多いね。キャラがはっきりしてるからみんなで面白がってる感じで。あと、自由度も高めじゃないかな。その分、勉強とかは自分で管理していかないとやばいけどね。あたし的にはお勧め」
年下の子を相手にこんな風にはきはき喋れるようになったんだな、と感慨にふけりたい気持ちを抱えつつ、わたしは津木さんの絵を彼に示した。なんかはずいわ、と笑う彼女は一人おかしげに手を叩き、まじまじと絵を見る少年の肩をぽんと叩いた。
「楠島くん、だっけ?」
「あぁ、はい」
「美術部とかは興味ない? 絵を描いたりなんか」
「いや、苦手です」
「あたしもまだぜんぜんだけどさ、やってみると案外いけるかもしれないよ。掛け持ちもできるし。緑塚入ったら、部まで遊びに来て」
「これは」楠島くんがそっと絵を指さした。「水墨画ですか?」
水墨画? どの辺が? どういう質問? と、わたしと津木さんは見つめ合う。疑問を分かち合う。沈黙に異変を感じたのか、楠島くんはいつになく大きな声を出した。
「違いました! 水彩画って言いたかったんです!」
「あぁ、なるほどね! 水墨画って雪舟とかのやつじゃん、楠島くん面白い!」
水彩画じゃなくて油絵だよ、と教えられる彼の顔に、照れくさそうな笑みがあった。笑ったのを初めて見たかもしれない。言い間違えた恥ずかしさでむしろ気がほぐれたのか、絵の種類の解説を聞く彼の表情はいっそうほころんだ。時計を見ると、森野谷先生との待ち合わせ時刻が迫っていた。待たせてしまえ。この二人のやりとりのほうが、はるかに尊いのだ。
クラスの店番に行かなくちゃと津木さんは会話を切り上げ、わたしたちは彼女と一緒に美術室を出た。トイレに行った楠島くんを待つために廊下に留まっていると、津木さんはかしこまった様子でわたしに向き直った。ありがとうございました、と丁寧に頭を下げるので、にわかにあたふたしてしまう。
「学校行けなかったとき、先生、ずっと気に掛けてくれてたじゃないですか。お礼言いたかったけど、学校の先生辞めちゃったって聞いて」
また泣いちゃいそうだからやめて、と両手をぶるぶる振った。
「お礼を言うのはわたしのほう。元気でやってるのわかってめっちゃ嬉しいから」
きちんと退任のお別れができなかったこと、指導が未熟だったことを詫び、彼女と正面で向き合って両手をつないだ。しんみりとするような、このまま踊り出したいような妙な気分だった。見知らぬ幼い子がトンネルを抜けるようにわたしたちの手の下をくぐり、何が起きたのかと驚いた直後、走っちゃ駄目とお母さんらしき人がその子を追いかけた。わたしたちは不思議なくらい大笑いした。突然のささやかな珍事が、なぜか無性に可笑しかった。
「あっ、楠島くん」
戻ってきた彼に爆笑のわけを伝える。「今ね、男の子がね」
「先生、話しても通じないって。てかなんでこんなに笑ってんのあたしら」
わたしたちが滑稽だったのか、はたまたつられたせいなのか、楠島くんも愉快そうに白い歯を見せてくれた。
「津木さん、彼が来年やってきたら、よろしくね」
わっかりましたあと小気味よい返事を残して、彼女はクラスのほうへと消えていった。
「遅かったじゃん、結構楽しめたか?」
正門で待っていた森野谷先生が尋ねた。
「楽しかったです」楠島くんが答えた。「美術部の人と、話しました」
へえ、と相づちを打つ森野谷先生は特に興味もない感じで、来週は城見だな、と短く続けた。頷く楠島くんの横顔を見ながら、緑塚にしますって言っちゃいなよと、わたしは心の中で念じた。美術室で見た彼の笑顔に、励まされていた。森野谷先生やお母さんが何を言おうと、楠島くんの味方をしようと、ひとり誓った。