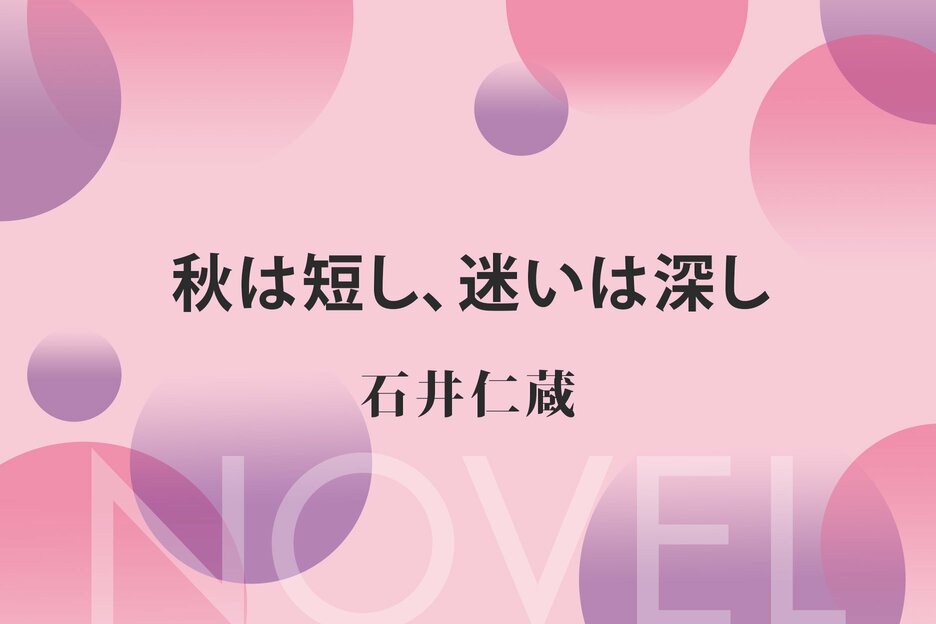「イッチー先生、あのねー、尾関くんがねー、イッチー先生のことをねー」「言うなバカ! 言ったら小五の全員におまえの秘密ばらす!」「ほらほら、そこで遊んでると中学生の邪魔になるよ!」「糸ちゃーん、二次関数のやつぜんぜんわかんないんだけどー」「ああこの問題か、やり方が少し特殊でね、あ! 曽川さん、今日再テストね!」「糸内先生! 三山さんのお母さんからお電話です!」「わかりました! ごめん、ちょっと待ってて」
授業と授業のあいだの時間はいつもにぎやかで、忙しい。
夕方からの授業を終えて教室を出てきた小学生と、夜の授業のためにやってくる中学生が入り交じり、各々の相手をしているところに保護者からの問い合わせがあったりするものだから、落ち着ける暇はあまりない。
「……はい、ええ、今日の分のフォローは体調が戻ってから行いますので、お大事になさってください」
子どもが風邪で休むとの連絡を受けたあと、数学の質問に来た中三生の対応をし終えたら、いつしか授業開始の時刻となる。わたしは教材を抱えて教室に向かう。今日の夜コマは中一生の授業。秋を迎えてすっかりと中学生らしさを備えた一年生たちにプリントを配り、前回扱った内容の復習問題を解いてもらう。制限時間は五分ね、とタイマーを押せば、それまでざわついていたクラスにすっと静けさが満ちる。出席簿のチェックを付けながらやっと、ほっと一息をつく。
わたしの職場。大手学習塾。育都アカデミー。
塾の講師という仕事を始めたのが今年の春で、夢中で取り組みながら早半年。前の職場から逃げ出したわたしをすんなりと、歓迎するようにして受け入れてくれたのはありがたいことで、勉学に勤しむ子どもたちの相手は率直に楽しい。小学生は時折憎たらしいけれどやはり可愛くて、単純な可愛さから脱皮しつつある中学生のアオハルな香りが、時々とても芳しい。
授業の始めからだらっと机にへばりつく姿には、あまり感心しないものの。
「岡本くん、お疲れかな? 部活が大変?」
「うー」
しぶしぶという様子で、サッカー好きの少年は体を起こす。一回り年下の彼は、背丈ですでにわたしを追い抜いている。「寝不足っす。昨日の夜にゲームしすぎて」
正直者である。ピピピピピ、とタイマーが鳴る。
「よし! じゃあ答え合わせね。眠気覚ましにバンバン答えてもらおうかな」
指名を受けた岡本くんは、マジかーと苦笑いを浮かべ、友人たちがくすくすと笑う。眠そうな子を頭ごなしに叱っても得られるものは少ない。クラスの雰囲気を調節しながら、授業を前に進めていくこんな時間が、わたしは好きだ。
「糸内先生、ちょっといいかな?」
授業が終わり、生徒が大方いなくなってから、安田校長は職員スペースの奥にある休憩室へとわたしを促した。何かやらかしただろうか、と内心どぎまぎしながら彼のあとに続き、ロビーチェアに腰を下ろす。お茶菓子の並ぶ背の低いテーブルを挟んで、正面に座る校長は、こちらの機嫌を窺うような控えめな笑顔だった。俳優の佐々木蔵之介に似ているな、といつも思う。白髪交じりで眼鏡をかけていて、くたびれた感じの分だけ、格好良さは割り引かれるけれど。
「本部から今日、話があってね」
校長は肩をすぼめて前のめりになる。声を潜める。
「正社員になる気はないかって相談なんだけど」
深刻な話かと息を詰めたわたしは、思わず笑ってしまった。なあんだびっくりさせないでよ、と友人相手ならつっこみたい。校長のきょとんとした表情を目にしてから、慌てて顔の筋肉を整える。
「すみません、てっきりクレームでも頂いたのかと思いまして」
「違う違う。よくやってますよ、アンケートも上々だし」
恐縮してぺこりと会釈。我ながら気ぜわしい。講師についてのアンケートは、担当クラスの生徒や保護者が対象だ。二ヶ月に一度、塾生専用サイトにて五段階評価で行われる。回答した個人名は明かされないしくみで、入りたての頃はびくびくしていたけれど、今のところは幸いにも悪くない評価を賜っている。
「正社員のほうが待遇もいいし、福利厚生もね……」
校長はなおも小声で話す。ほかの先生に聞かせたくないのかもと考えつつ、申し訳ないことに、あまり耳に入ってこない。非正規の講師でいるより条件はよく、今後の生活も安定する。わかっている。ほかにやりたいことがあるわけでもない。
それに、この仕事をわたしは楽しんでいる。
でも、耳の鼓膜にへばりついた言葉が、一年経った今もまだ取れない。
無理に掻き出そうとすればむしろ大きく響いてきて、痛みとかゆみがぶり返す。
──君は子どもを教える仕事に向いていない。
当時の上司からぶつけられた宣告を、拭いきれずにいる。
仕事を好きであることと、向いているかどうかは、別かもしれない。
そんな風に物思いに沈むのはたとえば、毎週開かれる会議の場。
生徒が来る前の時間に行われるもので、この日は校長やわたしを含めて七人の講師がひとつの教室に集まった。校長からは集客の状況など全体での共有事項が伝えられ、各クラスの担当が生徒の様子を報告していく。
受験シーズンを数ヶ月後に控えた十月の今は、小六と中三の志望校がもっぱらの議題だ。夏までの時点で定まっている生徒が多いものの、諸般の事情から変更を検討する必要も出てくるのだ。
「6Tの志望校に関してだけど」
書類を見つめる校長が眼鏡を持ち上げる。「宇野くんって海城志望じゃなかった? 偏差値的には微妙だけど、芝中まで下げちゃうのは駄目でしょう」
6Tは小六の中でも難関校を目指す生徒のクラスで、とりわけ重視されている。6Tの理系担当・宮崎先生は、小太りの体を乗り出して答えた。
「本人が芝中の見学に行って、気に入ったって話で」
「おうちの人は?」
「子どもの希望するところが一番ってスタンスで」
「だったら本人次第だね。まだ変えられると思うから、彼は必ず海城推しで行ってください。もっと高めまで上げたいかな。御三家まで視野に入れさせて海城に落ち着かせる形でもいいし。あと女子だと、大内さんか。成績伸びてきてるし、香蘭じゃもったいないでしょ、吉祥女子のレベルに誘導ね。雙葉まではさすがにきついかなあ」
一息に喋る校長の指示を聞いて、宮崎先生はまめまめしくメモを取る。その後もほかの小六クラスに話は及び、担当の先生たちは、生徒の偏差値と受験校を比較しながら、志望校のランクについて論じ合っていた。小六の担当がないわたしは聞き役に徹しつつ、次年度の参考にとレジュメにあれこれ書き込んだ。
学習塾は教育業。かつ、営利企業。あけすけな現実。営利企業には集客が不可欠だ。
集客のためには、高偏差値の学校にどれくらい多くの生徒を送り込めたかが問われる。少しでもその数を膨らませて見せるためにと、季節講習に一度参加しただけの生徒まで合格実績にカウントする塾もあるらしい。数字のアピールになりふりかまっていられない業界の事情なのだろう。
「中学入試はそんなところか。そしたら次は高校入試」
資料をぱらぱらとめくる音が教室の壁に響く。壁に貼られた大型サイズのポスターには、今年の春の合格実績がずらりと並び、難関校の名前がひときわ目立つように載せられていた。
「中一と中二の上位生は早めに誘導かけてほしいんですよ。ここ数年、育都生が全体的に安全志向っていうか、最難関を狙わない傾向があるんです。都立志望で青山とか新宿って書いてる子は、日比谷に持っていく。ジーマーチレベルの場合は早慶。今のうちからすり込んでおいてください。あとでまた話します」
まずは中三の様子を、と一瞥した校長と目が合い、背筋を正した。中学三年生のクラスはレベル別に三つに分かれており、わたしはそのうち二つを受け持っている。育都アカデミーの場合、一つのクラスは文系と理系の二人が担当するしくみで、理系のわたしと、文系の先生がペアを組み、それぞれの科目の指導に当たる。
「3L2は……と、うん、とりあえず成績との釣り合いは取れてるみたいだし、併願校も決まってれば問題はないか。変更点はない?」
校長の態度は6Tのときと比べて、明らかに和らいだ。椅子の背もたれに体を預け、生徒の情報が載った志望校リストを穏やかに眺めていた。気の抜けた感じすらある。質問を受けたのはわたしのペア担当、3L2の真岡先生。彼は淡々と答える。
「彼らについては、行きたい学校に確実に受からせるのが大事かと思います」
「そうだね。内申をもう少し足せるようにしてもらって」
校長はさしたる関心もなさそうにさらりと受け流す。担当としては複雑な気分だ。生徒と話して、保護者の方との面談を重ねて決めた志望校に、注文をつけられなくてほっとしたのは確かな一方、興味を持たれていない寂しさも漂う。3L2は成績的には「下位」のクラスだ。だから、集客の売りになるような実績は問われないし、校長も会社もさして気に留めない。
どちらが幸せなのだろう。期待をされず、希望の学校に行けるよう応援してもらえる生徒と、期待されたばかりに志望校を変えられてしまうかもしれない生徒。
そんなことを考えるうちに、わたしのもう一つの担当クラス、3L1の番になる。
最難関校とは言わないまでも、地域一番校を求められるレベルのクラスだ。地元の上位校を堅実に射止めてほしいと願う親御さんは多いから、校舎としての集客には難関校より大事な面もあると教わった。校長の目も鋭さを増した。
「和田さんはどう? 上を目指すの怖がってるっぽかったけど」
「大丈夫です。持って行けます」
喰い気味に答えたのはペアの相手、森野谷先生だ。ツーブロックの髪に肌は浅黒く、ジム通いが趣味だと語るだけあって、背広姿がぴしっと引き締まっている。スタートアップ企業のイケイケな社長みたい、という我ながらなんとも漠然とした印象を最初に受けて以来、うっすらとした心の距離感を縮められずにいるのは秘密だ。悪い人ではないと思うけれど、当たりが強い。
「今年の3L1はわりとみんなポテンシャルあるんで、チャレンジさせたい学校が結構多いんですよね。私立の併願パターンももうちょい詰めます。まあ本音を言うと、早めにZに上げてたらなっていう……ぶっちゃけ、前の担当を嫌がってたやつも何人かいたんで」
その話は、と校長がたしなめるように遮り、何人かの講師が苦笑した。中三の最上位クラスである3Zは、秋の初め頃に文系の担当が替わった。前任のベテラン講師が、許されざる問題を起こしてしまったのだ。厳しさから彼を恐れる生徒もちらほらいて、3L1から3Zに生徒を移しにくいと、森野谷先生はたびたびぼやいていたものだ。その講師が塾を去り、校長が代替の担当になってから、3Zに移籍した子も複数いる。
「楠島くんについてはどうかな」
校長が一人の男子生徒の名前を挙げた。「本当なら、3Zに戻したいけど」
わたしの受け持つ楠島秀道くんは、五月まで3Zにいた。ところが、くだんの文系担当と相容れないものを感じたらしく、3L1での受講を願い出たのだ。成績は少し停滞気味で、今では3Zに入るまでいくらか偏差値が足りない状況だ。
「前の担当の件もあるから、俺らもあんまり厳しくしきれないんですけど、そういう時期でもないですしね」
森野谷先生がわたしのほうを見る。黒目がちな力強い視線に捕まり、なんとなく頷いてしまう。「なんかあいつ、手ぇ抜いてる感じがしてイライラしちゃうんですよ。そう思わない? 思うよね、糸内先生」
「あ、いや、えっと、そうですねえ」
やっぱり当たりが強いな、と戸惑いつつ、曖昧に応える。言うとおりと感じられるふしはある反面、下手に同調して楠島くんを追い込む方に向かうのは嫌だった。
「まあいずれにせよ、あいつの志望校は城見で確定だから、そこに持っていくことだよ。3L1から城見に受からせれば、来年度の評判にもつながるし」
頷く。なんとなく頷いたでしょ今、とわたしがわたしに指摘する。この仕事は好きだけれど、好きになりきれない側面もある。今日の会議にはそれが凝縮されている。
塾の講師が会社の実績を念頭に置いて、生徒の志望校を決める。
大人たちが大人たちの都合で、子どもたちの未来について話す。
その学校がどんな学校なのか、どういう理由でその生徒に適しているのか。偏差値では表せないリアルな部分が何も見えてこないまま、話が進められていく。将来に対する希望を漫然と植え付けながら、目の前の分かれ道を数字で区切ってみせる。
そういうものだよ。
と、先輩講師が言う。割り切るほうが楽で、割り切らなくてはいけなくて、うまく割り切れる人間がきっとこの職を全うできる。小数の計算では割り切れない数字も、分数なら簡潔な答えが導けるように。大切なのは、明確な解を導くこと。「自発的な学びの心を育む」とパンフレットで謳う塾の中で、わたしたちに求められるのはその実、規定ルートの誘導係なのかもしれない。
そういうものかな?
と、自分に問いかける。
子どもの頃におかしいと思っていたことを、大人になって呑み込むのは、成長した証なのか、何かを諦めたからなのか。悩み抜いた真剣な考えを、青臭いと一笑に付す大人にむかついたり、軽蔑したりしたあの頃の自分は、忙しさに追われるうちにどうしようもなく薄らいでいく。
何か悩んでることでもあるの?
と、わたしは彼に問いかけたくなる。タイミングを見つけられないまま、相似と三平方と二次関数の組み合わさった数学の問題を解説する。
「……だからほら、直線Lと直線Mが平行って条件があるから、三角形ABCと、ここの三角形PQRが相似になるでしょ? 相似比は?」
説明用の図をA4用紙に描いてからふと見た顔は、どこか頼りない。短く刈り上げた髪に太い眉毛。ぱっと見では活発なタイプの子かと思いきや、クラスに友達もいなくてほとんど喋らない。中三の男子、楠島くんだ。
「一つ一つ図に書き込まなきゃだよ。手が動いてないじゃん」
楠島くんははっとしたようにシャーペンをノートに走らせる。森野谷先生の言うとおり、手を抜いているのか。どちらかというと、魂が抜けている風にも思えた。
楠島くんが3L1に移る折り、彼のお母さんは不満と不安をあらわにした。担当と合わないという理由で最上位のクラスを離れさせるのは不憫だ、違う塾を検討している。ごもっともなお申し出をいただいたわたしたちは、無料での個別フォローを提案し、どうにかこうにか今日に至る。この校舎は個別指導部門を併設しているので、ブースのひとつを使わせてもらいながら、毎週のフォローに当てた。個別指導は講師一人につき生徒が一人、ないし二人で、隣り合わせに椅子を並べる。講師との距離が近くて話しやすいため、生徒諸君がおおむね楽しげに取り組む中、楠島くんは静かなものだ。
「どうかな? 相似比が見えてこない?」
彼はノートを見つめたきり、わたしの質問にはかばかしい返事は寄越さない。
「それさえ見えれば補助線引いて、三平方で行けちゃう問題なんだけど」
解かせているのは、ある私立高校の入試からの一問。応用的ではあるけれど、彼の実力ならば充分に解ける。はずなのだが、攻略のカギとなる部分で止まっていた。一問に長い時間は割けないので、わたしはしびれを切らしてヒントを出した。
「あーっ! わかった!」と元気な声を上げたのは、彼ではない。背後のブースで別の講師の指導を受ける男子小学生だ。楠島くんのほうはといえば、快活さとはほど遠い静けさを保ち、無言で手を動かす。そして、なんとか解に辿り着く。
喜んだりほっとしたりするようなリアクションは、特にない。
「よしっ、解けたじゃん。要は相似比が見えるかどうかの勝負なのよこれ。でさ、この問題って、楠島くんの志望校の過去問から引っ張ってきたんだけど」
個別指導ルームの棚から、城見高校の問題を取り出して、机に置いた。
表紙を眺める彼の目を見て、一瞬、体の筋肉がきゅうっとこわばった。
正解を出せて嬉しいとか、ヒント無しで解けなきゃまずいとか、志望校に受かりたいとか、そんな内面が映らない沈黙の目。
短い言葉で表すなら、うつろな目。
一年前のわたしを夜な夜な苛んだのは、生徒が見せるこんな目だった。
──糸内さん、先生になったらいいんじゃねえの?
中学一年生のとき、特に仲良しでもないクラスメイトの男の子にそう言われたのが、始まりだったと思う。秋の中間試験が迫る日の休み時間、わたしは彼に数学の問題を教えていた。勉強はそこそこ得意だったし、自分が何かを教えることで誰かが喜んでくれるのは快い経験だった。その子の何気なく発した一言が、時を掛けて膨らんでいった。
上京して入った大学では教育学部に進み、教員免許を取り、東京の公立中学校で教員になった。一年生のクラス担任を命じられ、ひたすらに、がむしゃらに働いた。初年度だからと甘えてはいけない、保護者を不安にさせてはいけない、若い女性だからと軽んじられてはいけない。研修での心得を記したメモ書きを職員室の机に貼り付け、隙を見せない日々を送るよう努めた。
──二年目からは要領も掴めるし、多少はゆったりできるさ。
先輩教員からの励ましは残念ながら、わたしには当てはまらなかった。
次年度は二年生を受け持つのかな、という予想は裏切られ、三年生の担任を依頼された。そのうえ、バレー部の顧問にも任命されたのだ。教員の不足とか異動の事情とか、何がしかの説明を受けたけれどよく覚えていない。断るという選択を果たしていれば、教員を続けていただろうか。今となってはわからない。二年目になっても雑務に振り回される日々は変わらず、こういう生活をあと何十年も続けていくのかな、なんて疑問が頭にちらついていたある日、職員会議で一人の教員が手を挙げた。
──勤務時間の短縮を、検討してはもらえないでしょうか。
わたしより三つ年上の男性で、二年生のクラスの担任だった。彼は席から立ち上がるなり、職員室に集う先生たちにせかせかとプリントを配り始めた。「休憩時間の確保のための改善案」やら「部活動の日数制限」やらが、細々とした肉筆でびっしりと書かれていた。筆圧に面食らうような書面だった。了承もなしにこんなものを配るなと、校長が顔を赤らめて怒り出し、彼は即座にプリントの回収を命じられた。訴えが会議で取り上げられることはなく、三ヶ月後に教員を辞めてしまった。
革命の失敗。先輩教員たちは嘲るように口を揃えた。午前七時半に出社して夜九時過ぎまで働き、名目上の休憩時間は雑務で消え、土日祝日も部活の指導に追われる。主張の仕方はどうあれ、状況の改善を願った彼はまともだと思う。にもかかわらず、誰もが彼を嗤っていた。失敗した革命も、居合わせた人間の心には波紋をつくる。それ以来わたしは時折、足下のぐらつくようなめまいを覚えるようになった。
──押しつけないでほしいんです。先生の考えを。
あの日、わたしにそう告げた女子生徒の声がよみがえる。
そんなつもりはないよ、と慌てた弁明はきっと、空々しく響いたと思う。自分を見失ったまま空回りするわたしのありようを、彼女は的確に言い表した。
そのうつろな目が、今も忘れられずにいる。