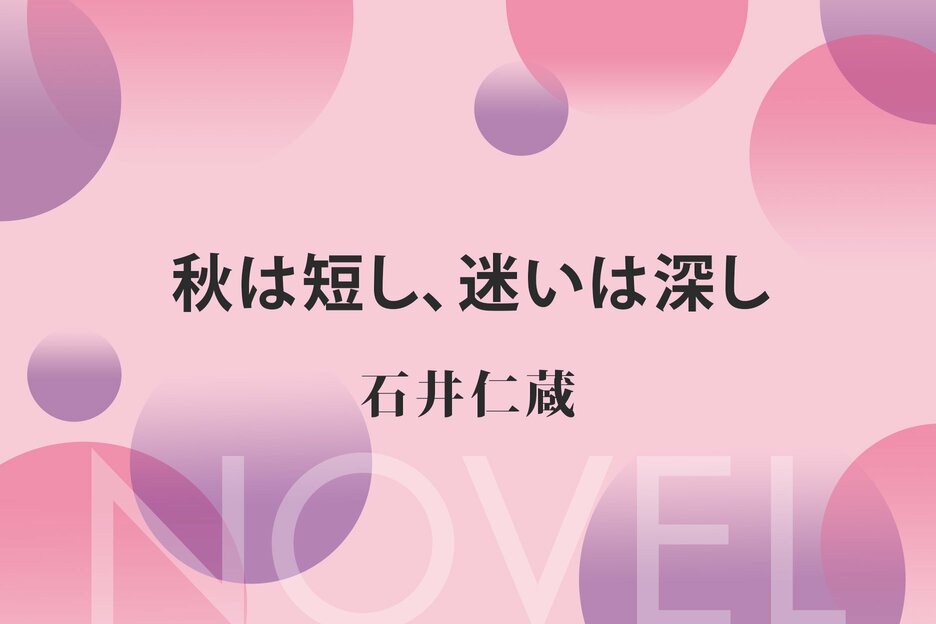志望校を変えたい。城見ではなく、緑塚に行きたい。
個別フォローを終えたとき、わたしの問いかけに楠島くんはとつとつと答えた。
城見は二度ほど見学に行ったがあまり魅力的に感じなかった、城見がいいと親が言うのでそれに合わせてきた、緑塚高校にはラクロス部があって興味を惹かれた、というようなことが、会話を通してわかった彼の気持ちだ。
「ラクロス部? あいつが今いるの、化学部じゃなかった?」
「ラクロスを描いたアニメを見て、やってみたいと思ったそうです」
「運動好きには思えないんだよな、体育も内申3だろ、確か」
楠島くんを帰してから、森野谷先生に相談したところ、彼は露骨に首をかしげた。
「緑塚なら今の偏差値で充分受かるじゃん。っていうか、五教科の内申で単願いけちゃうんじゃない? 単に逃げたいだけだろ、勉強から」
最後の一言は乱暴な決めつけだと思うけれど、数字的な評価は仰るとおりだ。私立緑塚高校は単願推薦制度を採用していて、中学の内申点が基準に達していれば出願できる。基準を満たした生徒が願書を送り、志望動機の作文を書いて面接を経れば、よほどの問題がない限り不合格にはならない。
言葉を選ばずに言えば、中学生にとって最も楽な入試だ。
「でも、楠島くん本人がそんな風に話したのが初めてで、彼なりに思うところがあるんじゃないかって」
「だったら併願で受けさせるか。駄目だな、城見の入試で手を抜いたらまずいし」
森野谷先生は独り言のように呟いて、ふわあっとあくびをした。「ほぉにかく」
とにかく、の発音もまとまらないうちに続けた。
「あいつの場合は、保護者が城見って言ってるんだから、城見でいいんだよ」
なんとなく頷く。その直前に、わたしは首を斜めに曲げた。
「おうちの方のご希望も大事ですけど、本人の気持ちも尊重しなきゃですよね?」
「おうちの方のご希望が大事だよ、会社的にも城見のほうがウェルカムだし」
言葉に詰まる、とはこのことだ。自分とはまるで異なる考えを無造作に放り出され、受け取ったものの正体を確かめるのにまごついた。お先に失礼します、と入り口のほうで声がして、受付の女子大生の子が頭を下げた。お疲れ、と返事をした森野谷先生は腕時計を見遣った。彼が奥に引っ込み、背広を羽織って出てくるまでのあいだ、わたしは動けずにいた。
城見高校と緑塚高校では偏差値のうえで開きがある。大学の進学実績にも差がある。だから、保護者の方が城見に行かせたいのはわかる。学歴の価値は否定できない。そこに価値があると人々が思うからこそ、学習塾は成り立っていて、森野谷先生の考え方を否定したら「ビジネス」としての塾はやっていけないのかもしれない。だけど。でも。
「言いたいことがあるなら聞くけど、帰り道でいいか」
掛けられた声にはっとする。速やかに机上を整える。荷物をまとめる。
そうだ。言いたいことはある。やっぱり受け入れきれない。
暑気が落ち着いて寒さが溶け込み、微妙なぬるさを保つ十月の夜風は、わたしが愛するもののうちで、わりと上位に入る。入っている。入っていたはずだった。けれど、仕事を辞めた去年の秋もこんな空気だったなと思い出すと、気持ちに小さなひびが入る。夜気に混じって漂う秋草のにおいも今は、心地よく感じられない。
「子どもの考えを尊重する、だっけ?」
建物を出てしばらく進んだところで、森野谷先生は口を開いた。ええ、とわたしは短く相づちを打った。彼の身長はおそらく一七七センチ。わたしよりも二十センチ高い。並んで歩くときの背丈の違いが、大学の頃の恋人と同じだ。
隣を行く彼には今、好意のかけらすら抱けずにいるけれど。
「子どもの希望どおりに進めるのが正しいって考えなら、俺はまったく同意できないな。会社にとっての顧客は保護者だろ? 顧客の満足を第一にするのが会社じゃん」
「高校に通うのは生徒ですよ」
わたしは答えた。彼はしばらく何も答えなかった。次に聞こえた言葉は、
「ん? それで?」
こちらを見下ろし、眉毛をひん曲げた。「だから何なんだ?」
「生徒のことを考えてあげなきゃいけないと思うんです」
「考えてるよ。よりレベルの高い学校に受からせて、選択肢を広げてやる。新人研修でも教わったんじゃないの?」
「偏差値がすべてじゃないですよね」
「だったらどう判断すればいい? 生徒の希望を叶えれば、そいつの将来はハッピーなのか? 根拠は?」
「行きたくない高校に受かっても、幸せになれないと思います」
「だからその根拠は何なのさ。俺が進んだのは第二志望の高校だったけど、楽しかったぜ。今の仕事もベストとは言えないが満足はしてる。第一志望の仕事に就いたけどすぐに転職しちまう人間だって、中にはいるだろ?」
ざく、と音の響きそうな一刺しが、わたしの胸を抉った。当たりが強いというより、この人は遠慮がないのだ。仕事帰りの駅までの道は、良くも悪くも本音を語りやすい場所なのだろう。わたしが教員を辞めたことは、講師の中で周知の事実だ。
「本人の気持ちは大事だよ」
駅の手前にある大通りで信号を待つあいだに、彼は言った。
「学習効率に影響するからね。目指したくないって状態のままじゃ、合格の可能性も下がる。モチベーションを下げないように扱いながら、こっちの考えに誘導する」
それが仕事だよ、とシンプルにまとめる。シンプルすぎると思う。再び言葉に詰まり、青信号に促されるまま、わたしは無言で駅まで歩く。
楠島くんは小学校の頃に別の大手塾に通っていて中学受験に挑んだが失敗してしまい、第二志望の学校に行った。しかし周りと合わず不登校気味になり、家の近くの公立中学に編入した。高校受験こそは成功を収め、質の高い学校に入ってほしい。
すでに何度も聞いたお話を、お母さんは熱を込めておさらいした。
「なのに今週になって別の高校に行きたいなんて言い出すもんだから驚いちゃって私、この時期に志望校変えるなんて弱気になったのかなと思って訊いたら、緑塚のほうが家から近いし仲のいい友達もそこに行くからとか言って、なんか情けなくなっちゃって私怒ったんですね、そしたら黙っちゃって部屋にこもっちゃって」
こちらの相づちも待たずに続く話を聞きながら、家での楠島くんはしんどい思いをしているのでは、と感じる。お母さんは専業主婦で、お父さんは建築士。ブラウンベージュのミディアムショートがぴったりで、オレンジのスカーフがよく似合う闊達なお母さんに、一人っ子の楠島くんはさぞや深い愛情を注がれてきたのだろうと察する半面、兄弟や姉妹のいるご家庭と比べたら期待の重みも大きいのかもしれないなと勝手に考えてしまう。
「緑塚だと国公立とか早慶上智に進学する数も城見の半分くらいなんですよね。あの子の性格的に、難関校を狙うのが当たり前って環境においてあげるほうがいいし、だから高校受験で高いところに行けるなら中途半端な私立中にいるよりよかったかなと思うんですけど今は」
「緑塚は合わないでしょうね、秀道くんには」
わたしの隣で、森野谷先生はためらう様子もなく言い切った。
「体育系の部活で人気なので、そういう志望者が集まってきやすいんですよ。自由な校風といえば聞こえはいいけど、緩い面もあるっぽいです。あそこに進学した子も何人か知ってますが、その中の一人と連絡取ったら、別の高校にしておけばよかったって嘆いてたんですよ、ここだけの話」
森野谷先生の話すあいだ、お母さんは我が意を得たりという調子でしきりに頷いていた。面談の最中、彼女の目線はもっぱら森野谷先生に向いていた。わたしは添え物のようにちょこんと座り、自動頷きマシンのごとくに首を動かすだけだった。若い女の教師は軽んじられる、という現実に落ち込むほど、うぶではない。わたしたち二人を客観的に捉えれば、頼りがいがありそうなのはどう見ても彼のほうだ。
「秀道くんの気持ちは早急に立て直します。お母さん相手だと本人も反抗的になるでしょうし、私たちにお任せください。目指せ城見、ってことで、我々三人で歩調を合わせていきましょう。糸内先生からもお願いします!」
二人に見つめられ、鼓動がにわかに速まる。秀道くんの気持ちが第一ですよ、などと言える流れではない。担当の意見がばらけているという印象を与えてはいけない、と焦ったわたしは、勢い任せに言った。
「城見高校の合格を、お約束します」
お約束は言い過ぎ。駄目だったときにクレームになるじゃん。
全力で取り組みます、とかでいいんだよ。
まあでもこれで、受からせるしかなくなったな。
面談のあとで森野谷先生から言われたことが、いちいちぶっ刺さった。なんであんなことを口走ったんだろう、一時しのぎのバカやろうめと自己嫌悪に陥り、その日の授業では板書のミスを繰り返してしまった。
「もう平気だよ。楠島と話して、城見目指すって約束させたから」
翌日、森野谷先生はけろりと言ってのけた。お母さんを後ろ盾にした彼の圧力を受けたら、楠島くんは従ってみせるよりないだろう。約束というのはそもそも、「させる」ものなのか。そんな風にして意見を呑ませても、果たして勉強に身が入るのか。というわたしの疑問を察したように、彼は続けた。
「口約束だけで勉強しないようじゃ困るから、個別の課題出してチェックしないとな。理系のほうでも課題の計画つくっておいてね」
「教えてほしいんですけど」
わたしは尋ねた。「卒業生の話をしてたじゃないですか、面談で。緑塚に行ったけど、違う高校にすればよかったっていう。その子は、どうして緑塚が嫌になっちゃったんですか?」
森野谷先生は、にいっと唇を横に広げた。
「いないよ、そんな生徒。万が一、お母さんが本人にほだされて、緑塚にしますとか言い出したら困るだろ? 事前にすり込んでおいたんだ」
怖い人だ。得意げに語る彼を前にして、明確に感じた。彼の思いどおりに事が運ぶのを、手助けするのはぜんぜん気乗りがしない。かといって、楠島くんの将来を私情で左右してしまうのは正しくない。
あの子は本当に気持ちを整理できているのか。言われるままに受け止めてやり過ごしただけなんじゃないか。わたし自身はどうなんだろう。どんな方法が正解なんだろう。
煩悶を抱えながら、3L1の授業後に、楠島くんを空き教室に呼んだ。
「城見が第一志望で、間違いないの?」
尋ねてみると、彼は、はいともいいえとも言わずに黙り込んだ。
「他の学校の名前も出してたから、気になっちゃって」
彼が返事を発するのには少し時間が掛かった。そのあとでようやく、「ちょっと迷ってる」と短く答えた。もともとこもり気味の声が、普段より余計にこもっている。
「どっちにも行きたい気持ちがあるの?」
「ああ、いや、えっと、緑塚、緑塚がいいです」
「ちゃんとお母さんに話した? 森野谷先生にも」
「話したけど」
そこで言葉が止まった。どうするべきだろう、と悩む。あくまでも彼に寄り添って、二人を説得しようと腹を決めるべきか。そうしたい、と直感的に思う。一方で、お母さんが納得しなかったらと不安な想像もふくらむ。希望を叶えれば生徒の将来はいいものになるのかと、帰り道の森野谷先生が口を挟んでくる。
本人の気持ちを大事にする。大事にしながら、こっちに誘導する。
それが仕事だ、という彼の声が頭の中に響く。
「緑塚も、悪くない学校だけどね」
わたしは結局、城見を推した。
迷いを押し殺そうと、まるで城見高校の回し者みたいにその魅力を伝えた。
「お母さんもすごく心配してたし、中学受験のこともあるから、今度こそより上の高校に行ってほしいって話してたの。お母さんもきっと喜ぶよ」
最低だ。生徒に寄り添ってあげるべき、なんて信条を一丁前に抱えていたくせに、実際は親のほうに肩入れしている。上とか下とかって考え方も、個人的にはあまり好きじゃないのに。
「城見にします」
楠島くんは言った。
彼の失踪騒ぎが起こったのは、翌週のことだった。
中学二年生に連立方程式の文章題について教えていたとき、安田校長が教室の後ろに顔を見せ、こっそりと手招きをした。楠島くんが授業の開始時刻を過ぎても現れない。すでに家を出たとお母さんは言うが、本人から何か聞いていないか。教室を出たわたしに彼は尋ねた。教室の時計を見ればもう二十分以上の遅刻だ。遅刻常習犯の生徒も中にはいるが、楠島くんが断りもなしに遅れるのは覚えがない。
「行きそうな場所とか、知らない?」
「すいません、思い当たらないです」
「わかった。私が外に出るんで、気にせずに授業を続けてください」
どうしたんですかあ、と二年生の子たちがざわめくのを収めながら、わたしは食塩水の量の求め方について解説を再開した。すぐにでも探しに行きたいという焦りを隠して、目の前の生徒には笑顔を保つ。この子たちには関係のないことだ、自分の仕事をすべきなのだと念じて、無事発見の知らせを待った。
授業が終わって終業時刻になっても、彼の消息は掴めなかった。
「先生方は帰って大丈夫です。私が残って連絡待ちますんで」
捜索から戻ってきた校長が言い、受け持ちでない先生たちは校舎を去って行った。じゃあお願いします、と校長に挨拶を告げ、鞄を携えたのは森野谷先生だ。
「帰るんですか」
批難がましく聞こえるのを承知で、声を尖らせる。帰るよ、と彼は素っ気なく答えた。ここにいれば見つかる確率が高まるのか、と嘯いてみせた。
「心配じゃないんですか、担当してるのに」
「いつもより周りに目を光らせて歩くよ。糸内先生は?」
「見つかるまで教室で待ってます」
「君が待ってて何の意味があるんだよ。ただの自己満足だろ」
わたしの嫌いな言葉を、彼は的確に放った。むかつきと不安を抑えきれず、わたしは荷物を整えて外に出た。
彼の行きそうな場所はわからない。とりあえず駅前のほうを、と足早に歩を進める。無事に見つかったとして、楠島くんが明日から塾に来てくれるかと、現実的な心配が頭をもたげる。
中学校とは違い、塾はいつでも退会の措置が執れる。退会の申し出をあっさりと呑み込む先生もいるけれど、わたしは嫌だ。関わった子が顔を見せなくなるのは辛い。それが辛くないならこの仕事を続けるべきではないと思う。
自己満足。耳にこびりつくその単語が、苦々しい過去を呼び起こす。
わたしが救えなかった彼女。
一人の女子生徒のことを思い出すのは、たとえばこんなタイミングだ。
──辞めたいんです、部活。
彼女が思い詰めた顔でそう口にしたのは、わたしのせいだったかもしれない。担当クラスにいたバレー部の女の子、津木凛々菜さんが、練習のあとで職員室にやってきた。週に五日の放課後練習に加えて朝練もあるうえ、部員の同級生と喧嘩して気持ちがくじけたと彼女は話した。痛切な面持ちで訴える生徒を前にしながら、軌道から外さずすませることしか当時のわたしの頭にはなくて、諦めない姿勢とか話し合うことの大切さとか、今思えばありきたりな言葉を並べてつなぎ止めようとした。考えを押しつけないでほしい。説得の最中に彼女は言った。うつろな目には、揺るがしがたい拒絶の意思が滲んでいた。
──学校が楽しくない。
欠席が重なり始めた津木さんは、力ない声で呟いた。家を訪ねたわたしに会いはしてくれたものの、下を向いたままで目を合わせようとしなかった。
楽しくなくても通っている生徒はいくらでもいる、なんて話をしても仕方ないから、彼女の不登校の理由を確かめるためにさまざまに質問を繰り返して、対処法を伝えた。彼女が顔を上げることはなかった。
学校が楽しくない、というのは当時のわたしにとって致命的な表現だった。他ならぬわたし自身が、毎日の仕事を楽しめなくなっていた。クラスの中で細かないざこざが頻発したり、顧問を務めるバレー部でも変な派閥が生まれたりして、思い描いた教師生活の色彩は日ごとに薄れていくばかりだった。
経験の不足、疲労の蓄積、ストレスの高まり。
抱えた荷物の重さを、いつしか強権的に振る舞うことでやり過ごすようになった。そういう接し方は、教職を務める者にとって、ある種の麻薬みたいなものだ。生徒たちを一方的に従わせる立場に快感すら覚えた。親しみや愛着、自分の描く理想像と引き換えに、支配の喜びに溺れかけたわたしの姿こそ、津木さんを不登校に追いやった原因に違いない。そんな風に客観的になれたのは、仕事を辞めてからだ。
スクールカウンセラーの先生のところに行こう、教室が無理なら保健室に登校する形でもいいよ、校長室に通う子もいるんだよ。
頻繁に電話を掛け、時には家庭訪問も行って、津木さんを呼び戻そうと努めた。ほかの雑務もなおざりにはできず、家に帰るのが十一時過ぎになるのも一度や二度ではなかった。
わたしはできることを一生懸命やっている。生徒たちのために。
そう信じてきた自己像が、ピキピキとひび割れて砕けたのが九月の半ば。
──一学期の期末は、このクラスの数学の平均点、残念ながら四クラス中最下位でした。次はなんとしてもトップになろうよ。そのための課題を用意してきたからね。
教卓に重ねたプリントの束をどんと叩いた。えーっ、と不満の声が飛ぶ、という展開ならむしろありがたかった。実際の教室に溢れたのは、重くて暗いため息。
──ジコマン。
とささやく声が聞こえた。おまえ言うなよー、と一人の男子が隣の男子をつつき、あちこちから忍び笑いが立ち上った。ジコマン、自己満、自己満足。わたしのことを指しているのだと察した直後、「いっつも自己満だよね」と女子の声も耳に届いた。
自己満って何のこと。
必死にやっているのに。みんなの学力を高めたいと思っているのに。
顔が熱くなった。涙がこぼれた。
校長に願い出たのは、それから数日後だ。
──一週間ほど、お休みをいただきたいんです。
普段の状況や申し出に至る経緯、精神的な状態などを話したが、校長から慰めや励ましはなかった。勝手に休むのは無責任だ、要領よくやらないからだ、生徒に信頼されないなら話にならない。
──君は子どもを教える仕事に向いていない。
散々な罵倒のあとで休みの許可が下りたものの、その後の期間をどう過ごしたのか、まったく記憶がない。リフレッシュとはおよそ呼びがたい、すべてが停止した時間だった。約束の一週間はあっという間に過ぎた。さあ今日から立て直そう、と起き上がろうとしたとき、体が言うことを利かなくなった。ベッドに横たわったまま、枕元から引き寄せた目覚まし時計の秒針を、空っぽの心でずっと眺めていた。