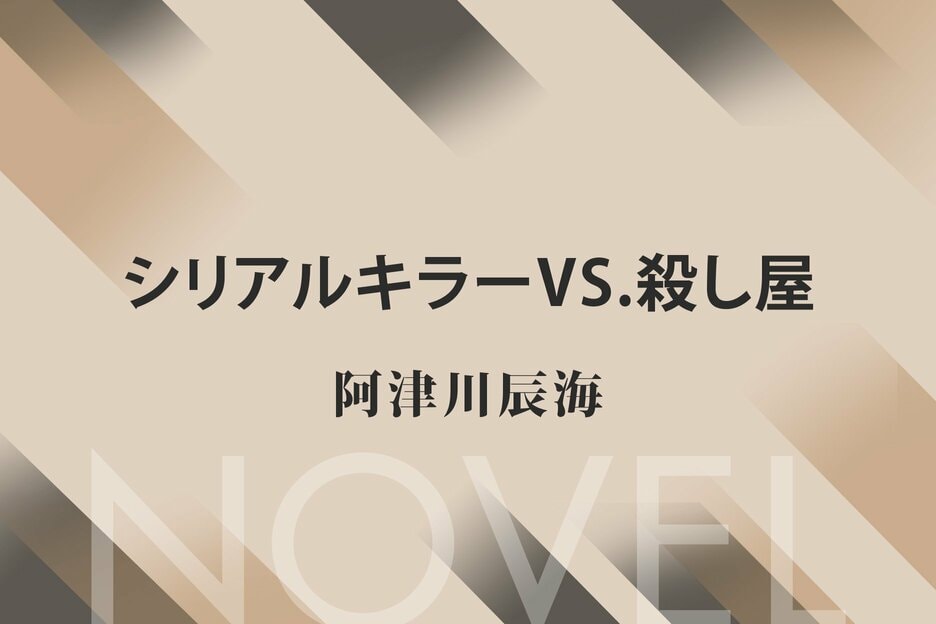7
十五日目。
おれは限られた体力で、少しずつ体を調整する。部屋に現れた虫も食べた。生きるためには仕方がない。
五十嵐が訊く。
「好きな食べ物はなんですか」
「そんな質問でいいのか? ……餃子、かな」
「ふむ。夕食選びに困っていたんです。どこかで出前でも取りますかね」
五十嵐の目は暗かった。
「十五問目。殺すのは、絶対に矢代でなければならなかった。そうだな?」
「——イエス」
十六日目。
おれは次第に、五十嵐という殺人鬼に本当の意味で好感を覚え始めていた。殺人者のよしみ、というわけではない。五十嵐が、自分のルールにフェアな殺人者だと確信したからだ。
「十六問目。おれを監禁し始めた日のことについて聞きたい」
「……」
「あの日、おれはお前を尾けていた。お前は突然道を引き返して来たな」
「……」
「あの行動には意味があった。そうだな?」
「……イエス」
五十嵐はおれの顔を見た。
「あの。そんな回りくどい質問……する意味、あるんですか」
「おれにはある」
五十嵐からの質問は「一番好きな景色」というものだった。おれは無難に「雨上がりの虹」と答えた。
十七日目。
「一度聞いたが、不安なのでもう一度聞く。お前の両親が交通事故で死んだ日付は、八年前の十一月二十八日、で合っていたか?」
「……イエス」
五十嵐は目をつむった。そして訊いた。
「……あなたの両親が亡くなった事件は、いつだったんですか?」
おれは黙り込んだ。覚えていなかったからだ。
十八日目。
「お前の働いている古書店には、何冊本があるか分かるか?」
「イエス。ちなみに、一万八七四五冊です」
五十嵐は淀みなく答えた。ハッタリのようには見えなかった。
「あなたは、なんのために人を殺すのですか?」
「仕事だからだ」
おれの正体を言ったようなものだが、五十嵐は正解を言う「解答権」を行使しなかった。
彼の望みは、分かっているつもりだ。
十九日目。
「お前は、おれの足枷の鍵を持っている?」
「イエス。明日も持っているでしょう」
五十嵐は続けた。
「どうして、殺すことを仕事にしたんですか?」
おれは答えに詰まった。五十嵐は「明日までに考えておいてください」と言って、部屋を離れた。
最後の日。
戦略も、体も、心も、仕上がっているとは言い難い。しかし、与えられた状況で最善を尽くした。
仮説も外れていない。
これまでの、五十嵐とのやり取りを反芻する。重要と思われるのは以下のことだ。
①五十嵐はこれまでに八十七人——矢代を加えれば八十八人を殺している。
②五十嵐は身分証等を見るまで、被害者の名前や住所、職業等の情報を知らない。
③見た目で被害者を選出しているのではない。
④被害者の性別は関係がない。
⑤五十嵐は八十八人目の標的として矢代を殺さなければならなかった。かなり危険な相手なのにそうする必要があった。
⑥五十嵐の両親が死んだのは、八年前の十一月二十八日である。
もう一つ重要な項目がある。そこを二十問目で確認したい。
扉が開く音がした。
「昨日の質問、答えは出ましたか」
五十嵐の言葉が背中に降りかかる。
「分からない。向いていると思ったから……かな」
親父のように、正義を貫いて殺されるぐらいなら、そんなものから背を向けて生きていたいと思った。五十嵐に言った言葉は嘘ではない。殺し屋という仕事は向いていた。決まりきった手口で、淡々と仕事をこなせば良かったから。
ターゲットとこんな風に長く、言葉を交わしたことはない。
振り返ると、五十嵐は立っていた。今日は悠長にパイプ椅子に腰かける気はないらしい。
五十嵐の口の端が持ち上がった。
「まるで、仕事について口にしているみたいですね。じゃあ、あなたの殺す理由を言い当てましょうか」
「お前は質問をしなくていいのか?」
「不要でしょう。あなたは殺し屋なんでしょう。だからぼくを殺しに来た。田辺アイの両親が、あなたに依頼したんだ。ねえ、そうでしょう?」
「正確には訂正が必要だが、おおむね合っている。正解でいいだろう」
実際には、おれは直接依頼されたわけでもないし、依頼人の正体も動機も知らない。しかし、そんなことはいいだろう。
「これで、あなたが当てられない限りは、ぼくがあなたを殺して終わりです」
五十嵐の顔は歪んでいる。失望と期待の間で揺れ動いているように見えた。
「まだ、おれの質問と回答が終わっていない」
「どうぞ」
「二十問目……もう一度、おれを監禁した日のことを思い出してほしい」
「ええ」
「お前は突然振り返って、おれとすれ違った……あの時、あのまま直進していたら——おまえは、走ってきた子どもを殺さなくてはいけなかった。おまえは、それを避けたかった。違うか?」
五十嵐の顔が期待に輝いた。
「その通りです」
「なら、お前の『ルール』について解答しよう。
お前は、その日すれ違った千百二十八番目の人間を殺害する。それがお前の『殺す理由』だ」
もちろん、五十嵐の両親が死んだ日、十一月二十八日に由来する数字だ。
おれは、エビスと訪れたサウナでの出来事を思い出す。当店で一万人目のお客様……。めでたい数字なら喜ばしいが、五十嵐にとってのその数字は、呪いでしかない。
普通の人間なら、「数えてみよう」と思っても、一日中持続することはないだろう。交差点で一斉に人がすれ違ったタイミングで、諦めてしまうに違いない。しかし、彼が数字に鋭敏なのは、十八問目で裏付けが取れている。
細かいことを言えばキリがない。恐らく、歩きながら視界の範囲内ですれ違った人物に限定するのだろう。電車に乗りながら、車窓の向こうで通り過ぎた人、あるいは自分が道を歩いている時に車で走り去った人、こういう人々はカウントしない。そうでないと、都会を一日歩いた人間がすれ違う人の数は、千を軽く超えてしまうはずだ。
——まさか、殺した相手は、全員が初対面だったのか?
——大抵、は。
継続的に殺人を犯している以上、通勤時に人を数えているはずだ。つまり、生活圏やエリアが重なっている人物を殺す可能性もある。だから「大抵」なのだ。毎日すれ違っている人間は、たとえ言葉を交わしたことがなくても「初対面」とは言えない。五十嵐はそう判断したのだろう。
彼が会社員ではなく、古書店のアルバイト店員だったというのも大きいだろう。通勤ラッシュに朝夕と巻き込まれていれば、すれ違う人の数は千では利かない。ラッシュのピークがやや過ぎてから通勤し、同じくやや過ぎてから退勤する。そのバランスだからこそ、「多い日で千百人」で済んだ。逆に言えば、雨などで人通りが少なければ、その日は殺さなくてもいい。
八年間に八十七人。一年あたり約十一人だ。諸々の条件を考えれば、満更あり得ない数字ではない。
そして、こう考えれば全ての辻褄が合う。
「お前は、路上で突然暴力を振るってきた矢代をどうしても殺さなければならなかった。その日千百二十八番目の人物だったからだ。お前の被害者は、お前の意思とは無関係に決定される」
それこそ、おれが五十嵐を気に入り始めた理由だった。自分の意思と関係なく人を殺す。これは、殺し屋の仕事と似ている。自らのルールに従う限り、性別や年齢にかかわらず、職業の貴賤なく、選ばれた人間を殺さなければならない。とてつもなく歪んでいるが——これは、フェアだ。
だが、彼はおれの知る限り、一度ルールを枉げた。
「おれとお前がすれ違ったあの日のことも、これで説明がつく。道の向こうから子供が走ってきた時、お前は千百二十七人とすれ違った状態だった。だからあのまま直進したら、その日千百二十八番目の人物として、子供を殺さなければならなかった。お前は、それを避けたかったんだな」
だから道を引き返した。そしたら、そこにおれがいたのだ。
スタンガンで気絶する前、五十嵐の声が聞こえた。
——ごめんなさい。
あれは、そういう意味だったのだ。
五十嵐は長い息を吐いた。
「……全て正解……です」
これで、殺しの資格を両方が得たことになる。
おれは足枷の鎖を素早く引いた。
鎖は既に五十嵐の足元に巡らせてあった。転ばせるところまでいかないが、わずかに体勢を崩すことに成功する。
五十嵐との距離を素早く詰める。
彼は懐からスタンガンを取り出した。
電極に触れないようにして、手からはたき落とす。
おれは手の中に隠していたものを広げる。
紐だ。
銀色の、少し幅広な紐。
十日目。本の出張買取作業で疲れたという五十嵐がおれのところを訪れなかった日。彼は下膳もせずにゴミを一日放置した。ゼリー飲料のパックは、三食分、そのまま残っていた。
おれはそれを一つだけこっそり隠し持っていた。翌日、五十嵐が部屋を訪れた時にゴミはまとめて捨てられ、いつものように数えられることはなかった。
そうして九日間の間、工作に勤しんだのだ。歯で少しずつパックを噛み切り、紐状にした。
強度に不安はあるが、凶器には使える。
おれはそのまま五十嵐にのしかかり、マウントを取った。
紐を首に巻き付ける。
両腕に力を籠める。
いつか報いを受けるものと思っていた。だから死ぬことなど怖くないとうそぶいていた。だが、生きていたかった。自分が何人殺したのか思い出したかった。餃子をもう一度食べたかった。雨上がりの虹をもう一度見たかった。
両親が死んだ日が何日だったのか確かめたかった。
こんなところで死ぬことだけは、ごめんだった。
五十嵐は首に巻き付いたものを外せずに苦しんでいたが、すぐに切り替えて、マウントから脱出しようとしている。腰を持ち上げられる。紐が緩んだ瞬間を、五十嵐は逃さなかった。
五十嵐はおれに頭突きを喰らわせ、窮地を脱する。
「二十問目を思い付きましたよ」
五十嵐が珍しく、早口で言う。
「あなたが鉄線やピアノ線、道具にこだわり続けるのは、最初の殺人のトラウマがあるからですね? 直接人の首に手をかけて殺すことが、あなたには出来ない。ねえ、そうでしょう?」
その言葉を聞いた瞬間、おれの意識は真っ白になった。
気が付いた時には、おれは五十嵐の首に手をかけ、その両手で首を絞めていた。
五十嵐の体から力が抜けていた。
結末は味気なく、呆気なかった。
五十嵐のポケットを探り、足枷の鍵を見つけ出した。二十日ぶりに足枷から逃れると、途端に体が軽くなる。
おれは階段を上がり、初めて五十嵐の部屋に入る。
入ってすぐのところに、カゴが置いてあった。おれの服と、荷物だ。服はきっちり洗濯してある。
服の上に、メモ用紙が載せられていた。
『これを読んでいるということは、ぼくとの勝負に勝ったということでしょう。おめでとうございます。
お預かりしていたものです。勝手に洗濯してしまい、すみません。
冷蔵庫の中のものは適当に食べても構いません。捨てられる食器が良ければ、戸棚の一番上の左です。ゴミ袋は足元の棚に入っています。
それでは、お元気で。
五十嵐将志』
服を着ると、おれはゴミ袋を取り出し、メモをくしゃくしゃに丸めて捨てた。
冷凍庫の一番見えやすいところに、冷凍餃子が置いてあった。二十日ぶりのまともな食事は、それだけで脳がとろけるようだった。体に力が戻り、頭がハッキリとしてくる。
動けそうだ。
食事の間、携帯を充電させてもらった。居室に時刻表示付きのデジタル時計と今日の夕刊を見つけたので、それらと一緒に五十嵐の遺体を撮影しておく。これで、エビスに頼まれた写真が出来た。七月二十五日まであと五日ある。依頼人の要求は達成出来た。
地下室にはおれの痕跡が大量に残っている。どのみち、全てを消すことは出来ない。ベッドのあたりだけでも水で流し、触った覚えのある個所は指紋を拭った。あとは、この地下室に眠る、矢代以外の八十七人の死者が、おれの痕跡を誤魔化してくれることを祈るしかない。
紙皿や割りばしなど、使ったものは全てゴミ袋に入れて、カバンの中に突っ込んでおいた。
おれの家に帰るには、渋谷で下車して、路線を乗り換える必要がある。
自分の家に帰るまで、すれ違う人を数えた。一人、二人。五十嵐にかけられた言葉を思い出した。三十人。三十一人。殺しのターゲットとあんなに長く話したのは初めてだった。八十五人。八十六人。優しくされたのも。二百三人。二百四人。まだ手に感触が残っている。三百七十三人。三百七十四人。十数年ぶりに人の首を絞めた手触りが残っている。
渋谷のスクランブル交差点を一斉に渡る無数の人間を見た瞬間、おれは数えるのを諦めた。
……この町には、人が多すぎる。
彼は、止めてもらいたかったのだ。彼の質問は、ぼんやりしたものばかりだった。おれの人を殺す理由を当てる気などなかった。真剣にゲームをしていたのは、おれだけだ。
最初は自分の意思で始めたのかもしれない。それでも、自分の意思ではもう止められなくなった呪いを、誰かに止めてもらいたかった。おれの荷物を見た時、彼には分かったのだ。おれが自分を殺しに来た使者だと。それを捕らえてしまったのだと。あの、道を走って来た子供のせいで。運命は彼を楽にはしてくれなかった。最後まで、苦しめ続けた。
彼は、おれに止めてもらいたかった。しかし、自分からそう言い出せはしなかったのだ。だから、歪なゲームを考え出した。
家に帰ってエビスへの連絡を済ませる。詳細は伝えず、ターゲットを仕留めたことを伝え、写真を送る。データはすぐに査収された後、ダークウェブ上から消え、エビスの「了解。」という素っ気ない言葉だけが表示される。
それもすぐに消える。
おれはそれから、洗面台で何度も手を洗った。
手の皮が剥けたあたりで、やめた。水が渦を巻いて飲み込まれていくところを、しばらく見つめ続けた。
(了)