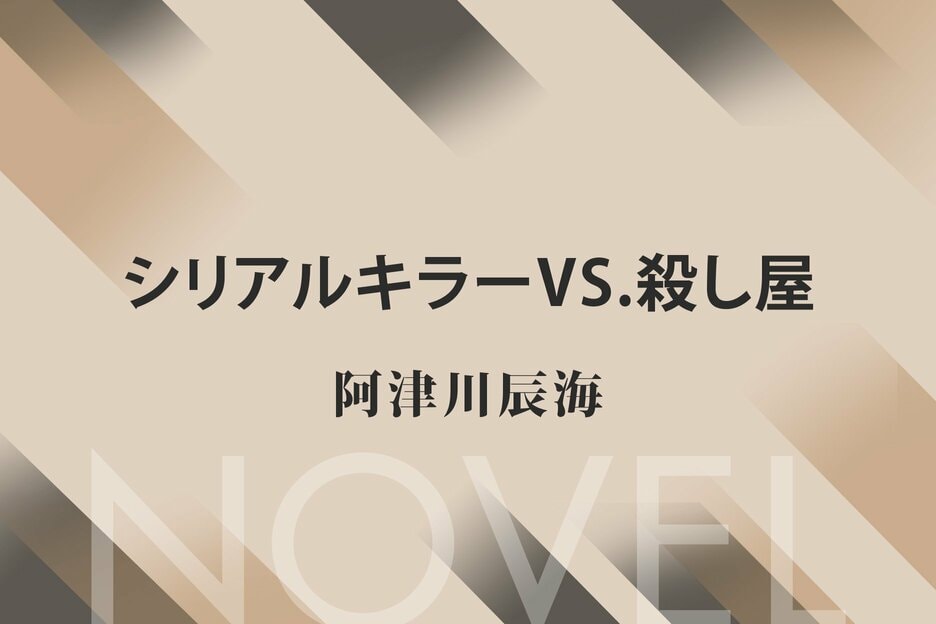3
……少しずつ意識が戻ってくる。頭は重く、激しく痛んだ。二日酔いの朝のような鈍重な体。最初に機能を取り戻したのは嗅覚だった。
病院のような臭いがする。
消毒液や薬品の香り……という意味ではない。消毒液の臭いの向こうに、糞便や腐臭、消し難い死の臭いが染みついている。
蛍光灯の強烈な光が、寝ぼけた両目を焼く。
「う……ああ……」
強烈に喉が渇いていた。口から出てくるのは、意味不明な言葉だけだ。
ぼやけた視界が、次第に像を結んでいく。
最初に目に入ったのは、ベルトで縛られた自分の両腕だった。椅子の肘掛けに括り付けられていて、身動きが取れない。バイク乗りが使うようなぶ厚い手袋が嵌められ、指も自由が利かなかった。
服を着ていない。
背中にも臀部にも、木の冷たく、硬い感触がある。両脚も椅子の脚に結び付けてあった。
指一本動かせない。
誰だ?
誰が、こんなことを。
殺し屋として、危険な目には何度も遭っていたが、こんな事態は初めてだった。油断したという他ない。
意識がブラックアウトする直前見えた顔……あれは、五十嵐だった。まさか? あの男が? どうして、こんなことを?
カツン、カツン、と足音が響いてきた。足音は次第に近付いてくる。
「……目が、覚めましたか」
おれの前に現れたのは、やはり、五十嵐将志だった。
彼の目はおどおどとおれを見ている。
「……あんたがやったのか」
五十嵐はビクッと体を跳ねさせたが、否定しても仕方ないと言うように、やがて、ゆっくりと頷いた。
五十嵐はおれの目の前にパイプ椅子を持ってきて、座った。五十嵐は目線が下に向きがちだから、一度おれの局部を見てしまい、気まずそうに目をそらした。
「服を脱がせたのは、すみません。危険と判断しました。そういう趣味があるわけではありませんのでご安心を」
最初に心配するのが、そこか? おれは何か言い返したかったが、そんな部分にかかずらっていたら話が前に進まない。
「だったら、どうして、こんなことを」
「どうして、と言われましても……」
どこか、他者に責任を転嫁しているような雰囲気がある。イライラして体が痒くなる。
「ここまで、どうやって運んできた」
「車で……」
意識を失う直前、車が近くで停まった音がした。
「こういう時にしか使わないんですよ。あなたをスタンガンで気絶させて、車で運んだんです」
あの衝撃は、スタンガンによるものだったのか。
「いつもはもっと慎重にコトを運ぶんですがね……あなたは危険だと判断しましたから、早急に動きました」
「おれの何が危険だと?」
「鉄線にピアノ線、携帯電話も二つ持っていましたね。片方はプリペイド式です。明らかに普通の持ち物ではありません」
「答える義理はない」
「カメラマンの名刺もカメラもありました。水野さん、とおっしゃるのですね」
五十嵐も少し落ち着きを取り戻してきたらしい。理路整然とした口調で、話を続ける。
「水野さんの持ち物、佇まいは、カメラマンのそれとはとても思えません。数日前から、私のことを尾けてもいましたね」
反応を示さないようにしようとしたが、遅かった。
「やはり、そうでしたか」
「……いつから気付いていた?」
「昨日、あなたとすれ違った時に、見覚えのある顔だ、と思いました。それで、ここ数日の記憶を辿ったら、心当たりがあったもので」
記憶力はかなり良いようだ。あるいは、注意力が優れているのだろうか。
「あなたの目的はなんですか」
おれは何も言わなかった。
おれ一人ならともかく——エビスを危険にさらすわけにはいかない。裏稼業に生きる人間としての、最低限のルールだ。
携帯にはパスコードでロックをかけてあるし、エビスとのやり取りは全て数分後には削除される。おれが口を噤んでいれば、問題ないはずだ。
「目的? なんのことだか分からんね」
「この状況でもとぼけますか……すごいですね。困りました。本来なら、すぐに殺すところなんですが、目的を確認しないと寝覚めが悪いですからね」
「おれを……殺すのか?」
皮肉なものだった。殺し屋が、ターゲットに監禁され、殺されるとは。
「それが、ぼくの『ルール』なので」
「『ルール』……?」
「こちらの話です」
五十嵐はおれの顔をじっと見た。
「あなた……ぼくを殺しに来たんでしょう」
「心当たりでもあるのか」
「ありますよ。腐るほどね」
五十嵐がおれを上目遣いで見た。
「……あなたが私を殺しに来たというなら、殺されてあげてもいいんですがね」
「嘘をつけ」
「嘘ではありません。そうでなければ、フェアとは言えませんからね」
「この状況が、既にフェアとは言えない」
五十嵐の表情は変わらなかった。彼は、店番しながら本を読んでいる時と同じ表情で、おれを見つめている。
「ゲームをしましょう」
「ゲーム……だと?」
「二十の扉、という遊びを知っていますか」
「……出題者が考えたお題を、解答者が二十個以内の質問で当てることが出来るか……そんなゲームだったか」
例えば、出題者のお題が「リンゴ」だとする。解答者は、「それは物ですか」「それは食べ物ですか」「和洋中でいうとどれですか」などの質問を繰り返して、「リンゴ」という答えに辿り着かなければならない。
「そうです。どうも、お互いを殺すという目的は同じようですから、その理由をお互いに当ててみよう、というわけです」
「当てたらどうなる?」
「先に当てた方が、相手を殺す」
「馬鹿馬鹿しい。当てられても『違う』と言い張れば済む話だろう。おれが先に当てた時、解放される保証は?」
「ぼくの言葉を信じていただくしかありません」
ふう、とため息を吐いた。
「質問の形式は?」
「どのようなものでも可です。イエス/ノーの二択で答えられるものから、長い回答を必要とするものまで。ただし、動機を直接聞くような質問はNGとしましょう。殺す理由、動機が分かったら解答しますが、それは一回のみとする。嘘を答えたことが分かった場合、その時点でゲームは終了。あなたを殺害します」
あと、と五十嵐は続けた。
「質問は、一人一日一問まで……としましょう」
「なんだと?」
おれは目を剥いた。
「その方が、じっくりと質問を考えられるでしょう」
彼はさっき、おれを襲ったのが「昨日」と言った。つまり、任務の期日まであと二十日以上ある。最終日までに五十嵐がおれを殺そうとする動機を当てることが出来れば、依頼には間に合う計算となる。不幸中の幸いで、エビスに受注の連絡はしている。任務遂行中は、エビスから連絡を取ってくることはないから、おれと連絡がつかないことを怪しむとは思えない。
「やるしかないようだな」
「分かっていただけましたか」
五十嵐はようやく、薄く笑った。
「じゃあ、ぼくの一問目です。最初は軽くいきましょうか。あなたは、人を殺したことがありますか?」
「……はい」
おれは、軽くいくつもりはなかった。
「質問だ」
「どうぞ」
「お前はこれまでに何人、人を殺した?」
この地下室に沁みついている死臭は、ただごとではなかった。
「ああ、上手いですね。ぼくがした質問よりも、一つ先の情報を得られます。水野さんの方がこのゲームに向いているかもしれませんね」
「いいから、早く答えろ」
五十嵐は思い出すような素振りも見せずに言った。
「八十七人」
こいつは困ったことになった。
おれのターゲットは、どうやら、シリアルキラーというものらしい。
4
食事は日に三回。ゼリー飲料や栄養補助食品、水などが与えられる。味も素っ気もないが、何もないよりはずっといい。
向こうはこちらの武器を取り上げて安心したのか、拘束具は足枷のみにしてもらえた。
足枷は、床に固定された寝台と繋がっている。鎖の長さは三メートル程度。部屋の隅にある便器には自分で行くことが出来るが、扉までは辿り着かない長さになっていた。
足を繋がれているので、姿勢は窮屈だが、寝台で横になることは出来る。板のようなマットレス、それも、多くの犠牲者の汗と汚れを吸ったのであろう、シミだらけのマットレスだが、これもないよりはマシだ。
……なんとか、抜け出さなくては。
おれは殺し屋として、多くの命を奪ってきた。おれを捕まえたのがクソシリアルキラーだと分かった時は、これも何かの天罰かと思った。しかし、こうして一人きり、冷たい部屋に放置されてみると、自分の中から「生きたい」という気持ちがふつふつと沸き上がってくるのに、驚かされる。
抜け出すための方法は二つ。
一つ目は、あのクソ野郎をぶちのめすこと。
二つ目は、あのクソ野郎が提案したゲームに勝つこと。
おれとしては前者の方法を採りたいところだが、さすがにおれの正体を怪しんで、向こうも警戒しているらしい。部屋の中には余計な道具は一切なく、ゼリー飲料のパックやキャップ、ペットボトルに至るまで全てのゴミを回収していく。武器ゼロ、体力的にも衰弱した状態で、体格だけは良いあの男に挑むのは危険だ。
「二十の扉」を実践するにあたって、紙とペンが欲しいと要求したが、これも受け入れられなかった。ペンの一本でさえ、こちらに武器となるようなものを与えたくないということだろう。徹底している。
二日目の……恐らく夜。時間感覚はとうにあやふやになっているが、最初の質問から、二十四時間ほど経っているはずだ。
五十嵐が訪れ、おれにこう質問した。
「あなたは特殊な道具で人を殺しましたか?」
「……はい」
「うん。やはりそうでしたか。では、あなたからも質問をどうぞ」
「……なぜ八十七人も殺してコトが露呈しないか、おまえの見解を述べろ」
おれは五十嵐の顔を見て言う。
「こういう質問でも、いいんだったな」
「ええ、構いませんよ。そうですね……全ての死体はバラバラに解体して薬品で溶かし、処理しています。被害者の家族は捜索願を出しているでしょうが、捜査の進行度は知りません。少なくとも、ぼくのところに訪ねてきたことはありません」
……なるほど。こいつはまずいことになった。
アメリカで一九七〇年から八〇年代にかけて十三人を殺害し、五十人以上を暴行した連続殺人・強姦事件犯「黄金州の殺人鬼(ゴールデン・ステイト・キラー)」は、複数の州にまたがって犯行を犯し、長らくの間、同一犯による犯行だと思われていなかった。「黄金州の殺人鬼」という名前も、ミシェル・マクナマラというジャーナリストによってつけられた名前だ。名前によって全体像が明らかになり、最後には捕らえられた。名付けられることで弱体化する妖怪のように。
死体の処理が完璧で、事件が顕在化していないというなら、これも「全体像」が分からない犯行だ。証拠は五十嵐の言葉しかない。「全体像」が分からない以上、警察は不審な行方不明者が相次いでいるとしか認識出来ない。
——つまり。
相手にしてはいけない人物を相手にしていることは、分かった。
警察の助けは期待出来ない。もとより期待出来る立場にはないが、これでますます絶望的になった。
結末は、二つに一つだ。
こいつを殺すか、殺されるか。
三日目。
「あなたが殺しに使ったのはあの鉄線ですね。そうでしょう?」
「……イエス」
五十嵐は薄く笑みを浮かべて頷いた。
「では、あなたの三問目を」
「……直近で殺した人物について教えろ」
五十嵐は表情を崩さない。
扉の近くに置かれた、やけに綺麗なパイプ椅子に座って話し始める。
「この前殺したのは会社員の女性でした。名刺と免許証から、佐藤亜実、大手生命保険会社の事務で、年齢は三十五歳、誕生日は十二月九日、神奈川県在住であることが分かっています。エリアは覚えていないなあ。……彼女について、他に何か聞きたいことは?」
「四問目のカウントにならないのか」
「サービスとしましょう。何せ、八十七人いますからね」
五十嵐は肩をすくめた。真面目なのか、ふざけているのか分からない。
「おまえの目から見た範囲で、容姿を描写しろ」
「ふむ」
五十嵐は目をつむった。
「……髪は素っ気なく後ろで括り、パンツスーツが似合う女性でしたね。あとはメイクが濃かったこと……ええと……」
五十嵐はしばらく悩んでいたが、やがて穏やかにはにかんだ。
「すみません。描写するというのが分からなくて」
「……だったら、構わない」
五十嵐がいなくなってから、おれは少し眠った。
四日目。
「あなたがこの前殺した人の話も聞きたいな」
五十嵐は無邪気な顔で言った。
彼が質問しに来るおかげで、今が監禁から何日目なのか判断出来る……それぐらいまで、おれの時間感覚は覚束なくなっていた。今、表ではどうなっているか、考えるだけで辛い。誰か、おれのことを捜してくれているのだろうか。家族はもういない。カメラマンの方ではどうか。「飛んだ迷惑野郎」として名を馳せている頃か。エビスにはもとより期待出来ない。しくじった相手とは手を切る。エビスは、そういう男のはずだ。
殺した相手。一つ前に……思い出さなくては。
「おれが……殺したのは……大手銀行の役員だった」
殺し方から日付までが細かく指定された、高額の案件だった。依頼人の正体については、考えたくもない。
おれが被害者について根掘り葉掘り聞くことで、同じ質問をされる可能性は考えておくべきだった。
なぜ銀行の役員のような人物を殺さなければならないか? 次に、「その役員とあなたはどういう関係だったのか」などと聞かれれば、おれは答えに窮することになる。初対面の相手を殺したなどと知られれば「殺し屋」というワードが五十嵐の頭をよぎるだろう。
もう猶予はあまりないのかもしれない。
おれがそれ以上続けないのを見て、五十嵐は小さく頷いた。
「そっちの番ですよ」
「二つ前に殺した人について教えろ」
「津村カスミ、二十二歳。大学生でしたね。念のため、女性です。確か……住んでいるところは九段下近くのマンション。誕生日は一月一日です」
「正月か」
五十嵐は虚を衝かれたように顔を上げた。
「え、ええ……珍しいですよね……」
「他には?」
「ロングヘアで清楚な感じの女性でしたね……それぐらいでしょうか」
おれは、五十嵐が津村カスミの情報をあまりにスラスラ述べたことに不審を覚えた。昨日の質問から予期していたのだろうか。それにしては、正月が誕生日であるのに今更気付いたというのは、おかしい。
五日目。
「最初の殺人を覚えていますか?」
おれはハッと顔を上げた。
五十嵐が部屋に入ってきたことにさえ、気付いていなかった。
「最初……」
「そう、最初です」
「……目出し帽を被った暴漢……だった」
「ほう」
五十嵐は興味を惹かれたようにおれを見つめたが、おれがそれ以上続けないのを見ると、「続きは明日にとっておきましょう」と言って、質問を打ち切った。
「あなたという人物に興味が湧いてきました。明日もここに来るのが楽しみです」
「まだ、おれの質問が終わっていない」
「ああ、はいはい」
「三つ前に殺した人について教えろ」
「須々木京平、五十二歳。男性です。工事現場に勤めている、はずです。大田区在住、誕生日は九月二十日。容姿は……筋肉質な体で、八十キロぐらいあったかな。堅肥りという感じで、特に足の筋肉がすごかったですね。そんなところでしょうか」
おれはそれ以上追及しなかった。
一つ前に殺した三十五歳の女性、佐藤亜実。
二つ前に殺した二十二歳の女性、津村カスミ。
三つ前に殺した五十二歳の男性、須々木京平。
被害者に一貫性がない。
しかし、五十嵐は「ルール」が存在するという。それならば、被害者には何か共通点があるはずなのだ。
誕生日も違う。職場も違う。住所も違う。
……共通点は、なんだ?
(つづく)