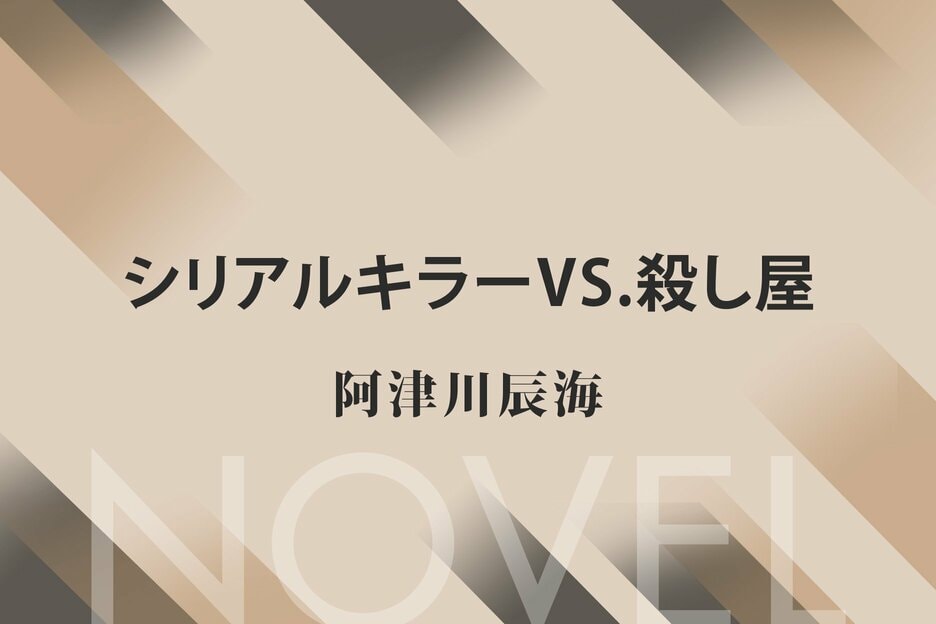5
六日目。
意識が常に朦朧としている。部屋の中の饐えたような臭いに鼻が順応してきて、危機感を覚える。
三人の被害者の名前や特徴を覚えておくのが、段々と困難になっていく。
おれがしていることに、何か意味があるのだろうか?
あの男は、ただおれをいたぶって楽しみたいだけなのかもしれない。ゲームの成否におれの生死は連動していないのかもしれない。今しているのはただ無駄な努力で、おれだけが命懸けのゲームだと思い込んでいるだけなのかもしれない……。
一日目に、武力での制圧を試みるべきだったかもしれない。だが時すでに遅しで、体にはろくに力が入らない。まともなものを食べていないせいだ。
いつの間にか、五十嵐が椅子に座っている。
おれも寝台に腰かけて、向かい合おうとするが、体が動かない。寝台の上に横たわったままのおれに、五十嵐が言う。
「六問目です。あなたは、なぜその暴漢を殺したのですか?」
おれは朦朧とした意識で、口だけを動かし続ける。
「……高校生の時だ。警察官の家に生まれたおれは、すっかりグレて友達の家を泊まり歩いていた。既に一人暮らししている奴がいたからな。家にいるよりずっと……気が楽だった」
五十嵐は黙って聞いている。
「ある日、着替えを取りに家に戻ったら、鍵がかかっていなかった。……壊されていたんだ。玄関に母さんが倒れていた。母さんの体の下に、血だまりが出来てたよ。父さんはリビングで背中を刺されてた。壁にかけてある木刀を取ろうとしたんだろう」
おれの心はいつの間にか、あの日の家の中にいる。
「暴漢は家の中に留まっていたんですね」
「昔、父さんに捕まった犯人が復讐したらしい。あとから警察に聞かされた。父さんは……正義感の強い人だった。どんな悪人も許さなかった。時には、悪人を捕まえるために行き過ぎたマネをすることもあったらしくて……だからそいつはお礼参りに来た。まあ……逆恨みだけどな。そいつは出がけの駄賃に金品を漁ってたから、まだ家にいたんだ。クズみたいな奴だったよ。暴漢はもうナイフを持っていなかった。おれは暴漢と殴り合いになり、最後にはマウントを取って、首を絞めていた。この両手で」
あの時の生々しい感触が手に蘇ってきて、おれは目を閉じる。おれは六問目の権利を行使しないまま、眠りに意識を預けてしまう。
七日目。
「昨日、五日分は答えてもらいましたから、しばらく回答役に徹しますよ」
どことなく、五十嵐には遠慮するような雰囲気があった。
昨日何を話したか、ろくに覚えていなかった。思い出せるのは、最初の夜の記憶を何度も反芻していたことだけだ。
「じゃあ……昨日できなかった六問目から。お前の最初の殺人は、どんなものだった?」
「田辺アイという女性でしたね。『ルール』に従って殺した最初の人物です。確か……神保町付近の大学の准教授だったかと。誕生日は六月二日ですね」
おれは、ふと思いついて聞く。
「七問目。田辺アイをいつ殺したか、覚えているか?」
「七年前の七月二十五日」
ようやく一つ、糸口を見つける。
八日目。
昨日の質問で、おれの依頼人の正体と動機がはっきりした。依頼人は、田辺アイに関係する人物だ。恋人か、あるいは親類か。
五十嵐の言葉を信じるなら、彼は被害者の体をバラバラにし、薬品で処理している。死体があがることはない。「七月二十五日」は、五十嵐にとっては「殺害した日」だが、遺族等被害者の関係者たちにとっては「行方不明になった日」になるはずだ。行方不明になってから七年後に、失踪宣告がなされる。死んだものとみなされ、相続などの措置が開始する。
依頼人は、その日までに決着をつけたいのだ。
問題は、ここから先だ。
依頼人は、なぜ五十嵐将志が田辺アイを殺した犯人だと突き止められたのだろうか?
つまり、あるのだ。
田辺アイと、五十嵐将志には、接点が。
おれは与えられた栄養補助食品を五十回噛んでから飲み込んだ。口の中の水分がなくなるのはいただけないが、代わりに頭は冴えてくる。水なら、熱中症を心配してか二、三本置いてくれるようになった。
反撃は、これからだ。
五十嵐が入室するなり、おれはこう聞いた。
「八問目。田辺アイの関係者で、誰か知っている人物はいるか?」
五十嵐は不思議そうに首を傾けた。
「いませんね」
九日目。
昨日の質問は空振りだった。もちろん、五十嵐が気付いていないだけで、五十嵐の身近に田辺アイの関係者がいるのかもしれない。五十嵐の周辺を根気強くあたれば、見つけ出せるのかもしれない。
しかし、それはおれが自由に動き回れれば……の話である。
五十嵐に「いません」と答えられた以上、こちらとしては手詰まりだ。
依頼人が五十嵐の正体に気付いた理由は、ひとまず棚上げにするしかない。五十嵐という男の行動を観察していれば、分かることなのかもしれない……。
「九問目……あんたにとっての、『トラウマ』はなんだ?」
「それは、どんなことでもいいんですか?」
おれは頷いた。
トラウマを起点に連続殺人を繰り返す——洋の東西を問わずよくある話だ。恋人や想い人との失恋や、母親から受けていた虐待などがトラウマになっている場合、そうした女性に似た顔の人物を見つけては殺す、という事例を聞いたことがある。
被害者には男性が含まれているが、失恋のトラウマに、男が関わっている可能性がないでもない。
五十嵐は、じっと黙って考え込んでいた。
沈黙が続く間、鉱脈を掘り当てたかもしれない、と期待で胸が高鳴った。
五十嵐が、口を開く。
「……両親がぐしゃぐしゃに潰れて、死んだ」
おれは目を見開いた。
「八年前の交通事故のことか?」
五十嵐が素早くおれを睨んだ。
「知っているのですか?」
おれは黙ることにした。
五十嵐はじっとおれを見つめ、ゆっくりと口を開いた。
「あなたの……言う通りです。八年前の十一月二十八日……両親はぼくの前からいなくなった。こんな家なんて……財産も、いらなかった。ただ、二人が傍にいてくれれば良かったのに……」
五十嵐は床を蹴るように立ち上がる。
「……二問分です」
そう言って、扉を叩きつけるようにして去っていった。
十日目。
恐らく。
五十嵐が現れない。扉の下から飲食物の載ったトレーだけはやり取りがあった。トレーにはいつもの食事の三回分が載せられていた。
しかし、姿は見せてくれない。昨日質問をした時から、もう三回食事をとった。夜。朝。昼。もうそろそろ来てくれてもいい頃のはずだ。
空のゼリー飲料のパックが積み上がっている。もう、そろそろ替えが来てもいい頃だ。
だが来ない。
五十嵐は来てくれない。
待つだけの時間が、一番辛い。気持ちを紛らわすことも出来ない。一通りの後悔は済ませ、一通りの反省も済ませた。五十嵐だけが、おれと世界との接点だった。
——八年前の交通事故のことか?
あれを一問分と捉えた。だから「二問分」というわけだろう。
だとしたら、今日はもう会わなくてもいい——五十嵐としては、そういう思考に至ったのではないか。
矢継ぎ早に質問を放ったことを反省する。本当なら、自分を責めるいわれもないのに。
なぜ。どうしてこんなことに。
いつ終わるともしれない思考のループに沈んで、帰ってくることが出来ない。
6
十一日目。
五十嵐がやって来て、視界が明るくなるのを感じる。
五十嵐はトレーを回収して、ろくに確認もせずにゴミを袋に突っ込んだ。
「ぼくの質問は一昨日してしまいました」
「『知っているのですか?』だな」
五十嵐が微笑んだ。それだけで、心が温かくなるのを感じた。
ストックホルム症候群に陥っているのを自覚する。おれは加害者である五十嵐に対して親愛の情を覚え始めている。これでは、いざ殺さなければならないという時に、手が鈍る。
おれはこの男を殺さなければならない。
その決意を新たにする。
五十嵐は目を伏せる。
「昨日はすみませんでした」
「え?」
「急遽、県外まで出張で本を買い取りに行くことになったのです。すごい量の蔵書で、ほとんど一日仕事でしたから……帰ってきて、すぐに眠ってしまったんです」
まさか謝ってくれるとは思わなかった。それだけで、何か救われたような思いがする。
……そんな思いを振り払って、おれは続ける。
「十一問目」
おれはゆっくりと「十一」と発声した。時間感覚を手放さないために。
「これまでの被害者について。氏名や誕生日などの情報は、免許証や学生証、名刺などを見るまで知らなかったのか?」
五十嵐はおれの顔を見た。
「イエス。ついでですから、田辺アイもそうだ、と回答しておきましょう」
昨日一日放っておかれたことで、頭の整理がついた。
最初に聞いた直近の被害者、佐藤亜実について、五十嵐は「名刺と免許証から」と口にした。
何気ない一言であったが、名刺や免許証を確認するまで、名前も誕生日も知らなかった、と取ることも出来る。おれがされたのと同じ手口で、スタンガンを使って攫った後、被害者の荷物を検めた。名刺や免許証などから、彼は被害者の名前等を覚えた……。
しかし、攫った時点で、殺すことは決まっているはずだ。攫った後、逃がした人物がいたとすれば、コトが露見していないというのはあり得ない。
十一問目。
折り返し地点。
おれは事件の検討を振り出しに戻さざるを得なくなった。
氏名。
職場。
誕生日。
容姿。
どれも、ミッシングリンクの中心にある「属性」ではない。
殺すまで、五十嵐はそれらの「属性」を知らなかったのだから。
十二日目。
「今日からはぼくも質問に戻らせてもらいますよ」
五十嵐はいつもの椅子に座った。
「ルール」を解く糸口も見えず、おれは追い詰められていた。これまでの推測を土台から覆され、絶望に気が塞いでいた。
「これまでに犯した中で、最も印象的な殺人は?」
五十嵐は真面目くさった顔で言った。
まるで殺し屋にする質問だ。おれの正体が分かっているなら、どうして解答権を使わないのだろう。五十嵐の態度は不可解だ。
「いちいち覚えていない」
「本当ですか?」
仕事だからな——と胸の中で答えておく。そこまで口に出してしまえば、それこそ殺し屋とバレてしまうだろう。
おれはふと思いついた言葉を口にした。
「……まさか、殺した相手は、全員が初対面だったのか?」
五十嵐は目を見開いた。やがて、口元に薄く笑みを浮かべた。
「大抵、は」
「大抵?」
「今のはノーカウントにしてあげましょう。要するに、何度か顔を合わせたことのある人はいた、ということです。ただ、あなたが恐らく想定しているような、知人とか友人とか……そういう人物はいませんね」
まるで謎かけのような言い回しだ。
ますます、分からなくなった。
十三日目。
この日が、おれと五十嵐の「ゲーム」のターニングポイントになった。
扉の開閉する音で顔を上げ、おれは息を呑んだ。
五十嵐は、頭に包帯を巻いていた。口の端も切れ、血が滲んでいる。脇腹のあたりを手で軽く押さえていた。もしかして、肋骨が折れているのだろうか。血と脂の臭いがその体から放たれていた。
いつもの椅子に座ってもなお、その呼吸は荒かった。
「お前、それ、どうしたんだ?」
これが質問になってしまうことにも気付かず、おれは言った。
五十嵐は自嘲気味に笑った。
「道ですれ違った男に殴られたんですよ。目はうつろで、言動もおかしかった。かなりヤバかったですね」
五十嵐は柔道の経験もあるというし、体格も良い。その彼をここまで傷つけたのだから、相手も同等かそれ以上の体格だったとみていいだろう。
「病院に……」
「あなたとのゲームが終わるまでは、そういうわけにはいきませんよ。それに、もう心配いりません」
五十嵐はそう言い、早々に椅子から立ち上がった。
「おい」
五十嵐の脚が止まる。
「質問は?」
ああ、と五十嵐の口から息が漏れた。忘れていた、とでもいうように。
「今までで一番大きなケガはなんですか?」
おれは虚を衝かれた。
「……大学の時、スキー合宿で骨折した。転倒時に手を突いて折れたんだ」
「あれは辛いですね」
五十嵐は頷いた。
幸いにして、殺し屋を始めてからは重篤なケガを負ったことはない。だから嘘ではなかった。
十四日目。
おれは、ようやく一つの結論に辿り着いていた。
五十嵐が部屋に入ってきた時、おれはスクワットをしているところだった。
男が全裸でスクワットをしている。五十嵐も、さすがに異様な雰囲気を感じ取ったのだろう。
「なんのつもりでしょうか?」
「それが質問でいいか」
五十嵐が頷いた。
「体がなまったから、少し動いていただけだ」
嘘はついていない。なまった体を動かしたいのは本当だ。ただ、本当の目的について語り落としているだけだ。
足枷をつけられ、栄養も水分も足りない今、体を動かすにも限界がある。しかし、いざという時に五十嵐を倒すことの出来るエネルギーが必要だった。心の方は既に持ち直している。おれの目の前にはハッキリと一本の道があった。
これから六日間。
おれがする質問に、五十嵐が全て「イエス」と答えたなら、おれの仮説は立証される。
もし一つでも外したなら、仕方がない——おれは、この仮説と心中するつもりだった。
五十嵐はじっとおれを見つめていた。
呼吸を整えると、五十嵐の体から、昨日よりも強い血の臭いが立ち上ってきた。シャンプーやボディクリームの匂いも混じっているが、その程度では誤魔化しきれない。
血の臭い。
それが、おれの仮説をまた裏付けてくれる。
考えていた質問の一つ目を口にした。
「昨日、お前をケガさせた男がいたな」
「それは質問ですか?」
おれは首を振った。
「質問はここからだ——お前は昨日、その男を殺害したか?」
五十嵐はおれを睨み付けた。
「……イエス。あなたのせいで、ここが使えないので、バスルームで作業するしかなくて苦労しましたよ。おかげでなかなか臭いが落ちない」
五十嵐は表情を歪めた。
「ついでに教えてあげましょうか。男の名前は矢代というようです。これで、話をしやすくなるでしょう」
それも、免許証で分かったことなのか? という質問は飲み込んだ。
もったいないからだ。
(つづく)