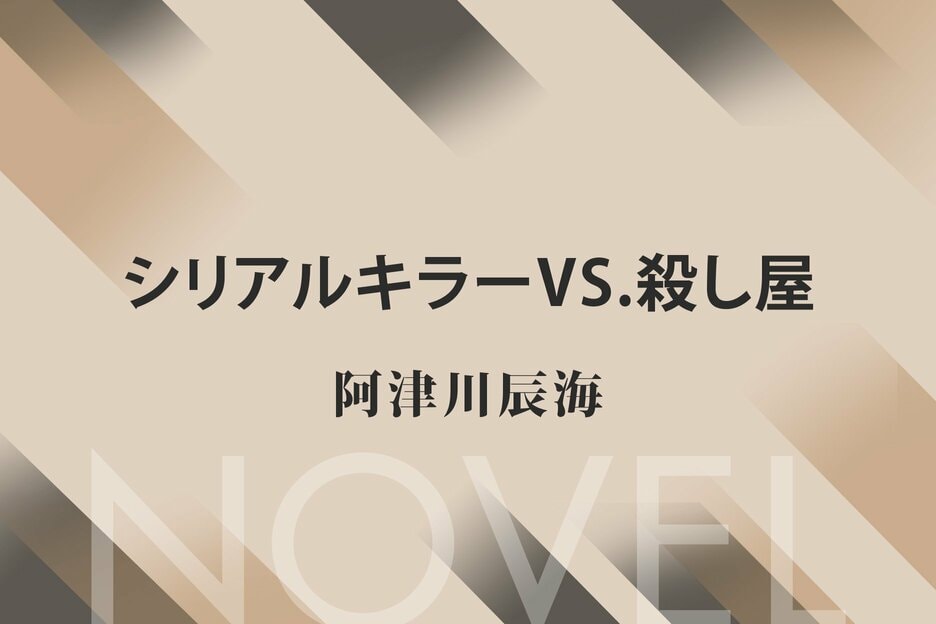1
背後からパン、と軽い破裂音がした。
おれは懐に手を突っ込み、鉄線を握りながら振り返った。
クラッカーの紙テープを頭に載せた客が、きょとんとした間抜け面を見せていた。
十名以上の従業員たちがその客を取り囲んで、嘘くさいまでの笑顔を向ける。
「おめでとうございます! あなたは、当店一万人目のお客様です!」
客も、それでようやく、事情が分かったらしく、照れくさいやら嬉しいやら、脂下がった笑みを浮かべて、従業員の手から花束を受け取る。彼は驚きました、とか、ラッキー、とか、意味のない言葉を矢継ぎ早に発した。無料券やらクーポン券やら、ちょっとした贈り物をいくつももらっている。これから記念撮影もするという。
「綺羅君、いいの。カメラマンの出番じゃない」
隣にいるエビスがニヤニヤ笑う。
そのあだ名通り、丸々と幸せそうに太った男で、胴はおれの二倍もあるだろう。耳たぶが大きすぎる耳は、餃子の皮のひだに似ていた。
おれは顔をしかめ、鉄線から手を離した。
「……今は、カメラマンじゃ、ありませんから」
「そうだねえ」
おれは本業のカメラマンとして働く傍ら、日本政府のご意向に従ってある副業に勤しんでいる。「綺羅星也」という名前で殺し屋をやっているのだ。今は「カメラマン・水野」としてではなく、「殺し屋・綺羅」としてエビスに会っている。
エビスは手にしていた鍵で扉を開けた。室内に入って靴を脱ぎ、手早く服を脱いでいく。
都内にある個室サウナの一室である。靴脱ぎと脱衣所を抜けた先には、ロウリュによって約百度まで温度を上げられるサウナ室と、水温十度以下の水風呂、デッキチェア二脚が並んでいる。
一枠九十分、完全予約制で、エビスの名義で予約を入れてもらっている。定員は二名。防音性も高く、密談にはもってこいの環境である。
加えて、ここでは「殺しの道具」を全て手放さなければならない。エビスにとっては、大きな安心材料なのだろう。
「じゃ、先入ってるね」
おれがワイシャツのボタンに手をかけるより早く、エビスはサウナ室に入って行った。サウナハットに自前のサウナマットのフル装備である。
「どうぞ」
どのみち、エビスの方が入っている時間は長い。
おれもさっさと服を脱ぎ、カバンからサウナハットを取り出す。
「さっきのことだけどさ」
サウナ室に入るなり、エビスが口を開いた。
「危なかったよね。あと一つずれただけで、『一万人目のお客様』になっていた」
「写真なんて撮られるわけにいきませんからね」
「さっきさ、ちょっと計算してたんだよ」
「計算、ですか」
「このサウナのオープン日は大体一年前。サウナ室は四つ。枠は九十分に清掃を含めた三十分のインターバルだから、一部屋につき、営業時間内に六回ローテーションを回せる」
「ふむ」
「一度の定員は二名だから、一日フル稼働すると、二人×四部屋×六ローテで最大四十八人の利用が見込める。定休日は月曜だけだから、週に六日。すると一週間には——」
「二百八十八」
「綺羅君も計算は早いね。つまり、フル稼働ならおおむね三十五週で目標達成出来る」
「でも、そうは上手くいかないでしょう。何度か使ってますけど、そんなに流行っている気もしませんし」
「だからちょうど一年後の、今日になったんだろうね」
エビスはニコニコと笑う。
「ああいうのって、九千九百九十人目くらいから、ソワソワしているんだろうね。団体客が来たらどうしよう……とか」
「個室サウナなんだから、それはないでしょう」
「じゃ、あれか。ぼくたちが受付した時からソワソワしてたわけだ」
「二十時から予約の誰かが、『一万人目』になるって計算でしょうからね。四部屋のうちの誰かが栄誉を受ける」
その「一万人候補」の全員が、今では全員裸になって、灼熱の環境下で汗を流していると思うと、なんだか笑える。
「うわ、そう考えると悔しくなってくるなあ。ぼくに鍵を渡しながら、『惜しかったなあ』とか思ってたわけでしょ? マスクの下でニヤニヤ笑ってたわけだ……」
「笑ってたとは限らないでしょう」
巨体を汗でてらてらと光らせた男は、ぶつぶつと口を動かすが、こういう時の彼は、怒っているわけではない。ただ、頭が動くのに任せているだけだ。
こういう時は、適当に相槌を打ちながら、しばらく聞き流しておけばいいとおれは知っている。
「で」エビスは唐突に言った。「次のターゲットの話だけど」
「はい」
全身を耳にして、居住まいを正した。既に八分はサウナ室の中にいる。かなりキツいが、ようやく本題に入ったのだから聞かなければならない。
殺し屋の仕事は、当然依頼に基づいて発生する。だが、殺し屋当人が依頼人と直接会ってしまうと、互いが互いの脅迫者に転じるとか、相手がおれの口を塞ごうとするとか、種々のトラブルが想像される。
そこで、仲介業者の出番というわけだ。
以前使っていた仲介業者は、諸事情により使えなくなり、一時は引退も考えた。ところが裏業界で名高い「エビス」の指名を受け、彼から直々に依頼を引き受けることが出来るようになった。仲介料は前より多くとられるが、信頼の置ける相手だ。それで、引退については考え直した。
エビスの唯一の悪癖は、サウナが好きだということだ。依頼人と話す時はまた別の空間を用意するらしいが、殺し屋の方は「いける口」であれば必ずサウナに付き合わされる。元々、サウナはそんなに得意ではないが、最近は付き合ってくれる人がいないと寂しそうにしていたので、おれの方から折れた。
だから、おれがサウナハットを買ったのは、趣味というより、実益を取ってのことだ。頭を熱から守っているだけで、だいぶマシになる。
エビスが淡々と続ける。
「五十嵐将志、三十六歳。世田谷区三軒茶屋の一軒家に住んでいるフリーターだ。写真は後で見せる」
もちろん、サウナ室に持ち込めるわけがないからだ。今はデータを頭に叩き込むのが重要である。
「フリーター、ですか」
「ああ。古書店でバイトをしている。職場は神保町だ」
「家は」
「両親のものだ。早くに他界している」
「三十六で、二親とも亡くなっているんですか」
「言っておくが、事件性はない。八年前に交通事故で亡くなった」
今は一人暮らし、外出はバイトの時に限る……とひとまず考えてよさそうだ。
「どうして依頼人はその男を殺したいんでしょうね」
「動機は問わない。うちもそういう方針でやっているからね」
おれは頷いた。おれ自身、今のところは通り一遍の疑問として口にしたに過ぎない。
もしエビスは依頼人から「本当のところ」を聞いていたとしても、おれに伝えることはない。無用のトラブルを避けるためだし、おれが余計な私情を挟むことを防ぐ意図もある。
「ただ、今回はオプションがついている。それがヒントになるかもしれない」
「オプション、ですか……」
大半の依頼人は、ターゲットの殺害という結果だけを求めるが、たまに、殺害方法や日付を指定する依頼人もいる。たとえば、妻が夫を殺してほしいと依頼してきた場合に、「何月何日の夜七時から九時の間に殺してほしい」とオプションをつける。これは、夫が殺されるとその妻が当然疑われるから、アリバイを作っておきたいというわけだ。
こういう依頼に応えるのも、プロの仕事だ。ただし、オプションに対応するための追加料金を取ることにしている。
「一か月後の七月二十五日……その日までに殺害してくれ、ということだ」
「締め切り付き……ですが、時間的な余裕はありそうですね」
以前の業者のところでは、三日後の殺害を依頼されたこともある。あまり余裕がないと、こちらも十分な計画を立てることが出来ない。
「通常の一に上乗せで、これだけ払ってくれるそうだよ」
エビスは指を三本立てた。
一三〇〇万、か。
二割をエビスに取られるとはいえ、悪い話ではない。
「一度、ターゲットの行動確認をさせてください」
「依頼を引き受けるのはその後?」
「ええ。極端な話、刑務所にでも入ってるっていうなら、一か月以内に殺害するのはムリです」
「なるほど。さっすが、綺羅君は慎重だねえ。高額の報酬でも揺らがないか」
「すみません」
「謝らなくていい。それも君の美徳だ」
おれがサウナ室に入ってから十三分。ようやくエビスが立ち上がる。
「水風呂に行くよ」
「二分後に出ます」
エビスが入った後は、水風呂の水位が下がる。時間を置いた方が、いい水風呂にありつける。
2
それから三日間、五十嵐の尾行を続けた。
がっしりとした体型の男で、スクエアフレームの紺色のメガネが特徴的だ。ジーンズにポロシャツという、素っ気ない服装で家から出てきた。髪はもじゃもじゃで、癖っ毛のようだ。何度も手櫛で直そうとしているが、まとまらないようだ。
写真とも完全に一致する。
SNSでは、日々食べたものや読んだ本などの投稿が主である。もはや半ば放置されているFacebookのアカウントからは、中学、高校と柔道部に所属していたことが分かった。おれよりも一回り体が大きい。鉄線やピアノ線を武器にするおれにとって、体格差は大きな壁ではないが、格闘になれば不利だろう。
隙を突いて、殺す方法。
それを編み出さねばならない。
通勤ラッシュが少し落ち着いた十一時頃に、五十嵐は自宅を出発して、三軒茶屋駅から田園都市線に乗り込む。田園都市線から直通運転する半蔵門線の駅、神保町で降りる。早めのランチに出てきた会社員や、周辺の大学に通う大学生たちで、町はそれなりに賑わっている。
彼は十一時四十分頃に古書店「うさみ堂」に着くと、店主と交代し、二十時の閉店時間まで一人で店を守る。店主は五十嵐の父親と幼馴染で、内気で人との関わりを好まない五十嵐をもともと心配していて、交通事故で彼の両親が亡くなったのをきっかけに、店で雇ったらしい。——というのは、「うさみ堂」店主が他の古書店の店主と喫茶店で話した時に、漏らした愚痴である。
店番をしている間、五十嵐は小さなカウンターの中で、大きな体を丸め、いつも何かしら本を読んでいた。
——一体誰が、こんな人畜無害そうな男を殺そうとするのだろうか?
おれには、そこが疑問だった。
四日目の夜のことである。五十嵐は帰宅途中の路上で、通りがかりの男性に因縁をつけられていた。
すれ違う時、五十嵐と男の体が軽くぶつかったのだ。男は顔を真っ赤にしていて、酔っ払っているのは明らかだった。
「謝れよ、てめえ!」
「ぶ、ぶつかった時、謝りましたよ」
「聞こえねえんだよ。聞こえるように喋れ!」
男は手に持っていたカバンで五十嵐を殴った。ビジネスバッグの角で殴りつけている。中にパソコンでも入っていたら、立派な凶器だ。暴行、傷害。おれはよっぽど割って入ろうかと思ったが、ターゲットの前で目立つわけにはいかなかった。
五十嵐は哀れなほど謝っていた。殴られている方が謝るいわれなどないのに、あまりに全面降伏の態で謝るものだから、男の方も最後は気勢を削がれたらしく、「気をつけろ」ともう一度怒鳴ってから、しゃがみ込んでいる五十嵐を解放した。
彼の態度、声音、生き方。その全てが、どことなく哀れを誘った。一種の人間を怒らせるタイプの哀れさである。だが、殺す理由にはならないだろう。
だが、それももはやどうでもいい。依頼人が望むことを、遂行する。それがおれの仕事だった。
五十嵐はふらふらとした足取りで立ち上がったが、三歩目にはいつもの歩調を取り戻していた。ひとまず、脳震盪などの心配もなさそうだ。
ターゲットがおれ以外の要因で死んだ場合は、金を受け取るわけにはいかない。つまらない結末にならずに良かった。
それに、今回は期日の指定がついている。
一か月以内に殺害したことを証明するため、殺害直後に日付を証明出来る形で死体の写真を撮ることが要求されている。日付が表示されるデジタル時計とその日の新聞でも傍に置いておけば、問題ないだろう。正確な日時ではなく、日付だけが求められるなら、充分なはずだ。あとは、警察に見つかりやすい所に死体を放置しておけば、翌日には事件報道が出るはずだ。
アフターサービスも欠かさない。プロの殺し屋として当然の姿勢だ。
『ご依頼のスーツ、クリーニングに出しておきます』
ダークウェブのSNSを通じて、エビスのアカウントに連絡をしておく。スーツだのクリーニングだというのは、あらかじめ決めておいた符牒だ。
メッセージにはすぐ既読がついた。『了解』の一言だけ返信があった。
おれもエビスもメッセージを消したところで、異変に気付いた。
前を歩く五十嵐が、きょろきょろと辺りを見回している。
夜十時、三軒茶屋駅からも離れた路地。街灯の下で、五十嵐は足を止めていた。
——尾行に気付かれたか?
尾行技術には自信があった。四日間、毎日服装を変え、サングラスなどの変装道具も変えているので、顔を覚えられているとは思わない。
五十嵐の向こうから、家族連れが迫っていた。五、六歳ぐらいの男の子が、駆けてきて、背後から母親らしき女性に呼び止められている。
五十嵐はこちらを振り向き、おれに視線を向けて歩いてきた。
おれはわずかに緊張する。しかし、こういう時に変な反応をするのはもっとまずい。殺す前から五十嵐に警戒されては困るのだ。
殺しの道具は常に携帯している。この場で殺すことも可能だが、今は目撃者がいる。手を出すのは得策ではない。
おれは歩調を変えずに、五十嵐に向けて歩く。
五十嵐はおれの顔をじろじろと見ていた。
——なんだ?
今までのターゲットと、どこか違う。
背中に冷や汗が流れるのを感じた。自分は何かミスを犯したのだろうか。五十嵐の視線は、おれの輪郭をなぞるかのように執拗で、遠慮がなかった。
すれ違ってようやく、五十嵐の視線から解放される。家族連れが通り過ぎた後も、イヤな感じは消えなかった。
振り返らずに歩き続けた。背後の状況を確認したいのはやまやまだったが、五十嵐がまだおれを見ていたら、と思うと、そんなリスクを取ることは出来ない。
より人気のない道に入った。
もういいだろうか。今日の尾行は切り上げて、帰ろう——そう思った時、近くで車が停まる音がした。
背後から、性急な足取りの足音がする。
振り返ろうとした瞬間、耳元で「ごめんなさい」という声が聞こえた。腰のあたりに何かが炸裂するような痛みが走る。意識がスパークし、明滅する視界に五十嵐の顔が茫と浮かんだ。
暗転。
(つづく)