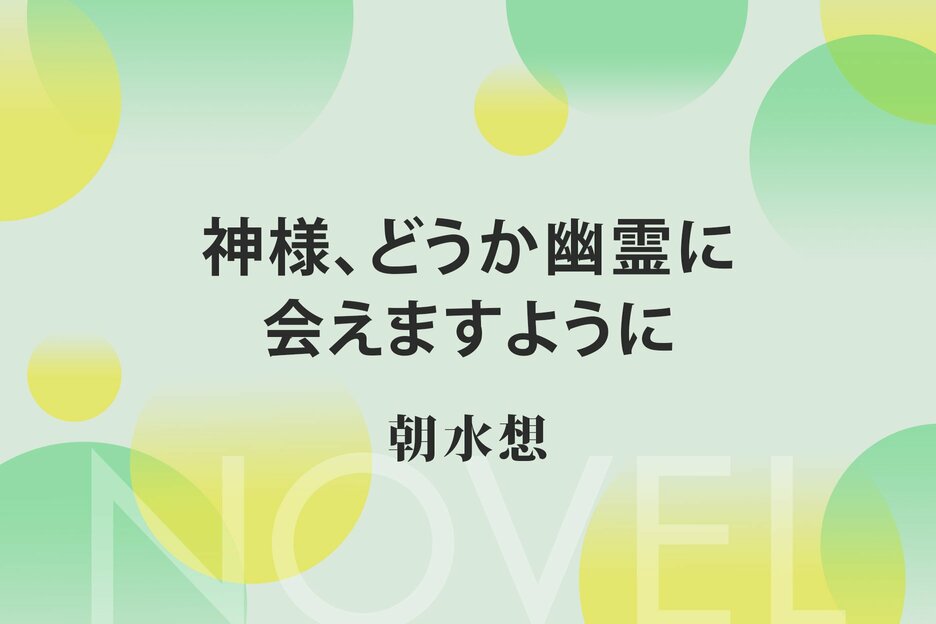誉人である礼香が、夫に会って聞きたいこととは何なのか。
最初は、夫を殺した犯人を知りたいのだと思った。
次に、夫を殺したのは礼香であり、太一の花火アイデアを知りたいのだと思った。
どちらも確証が持てない。
疑問の中心にいる人物に思い当たる。太一だ。
解決の糸口になるのは、おそらく太一という人間だ。この男が何を考え、どんな事情を抱えていたのか。
しかし本人はもう死んでいる。直接確認することはできない。
どうすればいいのかしばらく考える。同僚の目に映る腕のいい花火職人としてではなく、もっと深い部分を知る人間は、礼香以外にいないか。
考えた末に俺は、ひとつの答えに達する。それは家族。娘の花だ。
数日後、花が一人で丸来煙火店に帰省してきた。
「ただいまあ。お母さん?」
母屋の二階にある玄関口に現れた花は、二十代半ばの、ふくよかで健康的な体つきをしている娘だった。長く豊かな髪を無造作にまとめて、Tシャツにジーンズのカジュアルな服装だ。
俺は猫のシロの姿で、玄関先に出向き、にゃあと鳴いた。後ろから礼香も来る。
「どうしたのよ、急に帰ってくるなんて」
「ちょっとね。お母さん猫飼ってるの?」
「飼っているんじゃないけど、たまに遊びに来るの。名前はシロ」
花は居間に行くと、仏壇に手を合わせ、「事件のこと、何か進展あった?」と母親に聞いた。礼香は黙って首を横に振る。花は「そっかあ」と暗い顔をした。
「隆司さんと何かあったの」
「旦那と? 何もないって。たださ、なんとなく、アルバムが見たくなってさ」
花はちゃぶ台のそばに座り、母親の出したお茶をすすった。
昨日の夜、俺は終電で世田谷に戻り、花のマンションまで出向いた。深夜に枕元に立ち、額に指をあてて「お前は実家のアルバムが見たくなる」と唱えたのだ。したくなる、という程度ではあるが、人間の行動に働きかけることができる。神としての数少ない力のひとつだ。アルバムを開けば、人は思い出を語りだすはずである。
「ねえ、アルバムあったよね」
花が立ち上がり押入れを開けた。
「今、お父さんのことを思い出すと辛いでしょ」
礼香が止めに入ったが、「う~ん、直感? でなんかそうしたほうがいい気がするの」と花は取り合わない。俺が枕元で唱えたことは、強い衝動となる。俺も押入れの上に飛び乗り、にゃんと鳴く。
「ほら、シロもそのほうがいいって」
礼香はそれ以上言わず、二人はちゃぶ台でアルバムを開いた。俺は花のひざに乗り、それを覗き込む。温かくて思わずウトウトと眠りそうになり、慌てて目を開いた。猫に化ければ、猫なりの習性になる。人になったり、猫になったり、F市と世田谷を行き来したりしているのだから、疲れもする。
アルバムは礼香と太一の結婚式の写真から始まっていた。和装の二人はどこかよそよそしい。
「二人ともド緊張してるね」
「お見合いだったし、結婚式までほとんど会ってなかったから」
赤ちゃんを抱いている夫婦の写真、お食い初めや、七五三の写真といった記念の家族写真がならぶ。どれも太一は真顔であり、礼香もうっすら笑っているかどうかという感じだった。
「こう見ると、お父さんって笑ってないわ~」
「無口だったしね」
「でも優しかったけど」
花が遠い目になる。
「覚えてる? 私が小三の時さ、太ってるっていじめられてたじゃん。お父さん、それ知っていじめっ子のことボコボコにしたよね」
「いじめより、そっちの暴力のほうが問題になっちゃってね。お父さん、思い込んだら一直線だから」
「でも、あれからいじめられなくなった。暴力は良くないし恥ずかしかったけど……嬉しかった」
母娘は穏やかに笑みをかわした。太一は今、二人のなかで生きているんだろう。俺がサヨコを思い出すとき、そうであるように。
「ああ、この写真。これはちょっとお父さん笑ってるね」
礼香が一枚の写真を指さす。それは三人がそれぞれ、短冊をこちらに見せているものだった。おそらく七夕の写真だろう。花は三歳くらいの年齢に見えた。
「この短冊。私はまだ字が書けないから、お母さんが書いてくれたんだよね」
花の持っている短冊には、きれいな大人の字で「おかしやさんになりたいです」と書いてある。
「あ、これ覚えてる。数字だけ書けたから、自分の名前を数字で書いたの。は、な」
花が写真の短冊の「87」と書いた部分を指さす。その字だけ、みみずがのたくったようにへたくそだ。そうね、私たちの名前も書いてくれたよね、と礼香も頷く。
「お父さんは太一の『1』、お母さんは礼香の『れい』で『0』だったね」
写真の中に、太一と年配の男が写っているものがいくつかあった。揃いの法被を着ているから太一の父親だろう。それを見た花が少し声を落とした。
「前から聞きたかったんだけどさ……。お母さんって、辛くなかったの」
「何が」
「おじいちゃん、孫の私には甘かったけど、お母さんにはきつかったじゃん。料理の味付けにも厳しかったし。お母さんも花火好きだったのに、女は花火師になれんって関わらせてくれなくて。お父さんもおじいちゃんには頭が上がらなかったし」
「だって、お母さんは丸来家の嫁だもの」
礼香がさらりと言った。
「丸来家のやり方に従うのが当たり前でしょ」
「昔の考え方なんだろうけど、私には無理。それに、好きな人のためだったら頑張れるけど、お母さん、お父さんと好き合って結婚したわけじゃないんでしょ」
「夫婦の関係は、恋愛だけじゃないよ。目指す方向が一緒なら、うまくやっていけるものなの。お父さんとは、そうだな、同志みたいな感じかな。戦友とか」
「そっか。……二人ともあまりしゃべらなかったけど、心の底で信じ合ってたの、私も感じてたよ」
花が言う。社員から見ればビジネスライクで不仲に見えたようだが、決してそういうわけではなかったらしい。
花が少し迷った後、えいや、という感じで切り出す。
「あともう一つ気になってたの。もしかして、跡継ぎの婿を取りたかったんじゃないかって。私、サラリーマンの隆司と結婚しちゃったし、嫁に行っちゃったし……」
「だって、花はそうしたかったんでしょう? ならいいじゃない」
「でも、お母さんは家のために尽くしているのに」
礼香はゆっくりと首を横に振り、「そうじゃないよ」とつぶやいた。
「時代もあったと思う。でもね、私は結局こういう生き方しかできなかった。自分で何かをやろうっていうエネルギッシュなタイプじゃなかったから。花火は好きだったし、お父さんを支えるのはやりがいがあったよ。でも、その生き方を花に強制しようとは思わない。好きに生きたらいいよ。花火の仕事をしたいならそうすればいいし、そうじゃなければ無理に手伝う必要はない。私の分まで自由に生きてくれればいいと思ってる」
「お母さん……」
花は声を詰まらせた。
「お母さんも、もう自由だよ。おじいちゃんも、お父さんも、いないんだから」
今度は礼香が意表を突かれた。目を伏せて「そうだね」と短く返す。礼香が顔をゆがめる。今にも泣き出しそうな表情を見て、俺ははっとした。以前にかわした会話を思い出す。好きなものを数えた話をした時だ。「問題なのは、数でも深さでもなくて──」そう呟いて途切れた言葉。
アルバムの親子三人の七夕の写真。
礼香の本当の願いとは、もしかすると。
礼香と花が、一緒に夕飯を作り出したのを見て、俺は階段を下りた。階下は事務所だ。今は誰もいない。
猫の姿で、俺は太一の倒れていたあたりをうろうろと歩き回った。ワークデスクの上にひらりと飛び乗る。
太一の姿を想像する。このデスクと、西側の壁の間に太一は壁を向いて立っている。後ろから犯人が近づく。そして後頭部を殴り、太一は床に倒れる。
壁をよく眺める。白壁にはあちこちに細かなひびが入っている。そのほとんどは、天井と平行に横向きに入っていた。だが、太一が立っていたちょうど頭のあたりの位置の壁にあるひびは、ある一点を中心にして放射状に入っているものがある。
もしかすると、と俺は思い立ち、ジャンプして天井の梁に乗ろうとした。
何度か飛ぶが、梁は高くてなかなか届かない。
俺はレプリカの花火玉が並んでいる棚の上に飛び乗る。そこから後ろ足を伸ばし、梁に向けて跳躍した。
勢いで、棚の上の花火玉が床に転がる。ゴン、と鈍い音がした。
やっと梁の上に立つ。上から事務所の様子を見ながら、梁を歩く。梁は焦げ茶色をしていたが、上はほこりが積もって白くなっていた。ちょうど長方形の部屋の、東西の長い辺の真ん中あたりで足を止めた。
天井の梁は、縦方向と横方向の梁同士が、何本か直角に交わっている。俺が立っている真ん中あたりでも同じように交差していた。
思った通りだ。
その交差部分の十センチほどが、ほこりをかぶっていない。
顔を近づけて、よく観察する。うっすらと、ひっかき傷の跡があった。
二階へと通じる階段から、礼香が顔を出した。
「なんか音がすると思ったら……。お前、なんでそんなところにいるの」
俺はにゃおう、と返事をする。
「待ってて。今下ろしてやるから」
礼香は脚立を出して俺をつかまえ、床にそっと置く。
「花火玉もお前のしわざね。まったく」
落ちたのは十号サイズのものだった。礼香は持ち上げようとしてよろめいた。重さは八キロ以上ある、と山尾が話していた。苦労しながら、頭上にある棚の上に花火玉を戻す。
「いたずらはだめよ」
俺はにゃあと返事をする。
あとひとつ、確認しなくてはならないことがある。そのためには人間の姿にならなければ。俺は猫の姿のまま礼香と花が寝静まるのを待った。うっかり、俺も眠りこけてしまい、気が付いたら夜が明けかけている。慌てて階下の事務所へと下り、イナリ青年の姿に変わる。
誰もいない事務所で、俺は棚の上の花火玉を手に取る。一番端にある、直径三十センチの十号玉である。レプリカとはいえ、本物と同じ重量に仕上げてあるのでずっしりと重い。
中身は火薬ではないが、外見は本物と全く同じ。クラフト紙がぐるりと貼ってあり、花火の名前が太一の筆跡で書き込まれている。一見、普通の花火玉に見える。
俺は玉の周りを手で触った。クラフト紙は均等に貼る必要がある。微妙に感触がちがうところがあった。花火の名前が書かれた場所の、ちょうど裏側のあたりだ。
俺は花火玉をワークデスクの上に置く。
感触が違うあたりを手で何度か触る。やはり、そうだ。ここだけ周囲に比べてクラフト紙が少しだけ厚い。
普通の人間ならまったく分からないほどの厚みだ。
花火職人でなければ、見抜くことはできない。
俺はピンセットを使って、クラフト紙を一枚一枚はがした。
「何をしているの」
声の方を見れば、礼香が青白い顔をして立っている。
「凶器はここにあったんだな」
俺は、クラフト紙をはがした花火玉を、礼香の方へ向けた。
そこには、血痕が点々と残っていた。
「この血は、太一のものだろう」
「あなたは一体、何者なの」
礼香の声が震える。
「安心しろ。俺はおぬしの味方だ」
何しろ、礼香は誉人で、俺はその願いを叶える神なのだから。
ただ、叶えてやるには事実を知らなくてはならない。
「違う……。私は、殺していない」
礼香が怯えた目でこちらを見る。俺は静かに続けた。
「この狭い場所で、花火玉を太一の後頭部めがけて振り下ろすのは無理だ。重すぎて勢いをつけられないし、丸くて持ちにくい。女なら、持ち上げるのすら難しいだろう。だが、これが凶器であることは、血痕から見てあきらかだ。それなら、花火玉をどうやって太一の後頭部にぶつけたのか?」
俺は花火玉の頭にある、竜頭という縄でできた輪っかを指さす。
「花火玉に勢いをつけるためには、竜頭に紐を通して、振り子のようにすればいい。梁に紐をかけ、その先に花火玉をくくりつければ、大きな振り子が完成する。梁が直角に交わったところを使えば、大きくずれることがない。
梁には、紐をかけた跡も残っていた。それに、振り子にした花火玉が、勢い余って壁に当たってできたひびも。
あとは、何度かその振り子を動かし、軌道を確認して、そこに立っていればいい。勢いのついた花火玉が後頭部を強打し、死ぬことができる」
礼香が目をぎゅっとつぶって顔をそむける。
「そんな手間をかけて人を殺す強盗はいない。脅したとしても、殺したい人間を軌道上に立たせるのも無理だ。だから、太一は自殺としか考えられない」
礼香がはじかれたように顔を上げる。
「他殺と思われたのは、振り子にした紐と花火玉を回収した人間がいたからだ。それをしたのは、おぬしだな。夫婦で協力してやったことか」
礼香は即座に首を横に振る。
「違う。私は、何も知らなかったの。……あの日、飲み会から帰ってきて、外階段から二階の自宅へ上がった。でも、夫の姿がどこにもない。おかしいと思って二階から一階の事務所に降りたら、夫はもう」
礼香が手で顔を覆った。
「すると、こういうことだな。太一は全員が飲み会に出かけた後、自分で事務所を荒らして強盗が入ったように見せかけた。それから妻の携帯にメッセージを送った後、花火玉の振り子を使って自殺をする。それをあんたが最初に見つけ、花火玉と紐を片付けた後、思い切り悲鳴を上げる。駆けつけた他人は、太一が強盗に殺されたように見える」
礼香は話すことができなくなったように、黙り込んだ。
「俺はこれを誰にもしゃべるつもりはない。ただ、真実を知りたい」
「……何のために?」
「おぬしの願いを叶えるためだ」
「何、それ。意味が分からない」
「わからんでもいい。俺に話してくれないなら、警察か何かで取り調べを受けることになるだけだ」
「分かった、話す。話すから、誰にも知らせないで」
あきらめと決意を含んだ目で、俺を見る。
「なぜ自殺を他殺に見せかけようとしたんだ」
「夫の意図に、すぐに気が付いたから」
礼香が大きなため息をつく。
「あの日の何日か前、夫が私に相談してきたの。自分が入っている生命保険の契約書を持ってきてね。不慮の事故か、他殺に見せかけて自殺ができないだろうかって。そうすれば、自分にかけた保険金が下りるだろ、と。
冗談言わないで、って私は怒った。でもあの人は思い込んだら頑固な人で、花火の事故でも起こすか、強盗に殺されたことにすればいい、って言い張った。私も譲らなかった。命と引き換えに保険金をもらうなんて、ばかな考えだって。花火の事故があれば、会社の評判に傷がつく。強盗に殺されたように見せかけるなんて、素人にできっこないって。あの人は黙り込んだ。すっかりあきらめたんだと思っていたのに」
その時の言い争いは寮まで聞こえ、酒巻は夫婦喧嘩をしているものと思い込んだ。
一方で太一は強盗に殺されたように見せかける方法を考えた。その欠点は、最後のピースを誰かに埋めてもらわなければならない事だ。
「夫が死んでいるのを見て、私は叫びだしたくなる自分の口を、必死に手で押さえた。命を懸けてまで夫がやろうとしたことを、完成させるために、耐えた。覚悟が決まったら、急に頭が冴えた。震える手で、紐をナイフで切ったわ。花火玉がなくなったら、きっと怪しまれる。それならこの紐と花火玉は、隠すんじゃなく、人に気が付かれなければいいんだと思った。花火玉には血痕がついていたから、クラフト紙を貼り付けて隠し、麻紐は花火用のロープが入った段ボールに入れる。それだけで、強盗に襲われて殺された現場が出来上がる。犯人の侵入と逃走経路が必要だと気が付いて、最後に内側から鍵を開けておいた。それで犯人は顔見知りだと警察に疑われてしまった。よく考えれば、侵入経路として窓を開けておけばよかったんだけど、そこまで頭がまわらなかった」
必ず妻が筋書きを分かってくれると信じて、夫は自殺を図った。
「花火玉と麻紐をすぐ処分しなかったのはなんでだ」
礼香は皮肉っぽく口角を上げた。
「私は警察に疑われてた。当然よ、保険金の受取人は私。夫が死んでもっとも得をする人間だったもの。アリバイがあるとはいっても、誰かと共謀して夫を殺した疑いもあるでしょう。だから、何かを処分したり隠したりするのは目立ちすぎる。特に花火玉のレプリカは数が少なくて、なくなれば怪しまれる。麻紐はこの間の試し打ちの時に、燃やしてしまったけど」
試し打ちの時に、酒巻が新品のはずなのに切れた麻紐があると言っていたことを思い出した。あれが太一が自殺の時に使った麻紐に違いない。
「花火玉もほとぼりが冷めたころに処分するつもりだった」
それなのに、俺が花火玉の秘密に気が付いてしまった。
「なぜ、太一は自殺してまで保険金をもらうような真似を?」
「あなたは、自分よりも会社を大事にするような生き方が分かると言ったわね」
「そういう人間を多く見てきたというだけだが」
「コンテストで何度も優勝して、会社として知名度も上がってきていた。それで社員も増やし、社員寮を建て、工場も増築した矢先にコロナウイルスが世界中に広がった。花火大会は軒並み中止になって、仕事がなくなったの。借金だけ残して。投資が完全に裏目に出た。銀行の融資を申し込んだけれど、昔から付き合いのある信用金庫にさえ断られたわ。
私と夫は、花火を作る仕事を誇りにしていた。希望の灯をつなぐ使命を大事にしていた。七代続いたこの会社を、私たちの代で終わりにするなんて、夫は耐えられなかったんだと思う。自分の命と引き換えにするくらいに」
礼香はその場にしゃがみこんだ。
「お願い。このことは黙っていてほしいの、今は。保険金をつぎ込まなければ、会社は倒産してしまう」
すがるような目で、礼香は俺を見上げた。
「誰にも言わないと言っただろう。俺は警察でも、保険会社でもないからな。だが」
サヨコと美衣奈の姿を思い出す。死に別れる直前に、分かり合えた親娘だった。
それはお互い、本当のことを話したからだ。
「娘の花には、いつか本当のことを話したほうがいいだろう。自分の父親が、どんな最期を迎えたのかを知る権利があるからな」
「そうね。……あなたの言うとおり。分かったわ」
礼香が力なく頷く。
「私は、あの人に死んでほしくなかった。私が死にたかったくらいよ。花火職人たちは、夫を尊敬していた。夫が残れば、職人たちだってきっと辞めなかったのに」
「おぬしが死んだら、誰が花火のアイデアを考えるんだ?」
礼香が目を見開いた。
「なぜ、それを? あなたは、一体」
「悪いが、アイデア小屋の中のスケッチを見させてもらった。違和感を強く感じたんだ。字だよ。花火玉に書いてある太一の字じゃなかった。どのスケッチも、几帳面で優しい字だ。おぬしが俺に間違えて手渡した、好きなもののメモと同じ字だと気が付いたんだ」
礼香は言葉もなく、うなだれた。
「太一の父親が、女の花火師を認めなかったから隠していたのか?」
「それもある。……そもそも花火は昔から男の世界。夫が発表したほうが世間に認められやすかったの。お義父さんに見つからないように、たまに深夜に家を抜け出して、アイデア小屋にスケッチを残していた。昼間に夫がそれを確認して、自分のアイデアとして花火を製作する。私は表向きには花火製作に関われなかったけど、夫と共同で花火を作れることに満足していた。それなのに」
なるほど、夜中に抜け出す事に社員寮の酒巻が気づき、「外に男がいる」と勘違いしたわけか。
礼香は首を横に振り、独り言のようにつぶやく。
「どうして、こんなことに」
「残念だが悔やんでも太一は帰ってこない。おぬしには信じるものがあるではないか。それを信じぬくことだ。さすれば自ずと道が分かる。信念がぐらつく者は、いつも悩むもの」
「自分が信じること……」
礼香がつぶやく。目に力が宿る。
「ひとつしかない」
俺はこれですべてが分かった。
誉人が何を夫に聞きたいのか。それに対する夫の答えは何かを。
礼香が朝もやのなかを歩いてくる。
丸来煙火店のそばにある、清らかな川の河川敷だ。朝の散歩が、礼香の日課だ。
朝日が出る前の淡い光をまとった乳白色の霧に、礼香は見えたり隠れたりする。
それを俺は待ち構えている。
俺は太一の姿に化けている。正確には、太一の幽霊として。
狐に花火師としてインタビューを受ける太一の動画を見せてもらい、話し方、体の動き、手で耳の後ろをかく癖、すべてを真似ている。
礼香がこちらに気が付き、三メートルほど手前で立ち止まった。
礼香は口を開いたまま、声が出せずにいる。俺は待った。
やっと「あいた、かった」と震える声がきこえた。
「すまなかった」
俺ははっきりと言う。
「お前の言う事を聞かず、死んでしまって」
礼香は首を横に振った。
「あなたと同じ立場なら、私もそうした」
一歩、彼女が近づく。
「あなたに、聞きたいことがあるの。とても大事な事よ」
俺は頷いた。
「私が花火のアイデアを作り、あなたが完璧な花火玉に仕上げ、会社は大きくなった。でも、あなたがいない今、社員の心が離れつつあるの。だから私がアイデアを作っていたことを、皆に伝えようと思う。これからも丸来は新作が発表できるっていう事実を。
でも、あなたはそれを許してくれるのか、どうしても聞きたかった。丸来太一の裏側で考えていた人間がいたなんて、丸来の歴史に泥を塗ることになるんじゃないかって」
丸来太一がきっと言うであろうことを、俺は代弁する。
「俺が作る花火には、印がついていただろう」
「丸来の、丸印ね」
「あれは、丸じゃない。数字だ。ゼロ、つまり、れい。礼香の『れい』だよ。昔、花が俺たちの名前を書く時、数字を書いたよな。それと同じ」
「え……」
アルバムの七夕の写真には、それぞれの短冊に数字が書いてあった。
花は「87」、太一は「1」、礼香は「0」。
太一の作った花火に書かれていた印はきれいな丸ではなく、ひしゃげていた。それは丸ではなく「0」だったからだと気が付いた。
「俺はとっくに、あの花火は礼香のものだと思って印をつけていたんだ。それをみんなにちゃんと知らせる時がきただけのこと。気にすることはない」
「でも……。私は女で」
「花火職人の世界が男中心だったのは、昔の話だ。今は、女だろうが男だろうが、いい花火を作れば認められるはず。俺の技術は、社員の奴らに教えた。お前の花火のアイデアを、きっと形にしてくれる」
俺は向かい合った礼香の肩を、両手でつかんだ。
「すまなかった。お前が花火を考えていてくれたことも、俺の自殺を殺されたことにしてくれたことも、ずっと心のうちにしまっているのは、辛かったろう」
礼香の目が揺れ動いたかと思うと、大粒の涙があふれだした。涙は頬をたたき、そのまま地面へとこぼれ落ちる。涙をぬぐうこともせず、顔を真っ赤にして、礼香は泣き続けた。
やっと嵐が来たのだ、と俺は思う。ずっと静けさを保ち続けていた心に穴があいた。
「勝手を言ってすまんが、どうか花と会社を宜しく頼む」
おそらく、太一本人が必ず言うであろうことを伝えた。そして、俺自身の言葉を付け加える。
「これからはお前の心のままに生きてくれ」
背を向けて俺は歩き出した。
「待って、待っ……」
慌てて礼香が追いかけてくる。俺は歩みを早める。
礼香の手が、太一の背中をつかもうとして、空を切った。勢いのついた礼香が、前のめりになり、ひざをついた。
太一の姿は一匹の白猫に変わっていた。
礼香はあっけにとられている。
猫になった俺はひらりと身をひるがえし、もやの向こうに消えた。
朝日が上がり、ひとすじ、明るい光を投げかける。後ろから、ありがとう、という礼香の声が聞こえた気がした。
「いやあ、本当にたまげたぜ」
酒巻が首を傾げながらつぶやいた。
「おかみさんが、花火のアイデアを作っていたなんてなあ」
俺の送迎会と称して、母屋の二階で飲み会を開いていた。大きなテーブルには、花と礼香が作った料理が並び、花火職人たちとパートの女性も加わってにぎやかにそれを囲む。それを太一の仏壇が見守っている。
「いまや、礼香は人気者だな」
皿に山盛りになっているかっぱえびせんを頬張りながら俺は答える。もちろん俺のリクエストだ。
礼香が花火のアイデアを作っていたことが公表されると、業界は騒然とした。太一の花火にアイデアを出していた天才がいた、それは妻だった。次にこれまでの受賞歴がどうなるかが問題になった。だが賞は会社名義で受賞しており、社内の人間の作品には間違いはないため、取り消しにはならなかった。
業界だけでなく、一般のメディアも数少ない才能ある女性花火職人をもてはやした。入社を希望する若者からの問い合わせも増えた。その中には女性もまじっていた。
俺のそばに礼香が近づいてきた。
「残念だわ、もう辞めてしまうなんて。故郷のご家族が呼んでいるなら、仕方がないけど。あなたならきっといい花火職人になれたのに。戻ってきてくれたら歓迎するわ」
「ほかにやることがあるからな。遠慮しておく」
俺のもとには、すぐに次の誉人が来るだろう。
「あなたは、会社を守ってそれで幸せなのかって聞いたわよね」
「やるべきことをやるのと、幸せは別の話だからな」
「わたしね、今、幸せなのかもしれない。好きな花火を、好きですって言えて」
礼香の周りを取り巻いていた、あの張り詰めた空気は消えていた。代わりに、もっとおだやかでやわらかい雰囲気をまとっている。
好きなことリストのメモを見た時、礼香は「問題なのは、数でも深さでもなくて──」と口ごもった。あの台詞は、好きなことを好きだと言えない事だ、と続いたのではないか。
サヨコは、好きなものを数えれば幸せが分かると言った。でも、数えることはできても、それを公表できない場合もあるのだと俺は知った。
想像するだけしかできないが、それはきっと辛いことに違いない。
「よかったな」
よかった。人間などどうなってもいいと最近まで思っていたのに、そう思った。
少し酔った山尾が、「おかみさん」と割って入ってきた。
「僕、感動しました。丸来の花火が、おかみさんと太一さんの合作だったなんて。太一さんの代わりにおかみさんの考えた花火、作りますんで任せてください」
「でも、あなた会社を辞めたいって──」
戸惑う礼香に向かって、山尾が胸を張った。
「辞めるのやめます! 俺は丸来の星になってみせます!」
「何言ってんだ、お前はまだその星も満足に作れないだろうが」
山尾の頭を軽くはたいて、酒巻が赤い顔をしてからんでくる。
「この酒巻が、おかみさんの斬新な花火を完璧に形にしてみせますよ。太一さんから受け継いだ技術でね」
自分の胸をどんと叩く。
「お前は、太一とはうまくいってなかったんじゃないのか」
俺の言葉に酒巻は面食らった後、豪快に笑った。
「太一さんは俺の酒癖を嫌ってたからなあ。でもよう、仕事とは別の話だ。俺は太一さんの技術を尊敬していたし、太一さんも俺の筋がいいのを見込んで教えてくれた。すげえ花火を作るっていう夢は同じだからな」
どこかで聞いた話だ、と思った。そうだ、礼香が花にこう言っていた。夫婦の関係は、恋愛だけじゃない。目指す方向が一緒なら、うまくやっていける。
礼香が二人に向かって頭を下げた。
「私は花火のアイデアを出しただけ。それを花火玉にする技術は持ち合わせていない。どうか、これからも丸来の花火を一緒に作ってください。お願いします」
「頭上げてください、おかみさん」
山尾と酒巻が、慌てて言う。
「それから、私は外に男を作ったりしていませんからね」
頭を上げた礼香がいたずらっぽく言うと、酒巻が「いやあ、すいません」と頭をかく。その場に自然に笑いが起こり、広がった。
稲荷神社の本殿の屋根に、俺と、弁財天と、狐が座っている。
俺は白い小袖に、紫の袴をつけた少年。弁財天は、やはり白い小袖に赤い袴、おかっぱ頭の少女だ。そして狐は狐。これが俺たちの本来の姿である。全員、この世のものではないので人間には見えない。
屋根はへの字になった流造りの檜皮葺で、俺たちはその頂あたりに腰かけていた。
月は半月で、天空にかかろうとしていた。歩いてすぐの場所にある河川敷は人でごった返しているだろうが、神社は静かだ。花火を見ようとするなら、屋根に上らなければならないからだ。
「花火なんて、見飽きたわ。まあ、うるさすぎてどうせ眠れないからいいんだけど」
弁財天が言えば、狐が、
「私は大きな音も火も苦手です」
と耳を伏せて獣らしい発言をする。
どうやら、花火観賞には向かない者たちを誘ってしまったようだ。
「まあ、そう言うな。珍しいやつがあがるんだから」
俺がとりなすと同時に、ドンと音がして花火大会が始まった。
次々と夜空に火花が散る。
そのたびに、狐と弁財天の横顔が赤くなったり黄色くなったりする。
「で、今回の件、大神様への報告は終わったの?」
「私が責任を持って報告を」
狐が胸を張る。
俺は事の顛末とともに、人間は想いを大事にすること、死んだ後もそれが誰かに引き継がれることがあることを報告した。大神様からは、巻物にしたためたお返事をいただいた。「人の想い、他の生物にはなきもの。人の幸せに寄与する優れたものと見つけたり」と書かれていた。俺は今回よい働きができたらしい。
丸来煙火店の花火が上がったのは、大会の中盤だった。
丸い形の四分の一ずつ、色が違う。右上から時計回りに、色が順番に変化していく。素早い変化に、目が釘付けになる。
「これは面白い。花火なんて昔から変わり映えしないと思っていたけど、人間も色々考えるものねえ」
弁財天が珍しく感嘆する。
俺は花火を見ながら、会場のどこかで夜空を見上げている礼香のことを考えた。幸せに輝いているだろうその顔を。
(了)