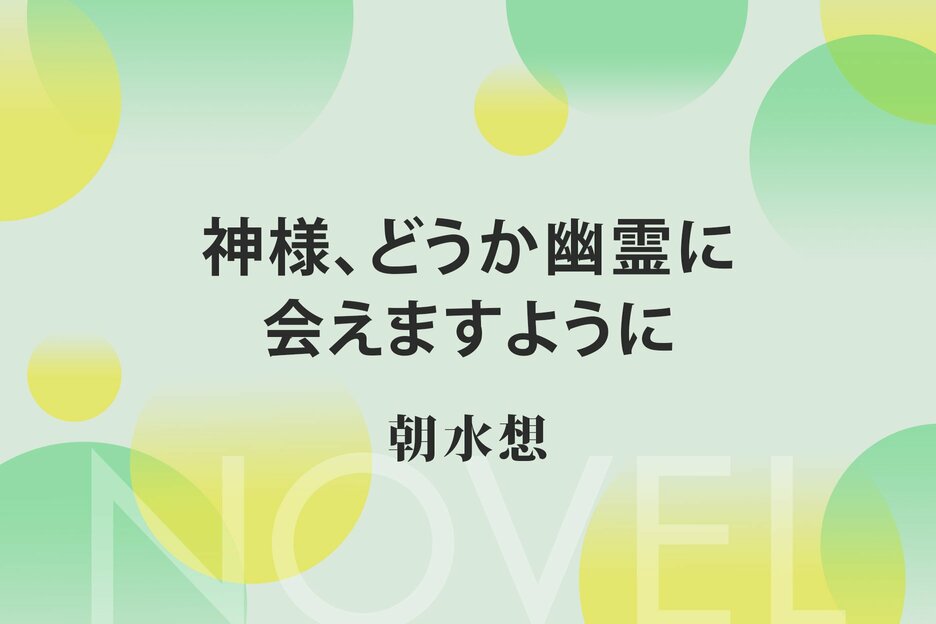ドンという響きが体を震わす。火薬のにおいがする。
夜空に光がはぜる。大きな花火が開く。丸い形の四分の一ずつ、色が違う。それが右上から時計回りに時間差できらめく。
別の花火が上がる。開いたと思うと、光は点滅しながらあちこちに向かう。まるで星々が今生まれたかのようだ。
見たこともない花火だな、と俺は感心する。
俺の周りにいる男たちから、歓声が上がる。
「すげえな」
「さすが、太一さんの花火だぜ」
口々に言う男たちは、揃って「丸来煙火店」と紺地に白文字を染め抜いた法被姿だ。青年の姿に化けた俺も、その一人だ。
「まだだ」
小さな声が聞こえて横を見れば、女の横顔が花火の光に白く浮かび上がる。
はしゃぐ男たちにくらべて、その声は硬く冷たい。
俺は皆の横顔を見ながら考えた。
この中の誰が人を殺したのだろうか、と。
誉人が俺のいる神社にやってきたのは、今から一ケ月前のことだった。
「稲荷神様、起きてください!」
本殿で寝ている俺の腕に、狐がかみついた。
思わず俺は飛び起きる。
「いてっ。なんだ、眷属の分際で神にかみつくとは」
「先ほどから大声で呼んで、揺さぶっているのに起きないので致し方なく。私としても粗暴をはたらくのは美学に反しますが、なまけ神にお仕えすると信念を曲げざるを得ず」
狐は澄まして前足をそろえ、ふさふさしたしっぽを一振りすると、鼻先を本殿の外に向けた。
「誉人がおいでです」
目をこすりながら本殿を出て、賽銭箱の上に座る。俺の体を、人間の投げる賽銭が通過する。もし彼らに神が見えるとしたら、小袖と袴を着た少年の姿を目にするだろう。
江戸から東京と地名を変えた後も、俺はこの稲荷神社に四百年ほど棲みついている。周囲には住宅や商店がぎっしりと立て込んでいるが、ここだけは木々が揺らぎ空も広い。
俺には天界が選んだ人間、「誉人」の願いを、必ず叶える使命がある。五十人分叶えれば天界に戻れるのだ。もう天界に戻れるはずだったのだが、まあ、いろいろあって追加であと五十人分叶えることになった。
俺の前に立った誉人は、神妙に手を合わせた。妙に静かな雰囲気の女で、年の頃、五十半ばというところか。俺は耳を澄ませる。誉人の心が聴こえてくる。
(神様、私の名前は丸来礼香と言います。どうか、神様お願いです)
狐がやってきて、賽銭箱の脇にちょこんと座った。
(どうか、私の死んだ夫に会わせてください。どうしても聞きたいことがあります)
丸来礼香は熱心に願うと、もう一度すがるような目で俺の方を見る。
死んだ夫に会わせろだって?
「おい、狐。死んだ人間を生き返らせるのは天界の許可がおりるのか」
狐が首を横に振る。
「もちろんだめです。神とて自然界に反することはできません」
「じゃあ、こんな願い叶えられっこないじゃないか!」
俺は頭を抱えた。これ以上失敗したら、天界におわす大神様に見限られてしまうかもしれない。それは困る。
「まあ、その話は後です。あの誉人、住所を言いませんでしたよね。追いかけて行って確認してこないと」
狐はするすると本殿の階段を降り、誉人の後ろについて鳥居を出ていく。狐の姿は人には見えないので、悟られることはない。
夜、狐は難しい顔をして神社に帰ってきた。
「どうも、一筋縄ではいかない事情を持っているようです」
「普通ではない願いに、一筋縄ではいかぬ事情か。この誉人はなかったことにならないのか」
狐はじろりと俺を見る。
「今様に言うと、あれだ。スキップ」
「そのような逃げ腰だから、天界に睨まれるのです」
「仕事が多いのは期待されているんだ」
「誉人の願いを叶えられなければ、天界へ戻るのはその分遅くなるんですぞ。眷属である私も一緒の運命という事をお忘れなく。とにかく、丸来礼香は東京郊外のF市に住んでいる者でした。そこで花火会社の社長をしているようです」
「F市はずいぶん離れているじゃないか。なんでまたこんな遠い神社に」
「この近くに結婚した娘が住んでいるので、たまたま泊まりに来たようです。二人の会話から察するに、礼香の夫はまだ亡くなって間もなく、四十九日を終えたばかりだと」
忌中は神社へ来ることは許されない。四十九日が明けたなら、まあよいだろう。
「それで、死んだ夫に聞きたいのは何なのか、分かったのか」
願いを叶えてやるためには、それを知らなくてはならない。
「分かりました。どうです、私は仕事ができるでしょう」
狐はもったいぶってコホンと咳払いする。
「驚かないでくださいよ。なんと、礼香の夫は殺されているんです。会社の事務所に押し入った強盗にやられたとか。犯人はまだ捕まっていません」
「ほう?」
「つまり、誉人の願いはこうです。死んだ夫に会って、真犯人を聞き出したいんですよ。何しろ、殺された本人は殺人犯の顔を見ているでしょうからね」
筋が通っている。狐の予想に間違いはなさそうだ。
その半月後、俺は丸来礼香の経営する「丸来煙火店」の住み込みアルバイトとして雇われた。
季節は六月の終わりで、花火会社が一番忙しい時期だった。人が来ないのか、ずいぶん前から募集がかかっていた。青年の姿に化けた俺が面接に行くと、礼香はろくに顔も見ずいつから仕事に来られるか聞いてきたほどだ。
面倒なので、「ヘルパー・イナリ」と同じ人間に化けた。今時の好青年顔である。さわやかな見た目のほうが、相手に警戒心を持たれずに調査できる。修行中の神である俺には二つの能力が与えられている。一つは地上の生き物すべてに姿を変えられる力、もう一つは人間の枕元に立てばその者を操ることができる力だ。
狐に留守番を頼み、俺はF市へと向かった。一時間ほど電車に揺られ、人気のない駅で降りる。駅前には何もない。歩いていくと、連なった里山のふもとに清らかな川が流れ、橋の上から釣り糸をたらしている子どもがいる。橋の向こうに民家が集まっていた。どの家も広い敷地を持った立派な日本家屋だ。そのなかの一軒が「丸来煙火店」だった。
仕事の初日、俺は丸来煙火店の事務所に赴いた。
事務所と言っても礼香の自宅の一階である。白壁に灰色の瓦屋根をのせた昔ながらの家だ。芝生だけの庭を挟んで向かいは社員寮になっていた。四人の社員と礼香を前にして俺は挨拶する。
「あ~、イナリと申す。外国人だからしゃべり方はおかしいかもしれないが、気にするな。よろしく頼む」
おもむろに、たーまや、かーぎや、と叫ぶ。「花火を作る人間にはそう言っておけば間違いありません」と、狐が勧めてきたのだ。しゃべり方が気にならないように外国人という設定にもしてあるし、うむ、ぬかりない。
それなのに、全員が眉間にしわを寄せ、警戒している。なぜだ。
「おかみさん、大丈夫なのかよ、コイツ」
一番年長の中年男が声を上げる。礼香はおかみさん、と呼ばれているようだ。
「いくらアルバイトとはいえ、火薬扱ってんだぞ。事故はごめんだぜ」
残りの若い三人の男も、控えめに頷いた。礼香がぴしりと言った。
「酒巻さん、意思疎通はちゃんと取れるんだから贅沢言わないで。雑用しか頼まないんだし。この夏を乗り切るのに、ちょっとくらい怪しかろうが使えない奴だろうが、誰かいてくれないと困るの。それとも、あなたたち休み返上で仕事する?」
四人が黙った。静かになったのはいいが、怪しいうえに使えない奴扱いは心外だ。
礼香がこちらに向き直り、「じゃあ、これから花火工場に案内する。車に乗って。社員のみんなも」と促す。
「ここで花火を作るんじゃないのか」
俺は棚の上を見て言った。そこには、丸い花火玉が小さい順に五個並んでいる。小さいものは直径が十五センチくらい、大きいものは三十センチくらいあり、ボウリング玉よりも大きい。茶色い紙が表面に隙間なく貼ってあり、さらに筆で何やらでかでかと書きつけてある。おそらく花火の名前なのだろう。
「ここはあくまで事務所。火薬を扱っているから、住宅のない山の上に工場があるの。棚の上のあれはね、レプリカ」
俺は礼香の車の助手席に乗った。フロントガラスに猫の人形がぶらさがっている。人形と一緒に十分ほど揺られたあと、ここで降りろと言われた。工場は山腹の草原の中に建っていた。外周をぐるりと壁で囲われ、入り口はひとつしかない。礼香が鍵を開ける。その鍵にも猫のキーホルダーがくっついている。
敷地は広々としていて、あちこちに「火気厳禁」の立て看板がある。いくつか頑丈そうなコンクリートの建物が点在していた。平屋の民家くらいから倉庫のような高さのある建物まで、大きさはまちまちだがそれぞれ独立しており、歩いて移動しなくてはならない。俺の先を歩きながら礼香が説明する。
「ここは、火薬を配合する場所よ。あっちは、星掛けをするところ」
「ほしかけ?」
「花火はボールのような丸い球のなかに、さらに小さな火薬の粒が詰まっている。それを星と呼ぶの。星掛けは、粒に火薬をまぶしながら釜のなかで回転させて、大きくしていく作業」
「そうか。一回見せてくれ。そしたらできる」
後ろについてきていた酒巻という中年男がせせら笑った。
「何言ってやがる。星掛けができるようになるのに五年はかかるんだぜ。できるわけないだろうが」
「そうね。初心者には無理」
礼香も頷く。失礼な。神は一を見れば万ができるのだぞ。
「星掛けができたら、あの乾燥室で乾燥する。玉詰め場で、玉皮っていう半円形の容器に星を詰める。花火の種類によって詰め方が違うから、職人の技術がいる。玉皮同士を合体させて球状になったら、最後に玉貼りという作業よ」
「あの小さい建物は、なんだ」
俺は説明にない小屋のような建物を指さす。コンクリートの壁に、アルミ製の扉が付いている。窓は小さなものがひとつ。
「ああ、あそこはあなたには関係ないの。玉貼り場を案内するから、こっちに来て」
礼香に促されて大きな建物に入ると、三人の中年女性がテーブルを囲んで何やら作業をしていた。テーブルの上には、花火玉と茶色い紙が載っている。花火玉は直径が十センチくらいのものから、三十センチくらいのものまであった。
「ここが玉貼り場。細長いクラフト紙を、花火玉の表面が隠れるように貼り付けるのよ」
「これなら俺にもできそうだな」
「簡単そうに見えるけど、均等に貼らないと花火がきれいな形に開かない。大事な作業なの。彼女たちも、長年うちで勤めてくれているパートさんなのよ」
困ったような顔をする礼香に、酒巻がだみ声をかける。
「おかみさん、そんなに言うんなら一回やらせてみたらどうだい、え? 花火なめんなよ若造」
「酒巻さん」
礼香がたしなめようとしたが、俺はさっさとテーブルにつき、花火玉を手に取る。言われっぱなしは神がすたる。周囲の女性たちの見よう見まねで、クラフト紙をぐるりと一周貼り付ける。
「できたぞ」
酒巻に手渡すと、ニヤニヤと笑っていた顔が、次第に真顔になっていく。
「嘘だろ。完璧だ。俺だって玉貼りができるようになるのに三年かかったのに」
礼香も、ほかの社員も一様に目を見張っている。そっちこそ、神をなめるなよ。
「スパイだ!」
酒巻が声を上げた。
「コイツ、ほかの花火会社のスパイだ。うちが花火コンテストに何度も優勝しているから、技術を盗みに来たんだ」
酒巻が俺を指さし、ほかの人間も疑わし気な視線を向けた。まずい。
「スパイ、チガイマス。国で傘張りの仕事、してた」
江戸時代に似たような職があったのを思い出し、俺はあわてて取り繕った。
「技術を盗まれるような大事な場所にはアルバイトを入れないから、たとえそうだとしても心配いらないわよ。そう、海外にはそういう仕事があるのね。雑用をしてもらおうと思ったけど、それなら貼りの仕事を手伝ってもらおうかしら。忙しい時期だし」
礼香の言葉にその場はおさまる。あぶなかった。まったく、人間を説得するのはいつも骨が折れる。なんとも疑り深い種族だ。
俺は社員寮の一室をあてがわれた。二階建てだが、俺の部屋は一階だ。単身者用のアパートのように個室になっている。簡単なキッチンにユニットバス、ベッドがあるだけだが独り身には十分だ。
窓を開けると、中庭を挟んで母屋兼事務所が見えた。強盗の現場だ。中庭、社員寮を含めるとかなりの広さになる。通常の家屋の門にあたるところには、車を出し入れしやすいように何もなかった。これなら誰でも入ってこられる。
事務所の入り口とは別に、外階段を上った二階には住居の玄関があり、事務所に出入りすることなく帰宅できるようになっていた。
初日の仕事終わり、俺は隣の部屋のドアをノックした。ジャージ姿の酒巻が顔を出す。
「なんだ、お前か。俺は忙しい」
用事も聞かずにドアを閉めようとする。俺は慌てて持参した日本酒の一升瓶をかかげてみせた。
「一緒にどうだ。固めの杯だ」
相手は閉めようとしたドアから手を離した。
「酒を持ってきたのか。それならまあ、付き合ってやらんでもない」
急に機嫌が良くなると、俺を中へと招き入れる。
今日観察したところ、この男が最古参のようだ。誉人のこと、事件のことを聞き出すには一番よさそうだ。
床に直接座り、ちゃぶ台を囲んで酒を酌み交わす。酒巻は日本酒の瓶をよく見て顔をしかめた。
「この酒、よく見たら『御神酒』って書いてあるな。どっかの神社から盗んできたんじゃあるめえな」
「安心しろ。正当な権利により入手した酒だ」
俺への供え物なのだから、問題なかろう。
「しかし、あんたも変な奴だな。日本語が怪しいのに、たまに固めの杯だの、正当な権利だの難しい言葉が飛び出す」
「江戸時代の癖が抜けな……時代劇が好きなんだ」
「まあでも、玉貼りができる人材が見つかって万々歳だろうよ、おかみさんも。何しろあんな事件があって、社員も辞めちまったし、募集をかけても気味悪がって人が集まらなかったからなあ」
酒巻は含みを持たせた言い方をする。しゃべりたくてたまらないという顔だ。俺は「事件って?」と水を向けるだけでよかった。案の定、酒巻は強盗事件のことを話し出す。
「あの日はさ、社員やパートの連中全員で、街の居酒屋で打ち上げをしてたんだ。太一さんだけは風邪をひいてたもんで、一人で母屋に残ってな」
「太一というのは、礼香の夫か」
「ああ、そうだよ。今はおかみさんが社長だが、亡くなる前は太一さんだった。夜の七時くらいから宴会を始めたんだけど、八時頃、太一さんから礼香さんにラインのメッセージが来た。その画面をみんなに見せていたから間違いない。みんなと飲みたかったのに、風邪をひいちまって残念だ、おとなしくふて寝する、みたいな内容だった」
つまり、八時まで太一は生きていたということか。
「九時過ぎに宴会が終わって、こっちに帰ってきたのが九時半ごろ。おかみさんは母屋へ、俺たちが社員寮に戻ってきて落ち着いた時、事務所から礼香さんの悲鳴がきこえた。慌てて事務所に行ったら、太一さんが血を流して床に倒れてたんだ」
酒巻は思い出したのか、太い首を何度も横に振った。
「事務所は荒らされてて、太一さんは後頭部を何かで殴られて即死だったそうだ」
「何かで?」
「凶器が見つかってないってことだよ」
「盗られたものは」
「金庫のカギをこじあけようとした跡が残ってた。だが、結局開けられなくて、何も盗られなかったらしいな」
人を殺してまで押し入ったにもかかわらず、何も盗らずに犯人は逃げたという事か。
「警察が捜査しているんだろう」
「当然やっている。警察も詳しく教えてくれないから分からんが、目撃者が見つからないみたいでな。難航しているらしい。ここだけの話だけどよ」
酒臭い息が急に小声になる。
「俺は、おかみさんが犯人なんじゃないかと思ってるんだ」
「ばかな」
礼香は死んだ夫に会いたいと思っているのだ。自分が殺した男に会いたいはずがない。
「俺にはそうとしか考えられん。事務所の鍵は中から開けられていて、誰かが侵入した形跡もなかった。太一さんの体には後頭部の傷以外、誰かと争った様子もなかったっていうじゃねえか。どう考えても顔見知りの犯行だろ。太一さんが犯人を招き入れて、後ろを向いた瞬間に殴られたんだ」
「それだけじゃ礼香が犯人とは言えない。顔見知りの人間はほかにもいるだろう。そもそも、礼香は飲み会にいたじゃないか。アリバイがある」
「どうかな。飲み会に行く前に太一さんを殺して、事務所をわざと荒らして、何食わぬ顔で来たのかもしれねえぜ。今考えれば、八時ごろ太一さんからのメッセージが来たのを、わざわざみんなに伝えたのも何だか怪しいな。あんなの、ちょっと細工すれば自動送信もできるだろ。生きていると偽装するための芝居かもしれねえ。何も盗られずに済んだのも、これで説明がつく」
「警察はいつ頃殺されたって見てるんだ」
「聞いた話じゃ、八時から九時の間って話だが」
「それなら、飲み会の前ということはないだろう」
「でもよ、飲み会が始まったのは七時だぜ。ここから歩いてすぐの場所だったし、それくらい誤差の範囲じゃないか。刑事もののドラマで見たんだが、死亡推定時刻っていうのは絶対じゃなく、数時間の幅があるのがふつうなんだと。それに、メッセージが来たから多分八時までは生きてたってことで、八時にしているだけだろ」
警察はもっと情報を集めて死亡推定時刻を割り出しているだろうが、酒巻の言う通り、メッセージも判断材料のひとつにはなっているはずだ。死亡推定時刻が八時から九時までなら、七時前に殺された可能性も十分あるだろう。
「夫を殺して、何の得がある」
「大ありだよ。おかみさんのもとには億単位の保険金が転がり込んだはずだぜ」
「しかし、自分の夫だぞ」
「お前さんには分かるまいが、あの夫婦は仲が悪かった。太一さんが社長で花火職人、礼香さんはほとんど花火造りにはかかわらず、経理を担当していた。二人が仕事以外の話をしているのを聞いたことがねえ。仮面夫婦ってやつかもな。
その上、おかみさんはたまに、夜中に出かけていくことがあるんだ。俺は外に男がいると睨んでる。事件の何日か前も、母屋で二人が大声で口喧嘩していたのが社員寮まで聞こえたんだぜ。あの勢いでやっちまっても不思議はねえよ。男と共謀してやったっていう可能性もある」
俺の喉の奥から唸り声が出た。誉人が殺人犯かもしれないとは。
その後さんざん管を巻いてから酒巻は酔いつぶれ、いびきをかいて寝始めた。俺はそっと自分の部屋に帰り、カーテンを開けて母屋をのぞいた。まだ二階に明かりがついている。
窓を開け、青年から白猫に変わると、するりとベランダから庭へ降りた。闇に紛れ、母屋の庇を使ってジャンプし、明かりのついた部屋を手すりからのぞきこむ。
畳の居間に、礼香がひとり、座り込んでいた。仏壇と向き合っている。
仏壇の上には中年男性が写った真新しい写真がある。おそらく太一だろう。六十代前半くらいの実直そうな職人だが、目は優しい。
礼香は写真をじっと見つめている。
神社に来た時も思ったが、妙に静かな雰囲気を漂わせていた。
眉間にしわを寄せ、写真のさらに奥を見ようとするように遠い目をしている。悲しんでいるようにも、怒っているようにも見えた。
ぼそぼそと写真に何かを話しかける。ガラス越しに、俺は口の動きを読む。
幽霊でもいいから会いに来てよ。そう言っていた。
礼香はそのまま動かなかった。何かの答えを探しているように。
(つづく)