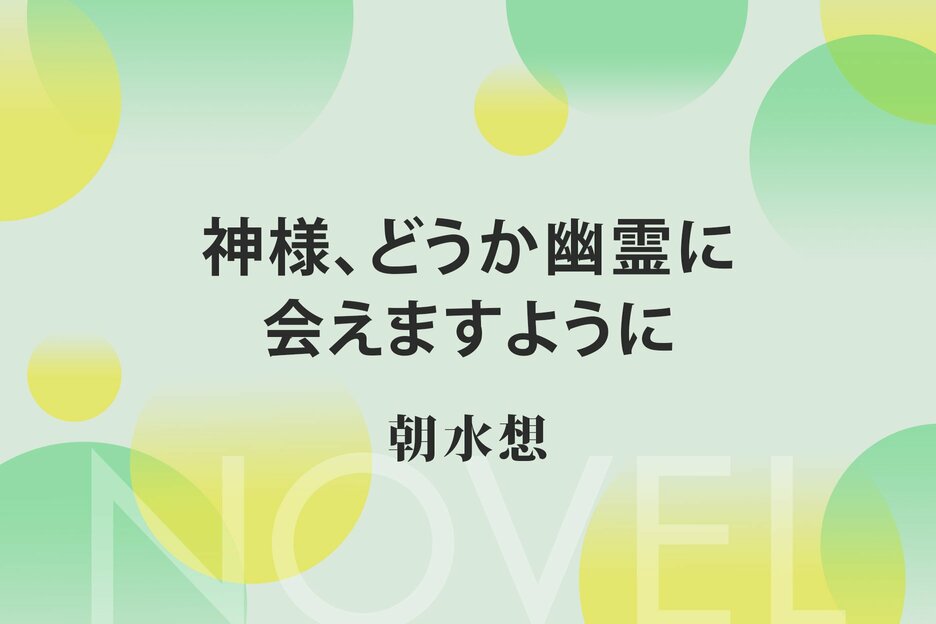俺は玉貼り場に配属になった。
花火玉に細長いクラフト紙を均等に貼り付け、乾かし、また貼り付けていく。地道な作業だ。俺はスパイと間違われないよう、何かと理由をつけてそれぞれの作業場をそれとなく見てみた。機械化されているのはほんの一部で、花火を作るというのはほとんどが手作業だと分かる。
作業場に怪しいところはないが、説明が省かれた小屋だけは誰の出入りもない。
こっそりアルミのドアを回してみたが、鍵がかかっていた。ひとつだけある窓も、すりガラスで中が見えない。
「何してるの」
後ろから声をかけられ、ぎくりとして振り向くと、同僚の男が立っている。人間に化けた俺と同じ年くらいの若者で、名前は山尾と言った。
「いや、休憩しようと思ったんだ。ここが休憩所かと」
「ああ、ここは違うよ。太一さんがアイデアを練っていたところで、誰も入らないようにおかみさんからきつく言われているんだ。僕も休憩だから一緒に行こう」
畳敷きの休憩場に着くと、二人で茶を飲んだ。休んでいるのは、俺たち二人だけだ。
「しかし、花火づくりは江戸時代と変わりがないな」
俺のつぶやきに山尾は笑った。
「ああ、花火師って華やかに見えるけど、ほとんど地味な作業しているんだよね。打ち上げるときだけだよ、エキサイティングなのは。でも、イナリさんはラッキーだよ。明日の夜、花火の試し打ちをするんだ。太一さんがコンテスト用に作った花火のね。だから今日の準備は手伝ってくれる?」
「相分かった。ところで、礼香と太一は、どんな夫婦だったんだ」
「どんなって?」
「仲が良かったとか、悪かったとか」
酒巻の言葉だけでは頼りない。情報は多く集めたい。
「う~ん、おかみさんは経理だから事務所にいることが多くて、工場に来ることも少なかったからなあ。玉貼り作業だけは手伝うこともあったけど。一年くらい前に亡くなった、太一さんのお父さんも花火職人だったんだ。昔気質の人でさ。『作業中はしゃべるな、危ない』って厳しかったから、夫婦でしゃべってること自体レアだった。でも、何でそんなこと聞くの?」
「礼香が太一を殺したって聞いたから」
山尾は、持っていた茶をこぼさんばかりにのけぞった。
「うわ、熱っ。びっくりした。酒巻さんだろ? 鵜呑みにしないほうがいい。僕はあの人こそ怪しいと思うね」
「なんでだ」
「腕のいい花火職人ではあるんだけど、酒にだらしなくてさ。太一さんにけっこう注意されてたから、恨んでたよ」
山尾は言ってしまってからまずいと思ったのか、「ここだけの話にしてね」としきりに俺に確認した。
「なんにせよ、早く犯人が見つかってほしいよ。太一さんが浮かばれない」
「そうだな。俺も早く犯人を見つけたい」
そして早く天界に戻りたい。
「僕、太一さんに憧れてこの世界に入ったんだよ。あんな独創的な花火を僕も作りたいと思ってさ。だからすごく残念だ。丸来は太一さんの才能が支えていた会社なのに」
「ずいぶん、太一のことを尊敬しているんだな」
「太一さんは、無口で職人気質だけど、根は優しくてさ。おかみさんは何だか、ビジネスライクっていうか、ちょっと冷たい感じがして」
そこで別のスタッフが休憩室に入ってきて、話は終いになった。どうやら太一は評判がよく、礼香は芳しくないようだ。
午後は社員何人かで、事務所に試し打ちに使う道具を取りに行った。多くの道具は事務所ではなく工場に置いてある。事務所にある古い道具から先に使ってほしいと礼香が頼んできたのだった。
挨拶の時はあわただしくてよく見られなかったが、強盗事件の現場だけによく見ておきたかった。
引き戸になった入り口は建物の東側にあり、扉の横に「丸来煙火店」と看板が掲げてある。入ると東西に細長いぶち抜きの部屋になっている。今時は古民家と言うらしいが、焦げ茶色の太い柱と、天井の梁がその大空間を支えている。
入って左右の南と北の壁には窓があり、入り口と向き合った西側はすべて壁だ。
手前には応接セット、その奥に事務机が二つずつ向かい合わせになったワークスペース。左手側には二階への階段と給湯場があり、右手側はロッカーがずらりと並んでいた。
ロッカーから荷物を取り出しながら、俺は聞いてみた。
「太一が倒れていたって場所はどこなんだ」
みんなの動きが止まり、気まずそうに顔を見合わせる。
「まあ、気になるよな。ここで働くんだから」
酒巻が言って、西側の壁とワークスペースの間の壁を指さした。
「ここだよ。壁の方を頭にして、うつぶせで倒れててな」
血を流していたと言っていたが、壁も床もきれいに掃除されていて跡形もない。西側の壁と事務机の間は、二メートルもなかった。ずいぶん狭い場所での犯行だ。犯人と太一はかなり密接に立っていたことになる。
黙っているのをショックを受けていると勘違いしたのか、山尾が「まあ、あんまり気にするなよ」と俺の背をたたいた。
翌日、日が暮れると社員総出で、工場の裏手の崖にある試し打ちの場所に向かった。皆揃いの法被を着て、朗らかな声と華やかな活気に満ちている。
「みんな、えらく楽しそうだな」
俺が言うと、「コロナがひと段落ついて、やっと花火大会が再開されたからね」と山尾が返した。
「コロナ禍の時は、ろくに花火を作ることさえできなくて、花火職人としては辛かったんだ。その間は本物と同じ、精巧なレプリカ花火を細々と受注生産していてね。博物館とか、小学校とかに。ほら、事務所にレプリカ花火があったろ。あれはその時の見本品」
「なるほどな」
同じく法被を着た礼香が前を歩いている。相変わらず静けさを保ったままだ。
前日の夜に設置しておいた、俺の胸ほども高さのあるステンレスの筒に、花火玉を入れていく。花火玉の頭に紐でできた小さな輪っかがついているのが不思議だったのだが、その輪に麻紐を結び付け、筒の上からゆっくりと下ろしていた。このためだったのかと合点する。
「花火玉っていうのは見た目より重いな」
俺がつぶやくと、一緒に作業していた山尾が説明する。
「これは直径三十センチの十号玉だけど、八キロ半の重さがあるよ。でも空で開くときは直径三百メートルにもなるんだ」
「花火玉に書いてある、この丸はなんだ」
クラフト紙を貼った後の花火玉には、筆文字で「芯入変化菊」だの「菊先紅青」だの花火の名前が書いてあった。その下に、やはり筆でひしゃげた丸印が入っている。
「ああこれ。太一さんが作った花火には、全部この印が入ってる。マルキタの印だと思うよ」
なんじゃこりゃ、と酒巻の声がしてそちらを見ると、麻紐を手にしている。紐の端がちぎれている。
「なんで新品なのに切れてるんだ」
「まあ、別にいいだろ。花火が上がる時に一緒に燃えちまうよ」
同僚に言われて、「それもそうか」と酒巻はそのまま、麻紐を花火玉に結び付けて筒の中に下ろした。何かが俺の中でひっかかった。何だ。わからない。
いよいよ打ち上げだ。種火を筒に投げ入れると、花火玉の下に敷いた火薬に点火して爆発を起こし、花火玉が打ちあがる。
花火大会と違い、一つ一つ、時間をあけて打ち上げる。それぞれ、見たこともない変わった花火だ。夜空に光がはじけるたび、花火師たちから歓声が上がる。
「すげえな」
「さすが、太一さんの花火だぜ」
まだだ、という小さな声に横を向くと、礼香が真剣な目で花火を見上げていた。周囲がはしゃいでいるのとは対照的だ。礼香のまわりの空気だけが、花火の喧騒から切り離されている。
俺は誉人がいつもまとっている静けさから、連想するものがあった。
嵐が来る前の、あの空気によく似ている。神社に人気が絶え、いつもは境内でのんきに歩き回っている鳥たちがいない。生温かい風が、木々をゆらす音だけが響く。
大地が、空が、力をためこみ、爆発させる前に見せる一瞬の沈黙。
礼香はいったい、何をためこんでいるというのか。
狭い場所で行われた犯行。おそらく犯人は近くに来ても警戒しないくらいの間柄。事務所と自宅は階段で行き来できる。飲み会の前に、夫を殺すことは可能だったかもしれない。もしくは、協力者が飲み会の間に太一を襲ったか。
もしかしたら、礼香はそんな大それた秘密を、自分の身に沈めているのだろうか。
試し打ちが終わると、すぐに片付けに入った。力仕事で疲れ切っているはずだが、皆どこか興奮している。礼香が俺に近づいてきた。
「ねえ、イナリさん。あなたは今日の花火、どう思った」
「変わった花火だ」
「それだけ?」
「まあ、うん、そうだな」
特別な花火を作っていることには感心するが、俺には特段の感想はない。花火など、夏になればどこかで上がっている。何百年も見ていれば、もう珍しくもない。
「正直に言えば、人がなぜ花火を見たがるのか分からない」
江戸の世で流行っていたものも、今となってはほとんど残っていない。手間のかかる花火が生き残っているのが不思議だった。
「花火って、一瞬で消えるけど、永遠に消えないものだとも思うの」
俺に聞かせるというより、独り言のように礼香が言う。
「とんちか、何かか」
横顔にふっと笑みがもれた。
「日本の花火の歴史を見ると、何度も花火大会が中止になってる。幕末の混乱期だったり、コロナウイルスが流行した時期も、そう。でも、必ず復活する。みんなが待ち望む。花火が上がるのは、世の中が平和であることの証だから。希望の灯りなの」
「希望の灯り」
俺は繰り返す。礼香が力強く頷く。
「そうね。私たちは花火という名前の希望を作ってる。過去の希望を、よりよい形で未来の希望につなごうとしている。襷を渡す途中で灯を消すわけにはいかない。だから会社を守りたい。こんな考え、若い人には古臭くて分からないわよね?」
礼香がこちらを見た。
「いや、わかる」
最近はとんと聞かぬが、少し前までは家というものが個人より優先されていた。家族はもちろん、奉公人までもが一丸となって商売に励んでいた商家。跡継ぎがなく、必死に末期養子を探す武家。
あの者たちは、自分が死んだ後にも続く何かを強く想っていた。それを伝えようとしていた。人が死んでも残る、想い。それはずいぶん大事なものらしい。
「花火は消えても、想いだけはずっと続くっていう事か」
「そういうこと」
「それで、お前は幸せなのか」
俺の問いに、礼香は驚いた顔をする。
「考えたこと、ないわ。私は、やるべきことをやるだけ」
「好きなものを数えてみるといい。そうすれば幸せかどうか分かる。俺の……友達が教えてくれたんだ」
サヨコは人間で、俺は神だ。神と人間が、友達と言っていいのかどうか分からない。だが、適当な言葉が見当たらない。
「そう。いい、お友達ね」
「ああ。もう死んだけどな」
サヨコを思い出すと、まだ生きているのではないかと錯覚する。肉体はなくなったが、俺が覚えている限りサヨコは俺の中にたしかにいる。奇妙な感覚だった。
サヨコにこの花火を見せたらきっと泣くほど喜んだだろう、と俺は少しだけ残念な気持ちになった。
山尾が「あの、お話が」と言って礼香に近づいてきた。礼香が目くばせをよこしたので、俺は工場の方へ引き上げるふりをして、杉の木の陰に隠れた。
「山尾さん、話って?」
「実は、今年の夏で会社を辞めたいんです」
「困るわ、あなたまで辞められたら……」
夜の森にうろたえる声が響いた。
「俺、太一さんの花火に憧れてました。でも、もう太一さんの新しい花火は一緒に作れないじゃないですか。何だか、むなしくて。田舎に帰ろうと思ってます」
礼香はなんとか引き留めようとしたが、山尾は取り合わない。俺はそっとその場を離れ、工場へと向かった。
(つづく)