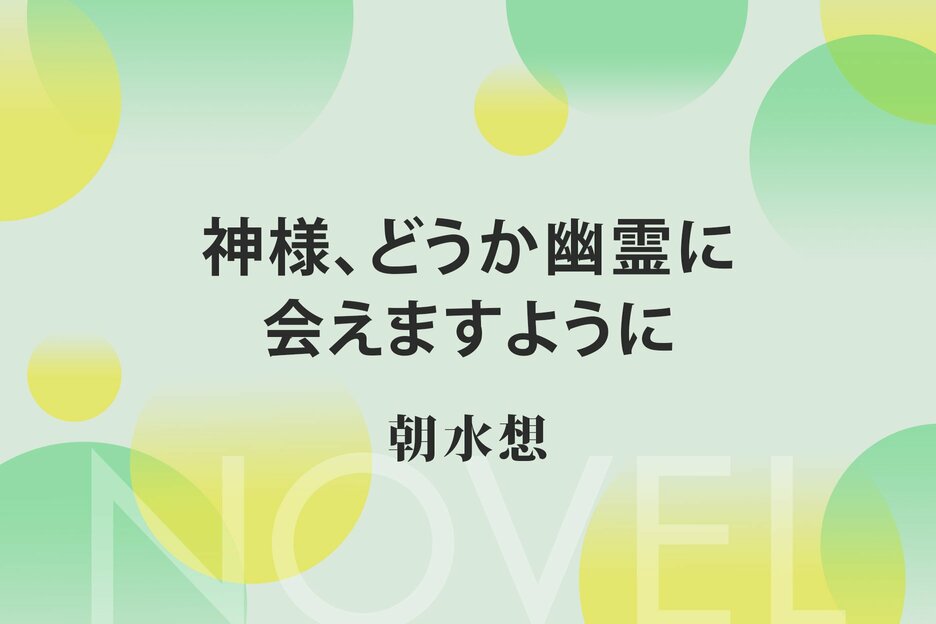仕事が休みになると、俺は電車に乗って世田谷の稲荷神社へと帰った。
「留守番、ご苦労であった」
「あっ、お帰りなさいませ」
本殿の扉を開けると、狐は何かを後ろに隠した。
「今、何か隠しただろう」
「いえ、ええ、そうですね」
背後に回り込むと、かっぱえびせんの空袋が床で揺れていた。
「ほお。俺の大好物のお供えを。留守番は辛くはなかったようだな」
「寂しゅうございました」
首を下げながら、狐は口の周りについた粉をぺろんと舌でぬぐった。
狐は礼香の娘を見張ってくれていたが、特に動きはないようだった。
「太一と礼香の娘の名前は、花と言って、夫とこの町内で二人暮らしです。一度だけ、太一の交友関係を聞きに刑事が家に来ました。でも太一の交友関係は狭くて、ほとんどが花火業の仕事関係です。社員やパートはみんな飲み会に参加していましたからね。花も事件当日の午後五時以降、世田谷のマンションに居たのが入り口の監視カメラに映っているので、アリバイが成立しています。新しい情報は得られなかったようで、刑事たちは肩を落として帰っていきました」
「こっちは色々と分かったような、分からないような」
太一は才能のある花火職人として人気があり、礼香は冷たいと思われている。太一が死んだことで、何人かの職人たちはすでに辞めてしまった。礼香が会社の実権を握った今、社員たちの心は離れつつある。花火会社を続けることに思い入れが強い礼香にとっては、危機的な状況のようだ。
これが丸来煙火店の現状。
一方、太一を殺した犯人探しはうまくいっていない。
現場の状況から、顔見知りの犯行と思われる。強盗は本当に入ったのかもしれないが、偽装の可能性もある。怪しいのは、夫婦仲が悪かったという妻の礼香、太一に叱られていたという酒巻だ。特に礼香は多額の保険金ももらっている。だが、ふたりともアリバイがある。
死亡推定時刻は八時から九時だが、数時間の誤差を考えると礼香か酒巻が飲み会の前に太一を殺し、メッセージを自動送信して太一が生きていたように見せかけるのも可能だ。もしくは、礼香の男が飲み会の最中に太一を殺したのかもしれない。皆が帰宅後すぐに太一の死体が見つかっているから、飲み会の後に太一を殺して事務所を荒らす時間はないだろう。
それとも、俺が気付かないトリックでもあるのか。
第三者が犯人なのか。
「誉人が犯人の可能性もあるのですか」
狐も驚いた様子だ。
「そうだ。だが、礼香が犯人だとしたら、太一の幽霊に会ってまで聞きたいことっていうのはなんだ」
「さあ、何でしょうね。財産の隠し場所とか? 聞く前に衝動的に殺してしまった」
「そんなの、自分を殺した相手に意地でもしゃべらんだろう」
「死んじゃってますからね、生きている人間よりも心が寛大かも」
「太一しか知らないことか。そうか」
あるじゃないか。太一にしか分からないことが。
「思いつきましたか」
「多分な」
「じゃあ早いところ、それを誉人に伝えて、終わりにしましょうよ」
「太一の幽霊はどうするんだ」
「本物の幽霊は呼べません。稲荷神様が太一の幽霊を演じればよいのです。幸い、太一は花火業界では有名人でインタビューの記事や映像が残っていますから容易いでしょう」
「まだ犯人探しも終わっていない」
「そんなもの、人間に任せておけばよいのです。誉人が犯人だろうとなかろうと、願いを叶えてやればこちらの仕事は終わりです。稲荷神様は人間の問題に首を突っ込みすぎる」
狐は大仰にため息をついてみせる。誉人の願いを叶えるのに時間がかかる俺へのあてつけだ。
誉人が殺人犯であれ何であれ、願いは必ず叶えなければならない。それが俺の使命だ。だが、犯人が礼香であるならば、裁きを受ける必要があるのではないか。
俺は夜更けの道を、月の光を頼りにひたひたと歩いた。
稲荷神社から二十分ほど歩き、弁財天神社の鳥居をくぐる。
拝殿の前まで来ると、どこからか白蛇があらわれて、俺の前に立ちふさがる。とぐろを巻き、赤い舌をチロチロと出しながら蛇は言った。
「これ、稲荷神。ここはおぬしの来る場所ではないわ。帰れ」
この蛇は弁財天の眷属だ。人間にその姿は見えない。相変わらず偉そうだ。おそらく仕えている神に問題がある。
「神に向かってそのような口をきくでないぞ」
「黙れ、おちこぼれ神」
「弁財天はおるのだろう。聞きたいことがある」
俺はかまわず、賽銭箱の前にぶら下がる本坪鈴を鳴らす。蛇は俺の足首に巻き付き、力を込めてその場から引き離そうとする。やめろ、やめない、と騒いでいると、本殿の扉が開いて弁財天が姿を見せた。
「うっさいわね! 何時だと思ってんの。神主が起きる」
おかっぱ頭に、白い小袖、赤い袴姿の弁財天は、少女の姿だが夜の中でも光り輝くほどに美しい。
やっと蛇は力を弱めて弁財天にひれ伏した。
「弁財天、誉人が殺人犯かもしれぬ」
「ここは神社です。何でも相談所じゃないんですけど!」
弁財天は荒々しい足音を立てて拝殿まで来ると、「話さないと帰らないでしょ」とあきらめ顔で俺と並んで階段に座った。
「人を殺めた誉人の願いも叶えるべきだろうか」
「そりゃそうよ。誉人の願いは是非を問わず、過不足なく叶えよと大神様がおっしゃるんだから。誉人は善人ばかりじゃないのは知っているでしょ」
「しかし、せめて裁きを受けさせるべきだろう」
「あなたって、本当に無駄なことを考える。今までならそう言うところだけど」
珍しく歯切れが悪い。
「何かあったのか」
「実は、男の誉人がある女と付き合いたいというので、仲を取り持ってやったのよ。二人はめでたく結ばれ、結婚することになった。でもその女はほかに男がいて、結婚後も関係を続けていたの。誉人はそれを知っても、その女が好きだから別れられず、ずっと苦しんでいる」
「おぬしのせいではなかろう」
「でも、願いを叶えるのにこっちだって苦労しているんだから、どうせなら幸せになってもらいたいもんだわ」
「いったい人間は、何をどうすれば幸せになるんだろうな」
人間の考えることがよく分からない。人間の世界では、善悪も幸不幸も、時代によって真逆になることすらある。
「裁きも善悪も幸せも、考えておやりなさいな、稲荷神。鳥のように人間の世界を上から見回してね。何しろあなたは神様なんだから」
「わかった。そうする」
弁財天は片側の眉を吊り上げて、にやりとする。
やはり、犯人を見つけなければな。俺は思う。
丸来煙火店に戻った俺は、仕事を続けながら礼香を見張ることにした。
だが礼香は自宅の一階の事務所で仕事をしていることが多く、仕事中はあまり接触がない。
礼香のそばにいるには、どうしたらいいだろう。
俺は仕事が終わると、自分の部屋から抜け出し、白猫に化けて母屋へと向かう。また庇を使って二階の部屋のベランダへと飛び乗る。窓をカリカリとひっかき、にゃあと何度か鳴く。
すぐに礼香が窓を開けた。
「まあ、お前どこから来たの」
驚く礼香の脇をすり抜けて、中へと入り込んだ。
「家に入りたいの?」
俺は畳の上で行儀よく前足を揃え、しっぽを一振りして、みゃうと返事をする。
礼香がふっと表情を崩した。
「待ってて。ミルクがあったから持ってくるわ」
礼香は猫グッズをたくさん持っている。やはり猫好きなようだ。
俺は待っている間、二階を見回した。畳敷きの居間は八畳ほど。真ん中に、どっしりした木造りのちゃぶ台が鎮座している。もともとは家族三人に舅も同居していたというからちょうどよかっただろうが、礼香一人の暮らしには広すぎる。ふすまの奥が台所で、その向こうが寝室のようだ。
ミルクをもらった後も、俺は部屋の隅に居座った。礼香も追い出そうとはしない。夜遅くになると、毛布を持ってきて猫用の寝床まで作ってくれた。
礼香が眠ると、俺はこっそり窓から抜け出して、寮に帰った。
そうして何日か、礼香のもとに同じように猫の姿で訪れた。気ままに通ってくる野良猫、と思ってもらうためだ。これで好きな時に礼香を見張ることができる。
昼間は人間の姿で玉貼りをしたり、雑用をこなしたり、せわしなく毎日が過ぎた。
ある時、礼香から事務所に呼び出され、折りたたんだメモ用紙を渡された。
「そこに書いてある備品を揃えて、工場まで運んでほしいの」
「相分かった」
俺はメモをひらいてみた。そこには几帳面な字でこう書いてあった。
花火づくり
娘と話す
猫と遊ぶ
朝の散歩
意味が分からない。
俺が黙っているのを見て、礼香がメモをのぞきこみ、俺の手からひったくった。
「間違えたわ」
顔が赤くなっている。
「あなたが言ったでしょう? 好きなものを数えてみればいいって。だから試しに、書いてみたわけ」
「ずいぶん少ないな。俺の方が多い」
最近の俺は、好きなものを数えるのが癖になったのだ。
礼香は肩をすくめて見せた。
「多いほどいいっていうのも分かる。でもね、好きの深さもあるじゃない。私は、花火が心の底から好きだから、それでいいの」
「なるほど」
好きの深さか。新しい考えだ。
「じゃあ、あんたは幸せってことだ」
俺の言葉に、礼香は目を伏せた。
「問題なのは、数でも深さでもなくて──」
会話は途切れたまま、宙に浮いた。礼香は備品のリストを改めて俺に手渡し、「今日中にお願いね」と言い添えた。問題なのは、何だっていうんだろう。
動きがあったのはその数日後だった。
俺はいつものように、夜、猫の姿で母屋にあがりこんでいた。
その日、礼香はなかなか眠らなかった。そして窓から社員寮の様子を見て、皆が寝静まったことを確認すると、仏壇の下の引き出しを開けて鍵を取り出した。何の鍵か分からない。着替えると、外へと出ていく。深夜の月が中庭の芝を白く照らしている。猫姿の俺も礼香の後ろについていった。
礼香が車に乗ろうとしたので、俺も入り込もうとしたが、つまみ出された。
「だめ。シロはお留守番よ」
いつの間にかシロと呼ばれるようになっていた。仕方なく俺は出ていく車を見送り、すぐに二階のベランダまで駆け上った。
そこから飛び降り、地上に着く寸前、体から羽が生える。大きく羽ばたく。白猫から白鳩に変わっていた。車を空の上から追って飛ぶ。
酒巻が言っていた。礼香はたまに夜中に抜け出すのだと。男がいるに違いないと。
だが、車は人気のない方角へと向かい、山道をのぼった。着いた先は花火工場だ。
真っ暗な工場の敷地を、懐中電灯を照らしながら勝手知ったる様子で歩いていく。
あの立ち入り禁止の小屋の前で足を止める。仏壇から取り出した鍵を使い、扉を開けて中に入る。明かりがつき、窓から周囲に漏れた。
窓をのぞいたが、すりガラスなので中の様子は分からない。
俺は白鳩のまま、扉の前に立つ。壁はコンクリートでできていて、窓も扉も虫すら通れないほどぴっちりと閉まっている。入り込むのは無理そうだ。二時間ほど待つと礼香が出てきた。また鍵をしっかりと閉めて、車で家に戻る。
礼香が犯人ならば、犯人の名前を知りたいわけではない。とすれば、太一に聞きたいのはきっと花火のアイデアに違いない、と俺は踏んでいた。
ここは太一が花火のプログラムやアイデアを練っていた場所だ。アイデアが何かの形で残っていないか、この場所を訪れるのは当然だ。きっと二時間の間に、それを探していたんだろう。俺の予想は当たっていた。
ただ、太一亡き今、なぜ現社長の礼香が夜中にこっそり忍び込む必要があるのかが分からない。日中、堂々と入ればいいではないか。
あるいは何かを隠しているのかもしれない。
たとえば、人を殺した凶器とか。
俺は翌日、行動を起こした。
いつも通り、礼香の家の居間で猫として眠っていた俺は、深夜に起きた。礼香がぐっすり眠っているのを確認すると、仏壇の引き出しを前足で開け、鍵をくわえてベランダから白鳩に姿を変えて飛び立った。
工場のアイデア小屋の前に来ると、俺はイナリ青年の姿に戻る。
鍵を開けて中に入り、明かりをつける。思ったよりも狭い場所だ。
使い込まれた大きな作業用のテーブルと、事務椅子が置かれただけのスペースだった。部屋の隅の棚には、火薬の分厚い専門資料が入っている。見るからに難しそうだ。棚の上には古い形のラジカセが載っていて、クラシックやポップスのCDが積んである。花火大会用の音源だろう。パソコンはない。
テーブルには雑然とものが置かれていた。両手を広げたくらいの大きな紙に、丸い形が鉛筆でいくつも書き込まれている。花火の演出アイデアだろうか。小さな紙には、花火の形のデッサンが描かれていた。引き出し線がいくつも引かれ、「硝酸バリウム+酸化銅」「五号?」などと書き込まれている。そんな紙が何十枚とある。花火玉の中の、星の配置を示した図もあった。
模型もぶらさがっていた。紙でできており、七夕飾りによく似ていた。くるくると渦を巻きながら円を描いたり、細長い流星のような形をしている。
太一が花火というものをさまざまな角度から考えようとしているのが分かる。
俺は部屋の隅々まで探したが、凶器のようなものは見当たらない。紙やスケッチばかりだ。
おかしなところはない。だが、何か強い違和感を感じる。
もう一度、デッサンの紙を、そこに書き込まれた小さな字を、俺は眺めた。
(つづく)