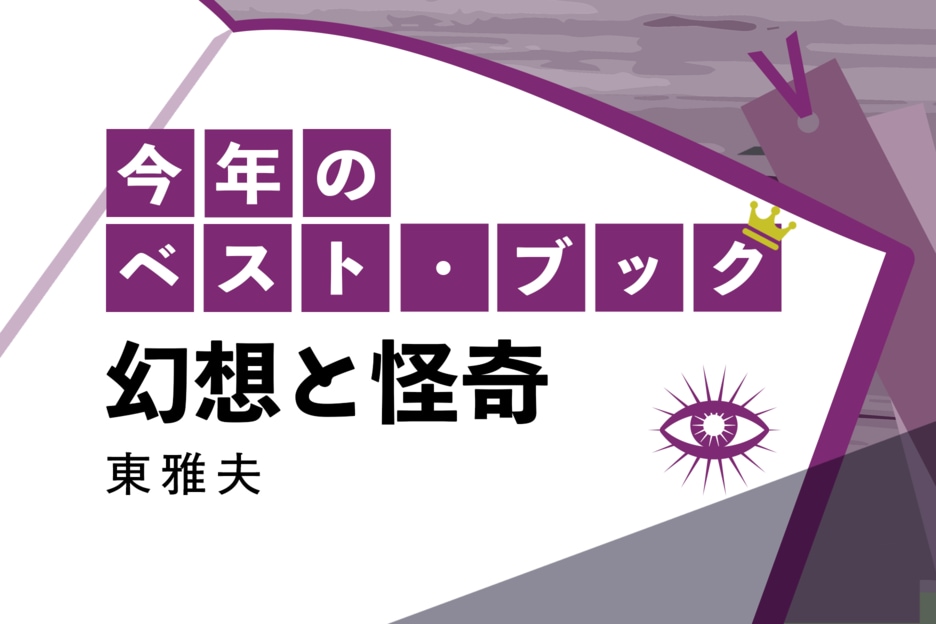2024年のベスト・ブック
【第1位】
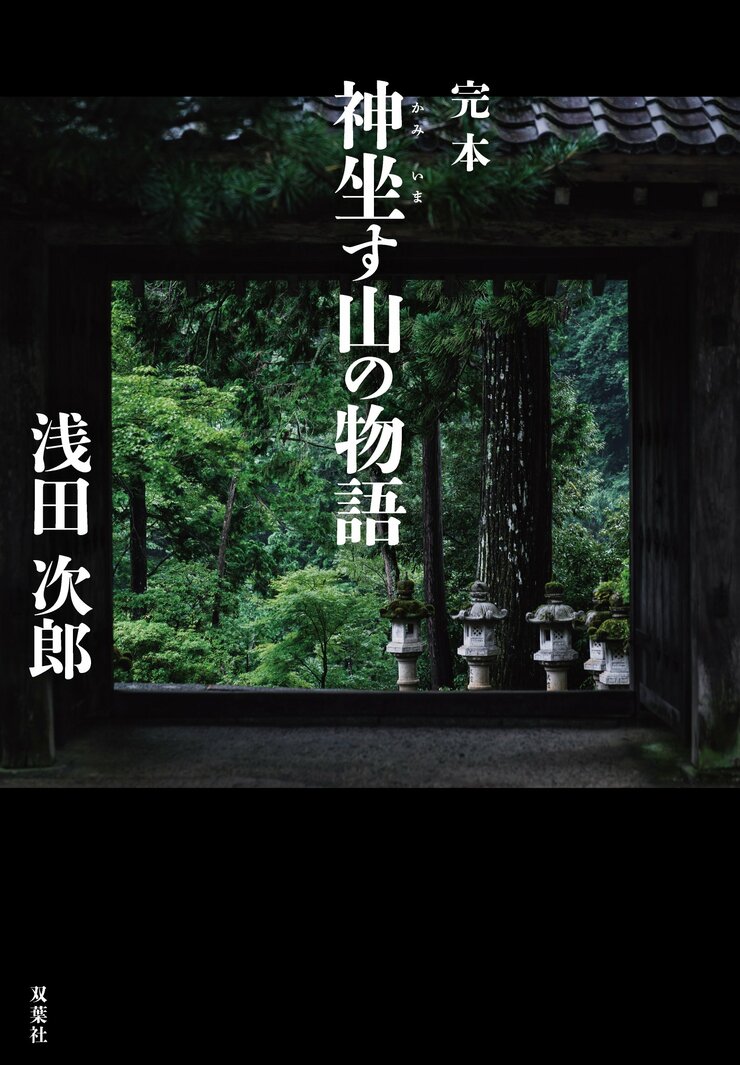
装幀=大路浩実
『完本 神坐す山の物語』
浅田次郎 著
双葉社
【第2位】
『ビロードの耳あて イーディス・ウォートン綺譚集』
イーディス・ウォートン 著/中野善夫 編訳
国書刊行会
【第3位】
『血腐れ』
矢樹純 著
新潮文庫
【第4位】
『深淵のテレパス』
上條一輝 著
東京創元社
【第5位】
『こっちをみてる。』
となりそうしち 作/伊藤潤二 画
岩崎書店
2024年。現実の世界は選挙・政変の年でした。政治体制があちこちでグラグラしています。ビジネスから日常生活までAIがあっという間に浸透し、駆動に必要な電力を求めて原子力がまたもやもてはやされようとしています。一方で自然災害は激甚化。とりわけ能登半島では震災に加えて豪雨まで、信じられないような被害が出ました。
浅田次郎が「小説推理」誌上に、ぽつり、ぽつりと折にふれ発表していた連作〈御嶽山物語〉が、このほど関東大震災に取材した新作「山揺らぐ」一篇を加えて、「完本」としてまとめられた。文芸として揺るぎないその結構といい、迫真の怪異描写の数々といい、これぞ「令和の遠野物語」だ! と呼びたくなるような、気概あふれる力作である。
実は浅田氏は、東京・青梅の「武蔵御嶽神社」に連なる「御師」の家筋に生まれた人物で、私は以前、氏の講演会が御嶽山頂の御実家(今は旅館として営業)で開かれることを知って、「小説推理」編集部の方々に同行して取材に赴いたことがあった。その時のことは、「幽」24号の「リアルか、フェイクか。」特集の巻頭に掲げられたインタビュー記事および「浅田次郎と霊地・御嶽山を歩く」に詳しく記したので、気になる向きは是非、御参照いただきたい。
今回新たに加えられた「山揺らぐ」は、在日朝鮮人による暴動騒ぎという根も葉もない流言飛語が、浮世離れした山上の神域をも揺るがした大震災秘話がナマナマしく綴られており、デマを鎮めようと奔走する鈴木家(=浅田氏の実家)の青年が犠牲となる。若くして逝った縁者に寄せる浅田氏の静かな悲憤が抑えた筆致の端々から伝わってくる名品であり、この大河物語を締めくくるのに、まことに相応しい逸品となっている。
大ベテランの筆力という点で、『完本 神坐す山の物語』に引けを取らないのが(疾うに故人だが)英国作家イーディス・ウォートンの幽霊譚や奇妙な不思議物語を、中野善夫氏が編訳した『ビロードの耳あて』である。若い頃にたまたま目にした怪奇小説アンソロジーで、作者の「あとになって」という短篇に魅了されてこのかた、大のウォートン贔屓となった評者にとって、本書はまさに干天の慈雨にも等しい一冊となった。なかでも砂漠の中の異教徒の廃墟で暮らす英国人の研究家に招かれ異国の地にやってきた同胞青年が見舞われる、世にも怖ろしい出来事を描き出す恐怖譚「一瓶のペリエ」など、ウォートンの美点が遺憾なく発揮された典型だろう(とある井戸が重要なモチーフとなっている点、『皿屋敷』から『山海評判記』を経て『リング』に至る、本朝怪異譚の系譜とも微妙にリンクしていて興味深いこと、このうえない!)。
さて後半には、本朝怪異小説の明日を担う気鋭の若手たちによる新作を挙げよう。
これまでもっぱらミステリー畑で注目を集めてきた矢樹純の短篇集『血腐れ』は一転、極めて純度の高い恐怖小説集となった。ミステリー出身者にありがちな、超自然現象と思わせて、最後に現実的なオチへと導く姑息な(「超自然至上」派の評者に言わせれば、ね)手法ではなく、あくまで謎は謎のまま、最後まで読み手に委ねようとする姿勢が、潔くも素晴らしい。死者の帰還、不吉な予言の成就、底深い復讐の念等々、一読、思わず背後を振り返りたくなるような血も凍る戦慄を、幾度となく味わわされた。
創元ホラー長編賞から飛び出した上條一輝の『深淵のテレパス』は、いま大流行中のリアルな怪談実話風……と見せかけて、実はその背後に、史実の重い堆積を感じさせる、非常によく練られた良作だった。海外ホラー紹介の先覚者として、多くの名作をこれまで送り出してきた東京創元社だけに、初の国内向け公募となった本賞にも、多くの良作が寄せられたが、それらの中で一頭地を抜く恐怖の切れ味と巧まざるユーモアを漂わせた本篇が受賞の栄冠に浴したのも、当然の結果と肯かれるのであった。
5冊目は、永らく話題沸騰の岩崎書店版〈怪談えほん〉が、満を持して公募した「怪談えほんコンテスト」の受賞作『こっちをみてる。』。いま人気絶頂のホラー漫画家・伊藤潤二を「装画」に起用するという気合の入れ方だった。伊藤氏も、全点を「油彩」で仕上げるという、尋常ならざる気合の入れようで、かくして唯一無二の「恐怖えほん」が、ここに誕生することとなった。いわゆる「人面疽」テーマの作品だが、さまざまな濃淡凹凸がすべて人の顔に見えてしまう……という錯視の恐怖が、止めどもなく拡大してゆく恐ろしさを、見事に捉えたとなりそうしちの文章も、お見事!
以上のベスト5のほかにも、今年は僅差で入選を逃した佳品がぞろぞろ……評者としては嬉しい悲鳴をあげる仕儀と相成った。
昨年度の泉鏡花賞作家である大濱普美子の『三行怪々』(河出書房新社)は、老いの悲しみに満ちた近年の作風とは異質の、驚きに満ちたショートショート集。凝縮された行数の中に濃密な小世界を封じ込めて「幻視の煌めき」を体感させる一冊となっている。
やはり昨年度、ノーベル文学賞を受賞したノルウェーの作家ヨン・フォッセ(伊達朱実訳)の『朝と夕』(国書刊行会)は、伊藤整の名作「幽鬼の街」を彷彿させるような冥界と顕界が入り混じるかのような世界に、茫然とさせられた、稀代の怪作。
また、山本善行撰の『衣巻省三作品集 街のスタイル』(国書刊行会)は、是非とも小生編纂の『我が見る魔もの 稲垣足穂怪異小品集』(平凡社)と併読していただきたい、神戸モダニズムと異界の気配あふれる異色の作品集だった。