家族でも友達でもない「隣人」という距離感。隣人だからこそ打ち明けられる悩みも、差し伸べられる手もある。「女による女のためのR-18文学賞」大賞受賞作家の最新作は、様々な事情を抱える住人たちが協働生活を営むコミュニティ型マンションを舞台に、隣人たちの緩やかな連帯を描いた連作集。
「小説推理」2025年1月号に掲載されたライター・瀧井朝世さんのレビューで『隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい』の読みどころをご紹介します。
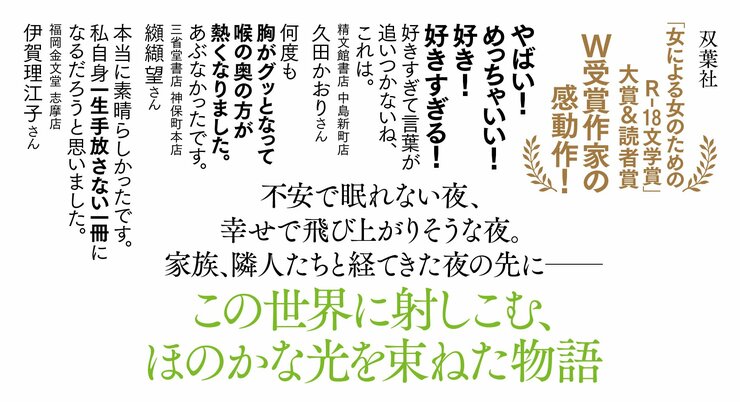
■『隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい』白尾悠 /瀧井朝世 [評]
住人たちが協働する、コミュニティ型マンションでの暮らしとは? 現代において、人と人が繋がる時に大切なこととはなにかを教えてくれる、切実で優しい“隣人模様”の連作短編集。
仕事やら何やらでストレスやプレッシャーにさらされる日々、せめて家ではゆっくりしたいもの。どこに住むかは多くの人にとって重要な案件だ。ではその家が、「多世代の住人が協働するマンション」だったら? 白尾悠の新作『隣人のうたはうるさくて、ときどきやさしい』は、北欧で誕生したコレクティブ・ハウジングというスタイルを取り入れたコミュニティ型マンション、ココ・アパートメントの“隣人模様”を描いた連作集である。
建物には各居室のほか、共用リビングやダイニング、キッチン、ランドリールームがある。運営・管理しているのはNPOだが管理の主体は住人による各委員会。居住者組合には理事長を置かないリーダー不在ポリシーで、定例会で何かを決める時は多数決ではなく合議制。共用部分の掃除や、月に数回の共同食事会の調理は当番制だ。
第一章の主人公は父親が海外赴任となり、家族のなかで一人だけ日本に残ることとなった17歳の賢斗。高校生に一人暮らしさせられないと、親が選んだのがこのマンションだったのだ。彼が入居したのはシェアタイプの部屋で、“ハウスメイト”は、暮らしの達人、70代の康子さんだ。
各章で主人公は入れ替わる。シングルファーザーの兄の幼い息子、つまり甥の面倒を見るためやって来る由美子、同棲相手との結婚を望むものの子供は要らない享、離婚を決意して小学生の娘を連れて入居した聡美、発達特性のある子供を夫婦で育てる和正、そして謎の多い過去を持つ康子さん。それぞれが切実な事情を抱えており、だからこそ、皆がこの協働生活に助けられていく。
互いに適度な距離を保ちながら、気持ちよく接している様子に、「こんな隣人関係、理想的ではないか」と思わずにはいられない。節度が保たれているのは、リーダー不在の管理体制も大きな要因だろうが、NPOの担当者、波多野の言葉にヒントがある。彼女いわく「やっぱり自立している方でないと、こういう暮らし方は難しいんですよ」。ここでいう自立とは、一人で生活できているという意味ではない。彼女は「自立って、(中略)自分の軸、自分の世界があるってことだと思うんです」と話し、自立した人は「他人にもその人の世界がある」と理解している、と言う。この姿勢は、隣人でなくとも、たいていの人間関係において大切なことではないか。居住者たちの悩みと、そこから一歩踏み出す姿には、多くの示唆がある。どんな環境で暮らす人も、本書から多くの発見を得るだろう。











