伊吹有喜さんの『犬がいた季節』は2021年本屋大賞第3位に輝き、山本周五郎賞にもノミネートされました。そんな話題作が待望の文庫化! 昭和の終わりから、平成、令和へと続く時代を背景に、普遍的な18歳の心を描き出しています。
「小説推理」2020年12月号に掲載された書評家・大矢博子さんのレビューで『犬がいた季節』の読みどころをご紹介します。
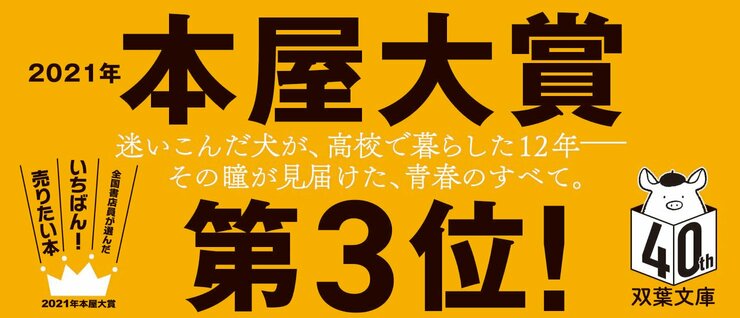
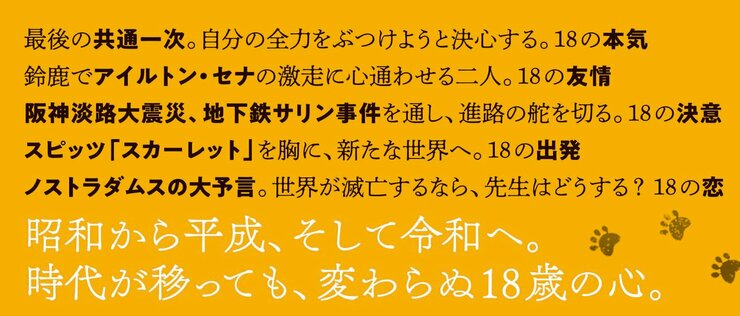
■『犬がいた季節』伊吹有喜 /大矢博子 [評]
四日市の進学校に迷い込んだ一匹の犬は、それから12年間、高校生たちの青春を見守った──。自分の「あの頃」と「故郷」が甦る感動の青春小説。
物語の始まりは昭和63年。捨てられた一匹の犬が、三重県四日市市にある進学校、八稜高校で保護される。子犬と成犬の間くらいだったその白い犬は、美術部員の名をとってコーシローと名づけられ、校長の許可を得て学校で飼われることになった。世話をするのは「コーシローの世話をする会」のメンバーたち。初代から3年おきに、その年の3年生を主人公にした物語が5話と、令和元年の最終話からなる連作だ。
昭和最後の年、女の子が勉強ができても仕方ないと家に縛りつける家族に反抗する少女。平成3年、自転車で鈴鹿サーキットにF1観戦に行った男子2人の冒険。平成7年のセンター試験の2日後、震災に襲われた神戸から祖母を引き取った家族。平成9年、東京で生まれ変わる資金稼ぎに援助交際をする学校一番の美少女。20世紀最後の年だった平成11年、死期の近い祖父を巡っていがみ合う家族に疲れ、英語教師に思慕を抱く少年。
アイルトン・セナ、『マディソン郡の橋』、阪神・淡路大震災、たまごっち、ルーズソックス、ノストラダムスといった言葉がその時代をまざまざと甦らせる。描かれる高校生たちの文化や流行り物は1話ごとに違う。けれど、同じなのだ。同じ青春なのだ。好きな人がいて、家族に反抗したり労ったりして、進路に悩んで。読みながら、どのページにも自分がいるような気がして、胸が詰まった。
高校生でいるのは人生の中のたった3年間だ。瞬く間に通り過ぎる幾つもの3年間を、コーシローはまるで川辺から流れる水面を見るがごとく見続ける。卒業してもずっと覚えていて、いつでも迎えてくれるコーシローは故郷の象徴であり、戻る度に成長し老いていくその姿は自分が経てきた時間を示す尺度でもあるのだ。読者は個々の主人公に自分を仮託する一方で、コーシローと共に帰ってきた卒業生の変化に一喜一憂するという二重の視点を持つことになる。これにより、読者は「点」の輝きと「線」のうねりを同時に体験できるわけで、実に上手いという他ない。
八稜高校のモデルは著者の母校だという。作中、ある人物が四日市の夜景を見ながら「私たちはここで暮らして、大きくなったんだ」と言う場面がある。登場人物の思いであり、著者の思いでもあるだろう。だがその時私の脳裏に浮かんだのは、自分が生まれ育った町の景色だった。登場人物とは育った時代も場所も違う。それでもこの物語は私自身の18歳を呼び起こしたのである。











