麻宮ゆり子による2018年発売の『碧と花電車の街』が、装いも新たに『花電車の街で』として文庫になった。文庫化にあたっての帯はこちら。

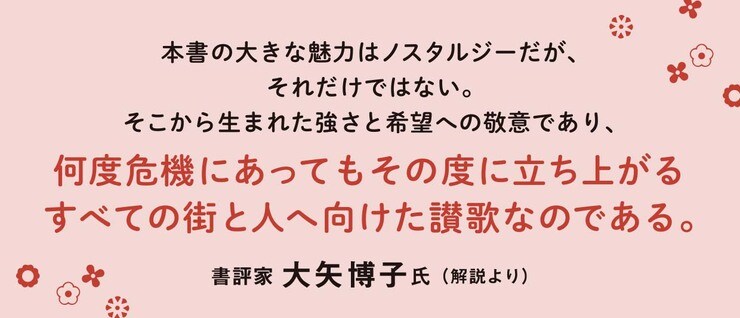
文庫化にあたり、単行本刊行時に「小説推理」2018年6月号に掲載された、書評家・大矢博子さんのレビューをご紹介する。
***
名古屋市中区大須。
織田信長が父親の葬式で抹香を投げつけたことで有名な萬松寺や、鎌倉時代に起源を持つ大須観音などを擁する古い門前町である。かつて遊郭があったこともあり、戦前までは歓楽街として栄えていた。映画館や劇場も多かった。今は中部地区を代表する電気街・パソコン街であり、メイド喫茶やコスプレサミットに沸くサブカルの街でもある。古いものと新しいもの、聖域と風俗。相反するものが横並びで成立する、不思議で元気な街だ。
麻宮ゆり子『碧と花電車の街』は、昭和三十年代の大須を舞台に、母親と二人暮らしの十代の少女・碧と、彼女を取り巻く人々を描いた物語である。
昭和三十四年、中学生の碧は映画と広告用の市電〈花電車〉が好きな少女。近所のストリップ劇場の人たちや地元紙の記者、長屋の大家さん、喫茶店の常連客など、大須ならではの猥雑にして個性的な人々の中で暮らしている。学校でテテナシゴと揶揄されたときも、大須の人々が守ってくれた。伊勢湾台風のときは、逃げ遅れた人々と一緒にきしむ長屋の中で震えながら踏ん張った。けれどそんなとき母が倒れ、碧の前にひとりの男が現れた……。
時代は高度経済成長期。時の流れの中で、碧の親しんだ映画館や市電は少しずつ姿を消していく。初恋の人も友達も大須を離れていく。ここにあるのは、人も街も、ひとつのところに永遠にとどまっているわけにはいかないという寂しさとほろ苦さ、けれどだからこそ人は成長していくのだという強さと希望だ。
碧は大須を「ごった煮の街」と表現する。前述したように普通なら並び立たないようなものが平気で並ぶ街だ。思えば昭和三十年代も「ごった煮の時代」ではなかったか。消えゆくものと伸びゆくものが歪に、けれどパワフルに混じり合った時代。「ごった煮の時代」に「ごった煮の街」で、ひとりの少女の夢と悲しみと葛藤と喜びと迷いと恋と恐れと……つまりは「ごった煮の心」をつぶさに描き出したのが、この物語なのである。
人は誰しもごった煮の時期を過ぎ、ひとつの道を選んでいく。だがその力はごった煮の時期に育まれたものだ。本書の大きな魅力はノスタルジーだが、それだけではない。そこから生まれた強さと希望への讃歌なのである。
過去二作の飄々とした麻宮作品とはかなりタイプが異なる。魅力的な新境地を見せてくれた。
(『碧と花電車の街』より改題)










