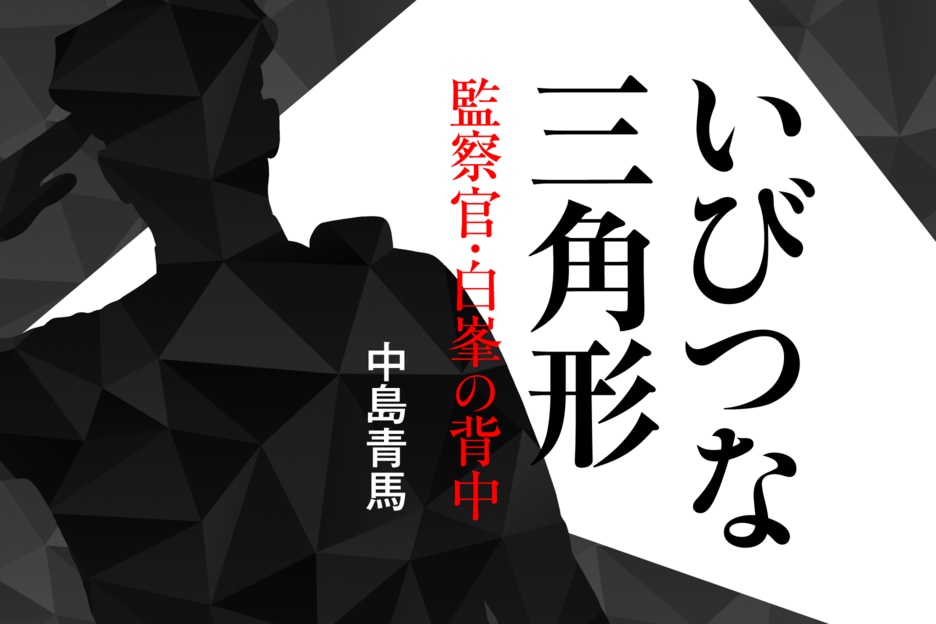「只野係長は今日も休みなのか」
戌井ではなく只野のことを聞くと、酉埼の表情が曇った。
「熱を出したらしくって。今日で三日目です。感染症ではないようですが」
「君から見て、只野係長はどういう人物だ。管理職として、だが」
「あまり目立つ存在ではないですね。もっとも、うちの係とは部屋が違うので顔を合わせる機会は少ないですけど。ただ部下の扱いに関しては留置係の人間から愚痴られたことがあります。塚原の素行の悪さに周囲も辟易していたようですが、何しろ最年長でしたから。本来、それを注意し、指導するのが上司の役割ですけどね」
「叱れない上司か」
「ええ、うちの係にも定年近いベテランがいます。素行が悪いわけではありませんが仕事の面では多少問題を抱えています。年上の部下を持つ苦労は身に染みていますよ。だからといって放置していいわけじゃないですから」
「君の言うとおりだ。上に立つ人間には相応の覚悟が必要だ。嫌われようが疎まれようが自分の信念を貫く覚悟がね」
「私は、白峯さんの背中を見てそれを学びました。迷ったときに思い出して道標になる人に出会えたのは幸運でした」
真顔で言う酉埼から、ちょっと目を逸らした。
素行の悪さを上司が注意せず、見て見ぬふりをしていたとすれば、不正を働く「機会」があったということになる。単に只野が「叱れない上司」だっただけなのか、あるいは三年前の一件が関わっているのか。
「お待たせしました」
戌井が戻ってきた。コピーを受け取る。
「他にも手伝えることがあれば、お申し付けください」
「分かった。何かあれば連絡させてもらう」
二人に礼を言い、名越署を出た。酉埼から預かった崎田の名刺を取り出す。
警察を辞め、新たな人生を歩んでいる崎田に過去の話を聞くのは心苦しい。拒絶されるかもしれない。
私は祈る思いで名刺に記載された番号に電話をかけた。
名越市のショッピングモール内にあるカフェ。
午後二時。時間通りに崎田が店に入ってきた。
その姿を見て、安堵した。スーツ姿で、身だしなみにも、雰囲気にも崩れたところはない。どういう理由にせよ、退職の道を選択した人間がすさんだ生活をしている姿は見たくない。
「お時間いただきありがとうございます」
「前の職場についてお聞きになりたいことがあるというお話でしたが」
話し方にも落ち着きが感じられた。
「今更、という気もしますが」
「申し訳ございません。崎田さんが以前勤めていた職場で起きた問題を調査しております。背景となる出来事について、崎田さんがご存じではないかと思いまして」
「思い出したくない出来事もありますが」
言葉とは裏腹に、崎田の表情に暗いものは感じない。
「三年前の四月、ある日を境に弁当が一個多く発注されるようになりました。私は何か原因があったと考えています」
私の言葉に、崎田はすぐに思い出したようだ。
「その件ならよく覚えています。何しろ私が転職するきっかけになった出来事ですから。確かに、夕飯用の弁当が一個足りないことがありました。人数分発注したはずが、手違いがあったようで」
周囲を気にして言葉を選んで話してくれるのはありがたい。
「足りない分はどうしたんですか」
「業者に連絡しましたが、すぐには対応できないと言われました。食事の時間は決まっているので、上司に報告し、スーパーに買いに行きました」
それだけでは、弁当を多く発注するようになった理由として弱い。私の思いを読み取ったのか、崎田がうなずいた。
「もちろん、それだけではありません。その日のお客さんに、一人アレルギーを持った人がいました」
崎田が声をひそめた。
「発注時に卵アレルギーのお客さんが一名いることは伝えてありました。足りなかったのはその分です。そのお客さんの分だけ、普段と違う弁当の容器だと不審に思われるからと、全員分代わりを用意するよう指示されました。ご存じかと思いますが、施設の食事は、一日分のカロリーや栄養価が細かく決められていて、スーパーの弁当で条件に合うものは限られます。結局全員分同じ弁当を用意しました。もちろん卵アレルギーのお客さんの分は卵焼きを取り除いて。しかし、わずかに他の食材に付着していたのか、夜間に肌のかゆみを訴えました。幸い症状は軽度で本人から預かっていたアレルギー薬を服用させると症状は治まりました」
弁当の不足と卵アレルギーの被留置者がつながった。
「代わりの弁当への配慮が足りていなかったことも事実です。しかし、同様の事態が起きないよう、業者に注意を促すことは必要でした。しかし、上司に止められ、代わりに翌日から一個多く発注するよう指示されました。数だけは不足しないように、という理由で」
アレルギーを持った被留置者への対策としては十分ではない。なぜ、そこまで業者に遠慮したのか。
「弁当の発注先は老夫婦が切り盛りする名越市内の定食屋で、三十年間、弁当を配達し続けてくれていました。そして二ヶ月前に感謝状を贈り、地方紙や県内版のニュースでも報道されたばかりでした。感謝状を贈り報道までされた手前、その定食屋と事を構えたくなかったんでしょうね」
「当時の上司の判断ですか」
「直接の指示は係長の只野さんでしたが、おそらく高田課長の考えでしょうね」
藤島から弁当の予備をいつから発注しているのか問われた時に見せた高田の動揺。調べるまでもなく、彼には分かっていたはずだ。
「当時の日誌を確認しましたが、今のお話は記載されていませんでした」
「書きましたよ、日誌には」
崎田の表情が硬くなった。
「次の日、何もなかったように書き直された日誌を渡され、印鑑を押すように命令されました」
崎田の表情が、改ざんという言葉を口にした時の戌井と重なる。
「言ってみれば記録の改ざんですよね。それを強要されたうえに、私が発注ミスをしたんじゃないかと疑われて、続ける気が失せました」
「それで転職を?」
退職、という言葉を私は避けた。
「転職して気付いたことがあります。民間企業は不祥事を起こしたら、いや実際に不祥事を起こさなくても世間の評判一つで経営が傾くこともあれば、つぶれることもあります。しかし、警察はどんな不祥事を起こしても、つぶれることはない。だから同じことを繰り返すのではないでしょうか」
私は言葉を返すことができなかった。
監察官になってから痛感しているジレンマ。
不祥事を起こした警察官を処分しても同じことが繰り返される。M県警だけの話ではない。他県警で起きた不祥事も同様だ。警察官が処分され、その県警の監察官室が再発防止に努める、とコメントを出しても、その再発防止策が警察内で共有されることは少ない。結果、類似の不祥事が各県警で発生する。
留置施設内での死亡事案も、繰り返し発生している。
「崎田さんの言葉、肝に銘じます」
「私も、辞めてから気付いたことですけど」
崎田の顔に笑みが戻った。今が充実している。そんな笑みだ。
最後に聞きたいことがもう一つある。
「転職して良かったと思いますか」
「はい」
崎田が即答した。晴れやかな表情だった。
「入社して三年ですが自分の意見を遠慮なく言えますし、それを取り上げてもくれます。収入もそれほど変わりませんでしたしね」
同じ質問を戌井に投げかけたら、彼はどう答えるだろうか。
崎田と別れ、酉埼に電話をかけた。もう一度、名越署に戻る。
警察を辞め、民間企業に転職した崎田。
民間企業を辞め、警察に転職した戌井。
戌井と話をしなければならない。今回の事案と関係があるわけではない。しかし、今話さなければ、戌井の心が警察から離れてしまうのではないか。いわれのない不安がわいてきた。
名越署に戻り、正面玄関を入ると、戌井が待っていた。
「係長は会議室で待っています」
戌井の後に付いて、午前中と同じ会議室に向かう。その背中を見つめながら、どう話せばよいか考えた。
会議室のドアが開いた。出てきたのは高田だった。目が合った。高田は驚いた素振りも見せず、どうも、と頭を下げた。視線は私に向けたままだ。妙にゆっくりとした仕草が爬虫類じみている。藤島の前で、不安げに顔色をうかがっていた男とは別人のようだ。
「その後、何か分かりましたか」
崎田の証言通りであれば、高田が日誌の改ざんを指示した疑いがある。その疑いをぶつけるためには、もう少し確証が必要だ。
「ええ、色々とね」
私が答えると、高田は唇を舐めながら笑みを浮かべた。
「署長から、再発防止対策を講じるよう仰せつかっています。今後、不心得者が出ないよう、署員教育に一層注力いたします」
言葉だけを切り取れば、言っていることに間違いはない。だが、今は白々しさしか感じない。
「どうぞ、酉埼が中で待っています。彼にも最大限の協力をするよう命じたところです」
高田がドアを押さえ、脇にどいた。私は礼を言い、戌井と共に会議室に入った。高田が閉めたドアの音がやけに大きく感じた。
「お疲れ様です」
酉埼が椅子の背もたれで体を支えながら立ち上がった。
「君の方が疲れているように見えるぞ。よっぽど強く私への協力を命じられたようだな」
酉埼が苦笑しながら首を振った。
「逆ですよ。お判りでしょう」
「まあな。崎田さんに話を聞いてきた。詳しく話すことは出来ないが、日誌については戌井君の見立て通りだった。証言がとれた」
私の言葉に戌井がうなずいた。
「酉埼、少し戌井君と話をしたい。構わないか」
「承知しました。私は邪魔が入らないよう、うるさい上司の相手をしています」
酉埼が会議室を出ていくと、私は戌井と向かい合って座った。緊張している様子はない。昨夜から、どんな場面でも、彼の落ち着き払った態度は変わらない。
「君のおかげで、三年前にも不正が行われていたことが分かった。それが今回の事案の要因になったこともね。改めて礼を言うよ」
「いえ、やるべきことをやったまでです」
戌井が生真面目に答えた。
「すまないが、君の経歴を調べさせてもらった。日誌の改ざんに気付いたのは、前職の経験があったからか」
やはり、戌井の表情は変わらなかった。杉本が面接した時も、このような態度だったのだろうか。熱意とは異なる意志の強さ。私が感じている印象を杉本も感じたのかもしれない。
「前の会社では、入社後、品質保証部門に配属され、製造工程の監査や、クレームの調査、再発防止を担当していました」
静かな口調だった。真っすぐに私と目を合わせている。静かな眼差しにいくらか圧倒されるものを感じた。
「私が在籍していた会社の不祥事はご存じかと思います」
私はうなずいた。
「きっかけは週刊誌への内部告発でした。製品の出荷検査記録の改ざん。すぐさま内部調査チームが作られ、私もそのチームに組み込まれ、不祥事の調査と再発防止を命じられました。あらゆる記録を調べると、普段の監査で見落とされているものも多くありました。調査を進め、出荷検査部門が組織ぐるみで関わっていただけでなく、設計にも問題があり、顧客の認可を取得する段階からデータの改ざんが行われていたこともつかみました」
「当初は現場の作業者数人しか関わっていないと報道されていたはずだ」
「ええ、最初の調査結果は握りつぶされました。関わっていた人間があまりにも多すぎたのです。その中には当時の役員も含まれていました。結局、それは次の内部告発につながり、組織ぐるみで調査結果を隠蔽しようとしたことも明らかになりました」
戌井が目を閉じ、深く息を吐いた。
「組織が不祥事を起こすことはあるでしょう。重要なのはその後の対応だと思っています。私は、組織が対応を誤る現場を目の当たりにしました。それでも、私には何もできなかった」
「それで、会社を辞めたのか」
「はい。社長以下、経営陣が辞任し、体制は変わりましたが、それで会社の体質が変わるとは思えませんでした。警察ならば、不祥事が起きても対応を誤らず、厳正な対処をするのではないか、そう思いました。何より規律を重んじる環境に自分を置きたかったのかもしれません」
警察は不祥事の事後対応を誤らない。そう信じて警察の道を選びながら、正反対の事実を自分の手で見つけてしまった。
いや、見つけさせたのは私だ。
「戌井君、巻き込んでしまってすまなかった。警察だから間違いを犯さないというわけではない。残念ながら今回の事案も三年前の間違った対応が招いたものだ。幻滅しただろう」
「いえ、今はまだ幻滅していません。白峯さんがおっしゃった、真の原因をつぶさなければ、真の再発防止にはならない、という言葉。それを信じています」
任せろ、などと安易に答えることはできなかった。
「全力を尽くす。それだけは約束する」
頼りない答えに聞こえたかもしれない。
しかし、それが今言える、精一杯の言葉だ。
転職して良かったか。
その質問を、今はまだ戌井に投げかけることはできない。
名越署を出て、監察官室に戻った。
「やはり、調査を続けていたようだな」
佐伯には、自分の行動が読まれているだろうとは思っていた。
「わざわざ戻ってきたんだ。それなりの報告があるんだろうな」
私は今日一日の調査結果を報告した。同時に、戌井から提供された看守勤務日誌の筆跡鑑定の許可を求める。
「戌井という男、内部監査のレクチャーを頼みたいくらいだな。目の付け所が良い」
佐伯が誰かを誉めるのは珍しい。
「筆跡鑑定の件、許可する。前例がないだろうな、内部文書の筆跡鑑定は」
「そうでしょうね」
「改ざん前の日誌だが、残っていると思うか」
私はうなずき、自分の考えを話した。日誌は残っている。そう考えるとつじつまが合う。
「筆跡鑑定の結果が出たら、関係者の聴取を行います」
「分かった。明日の午後、本部に三人を集める。段取りは私が進めておく。白峯はすぐに筆跡鑑定を手配しろ」
席に戻り、科捜研に警察専用回線で電話をかけた。私が名乗ると、電話越しに戸惑う気配が伝わってきた。
専用ソフトによる簡易鑑定であれば文書をPDFで送るだけで鑑定できる。担当者の回答を受け、すぐに日誌のコピーをスキャンしメールで科捜研に送った。
二時間後、科捜研から筆跡鑑定の結果がメールで届いた。結果は戌井の読み通りだった。
午後七時。明日に備え、帰り支度をしていると、酉埼からメールが届いた。メッセージを読み、添付ファイルを開く。その内容は直接今回の事案に関係するものではない。しかし、ある人物を追及する一手にはなるかもしれない。
勝負は、明日だ。