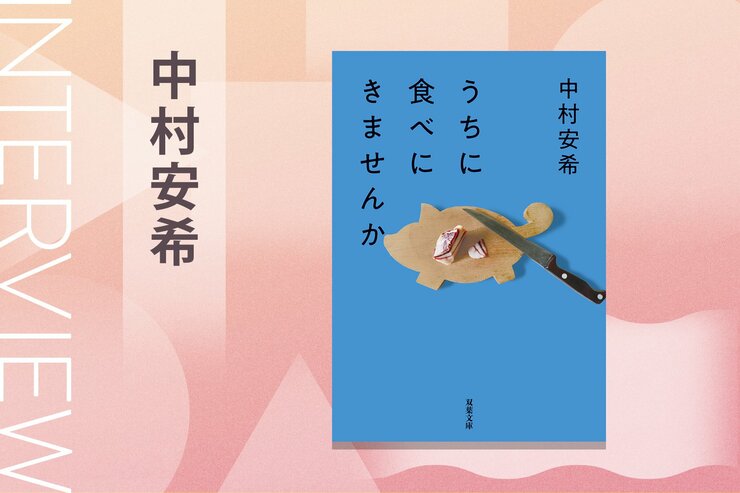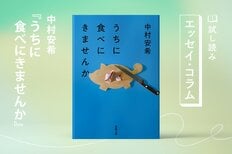ノンフィクション作家・中村安希さんの最新エッセイ『うちに食べにきませんか』は、旅先で出会った人の家に招かれ、食卓を囲むなかで生まれた小さな奇跡が綴られている。
世界各地を歩き、知られざる人々を記してきた著者はいま、地方の限界集落で古家を修繕しながら暮らす。遠くへ向かうのではなく足元を深く掘る生き方へと舵を切るきっかけとなった本作への思い、そして移動をやめた今、世界をどのように見つめているのかを聞いた。
「何者」にも見えない姿で歩く
――中村さんが海外で初めて会った人の家に招かれたり、旅先で人の輪に自然に入れたりするのは、どうしてだと思いますか。
中村安希(以下=中村):無理して打ち解けようとしてないからでしょうか。相手も自分も無理せずいられる人とは、うまくいく気がします。
――危険な目にあったことはありませんか。
中村:ありますが、経験を重ねるうちに、旅慣れた雰囲気が自分を守ってくれるようになりました。観光客の多い街を歩けば、服装や表情、視線ひとつで「この人はカモだ」と見抜かれます。リアクションも過剰で、どこか浮ついていて、地に足がついていないというか。若いころは、私も「騙しやすい」存在だったのかもしれません。旅の安全マニュアルどおりに行動したとしても、それは想定内の安心でしかない。悪意のある人は、その想定を逆手に取ってきますから。
――旅をしている時に気をつけていたことはありますか。
中村:服装です。なるべく何者にも見えないようにしていました。金持ちにも貧乏にも、バックパッカーにも日本人にも見えないように。先入観を与えない格好をして人に近づくと、相手も身構えないんです。新聞記者の友人にこの話をしたら、「その感覚は取材にも使える」と言われました。
――エジプト、シリア、ウガンダ……など17ヶ国の記録が本作には収められていますが、言葉が通じないことも多かったと思います。
中村:英語ができる・できないはあまり関係ないと思います。それより大事なのは、相手に合わせて語彙を選ぶ姿勢。ブロークンイングリッシュ同士で会話するほうが伝わるときもあります。
――見ず知らずの日本人である中村さんを家に招き入れてくれる人たちの姿が、とても印象的でした。
中村:私を飛び込ませてくれた人たちは、本当にすごいと思います。相手を見極めながらも、必要以上に飾らず、ただ「来てよかった」と心から言い合える時間をつくってくれました。日本のなかだけで気の合う人を探そうとすると母数が限られますが、世界に広げればチャンスはずっと広がる。全然知らなかった国にも、自分と波長の合う人たちはたくさんいるのかもしれません。
――中村さんの旅疲れを吹き飛ばした牛骨スープのエッセイに登場する、スロベニアのご友人が、本書のカバー写真を撮影されたそうですね。
中村:旅の途中で英語のブログをやっていて、その読者の一人が彼女でした。お互い第二言語の英語でやりとりをしていたけれど、吸い込まれるように仲良くなって。彼女が送ってくれたスラニーナ(豚の脂身の塩漬け)の写真は、10年以上お気に入りにしていて、それがカバーになりました。

毒にも薬にもならないところの豊かさ
――かつては「旅をする以外の方法で世界を知ることがわからなかった」と著書に書かれていましたが、2020年以降、一度も旅をしていないそうですね。
中村:世界のニュースは毎日あふれているけれど、それがすべてではないと旅に出る前から思っていました。たとえばアフリカには54カ国あるのに、ひとまとめに「アフリカ」と語られてしまう。アジアも同じです。誰かが決めた基準だけで世界を見ることに、ずっと違和感がありました。
海外へ行くからといって、無理に人と出会う必要はありません。美味しいものを食べ、きれいな景色を見て、「楽しかったな」と帰ってくるだけでもいい。旅の初めは、私も異文化や珍しい食べ物に心を惹かれていましたが、100ヶ国ほど回ると、風景はあくまで背景にすぎないと感じるんです。
「世界を知る」という行為そのものには、次第に興味がなくなっていく。結局、私が見ていたのは人で、目の前の個人との関係に重心を置くようになりました。それは、海外でなくても、日本でも十分にできる。たっぷり時間を使って、散々動き回ったからこそ、ようやく分かりました。
――旅をして世界を見ていた時期を経て、現在は、地方の限界集落で古家を改修している最中だそうですね。どんな心境の変化があったのでしょうか。
中村:「ジャーナリズム」と呼ばれるジャンルから手を引いたことが大きかったと思います。香港大学の大学院でジャーナリズムを学んでいたときに思ったのは、メディアにはそれぞれの立場や語りたい物語があって、「こう伝えたい」という意志が先にあるということでした。そこにあわせて、絵になる瞬間を切り取っていく。その営みこそが、ジャーナリズムの姿なのかもしれない。だから私は、報道というものをジャーナリズムというより、どこかアクティビズム(運動)に近いものとして感じることがありました。
ノンフィクションを書いていた頃、私はその限界をどうにか破ってみたかったんです。けれど、結局世の中はいつも、誰かが誰かに意見をぶつけ合う構図で動いていく。主張と主張のぶつかり合いのほうが、ずっとわかりやすく、刺激的だからでしょう。そんな中で、利害に結びつかない言葉や善悪の判断がつかないような出来事は、いつも見過ごされてしまう。けれど、本当はそうした「毒にも薬にもならないところ」にこそ、人々の静かな営みがあると痛感して。報道の枠の外にあるその景色を、ずっと見たかったのかもしれません。地域の人たちと協働しながら生きることで、地方のコミュニティや誰かの人生に触れられる今の暮らしにも、旅先と同じかそれ以上の面白さがあります。
――森の中で、古家を自らの手で解体し電気・水・下水を引くところから始めて1年半が経ったそうですが、いまはどんな一日を過ごしているのでしょうか。
中村:旅ばかりしていた頃は飼えなかった犬のひばりとリンダを迎えてから、生活が変わりました。朝は4時半頃に起きて、5時過ぎには家を出ます。湖畔のそばで、犬たちが自由に走り回るのを眺めています。週に数回「遠足」もあって、犬を飼っている仲間たちと朝早くから2時間くらい歩くんです。森の家で作業する日は、さらに早く家を出て、犬といっしょに山を登ってから作業を始めます。
――最後に振り返ってみて、本作はどんな1冊になりましたか。
中村:これまでにやってきた自分なりの旅とこれからの暮らしを繋いでいく1冊かなと。旅先で偶然経験することができた出来事を時間を置いてもう一度噛み砕いて、「そこに何が起きていたのか」を見つめ直した作品です。特別なものを探して遠くへ行かなくても、身近なところにもドラマはたくさんある。それを受け取れるかどうかは、きっと心の準備次第なんだと思います。この本は、その受け取る力についての記録でもある気がします。
――最後に、読者の方達へおすすめの一篇を教えてください。
中村:チュニジアの砂漠の家を訪ねた「うちに食べにきませんか」ですね。損得を超えて誰かを迎える、その時間のあたたかさを思い出させてくれます。