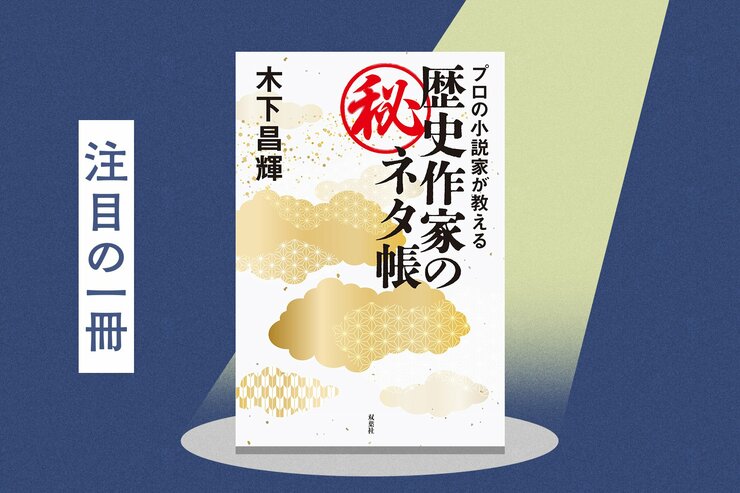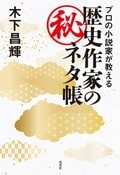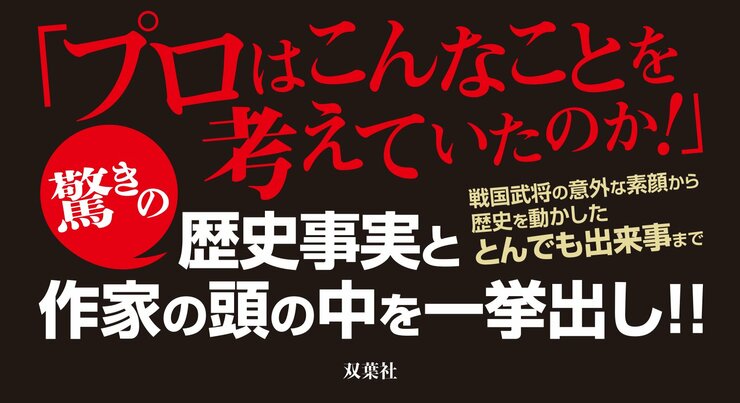
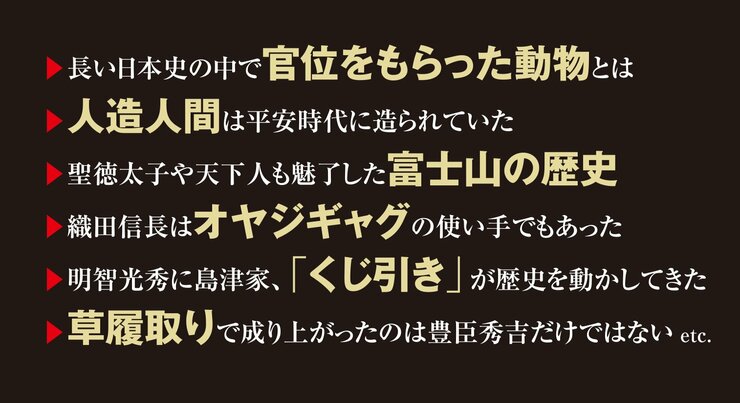
これまで4度も直木賞にノミネートされるなど、実力派にして強い人気を誇る木下昌輝氏。その魅力の一つは、歴史小説を新たな視点や見せ方で執筆していることだろう。
プロの歴史作家は史実から何を見て、何を感じているのか。創作のアイデアとなった意外な史料を著者自身が明かす異色のエッセイが『プロの小説家が教える 歴史作家のマル秘ネタ帳』だ。
木下氏にとって小説のネタとは何か。尋ねてみると、「寿司屋で言ったら本当に魚のネタに当たるもの」とその重みを明かしたうえで、“調理方法”などで作品のすべてが変わるとも話す。だからこそ、「ネタと言っても、全部、史実として分かっていると全然面白くないんですね。だから、一部、史実が分からない、いろいろな解釈ができるネタが一番嬉しいし、燃えますね」と、“調理の幅”が大きいものこそが小説家にとって歓迎すべきと言葉にするのだ。
歴史作家にとって、ネタ探しで大きなウエイトを占めるのが専門書に当たること。一冊を書きあげるために、関連書籍30冊以上を読むばかりでなく、「一冊を3回、4回と読んだり、効率が悪い情報収集をしています」と振り返るが、その“効率の悪さ”が新たなインスピレーションを呼んで「作品に深みを与える」と言い切る。
そうやって収集してきたネタや面白いと思いながらも作品に用いなかったネタを収録したのが本エッセイなのである。
歴史作家の頭の中を垣間見ることができる、その一部を特別公開しよう。
第5話 富士山に魅せられた英雄 1
「其の高さ測るべからず」
そう書かれたのが、霊峰富士山である。
書いた人物は、都良香という平安時代の貴族だ。大学寮という平安朝の教育機関で菅原道真も合格した「対策」という超難関試験を突破した男だ。
彼は『富士山記』という書物に、富士登山をした男から見聞きした内容を書き留めている。これがかなり詳細で、間違いなく登山経験者から取材したものだといわれている。
ちなみに、冒頭の文章の後には「史籍の記せる所をあまねくみるに、いまだ此の山より高きは有らざるなり」と続く(適宜難しい漢字はカナに直した)。
都良香が取材した人物こそ、日本最初の富士山登山者といわれている。
ただし伝説もいれると、聖徳太子が最初の登山者になる。
聖徳太子が二十七歳の時のことである。西暦でいえば五九八年、推古天皇は全国から名馬を集めさせた。その中に、甲斐国から送られた馬がいた。体が黒く足が白い馬で、それを聖徳太子は非常に気に入ったそうだ。そして、調使麿という男に飼育させた。
ある日、聖徳太子が調使麿とともに馬に乗ると、なんと都から富士山頂まで一気に飛んだという。
現代のヘリコプターや飛行機も真っ青な跳躍力だ。そして、信濃国などを見て回ってから、三日後に都へと帰ってきた。黒馬にタンデム騎乗させられた調使麿も富士登山第二号にいれてあげたい。
まさか、本当に聖徳太子が馬で一飛びでついたわけではないだろうが、そんな伝説を創作するほどに富士山は人々を魅了してやまない。ちなみに、富士山の七合目には、聖徳太子と馬の銅像が安置されていたという。
役小角にも富士山登山伝説がある。西暦で六九九年の頃、役小角は伊豆大島に流罪となった。だが、法術師でもある役小角は離島から富士山までたびたび登山したという。理由は、富士山で修行するためだ。昼は伊豆大島で修行し、夜になると富士山で修行したというのだ。さすがは山岳信仰の修験道の生みの親である。島だけでは修行が物足りなかったと見える。こちらは聖徳太子とちがい、自分の足で登ったようだ。

富士山に魅せられたのは、日本人ばかりではない。
中国、秦の始皇帝と彼に仕える方士、徐福もそうだ(方士とは、日本でいう陰陽師)。
秦の始皇帝は中国を統一し、最初の皇帝になった後、不老不死の術に興味を持つ。
そんな彼に、徐福は「東の海の先にある蓬莱山に仙薬があり、これを飲めば長生不老となる」といった。日本はこの時、まだ弥生時代、卑弥呼が活躍するより四百年以上前のことだ。
ちなみに、後の中国の史料『義楚六帖』には〝蓬莱山は富士山である〟と明記されているという。つまり、徐福は、東の先にある富士山に不老不死の薬がありますよ、といったのだ。
始皇帝はただちに船団を派遣することになった。率いるのは徐福である。
しかし、第一回は失敗したらしい。
徐福いわく「大鮫に邪魔をされた」ということだ。
さらに第二回の探検団が結成される。今回も指揮をとった徐福は、見事、蓬莱山の使者とコンタクトをとることに成功した。
戻ってきた徐福いわく、
「仙薬が欲しければ、良家の男女と百工を献上せよ、と仙人界の使者はいっております」
百工というのは、様々な職人のこと。なぜ、優れた仙術を使える仙人が、彼らからしたらローテクノロジーの職人を欲したのかは不明だが、とにかく始皇帝はその報告を信じた。
男女三千人と五穀の種と百工を派遣したというから凄まじい。
だが、徐福は帰ってこなかった。実は、すべての報告が出鱈目だったのだ。逆に彼は、仙薬探しを名目に始皇帝の独裁政権下からの亡命を果たすことに成功した。
しかし、蓬莱(日本)は当時、やっと稲作がはじまったばかりの弥生時代。とてもではないが、身一つで亡命しても生きていけない。そのために、偽りの仙界の使者の要求を伝え、百工と労働力として三千人の良家の男女、そして食料のもととなる五穀の種が必要だったのだろう。
脱獄や脱走をあつかった事件や物語は数多いが、これほど大規模なものはないのではないか。中国版のプリズンブレイクはやはりスケールがちがう。
ちなみに、富士山周辺には徐福の子孫と称する一族が住んでいる。山梨県富士吉田市に伝わる史料にはこう書いてある。
来日した徐福のメンバーは、五百五十二人。八十五隻の船でやってきた。
彼らが富士山に登ったかどうかは記載されていないようだが、富士山によって大きく運命が変わった人物たちといえよう。
さて、話を都良香に戻そう。彼が最初に取材した人物は誰であろうか。私が妄想するに、紀長谷雄ではないだろうか。
紀長谷雄は都良香の弟子で、同様に大学寮に入学し、対策という難関試験に合格した。
菅原道真の学友でもある。「第四話 人造人間の日本史」では、美女をかけて鬼と双六の勝負をした。
そして、文才もあった。それゆえか、紀長谷雄は『竹取物語』の作者ではないか、といわれている。
さて、『竹取物語』の最後を思い出してみよう。
かぐや姫に去られた帝は、姫からもらった不老不死の薬をもてあました。家臣に「天に一番近い山はどこか」と問うと、「駿河国の山」だという。
帝は家臣に命じ、その山頂で不老不死の薬を焼いた。
その山は不死の山──富士山と呼ばれるようになり、薬を焼く煙は今も山頂にたなびいている、という。
あるいは、富士山に登頂した紀長谷雄が、当時、活火山だった山頂の様子からイメージを膨らませて『竹取物語』を書いたのかもしれない。
ひとつ確かなのは、『竹取物語』を書いた謎の作者にとっても、富士山は魅力ある題材だったということだ。