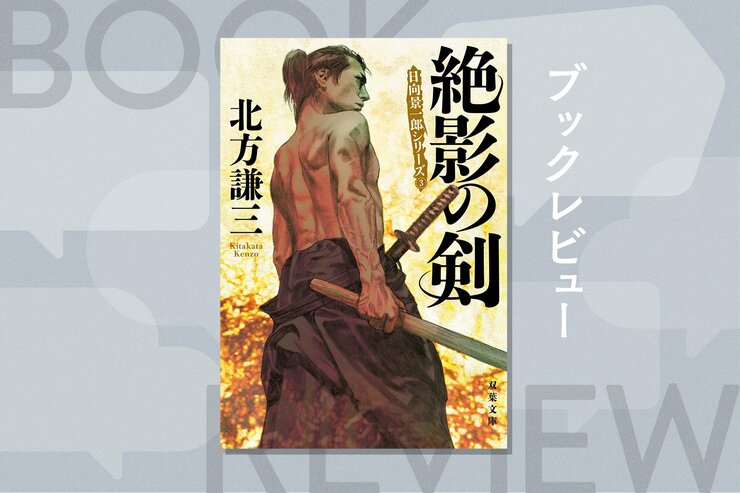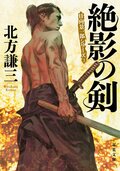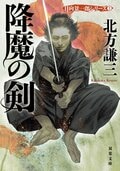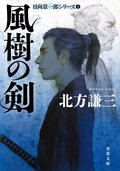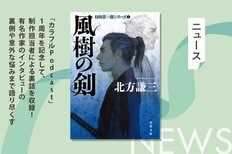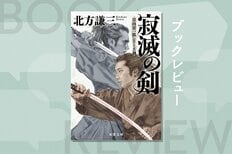シリーズ5作の中で「もっとも激しい暴力小説」と文芸評論家の池上冬樹氏が語るのが「日向景一郎シリーズ」第3弾『絶影の剣』だ。祖父から受け継いだ最強の剣術である日向流をつかう景一郎が10歳の弟・森之助とともに訪れたのは奥州・一関。そこでは藩兵に包囲され、皆殺しの憂き目に遭おうとしていた村人たちがいた。東北の山中にある村で起きた悲劇はやがて江戸の人たちを震撼させる事件へと繋がっていく。傑作時代小説の池上冬樹氏による文庫解説を公開する。
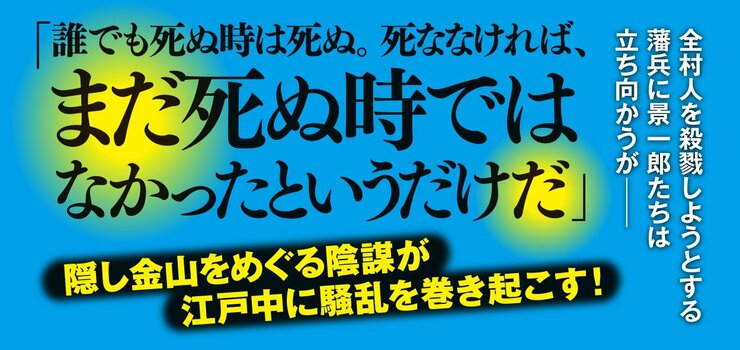
■『絶影の剣〈新装版〉 日向景一郎シリーズ 3』北方謙三 /池上冬樹 [評]
いやあ凄い凄い。日向景一郎シリーズ全5作の中で最も激しい暴力小説といっていいだろう。動から静へというのが第2巻だったが、シリーズ3作目の本書の前半は、動から動へとひた走る。アクションにつぐアクションの連続で、読む者の血をわきたたせ、昂奮させ、戦いに夢中にさせる。読むのがもったいないくらいに面白いのだが、次第に読み進めるのが辛くなるほど、人物たちの苦境が身にしみてくる。これ以上の不幸を見たくないからである。もちろん日向景一郎は、不死身であるけれど、農民たちの被害に胸がつまるのだ。座して死を待つしかない絶望的情況に追い込まれるからである。そして物語の後半は一転してクールな謀略劇となる。この二段構えの展開が抜群である。
物語は、まず、日向景一郎と森之助の旅の場面から始まる。
向島の薬草園の頭である菱田多三郎に頼まれて、日向景一郎と森之助は奥州・一関に旅に出る。薬草の種子を医師の丸尾修理に届けるのが目的だった。夏になる前に播けば、秋の終わりから使えるという。西は洪水、東から北は旱魃に襲われて飢饉に瀕し、多三郎はどうやって届ければいいか迷っていたが、自分が行こうと景一郎が申し出たのだった。
15日後、景一郎と森之助は一関につき、丸尾修理に種子を手渡すが、丸尾修理の養生所には町はずれにもかかわらず武士が数人たっていた。景一郎と森之助が山に向かうと六人の武士が近づき、何を調べにきた、あの医者に呼ばれたのかと聞かれ、斬りあいになり、景一郎はあっさりと斬り捨てる。丸尾修理の療養所に戻り、事情を伝えると、山で疫病がはやっているというが、人にうつる疫病ではなく、毒物によって農民たちが死んでいる、毒消しをもって行こうとしているのだが、藩医が疫病ときめて行かれない、3つの村を閉鎖して出入りを禁止しているというのだ。
景一郎は丸尾修理とともに封鎖された山間の小村にむかう。そこで見たものは水に毒をもられ、脱出を図ろうとして殺された村人たちの死体の山だった。どうやら新たに発見された金山を守るために、山を管理する伊達藩と田村藩の藩兵たちが村を壊滅させようとしていた。景一郎たちは村人たちを組織して、圧倒的な戦力を誇る藩兵たちと徹底的に戦おうとするのだが、情況はきわめて不利であり、勝算などひとつもなかった。
ここにあるのは、「去るのも死、残るのも死」(146頁)という情況だろう。もはや「残酷なことだなどという言葉は、この村にはもう存在していない」(140頁)。それほど過酷で凄惨すぎる行為と場面にあふれている。襲いかかる藩兵たちを殺し、村人たちも次々に殺されていく地獄だ。「ほんとのことを言うと、俺はいま、自分が生きているか死んでいるかも、わからねえ。もしかすると、景一郎さんも俺も死んでいて、地獄でこんなことを喋っている、という気もする」「なるほど。ここは確かに地獄だ」(157頁)という会話が出てくるが、そして本書を読んでいない読者は引用だけを読むと大袈裟ではないかと思うだろうが、違うのだ。もう目を覆いたくなるほどの場面の連続で、凄まじいのである。
おそらく多くの読者は、前半の設定だけを読んで、黒澤明の名作『七人の侍』を思い出すだろう。野盗たちの暴虐にたえかねた農民たちが浪人たちを味方につけて対抗する集団抗争劇だ。農民たちを守り、戦い抜くという点ではたしかに『七人の侍』ではあるけれど、しかし内実ははるかに厳しい。残酷という言葉はもう村には存在しないというほど、残虐さが普通になっていて、殺戮に続く殺戮、拷問、集団レイプ、幼児殺しなど無法地帯なのである。だが、この無法地帯での人間の営みを見つめることこそが、北方謙三が歴史時代小説を選んだ理由でもある。
「日本を舞台にしたハードボイルドを書こうとすると、アメリカを舞台にしたハードボイルド小説のようなわけにはなかなかいかない」と、北方はあるエッセイに書いている。「日本の場合、警察機構が発達しているから無法というものが通用しにくいのだ。拳銃を登場させるのだって、リアリティの確保に相当のエネルギーを要する」。だから「日本の現実に準拠したリアリティを求められるなかでハードボイルド小説を書いていくうちに、どんどん閉塞していってしまった」。これを打破するにはどうすればいいかをずいぶんと考え、結局、「閉塞状況を打ち破るためには、内面に向かうしかなくなってしまう。純文学を書いていた頃、さんざんこれをやって煮詰まった。違う展開を考えたかった」という。そしてその違う展開こそが、歴史小説だった。
「男の死に方。裏返して、男の生き方。ハードボイルド小説でぼくが書いてきたのは、一貫して男の生きざまだった。それを、もっとダイナミックに物語を展開できる世界。ぼくは、それを歴史小説に見つけたのだ。
歴史というのは、よくよく読んでみると、ほとんど血で綴られている。大量の血が流れているのだ。何百人、何千人をその場で殺すことさえ、歴史のなかでは充分にリアリティをもっている。
人を殺す。人を死なせる。死の恐怖を味わう。死の恐怖にさらされる。死の危険に直面する。歴史小説なら、こういうことがリアリティに縛られることなくいくらでも書ける。つまり、ハードボイルド小説よりもはるかに人間をダイナミックに動かすことができるのだ。これが一番の魅力だった。」(以上引用はすべて『風待ちの港で』(集英社文庫)所収「風の立つ港で」より)
はるかにダイナミックに動くのが、いうまでもなく日向景一郎であり、めざましい働きを見せるのが森之助だ。前作『降魔の剣』から五年、景一郎は30歳、森之助は10歳になっている。藩兵たちと村民たちの争いが激化しても、景一郎は土いじりをやめないのだが、危機が迫れば、一気に行動をおこし、命令をだして、農民たちを組織して防御にまわり、同時に攻撃へと転化する。その臨機応変かつ具体的な用兵、苛烈な行動力、さらに景一郎自身の鮮やかな剣戟で、ときに勝利を掴みもするが、それは一時にすぎない。圧倒的な兵力には差がある。それでも、10歳の森之助がいることで、しばしば事態は有利に動く。「森之助は、剣の腕前も10歳とは思えない、と杉屋さんに聞いたが」と丸尾修理が江戸の薬種問屋杉屋に聞いた話を問いかけると、次のような会話になる。
「未熟です。人を斬ったことはあるのですが、兄上のようにひと太刀で両断するなどということは、とてもできません」
十歳で、人を斬ったと平然と言えるところが、修理には驚きだった。この兄弟には、修理の理解を超えたところがある。
「大人になったら、兄上に勝てそうか?」
「わかりませんが、いつか兄上を斬らなければなりません」
「なにを言うのだ、森之助」(略)
「仕方ないのです。父の仇ですから。伯父上にも、兄上にも、そう言われています」(67~68頁)
そう語る森之助が数日後、景一郎にいわれて、みなの前である者を斬りすてることになる。読者はこの場面には度肝を抜かれるだろう。え? そこまでやるの? やらせるの? と驚いてしまうが、もともと父親殺しからはじまり、兄と弟の果たし合いで終わるシリーズなのである。「人を殺す。人を死なせる。死の恐怖を味わう。死の恐怖にさらされる。死の危険に直面する」ことを登場人物だけではなく、読者にもまざまざと体験させる小説なのだ。「歴史小説なら、こういうことがリアリティに縛られることなくいくらでも書ける」と豪語する作者だけあって、戦慄の場面がたんたんと鮮烈に描き出されていて怖い。
それにしても、そこまで残酷なことをさせなくてもと思うのだが、森之助の成長を描くには必要なことだろう。そもそも景一郎には「できるだけ人を斬らせよう」という考えがあった。「立会で斬るだけが、人を斬ることではない。抵抗しない者でさえ、ほとんど無感動に斬ることができる。祖父の将監がそうだった。自分も、そうなりつつあるのかもしれない」(154頁)。
いったい何だろう。この虚無感、この悟り、この諦念、そしてこの死生観は。「誰でも死ぬ時は死ぬのです。死ななければ、まだ死ぬ時ではなかった、ということですよ」(215頁)という言葉が中盤に出てくるが、これと似た言葉は北方謙三の小説によく出てくる。いちばん印象的なのは北方の『水滸伝』の一節だろう。
もともと『水滸伝』は中国の四大奇書の一つで、108人の豪傑たちが山東省の梁山泊に集結して、官軍と戦い滅びる物語である。民間説話が元になっているので、編者によって物語は異なるが、共通しているのは、108人の豪傑たちが梁山泊に勢ぞろいすること。その約束事を北方は破る。なぜなら北方は、原典を徹底的に解体し、全く新たな物語に再構築したからである。
北方の『水滸伝』は一言でいうなら、革命小説。ある対談(北方謙三編著『替天行道|北方水滸伝読本』所収「対談1 掟やぶりの『水滸伝』を語ろう 加藤徹/北方謙三」)で北方が語っているが、“キューバ革命がもっていた変革へのロマンチシズム”を『水滸伝』に移しかえた。梁山泊をキューバ島に見立て、宋王朝(米国)と対決する構図である。腐敗した体制のなかで虐げられている民衆が反乱を起こし、国を倒さんとする 物語だ。これは明らかに学生運動に参加した全共闘世代の思い入れだろう。だが観念的に革命を語るのではなく、あくまでもリアリズムで押し通す。つまり時代も国も違えども、まさに現代の小説として書かれている。それが吉川英治の『新・水滸伝』や柴田錬三郎の『柴錬水滸伝 われら梁山泊の好漢』ほかの類書と決定的に違う点だろう。
“変革へのロマンチシズム”というにはあまりに凄絶な死が多数描かれるけれど、そこに無残さはない。男も女も、志を全うするうえで、「死ぬべき時に、死ねばいい。死ぬべき時は、むこうからやってくるはずだ。その時までは、精一杯生きる」(『水滸伝六 風塵の章』311頁)と考えているからである。
『水滸伝』(全19巻)の刊行が開始されたのが2000年であり、本書『絶影の剣』の刊行も同年である。雑誌連載も同時期。『水滸伝』では潔くも苛烈な人生の数々が描かれるけれど、本書はどちらかといえば無残な人生だろう。全うすべき志をもつ者たちの変革の物語ではなく、日向景一郎がそうであるようにアナーキーで虚無的なヒーロー(中里介山『大菩薩峠』の机竜之助や柴田錬三郎の眠狂四郎に連なるヒーロー)の物語であるからだ。ただし本書では丸尾修理だけが、後半で志をもち、ある行動にうってでようとする。丸尾修理が後半の主人公なのである。物語の興趣にふれるので詳しくはいえないが、謀略と抵抗のドラマが展開する。村で凄惨な地獄を経験した丸尾修理が、己が性欲に負け、自らの本性を知り、だからこそ自らを恥じ、大義を求めて大胆な賭けに出ようとする。潜伏中の内藤新宿での女体への耽溺も、獣性に目覚め、破壊衝動をとがらせていく過程に見えて魅力的だし、そんな丸尾修理を後方で支える景一郎たちとの連繋もいい。支援する側には景一郎や丸尾修理と当初敵対していた者も含まれていて、彼の最期の行為などは、まさに“死ぬべき時に、死ねばいい”という境地で実に印象深い。
北方謙三の歴史時代小説と中国小説の特色などについては、次回以降でふれようと思う。まずは、圧倒的な臨場感と緊迫感をもつ本書『絶影の剣』を読んでほしい。日向景一郎シリーズを代表する傑作であり、北方謙三の歴史時代小説のなかでもトップクラスの趣向に富む物語だ。大胆なことをいうなら、シリーズを本書から読んでも問題はない。物語は独立しているし、本書に惹かれたなら、シリーズ第1作『風樹の剣』を手にとればいい。『水滸伝』と『岳飛伝』の文庫解説でも書いたことだが、大河小説または優れたシリーズはどこから読んでもいい。逆にいうなら、途中から読んでつまらないなら、その程度のレベルでしかない。一冊一冊の質が高くなければ、優れたシリーズにはならない。北方謙三のシリーズ作品は、どの巻から読んでも面白い。それは一作一作が充実しているからである。ぜひ本書を読まれよ。