20年以上、戦場を舞台にした小説を描き続けている古処誠二氏。とりわけ近年は第二次世界大戦下のビルマを物語の舞台に選んでいる。本作では、戦争が終わった後、俘虜収容所に収監されている日本人少尉と語学将校の英人大尉との間で緊迫した心理戦が繰り広げられる。そして物語のラスト、私たちの胸を衝くある人物の想いとは──。
「小説推理」2023年6月号に掲載された書評家・細谷正充さんのレビューで『敵前の森で』の読みどころをご紹介します。
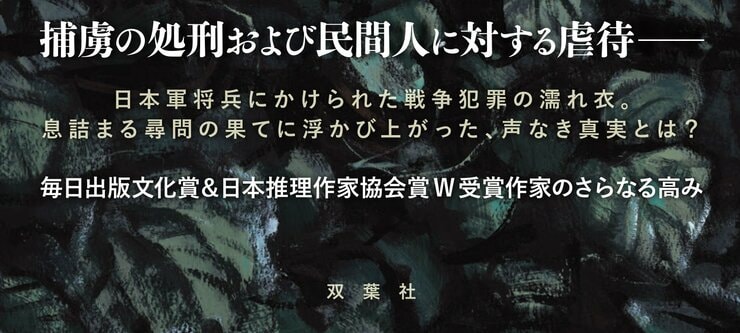
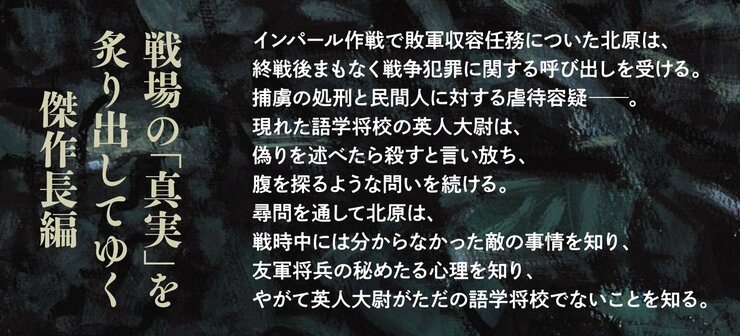
■『敵前の森で』古処誠二 /細谷正充[評]
戦争犯罪はあったのか。俘虜収容所にいた北原信助は英人大尉から、執拗な尋問を受ける。
古処誠二の最新作は、戦場の真実と、人間の想いを照らし出す。
自衛隊内部の事件を描いた本格ミステリー『UNKNOWN』(現『アンノウン』)でデビューした古処誠二は、第4長篇『ルール』から戦争小説へ転身した。以後、さまざまな戦争小説を発表しているが、第二次世界大戦下のビルマを舞台にしたものが多い。「小説推理」に好評連載され、このたび単行本になった本書も、ビルマが舞台である。
戦争が終わり、ビルマで戦っていた北原信助少尉は、現地の俘虜収容所に収監されている。その北原が、英人大尉に呼び出された。語学将校だという英人大尉は北原に、捕虜の処刑および民間人に対する虐待容疑による、戦犯容疑がかかっているという。インパール作戦で敗軍収容任務についた北原たちに、何があったのだろうか。
物語の半分以上は、北原たちが命じられた敗軍収容任務に費やされている。乾坤一擲のインパール作戦が失敗に終わり、マラリアや負傷などにより自力での撤退が困難な日本兵を、救出しなければならない。しかし、自動貨車大隊から抽出された土屋隊の一員である、見習士官の北原に、実戦経験はなかった。兵補であるビルマ人のモンテーウィン少年は逃亡。部下の佐々塚兵長は、英印軍の軍使として来た山岳民族のラングカンを、勝手に拘束してしまう。さらに対岸の英人指揮官との口合戦に、激しい戦闘と、北原の視点で敗軍収容任務の一部始終が綴られていく。
その合間に、北原と英人大尉のやり取りが挿入される。互いの腹を探り合うような2人の会話は、緊張感に満ちている。それにしても英人大尉が、北原を戦犯と疑う理由は、どこにあるのだろう。読者は、北原視点の部分により、彼が戦犯でないことが分かっている。とすれば単なる誤解なのか。それとも本当のことを知ったうえで、あえて戦犯にしようとしているのか。英人大尉の思惑が明らかになったときは驚いた。ああ、だから物語の時間軸が戦後なのか! ミステリー作家として出発した作者は、戦争小説でもミステリーの趣向を積極的に取り入れている。本書もそのような作品であり、この時代、この場所だから成立する真相に感嘆してしまうのだ。
さらに続けて、ある人物に対する北原たちの想いが露わになる。エピローグによって、その想いが強まる。北原を始めとする日本兵は、勇者でも英雄でもない。だが彼らには、人間として大切な心があった。古処誠二の戦争小説は、極限状態に投げ込まれた普通の人に寄り添っている。だからこそ、胸を打たれるのである。









