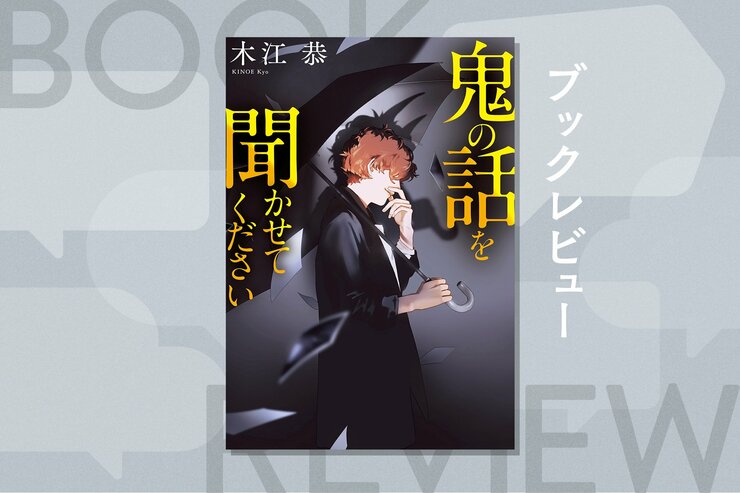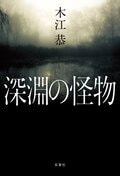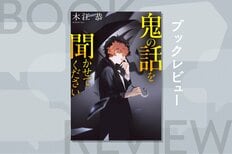第39回小説推理新人賞奨励賞を受賞しデビューした、気鋭の作家・木江恭による『鬼の話を聞かせてください』が文庫化!
「あなたが体験した“鬼”の話を聞かせてください」というSNS投稿企画に寄せられたのは、3つの奇妙な事件だった。投稿者の体験談を聞いて、真相に迫る写真家・桧山。やがて彼の推理は、誰もが目を背けたくなるような最悪の可能性へと辿り着いていく。
性格最悪の安楽椅子探偵が活躍する本作の読みどころを、ミステリ評論家・千街晶之氏の文庫解説からご紹介します。
■『鬼の話を聞かせてください』木江恭 /千街晶之[評]
ミステリ史上、最も性格の悪い安楽椅子探偵が登場する小説——木江恭の『鬼の話を聞かせてください』(2023年1月、双葉社刊)には、そのような表現が相応しい。
安楽椅子探偵とは、事件現場に赴くことなく、情報のみを頼りに真相を推理するタイプの探偵のことである。ジャック・フットレルの「思考機械」シリーズのオーガスタス・S・F・X・ヴァン・ドゥーゼン教授、アイザック・アシモフの「黒後家蜘蛛の会」シリーズのヘンリー、鮎川哲也の「三番館」シリーズの三番館のバーテン、都筑道夫の「退職刑事」シリーズの退職刑事、北村薫の「円紫さんと私」シリーズの春桜亭円紫、東川篤哉の「謎解きはディナーのあとで」シリーズの影山などが有名だ。しかし、本書に登場する探偵役は彼らの誰とも違う。彼は、謎を解くことで不安を解消するのではなく、逆に不安へと突き落とすのだ。それも、謎解きを聞かされた者が二度と安らかに眠れなくなるほどの、底無しの不安へと。
では、そのような特異な探偵を生み出した木江恭とは、どんな作家なのか。
著者は1988年、神奈川県生まれ。2017年、短篇「ベアトリーチェ・チェンチの肖像」が第39回小説推理新人賞奨励賞に選ばれ、同作を含む短篇集『深淵の怪物』で2019年に小説家デビュー。同年、「レモンゼリーのプールで泳ぐ」で第1回ドラマデザイン社舞台シナリオ大賞を受賞しており(2020年に舞台上演)、脚本家としてはドラマ『ギフテッド』(東海テレビ・WOWOW、2023年)がデビュー作となる。他に、ドラマ『3年C組は不倫してます。』(日本テレビ系、2024年)、ドラマ『失踪人捜索班 消えた真実』(テレビ東京系、2025年)などで脚本を担当している。
「レモンゼリーのプールで泳ぐ」は、ドラマデザイン社のホームページの紹介によれば、ガールズバーの店員が襲ってきた男を殺してしまい、自分たちの居場所を守るために店員たちが店の冷凍庫に遺体を隠す……という内容である。他の脚本作品もミステリが多く、著者のこのジャンルへの愛着が窺える。初の著書『深淵の怪物』には、意外性とともに不穏な読後感が尾を引く4つの短篇ミステリが収録されている(そのうち「さかなの子」は第73回日本推理作家協会賞短編部門にノミネートされた)。
そんな著者にとって初めての連作ミステリが本書である。まず、「プロローグ/エピローグ」という不思議な数ページがあり、続いて、第一話「影踏み鬼」(初出《小説推理》2022年2月号)が始まる。フリーライターの霧島ショウが「あなたの体験した『鬼』の話を百字以内で聞かせてください」というアンケートをSNSで実施したところ、50人を超える男女からの投稿が集まった。そのうちの一人である斎藤明良のもとに、霧島の代理だという写真家の桧山が話を聞きに来た。最初は投稿したことを後悔していた明良だが、相手の言葉に乗せられて、小学二年生の頃の思い出を語りはじめる。母と二人暮らしだった彼女は、祖母の新盆のため、初めて母の実家・妹尾家を訪ねたが、かつて母を勘当した祖父は、今でも母を許していなかった。のみならず、同居する家族とも折り合いが悪い様子だ。そんな祖父が、納戸で首吊り死体となって発見された。警察は自殺と判断したが、明良はその夜、祖父の部屋にいる人影を目撃していた……。
桧山は、一定のルールの中で最も矛盾の少ない解を正解と見なすと定めて、明良の証言に含まれた情報を思いがけないかたちでつなぎ合わせ、説得力のある仮説を紡いでゆく。にもかかわらず、結末に謎が解けたという爽快感はなく、後味の悪さは尋常ではない。その解が真実だという保証はないとしても、それが真実である可能性が存在することを一度認識してしまった以上、明良は桧山の推理に呪われ続けることになるのだ。
実は、霧島ショウや桧山が登場するのは、この短篇が最初ではない。先ほど言及した「さかなの子」(初出《小説推理》2019年8月号)に既に登場しているのだ。二週間前に殺人事件が起こり、その被害者の息子が通う中学校の教師である浜崎のもとに、「週刊レアリティ」の記者・霧島ショウを名乗る男がやってくる……という内容である。推測だが、「さかなの子」が日本推理作家協会賞短編部門にノミネートされるほど高く評価され、霧島や桧山をこの一篇だけで使い捨てにするのはもったいないキャラクターであると考えて連作化の構想が誕生したのではないだろうか。
第二話「色鬼」(初出《小説推理》2022年6月号)で扱われるのは、街のあちこちでカラースプレーによる落書きが繰り返されるという事件。犯人は「色鬼」なる通称で呼ばれるようになったが、やがて殺人事件にまで発展する。雑居ビルのあいだの路地で、全身をカラースプレーで塗り潰された少女の死体が発見されたのだ。その第一発見者である警察官・壇裕司のもとに、被害者遺族の依頼を受けた霧島を名乗る男がやってくる。
第三話「手つなぎ鬼」(初出《小説推理》2022年7月号)では、海辺の町に住む老人・樫本一彦のもとを霧島と名乗る男が訪れる。その町では60年前に放火殺人事件が起こっていた。「心中立鬼女」と呼ばれた犯人は他ならぬ樫本の妹だと思われていたが……。
ここまでの三篇は、桧山が事件関係者から情報を聞くだけで過去の事件の「真相」に迫る、典型的な安楽椅子探偵ものである。しかし、桧山は自分の推理で、証言者が心理的に楽になることを許さない。必ず、何らかの不安を植えつけてから帰るのだ。果たして桧山とは何者なのか、何のためにこのような行為を繰り返しているのか……という疑問が読者の心に残るだろう。
タイトルを見てホラー小説だと思い込んだ読者もいた筈だが、本書での「鬼」とは比喩的なものだ。双葉社の文芸総合サイト「COLORFUL」2023年2月14日に掲載された著者のインタビューによると、「人間は、自分が理解しきれない事象やすんなり消化できない体験に遭遇した時、無理やりにでも『納得できるストーリー』をこしらえようとすると思います。形だけでも『何か』のせいにして、わかったことにしたい。昔話の『鬼』も、死や天災、疫病などの『解決できない事象』を吞み込むために作られた『万能犯人』としての一面があるように思います。そういった象徴的な意味で、『鬼』という言葉を選びました」という理由があったようだ。また、「真相はかならずしも事実ではありません。この構造に面白さがあるように思いますが、どこから着想を得ましたか?」という問いには、「『事実や現実』と『誰かが信じる真相』が必ずしも一致しない、という仕掛けは、京極夏彦先生の『巷説百物語』シリーズに影響されている部分があります。ただ、『真相』の残酷さは桧山のキャラクターによるところが大きいです」「ご指摘の通り、桧山は意地悪な探偵です。ひとの罪や秘密をずけずけと暴く。そういうお前は何様だ、と言いたくなる。とはいえそれは、ミステリーの探偵役が多かれ少なかれ背負う業なのかもしれません。桧山はあえて、その業を超越した『天災そのもののような探偵』として描きました。事実とは限らない『真相』で周囲を翻弄するのも、人間にはどうすることもできない『人外』らしさの表れです」と答えている。
日本における「鬼」は、「桃太郎」などの昔話における敵役や、仏教の地獄の獄卒……といった一般的なイメージに収まりきらない。『日本書紀』で言及される「鬼」とは、ある時は天孫降臨の際に排除された国津神=先住民族であり、ある時は景行天皇が日本武尊に征伐させようとした東夷であり、またある時は大笠を着て山上から斉明天皇の葬儀を覗き見ていた正体不明の何者かだった。古代から日本人は、排除の対象を「鬼」と名づけ、国家の危機、集団の窮地、個人の不安などの原因を押しつけてきた。その意味で、「鬼」はまさに著者が述べる通り「万能犯人」なのだ。本書においては、忽然と現れて証言者に災厄を齎す桧山が「鬼」だとも感じられるし、証言者たちが体験した事件の犯人が「鬼」だとも言えるし、更には、人に言えない秘密を抱えた証言者本人こそが「鬼」だとも考えられるだろう。そんなおぞましい「鬼」たちの物語なのに、読むのを止められない。そこに、この連作のユニークな魅力がある。
第四話「ことろことろ」(初出《小説推理》2022年8月号)は、老人の転落死という事件を扱っている。ただし、このエピソードだけは安楽椅子探偵ものではない。これを読み終えた後、もう一度巻頭の「プロローグ/エピローグ」に戻ってみよう。ある登場人物のイメージに、そこで変化が生じないだろうか。謎を解くことは、時として人間の運命を激変させる呪いである。本書は、推理によって他者の人生に介入し呪いをかけた者とかけられた者の宿命的な物語であったことが、この第四話で判明するのだ。その意味で本書は、巧緻な伏線と真相の意外性を兼ね備えた本格ミステリであると同時に、謎を解くという行為に付随する危うさに鋭く迫った物語でもある。
先述のインタビューで、「テーマは、とても広い言い方になってしまうのですが、『人間の心』を書き続けたいと思っています」と述べていた著者。人間の心には「鬼」が潜む——誰の心にも。それを生み出す呪いのメカニズムを、著者はこれからも書き続けてゆくのだろうか。ひとの心をざわつかせる物語として。