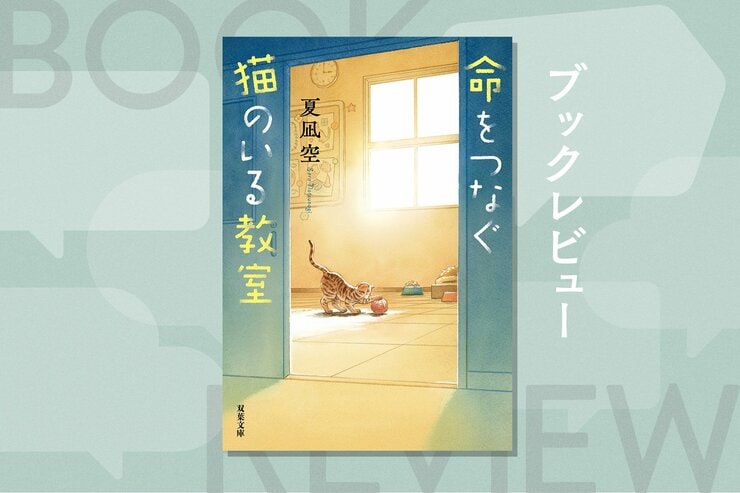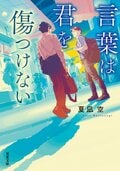発達に特性のある子どもたちが通う「放課後等デイサービス」で働く夏帆の愛猫・ツムジが、悪性リンパ腫の診断を下される。子どもたちの目に触れないようにすることを条件に、夏帆はツムジを施設に連れてくるが、あやまって子どもたちに見つかってしまい——。
努力だけではどうにもならない運命に直面しても、諦めずに生きていくことの大切さを思い出させてくれる、『命をつなぐ猫のいる教室』の読みどころを書評家・あわいゆきさんのレビューでご紹介する。

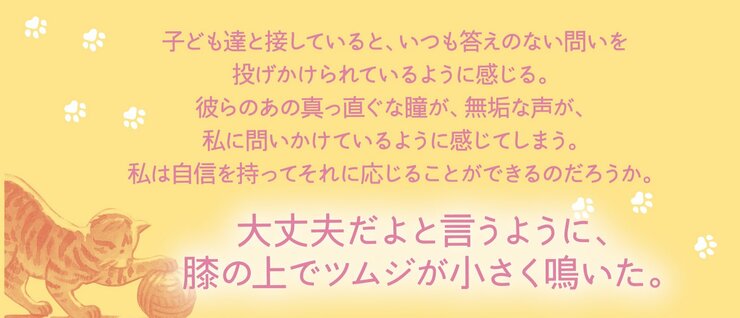
■『命をつなぐ猫のいる教室』夏凪空 /あわいゆき[評]
同じようにみえてもまったく異なる、自分だけの「感情」を手放さないために——余命わずかな猫がつなぐ、現実に立ち向かうための力
生きていると、ままならない現実に何度も直面する。自分の思うようにいかなかったとき、人口が減って寂れていく街を目にしたとき、大切な存在が一生を終えてしまうとき……。もし強固な現実を前に挫けそうになったら、私たちはどう現実と向き合えばいいのだろうか?
児童指導員に転職して9ヶ月目になる夏帆が直面した現実は、愛猫のツムジに下った〈悪性リンパ腫〉の診断だった。緩和ケアではなく抗がん剤による延命治療を選んだ夏帆は、いつ容態が急変するかわからないツムジを勤務先の放課後等デイサービス施設「パルマ」に連れてこれないか、教室長の大瀬良に相談する。許可を得たものの、施設に通う子どもにツムジが見つかったことで、子どもたちとツムジの交流がはじまる。
放課後等デイサービスにやってくる子どもたちは、発達になんらかの特性をもっている。こだわりが強い、落ち着きがない、字を書くことが難しい……困難を抱えた子どもたちを前に、ASDやADHD、LDといった単語を浮かべる読者も多いだろう。だが、特定の単語で特性を括ってしまうと、特性と向き合って生きている、ひとりひとりの感情をとりこぼしてしまう。だからこそ、作中ではそういった用語が一度も使われない。同じ名前で括られてしまいそうななかにある小さいようでとても大きな差異に対して、夏帆たち指導員はあくまでも差異ではなく個性として向き合う。それをごく自然と書いてみせるのは、作者の誠実さのあらわれだ。
一方で、特性に完治という言葉はない。だからどれだけ真摯に寄り添っても、特性によって誰かに迷惑をかけてしまったり、苦しめられたりするときがある。生まれもった特性に抗うことはできないのか──容赦ない現実を前にして、夏帆は子どもたちの将来を諦めそうになる。延命治療を続けるツムジの体調も悪くなっていく。
夏帆を立ち直らせるのは、施設に通う子どもたちのすがただ。子どもたちはツムジが回復するように願う。そして交流を重ねることでそれぞれの感情を育み、困難を少しずつ乗り越えていく。
現実を見ればツムジの死は避けられず、生まれもった特性も完全にはなくせないかもしれない。それでも生きてくれるはずだと信じて、諦めずに困難に立ち向かう──「感情」の力で運命に抗うことはできるのだ。そのためには、現実に挫けて自分だけの感情を手放してはいけない。すべてを諦めて運命に身を委ねるのと、運命を受け止めて自ら決めた選択は、たとえ結果が同じでも信じる気持ちに大きな差がある。
そして、諦めずに抗い、信じることではじめて変えられる運命もあるのだと、物語を通じて最後に希望が示される。読み終えたとき、現実に立ち向かうための力が間違いなく胸のなかに灯っているはずだ。