現役AI研究者にして、2001年に『われはフランソワ』で直木賞候補にもなった山之口洋が、10年の沈黙を破って発表した次世代警察小説『SIP 超知能警察』が文庫化された。
AI捜査を武器に、敵対国家、テロリスト、犯罪者を取り締まる「超知能警察」の活躍を描いた本書は、2022年に第28回大藪春彦賞候補になるなど、「AIが生活や文化と密接になった今こそ読んでほしい作品」として高く評価されている。
そんな本書の読みどころを、巻末に収められた書評家・細谷正充さんによる解説からご紹介する。
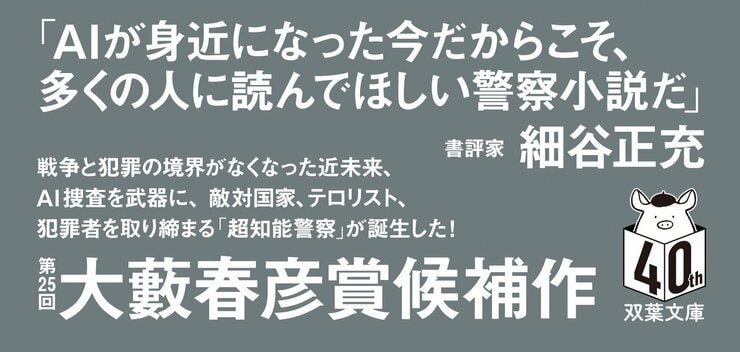
■『SIP 超知能警察』山之口洋 /細谷正充[評]
山之口洋は、予測不能な作家である。なにが予測不能なのか。まず作品の内容だ
一九九八年、第十回日本ファンタジーノベル大賞を受賞したデビュー作『オルガニスト』は、ミステリー・SF・青春小説など、さまざまなジャンルを融合させたファンタジーであった。以後、近未来SF・西洋史劇・時代ファンタジー・青春小説など、多彩な作品を発表しているのだ。次に出てくる物語が、どんなものかさっぱり分からない。まさに予測不能であり、だからこそ読むのが楽しくてならないのである。
もうひとつの予測不能が、作品発表のペースだ。作者は、一九六〇年、東京都に生まれた。東京大学工学部を卒業すると、人口知能研究関係の研究所や松下電器(現・パナソニック株式会社)で、AI(人工知能)の開発に携わりながら、作家デビューを果たしたのである。二〇〇一年に退社し、作家とフリーIT技術者を兼業とする。二〇〇六年には、「紙のキーボード」の開発で経産省・情報処理推進機構(IPA)より「スーパークリエータ」に認定されたのだから、IT関係の仕事にも力を入れていたのだろう。その一方で小説は、先に触れたように、一作ごとに内容をガラッと変えている。ほぼ一、二年に一冊のペースと、現代の作家としては寡作だが、そうなるのも当然といっていい。
そんな作者の長篇が、二〇一一年の『暴走ボーソー大学』を最後に途絶えてしまった。いったい、どうしているのだろうと、折に触れて思っていたら、十年の歳月を経て本書が刊行され、大喜びをしたのである。
『SIP超知能警察』は、二〇二一年十月に双葉社から刊行された書き下ろし長篇だ。物語の時代は、二〇二九年。二〇二五年の大阪万博では大規模テロが起こり、南北朝鮮は表向きは平和に統一され、統一朝鮮共和国が誕生している。
ストーリーは、市ヶ谷の防衛省に入省して八年目の相楽佳奈江が、朝鮮の慶州で犬に襲われ、大怪我をする場面から始まる。現場に駆けつけた男性医者によって助けられた佳奈江は、やがて日本に戻って仕事に復帰するが、記憶の混濁や短期消失など、体に不調を抱えるようになった。
このエピソードを「プロローグ」にして、メインの物語が始まる。警察庁科学警察研究所の情報科学第四研究室の室長・逆神崇は、AI捜査の普及と発展を提言していた。AI技術の進歩により変化する犯罪に、従来の警察の方法では、対処しきれないと確信しているからだ。そんな彼が率いる第四研究室(逆神研)に、警察庁の謎多き副長官・木戸亮一郎から特命が下った。調べる事件は、
A「日本海側各県における無戸籍児童増加の背景調査」
B「防衛省管内における連続不審事象の真相解明」
C「東北各県における『卒業アルバム』損壊多発事件の背景調査」
の三つだ。バラバラな三つの事件に、いかなる関係があるのか。個性的な部下たちと共に動き、AIによる巨大な深層学習ネットワーク“VJ”のインターフェイス用人格ジーヴスを使って、調査を進める逆神。やがて彼らの前に、驚くべき謀略が現れるのだった。
本書は作者初の警察小説である。ただし独自色が強い。AIに関する技術や知見が、山のように盛り込まれているからだ。最初から、逆神と木戸がディープなAI談義を始めるので、この作品はどこに向かうのかと、困惑してしまったほどだ。
だが、このAIに関する部分が、とても興味深い。繰り返しになるが作者は、人工知能研究関係の研究所や家電メーカーでAI開発に携わるという経歴を持つ。それだけにAI技術の進歩により、変化する社会への認識がリアルだ。特に、犯罪に対する考え方は、恐ろしいほどの説得力を持っている。たとえば逆神がいう「犯罪のシンギュラリティ」について木戸は、
「君は最近の論文でこう書いている──《技術的特異点》は犯罪や戦争の領域で先駆けて起こるかもしれない。近い将来において、われわれ警察が逮捕しなければならない犯罪者は、人間ではないかもしれないし、法的責任能力を持たないかもしれない」
といっている。他にも、深く考えるべき会話や文章が続出するのだ。正直にいえば本書を最初に読んだとき、書かれていることのすべてが理解できたわけではない。再読した今でも、やはりすべてを理解したと言い切れない。それでも近年の、生成画像AIを巡る騒動や、チャットGPTの問題点などを通じて、作者の主張はよりリアルに感じるようになった。だから本書は、AIが生活や文化と密接になった二〇二四年の現在にこそ、読まれるべき作品といえるかもしれない
もちろんAIは、あくまでも道具である。事実作者は登場人物のひとりを通じて、
「AIから逃げる必要なんかない。どんどん使いやすくなるAIを、人間と同じ社会の一員として受け入れ、自分の仕事を肩代わりしてもらえばいいだけなのだが」
と書いている。AIの開発に携わった人間の、偽らざる気持ちだろう。結局のところ、人が技術とどう付き合うかということが、一番肝心なことなのである。
さて、ストーリーに話を戻そう。第四研究所のメンバーは、リーダーの逆神以下、井伏健二・西田宙・小森田信吾・物原瞳・須田マクシミリアンの六人(P・G・ウッドハウスのユーモア小説「ジーヴス」シリーズの主人公から名前づけられ、英国紳士の仮想人格を持つAIアシスタントのジーヴスも仲間といっていいだろう)。三つの案件が日本海側に集中していることから、金沢に「SIP株式会社」という拠点を構え、手分けをして調査を始める。防衛省の第二情報保安室所属の来嶋奈海一等海尉と、航空自衛代第六航空団の才谷彰三等空佐もメンバーとして加わる。一癖も二癖もある第四研究所の面々の調査により、しだいに明らかになっていく、それぞれの案件の真相が面白い。
なかでも注目したいのが、物原瞳が担当するA案件だ。現地でストリートチルドレンのことを調べている任田巡査部長から、ショータという少年とサヤという少女を紹介された物原。サヤという少女と親しくなるが、彼女が失踪してしまう。調べるうちに意外な事件も掘り起こすことになり、リーダビリテイが加速していく。また、ストリートチルドレンたちを心配し、上や横からヤイヤイいわれながら、他の地域の警官たちと連絡網を作っている任田には、いぶし銀の魅力があった。C案件で、小森田がまず訪ねた酒田署の穂積巡査部長もそうだが、地道かつ誠実に働く警官の姿も描かれているのだ。人間の持つ矜持や優しさを、しっかり表現していることを、忘れてはならないだろう。そこにも作者の主張が込められているのだ。
さらに本書には、ミステリーとしての重要なポイントがある。無関係に見える案件が、どう繋がるかという“ミッシングリンク”の謎である。随所に、佳奈江のパートも挟まれているが、それを含めてすべてが繋がったとき、巨大な陰謀の構図が見えてくる。なるほど、これを成立させるために、あの設定があったのかと、驚きつつ納得。凄いことを考えるものだ。
しかも真相が明らかになってからも、切迫した状況が続き、緊張感が途切れることはない。終盤は、もはや冒険小説だろうといいたくなるアクションの連続で盛り上がった。一方、ジーヴスの扱いに、AIとの付き合い方の難しさも感じる。作中で言及され、「エピローグ」であらためて示されたAI時代の『倫理』の問題は、もはやフィクションではないのだろう。AIが身近になった今だからこそ、ひとりでも多くの人に読んでほしい、作者ならではの警察小説なのである。









