大沢在昌のデビュー作は、「第1回小説推理新人賞」を受賞した短篇「感傷の街角」だった。だが、初の著書は、同作と同じく、探偵事務所の失踪人調査人として働く佐久間公が活躍するシリーズの長篇『標的走路』である。この度、その『標的走路』をはじめ、「感傷の街角」を表題作とする短篇集を含む、初期の佐久間公シリーズの4冊が双葉文庫入りすることになった。日本を代表するハードボイルド作家として活動を続ける大沢在昌の原点ともいえる作品群だ。佐久間公とはいったいどんな主人公なのか。大沢に、彼について語ってもらった。
取材・文=杉江松恋 写真=鈴木慶子
ハードボイルドは古臭いものと思われ始めていた。だから、読者をハラハラさせたかった
大沢在昌(以下=大沢):私にとっては書き下ろしで出た『標的走路』が最初の著作です。「フタバノベルス」というレーベルが創刊したばかりで、『標的走路』はたしか、ナンバリングが一桁なんですよ。双葉社の小説誌である「小説推理」は2、3ヶ月に1回のペースで書かせてくれました。勉強の場をくれたんです。
──『標的走路』は最初の本だから、胸に期するものがありましたか。
大沢:それまで長篇を書いたことがなかったので、気負いはあったかもしれませんが、佐久間公は私が高校時代に考えたキャラクターなので、人物像は把握できていました。
──佐久間公という名前はどういう由来でつけたものなんですか。
大沢:周りにその名前がいなくて、佐久間ってカッコいいな、って思っていたの(笑)。字面先行ですね。2年くらい前に気づいて愕然としたんだけど、私の主人公ってほとんど「さ」で始まる名前なんですよ。「鮫島」「佐江」「冴木隆」「坂田勇吉」。みんな「さ」で始まる名前なんですよ。編集者も、誰も指摘しなかったんですよね。
──『標的走路』は私立探偵小説の始まり方をしますが、中盤から冒険小説の展開になって、後半はさらにびっくりするような変貌を遂げます。豪華な展開ですね。
大沢:これを書いたころハードボイルドは古臭いものと思われるようになっていたから、冒険小説でもなんでも入れて、とにかく読者をハラハラさせたかったんです。初めての長篇だから最初で最後、レジュメなんか作って書いたけど、それ以降は話の構造だけ決めておけば、プロットなんて立てなくても書くことができた。
私の本はまったく売れなかった。でも若かったから、未来には希望しかなかった
──佐久間公ものではない第2長篇の『ダブル・トラップ』を書いた時点で24歳。もうプロットなしで書けると判断されたんですね。その若さで迷いがないと言いますか。
大沢:迷うもなにも、そのころ私の本なんかまったく売れなかったんですよ。でも書き続けるしかなかった。書いていれば、そのうち何かあるだろうって。まだ若いから、未来には希望しかなかったんです。1980年代の前半はハードボイルド・ブームと言われて、私もいろいろな特集に引っ張りだされたりしたけど、冷静に見ていましたね。「これはハードボイルドじゃなくて、北方謙三さんのブームじゃないか」って。北方さんをはじめ、船戸与一さん、志水辰夫さん、逢坂剛さん、一緒にやっていた仲間が賞を獲ってブレイクしていく。私だけがずっと〈永久初版作家〉まっしぐらだったんです。1989年に勝負作『氷の森』を書いたけど空振りで、やけになって翌年『新宿鮫』を書いたら、これが当たった。
──1980年代に書かれた佐久間公は、大沢さんにとって雌伏期の相棒ですよね。
大沢:そう。だから、公には良い思いさせてねえなって(笑)。後になって出した『雪蛍』と『心では重すぎる』は本としても売れたし、評価もされたんだけど、すでに私が50歳近くなってましたからね。若いときは公に、苦労しかさせてなかった。
佐久間公は、自分の分身だという感覚がずっとあった
──糟糠の妻みたいなもんですね。
大沢:妻じゃないけど(笑)。公が自分の分身だという感覚はずっとありました。
──佐久間公ものの最初の短篇集が『感傷の街角』ですが、印象深い作品はありますか。
大沢:「風が醒めている」は、原稿を落とした人がいて、代わりに書けって言われたんです。原稿用紙で60枚、実際には3、4日間で書いたんじゃないかな。それに山野辺進※さんが挿絵をつけてくださったんです。山野辺さんが「素晴らしい短篇だ」と言ってくださって、憧れの存在だったから有頂天になったのをよく覚えていますね。「あなたは必ず直木賞を獲るから、がんばって書きなさい」とも。実際に獲ったときは「僕が思ったより3年遅かったね」って言われましたけど(笑)。『感傷の街角』は毎回実験しているんですよ。本格ミステリー風あり、タイムリミット・サスペンスありで。主人公は人捜しをし、その過程で事件に巻き込まれる。事件の形を変えることでいろいろ試すことができました。
※山野辺進
画家・イラストレーター。1960年代より、推理小説を中心に挿絵を多数描いている
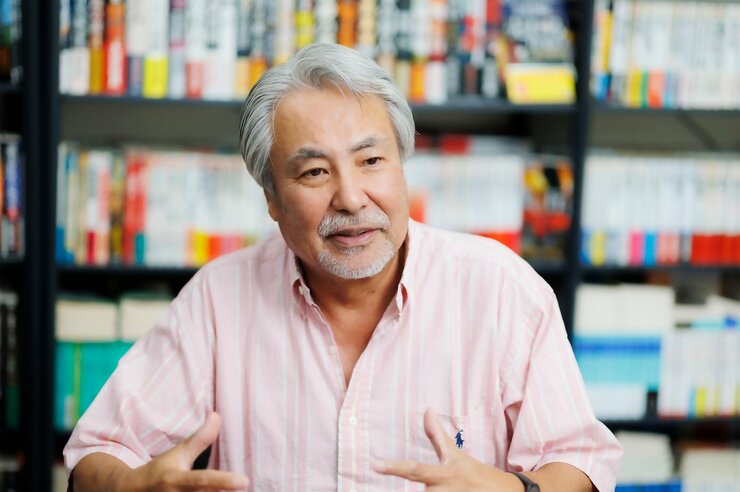
まっとうな人たちが生きる世界と、グレーな人たちが生きる世界。その狭間を行き来して、色んな人たちを見てきた
──音楽やファッションなど、当時の風俗が細かく書きこまれているのに驚きます。
大沢:「小説推理新人賞」を受賞したとき、ハードボイルドにしては青臭すぎると言われたんです。でもハードボイルドの匂いのある小説だと。それを聴いて、勝負するには青臭さしかないと思ったんですよ。背伸びして、かっこつける。このシリーズを好きになってくれた人は、私と公の背伸びを気に入って成長を見守ってくれたんだな、と後で思いましたね。
──「感傷の街角」は佐久間公が横浜で事件に巻き込まれる話で、文中に矢沢永吉と松任谷由実への言及があります。おそらく当時の日本ミステリーでは初だったと思います。
大沢:大学のときにフェリス(女学院大学)の子と付き合っていて、やたらと山下公園とか石川町でデートしてたんですよ。あと出てくる街は六本木、広尾。そのへんで調子に乗ってふわふわ遊んでいた自分そのままです。社会経験がないから、自分が見たものしか書けないわけですよね。一方で、まっとうな人たちが生きる世界と、そうではないグレーな人たちが生きる世界があって、自分はその狭間を行ったり来たりして、色々な人たちを見てきました。そういう裏の世界を書けるのは自分しかいない、という自負もありました。自分にしか書けないものを書くことによってしか小説家って前に進めない。そういう思いは今でも強くあります。
──佐久間公は危難に遭う主人公ですね。敵から暴力を受けて傷つくことも多いです。
大沢:そうじゃなきゃ嘘だと思います。鼻っ柱が強いから突っ込んでいく。そうなれば小突き回されることも多いでしょう。でも逃げない。歯を食いしばってしがみついていく。それが佐久間公だというのが自分の中ではありました。私はディック・フランシスのシッド・ハレーもの、特に『利腕』※がすごく好きなんです。あのラストシーンが象徴的で、シッド・ハレーの意志が最後には勝つ。ハードボイルドを書いていく上で大事なのは体力や武器じゃない、心なんだ、ということは大事にしていきたいと思っています。
※『利腕』
元騎手で片腕の調査員、シッド・ハレーが主人公のミステリーシリーズ第2弾。エドガー賞などを受賞した傑作
佐久間公の新作を書くとしたら──遺作だな(笑)
──1987年の長篇『追跡者の血統』をもっていったん佐久間公ものは中断されます。それはなぜだったのでしょうか。
大沢:一人称の〈僕〉で若者を書くのが辛くなったんです。だから29歳で止めた。そこからは、大人のハードボイルドを書こうと。1996年に『雪蛍』で再登場させたときに、公の一人称は〈私〉に変えています。次の『心では重すぎる』は重い内容で大変だったんだけど、これを終えないと自分の中で佐久間公に決着がつかないと思って書き切りました。今でも「佐久間公の新作を」と待ってくださる方が多いのはありがたいことですね。
──もし、再開するとしたら、公にはやはり歳を取らせなくちゃいけないですか。
大沢:取らせると思います。実は、公が出る「無辺の夜に生きる」という短篇を前半だけ、講談社の小説誌「小説現代」に書いたことがあります。東日本大震災について自分が何かできないか、ずっと考えていたことを絡めて書いたんですけど、体力的に辛かった。公も年齢を重ねて変わっているから、今の彼を自分なりに理解しないと始められないですよね。難しい。
──でも読んでみたいですね。今回の初期作品も、若い方には私立探偵小説の原風景として読まれるんじゃないかという気がします。だから新しい佐久間公も機会があればぜひ。
大沢:じゃあ、遺作だな。私の絶筆はたぶん、佐久間公になりますよ(笑)。そのくらいの寛大な気持ちで考えていただければ。












