人生の最後に贈りたいものはなんですか? 遺品配送業者で働く配達人・七星が活躍する『天国からの宅配便』(柊サナカ著)がこのたび文庫化された。
単行本刊行時から様々な反響があった本作。生前に依頼人から託された荷物は、自分自身よりも残された大切な人たちへの優しさを詰め込んだ小包みばかりだ。亡き人の想いに思わず涙がこぼれる感動の物語を「小説推理」2022年4月号に掲載された書評家・大矢博子さんのレビューで読みどころをご紹介する。
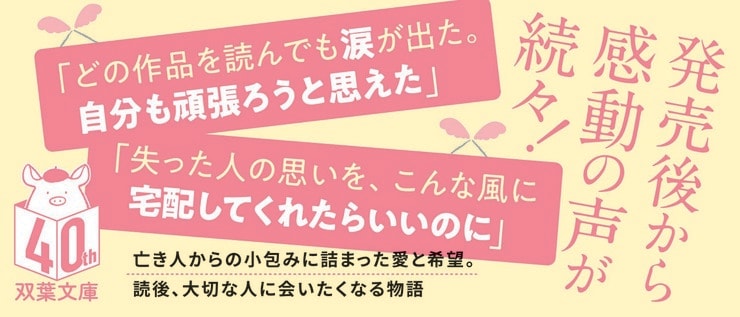
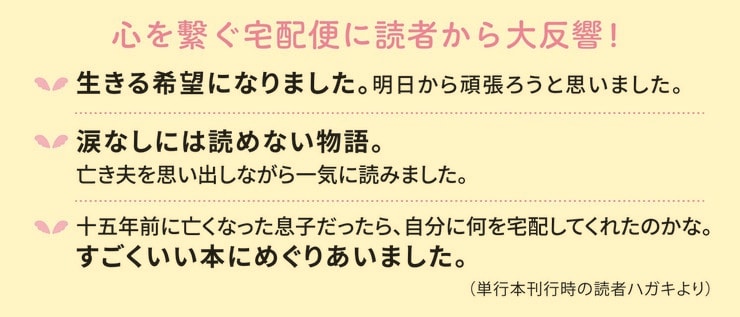
■『天国からの宅配便』柊サナカ /大矢博子[評]
亡くなった人から届けられた宅配便。それは残された人の人生を照らし、心の凝りをほぐしていく──生きていることが愛おしくなる、ぬくもりの物語。
同居して楽しく老後を過ごしていた女友達2人に相次いで先立たれ、孤独の中で家事すらしなくなってしまった75歳の夕子。近所の助けも拒否し、ゴミ屋敷で暮らす彼女のもとに、ある日、宅配便が届いた。夕子がともに暮らしていた亡き友人2人の遺品だという。訝しみながらも中身を見てみると、そこにあったのは……。
というのが第1話「わたしたちの小さなお家」である。以降、物語は連作の形で、第2話「オセロの女王」では閉鎖的な田舎から出て行きたくて祖母とケンカの絶えなかった女子高生のもとに、第3話「午後十時のかくれんぼ」では家庭に居場所のない中年男のもとに、第4話「最後の課外授業」では問題をかかえた大学生たちのもとに、それぞれ亡くなった人からの宅配便が届く。
ファンタジーめいた設定だが、これは現実の物語であることをまずお伝えしておこう。誰かに渡したいものを亡くなる前に託しておけば、死後にそれを配達してくれるという宅配サービスの物語なのだ。
もう会えない相手から届く贈り物とメッセージ。中には何年も会ってなかった相手もいる。なぜその人は、それを業者に託したのか。何を伝えたかったのか。その理由がわかったとき、受け取った側がそれぞれ抱えていた生きづらさや問題が、まるでもつれた糸をほぐすように解かれていく。託される思いのあたたかさに、読んでいるこちらも胸のしこりが溶けていくような感覚を覚えた。特に第3話はミステリとしても実に秀逸だし、第4話の結末には一気に世界に色がついたような爽快感を覚えたものだ。
だが読みながら──特に第2話と第3話には、どうしても気になることがあった。なぜそれを生きているうちに伝えなかったのか。もう取り返しがつかないじゃないか。
そう考えさせることこそが物語のテーマなのだと気付かされたのは、第4話とエピローグを読んだときだ。この物語は、自分が死んだ後そばで見守ることはできないが、どうか幸せでいてほしいという思いの発露であると同時に、お互い生きているということがどれだけの僥倖か、生きて思いを伝えられるということがどれだけ幸せなことか、それを描いているのだ。
生きているということがとても愛おしく感じられる。この一瞬はかけがえのないものだと心に沁みる。自分は誰に何を遺したいと思うだろう。いや、その前にちゃんと伝えよう──そう思わせてくれる物語だ。











