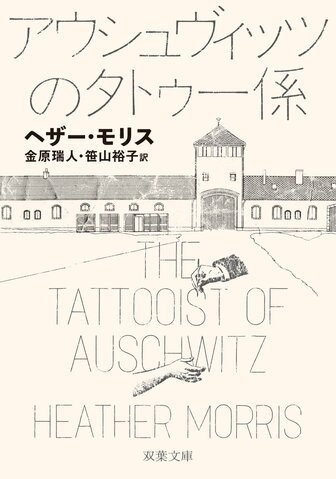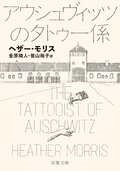第二次世界大戦中の「絶滅収容所」アウシュヴィッツ=ビルケナウで、生き延びるために同胞である収容者に囚人番号を刺青する役目を引き受けた男性ラリ・ソコロフ。その独白をもとに書かれ、全世界で350万部を売り上げる大ベストセラーとなった小説が『アウシュヴィッツのタトゥー係』です。2019年に邦訳単行本が刊行された本作が、このほど待望の文庫化となりました。
翻訳を担当した金原瑞人さん(笹山裕子さんとの共訳)によるあとがきを一部再編集し、本書の魅力をお伝えします。
■『アウシュヴィッツのタトゥー係』ヘザー・モリス /金原瑞人、笹山裕子 [訳]
第二次世界大戦が終わったのははるか前のような気がするのに、なぜいま、また、さらにアウシュヴィッツ(ナチスの強制収容所)なのか。
それはある意味、黒人問題を扱ったフィクション、ノンフィクション、映画がいまでも次々と発表され、大きく取り上げられるのと同じだと思う。ここ数年でも、アンジー・トーマスの『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ』、コルソン・ホワイトヘッドの『地下鉄道』、ジェイムズ・ボールドウィン原作、バリー・ジェンキンス監督の『ビール・ストリートの恋人たち』などの小説や映画が評判を呼んだ。なぜいま、また、さらに黒人小説、黒人映画なのか。答えは簡単で、いまだにその問題が解決されていないからだ。それどころか、いっそう生々しい形で現在、表面化してきている。そしてそれは、差別とは何かという根源的な問題をわれわれに突きつけてくる。
おそらく、ナチスの強制収容所を扱った作品がいまもって書かれ続け、撮られ続けているのは、いまだに解決されていないからだ。なぜ、あのようなことがありえたのかという問題が。このことは、戦争とは何か、差別とは何か、狂気とは何かという根源的な問いをわれわれに突きつけてくる。そして世界情勢をみれば、それに似た状況があちこちにあり、似た状況が生まれかねない地域もあちこちにある。終戦後、いまほど、アウシュヴィッツが生々しく感じられる時代はなかったかもしれない。
そんななか、また新しい視点からの作品として、この『アウシュヴィッツのタトゥー係』が注目を集めている。これは、第二次世界大戦中、実際にアウシュヴィッツとビルケナウで、被収容者たちに数字のタトゥーを入れていたルドウィグ・アイゼンバーグからきいた話をもとに、ヘザー・モリスがフィクションとして書き上げたものだ。
主人公はラリ。ラリはアウシュヴィッツに収容されて早々、この役につく。最初は同胞の腕に針を刺すことに抵抗を覚えるが、そのおかげで収容所のなかでもある程度の自由がきくようになる。そして見張り役のドイツ兵をうまくあしらい、さらに外部と接触できるようになると、被収容者たちの持ち物を整理・処分している女たちがみつけた宝石や金を食べ物などに換えたり、余ったものを仲間に分けたりするようになる。やがてギタという好きな女の子ができて、その子とも特権的な立場を利用してたまに会えるようになる……というふうに紹介すると、じつに運のいい男の物語のようにきこえるかもしれない。事実、ラリは地獄のような収容所で生きのびる。
しかし、この作品を最後まで読んだ人は決して、そうは思わない。それはラリがアウシュヴィッツに収容されて間もなく、高熱を出して倒れたときのエピソードからもわかる。殺されかけたラリを救った男が、代わりに死んでいく。「ひとりを救うことは、世界を救うこと」というラリのいった言葉をつぶやいて。そのあとも、同じ棟の男たちが代わる代わるラリを介抱する。服がよごれると、前の晩に死んだ仲間の服に着替えさせる。こうしてやっと意識を取りもどしたラリはつぶやく。
「この借りは、返すことができない。今、ここでは返せない。つまりは永遠に返せないということだ。」
ラリはまわりを冷静に観察し、必死に頭を働かせて、しぶとく、したたかに生き残る。それは生還してギタと結婚するためでもあり、永遠に返せない借りをなんとかして返すためでもある。そしてナチスに抵抗するためでもある。
ある場面で、ラリがギタにこういう。
「きみも英雄だよ、ギタ。きみたちふたりが生き抜こうとしていることが、ナチスの人でなしどもに対する一種の抵抗なんだ。生きようとすることは、堂々たる抗議、英雄的行為だよ」
ただ生き残ることが英雄的行為になるような状況で生き残ることがいかに厳しいか、いかにつらいか、それをラリは身をもって実感する。
自分が助けたつもりの男から「あんたをぶんなぐって、名前を吐かせる。おれは人殺しなんだ、ラリ」といわれたときは、知っているかぎりの悪態をつく。
無残きわまりない遺体焼却炉での仕事を終えて、こんな思いをするくらいなら撃ち殺されたほうがましだと思っていると、見張り役のドイツ兵から、こういわれる。
「知ってるか、タトゥー係。間違いなくおまえは、オーブンの中に入って生きて出てきたたったひとりのユダヤ人だよ」
さらにラリは無意味に殺されていく人々をみていく。そして最後には運よく、故郷に帰り着くのだが、それを「運よく」といえるのかどうか。タトゥー係という特殊な立場にいたため、普通の被収容者たちが目にしなくてもすむものまでみてしまうし、みせられてしまう。家畜を運ぶ列車でアウシュヴィッツに運ばれてくる途中で死んでいたほうがましだったかもしれない。
ラリは、アウシュヴィッツという現実を後世の人々に語るため、その証人として神から遣わされた人物だったような気がする。晩年になり、重い口を開いてアウシュヴィッツでの体験を語りはじめたのは、「あのようなことが二度と起こらないため」だった。
しかし、その後も次々に戦争やテロが勃発し、多数派が少数派を排除しようとする動きは各国で高まりを見せている。二十一世紀になって、世界はいよいよ混乱し危機的な状況に陥ってしまったかにみえる。この歴史の大きなうねりの中で起きているできごとが、のちにどのように評価されるかはわからないが、今のところ未来は決して明るくない。
だが、そこにもまだ希望はある。そのことを、この作品は教えてくれる。
強制収容所で、敵に使われ、仲間の体を傷つけ汚すことになっても生きのびる道を選んだラリの物語は、悲しみ、怒り、義憤に満ちているが、その奥底にはつねに希望の光がある。もともとあまり信心深くなく、自分がユダヤ人であるという意識も希薄だったラリは、強制収容所の不条理の中で完全に信仰心を失うが、それに代わって心の支えになったのが、ギタとの未来やナチスへの憤り、そして宗教や人種を理由に同じように差別されている人たちへの人間愛だったのだろう。それが「ひとりを救うことは、世界を救うこと」という信念と、ときには危険を冒してでも目の前の人を助けようとする姿勢につながり、めぐりめぐってラリ自身を救うことになる。精神科医のヴィクトール・E・フランクルも、強制収容所での経験を綴った『夜と霧』(みすず書房)の中で、生きのびたのは最後まで希望を見失わなかった者だったと述べている。
この作品はまた、この世には語られないまま失われていった物語がたくさんあるということを教えてくれる。別れの駅ではじめて涙をみせた父親、ラリをかわいがり多くのことを教えてくれた母親、レジスタンスに参加したという兄やその妻子、ギタの両親、強制収容所で出会った人々。みなそれぞれに人生があり、大切な人がいて、それぞれの物語を紡いでいたはずだ。
歴史からこぼれ落ちてしまったそんな人々の物語を伝える作品のひとつとしての本書の役割は大きい。
五十年以上背負ってきた罪悪感に折り合いをつけ、「あのようなことが二度と起こらないため」に自らの物語を遺してくれたラリの思いが、さらに多くの読者にとどくことを願ってやまない。
【あらすじ】
第二次世界大戦下の「絶滅収容所」アウシュヴィッツで、生き延びるため同胞に鑑識番号を刺青し名前を奪う役目を引き受けたユダヤ人の男。彼はある日、その列に並んでいた女性に恋をした。「必ず生きて、この地獄を出よう」そう心に決めた彼は、過酷な状況下でありながらも、自らの尊厳と人間らしさをを守りながら闘い抜く。実在のタトゥー係の証言をもとに書かれ、全世界で350万部となったベストセラー、待望の文庫化。