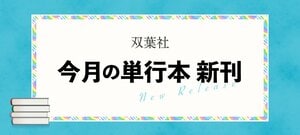『文身』『水よ踊れ』などの岩井圭也氏が、新刊『この夜が明ければ』を刊行する。
舞台は北海道の港町。漁港の季節アルバイトに集まった7人の男女のうち、1人が不審死したことから、宿舎の中で熾烈な犯人捜しが始まる。通報を拒むアルバイト達には、それぞれひた隠しにしている秘密があるようで――。たった一晩で「正しさ」の価値観が劇的に変化する、怒濤のノンストップ・ミステリ。
「小説推理」2021年12月号に掲載された書評家・大矢博子さんのレビューと帯デザインと共に『この夜が明ければ』をご紹介する。

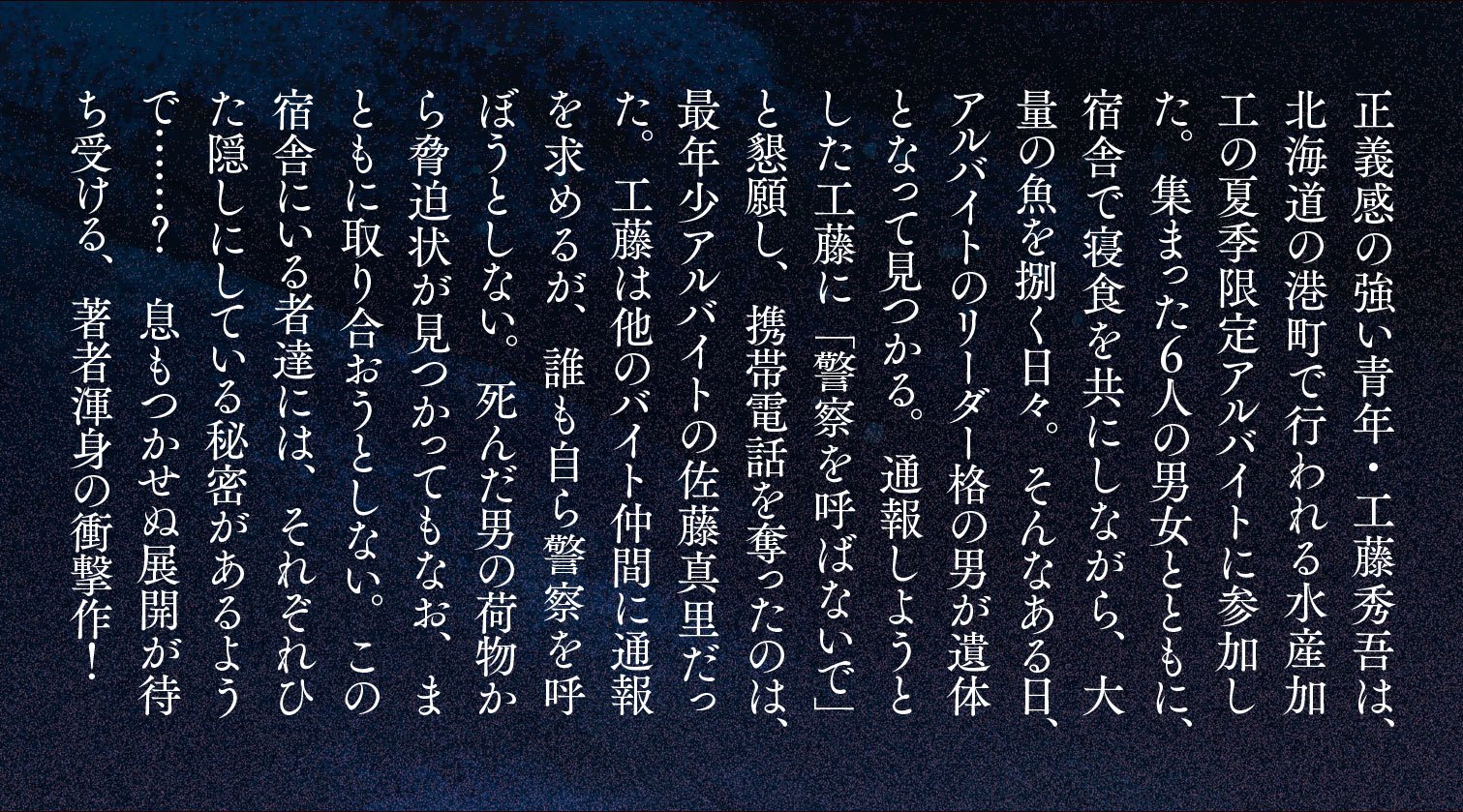
■『この夜が明ければ』岩井圭也
二十五歳の工藤秀吾は、北海道の港町で行われる水産加工の季節バイトに参加した。大量に水揚げされたカラフトマスを捌く仕事で、二ヶ月間、食住が提供される。
同じバイトに集ったのは、彼を含めて七人の男女。仕事にも慣れ、各人の個性も少しずつわかり、空き時間にはサイクリングに出かけたり談笑したり、夜には宿舎のロビーで酒盛りをしたりという日々を送っていた。
ところがある日、バイトのリーダー格である中野大地が砂浜で死体となって発見された。秀吾は慌てて警察に電話しようとするが、なんと六人中四人が通報に反対する。そのうち脅迫状らしきものが見つかって他殺の可能性が増すが、それでもなぜか警察に届けることを頑なに拒む人々。そこにはそれぞれ、人には言えない秘密があった──。
犯人ではないかと疑われ、行動の不自然さを指摘され、彼らは仕方なくひとりずつ秘密を語り始める。そこからはもう一気呵成だ。ページをめくる手が止まらなくなった。
その秘密をここに書くわけにはいかないが、皆がそれぞれ何かから逃げている、ということまでは言ってもいいだろう。個々人の物語はそれだけで何本もの短編小説が書けるほど濃密で、胸に迫る。
彼らの置かれた状況が決して特異なものではないということに留意されたい。今も多くの人が彼らと同じような閉塞感に直面し、足掻いている問題ばかりなのだ。むしろ彼らは逃げることができてよかった、とすら思える。そして何よりここで大事なのは、彼らをそこまで追い詰めた側はそれが正しいと思い込んでいる、ということだ。
描かれるのは逃げた者たちの話だが、読みながら、自分は追い詰める側になってはいないかと何度も自問した。むしろそちらこそが本書の眼目と言っていい。
保身のため、あるいは自分の利益のため、誰かを犠牲にすることを、私たちは当然と思っていないか。自分の価値観で人を判断し、合わない場合は相手に非があると考えてはいないか。さまざまな格差が自己責任の名のもとに切り捨てられる今、本当にそれでいいのかと本書は鋭く問いかけてくる。これは逃げる側の話ではない。人を逃げざるを得ない状況に追い込む者の話なのである。そうと気づいたとき、背筋を冷たいものが走った。
そして終盤に待つ意外な真実。一夜だけの物語とした構成も、伏線の張り方もともに巧妙で、ミステリとしてもレベルが高い一冊である。