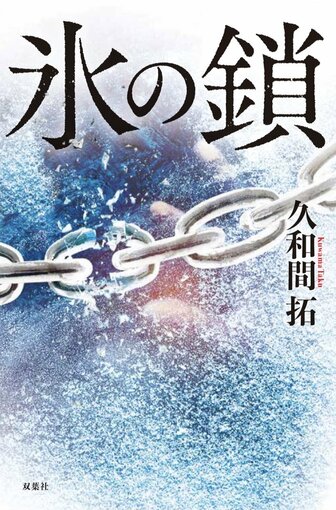母を殺した男は出所後、何の反省もなく平然と生きていた。余命宣告された息子がそれを知った時、長年殺意を縛りつけていた鎖は弾け飛んだ。その男に裁きを下すのは、許されざる行為なのか? 最愛の妻のため、ボクシングの世界戦を控えた兄のため、残された道は完全犯罪しかなかった──。
小説推理新人賞作家による慟哭の社会派ミステリー『氷の鎖』を、「小説推理」2021年11月号に掲載された書評家・日下三蔵さんのレビューと帯デザインと共にご紹介する。
***
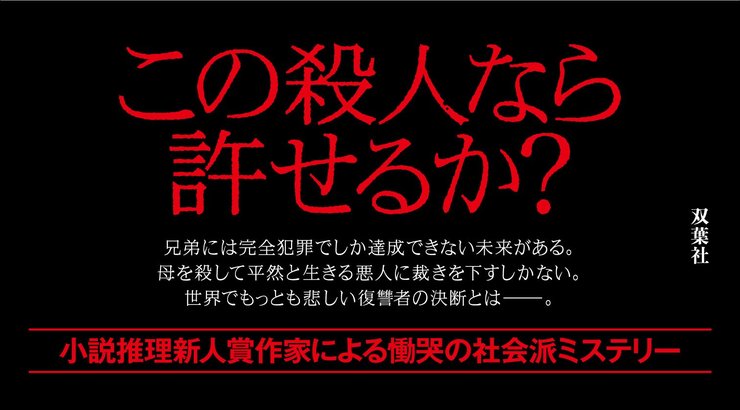
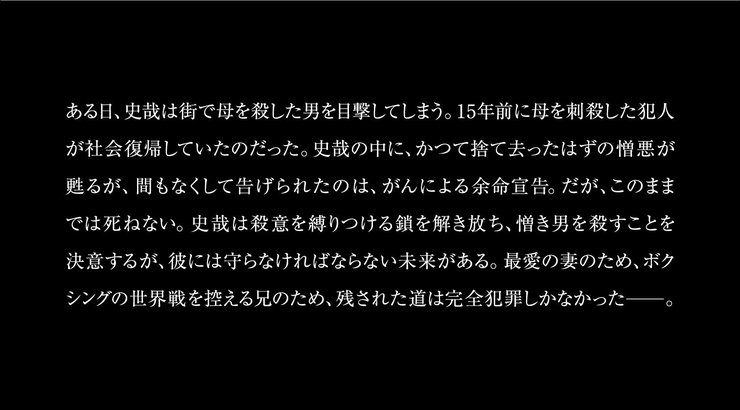
***
二〇一六年に「エースの遺言」で第三十八回小説推理新人賞を受賞した久和間拓の、初めての長篇作品が書下しで刊行された。
芹沢史哉は幼いころに両親を相次いで亡くし、祖父母の家で育った。ボクサーとして将来を嘱望されていた兄の臣吾は、弟のために一度は夢を諦めて就職していたが、三十歳の時にカムバックして、世界ランク十三位にまで上がった。
その臣吾の世界タイトルマッチ戦を控えて、史哉と妻の真帆、臣吾の恋人・潤、学生時代から臣吾の面倒を見ていた伏見ジムの会長、皆が希望に包まれる中、史哉に衝撃的な事態が起きる。
町ですれ違った男が、母を刺殺した犯人だったのだ。男は逮捕されたが、アルコール中毒による心神耗弱を理由に罪を減刑され、判決はわずか懲役六年であった。
男の後をつけ、彼がいまだに飲酒を続けていることを知った史哉は、心の底で抑えつけていた殺意が膨れ上がるのを感じる。
それでも常識と理性で復讐殺人の衝動を抑えていた史哉だったが、診察に訪れた病院で膵臓ガンを申告されてしまう。余命半年。だったら延命治療よりも復讐をすべきなのではないか……。
だが、自分は死んでしまうにしても、残された家族に迷惑はかけたくない。そのためには絶対に証拠を残さない完全犯罪を遂行する必要があった。
かくして史哉は文字通り決死の覚悟で犯罪計画を練っていくことになる。まったくの素人が、人ひとり誰にも気づかれずに殺すことなどできるのだろうか――。
デビュー作を表題とした作品集『エースの遺言』もそうだったが、作者は奇抜なトリックや予想外の犯人には興味を示さず、人間関係の機微の中から謎とサスペンスを生み出し、意外な真相を提示するタイプの書き手である。
つまり、ドラマとしての面白さがミステリとしての読みごたえに直結する作風であり、本書でも抑え切れない殺意に揺れて苦悩しつつ、完全犯罪の計画を進めていく史哉の心情に、多くのウェイトが置かれている。
この物語は臣吾のタイトルマッチの試合で幕を閉じることになるが、史哉はそこで何を見ることになるのか? ぜひ読者の皆さんにも、自分の目でそれを確かめていただきたいと思う。