9月に刊行された穂高明さんによる『ダブル・ダブルスター』。
「ダブル・ダブルスター」とは通称で、正式名称はこと座ε星(イプシロンせい)。地球から約160光年の距離に位置する多重星で、全天にみられる多重星の中で最も傑出していると言われている。ダブル・ダブルスターは何がそんなにも珍しいのか? そして、それがタイトルになっている理由とは? しかし、本書『ダブル・ダブルスター』は天文のお話ではない、親子の再出発の物語なのだ。
「小説推理」2021年11月号に掲載された書評家・大矢博子さんのレビューと帯デザインと共に『ダブル・ダブルスター』をご紹介する。
***
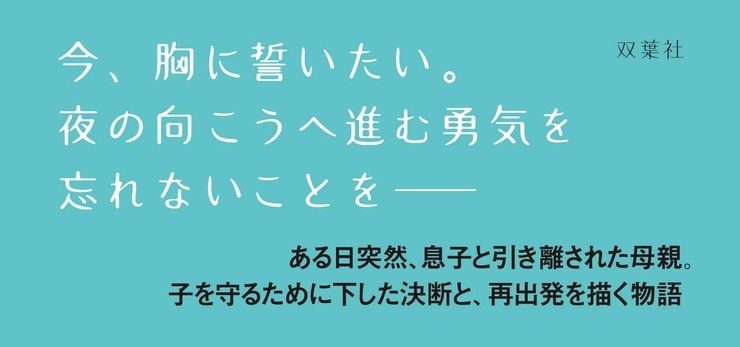
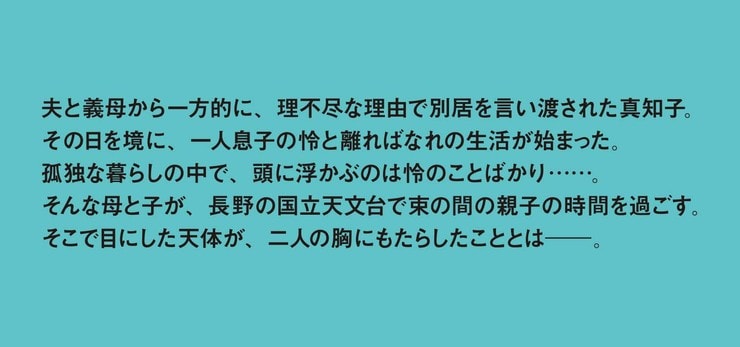
***
真知子に向かって、何度心の中で叫んだことだろう。その叫びは「逃げろ!」だったり「負けるな!」だったり、「行け!」だったりした。自分の中に真知子がいて、自分が物語の中に入っていって、なるほどこれがダブル・ダブルスターか、と腑に落ちたのだった。
物語は婚家を追い出されて一人暮らしを始めた真知子の描写で始まる。子宮と卵巣の病気で苦しんでいても見向きもしない夫。地方出身の真知子を見下し、病気になったのは信仰心がないからだと責める姑。ついには真知子の入院中に勝手に別居を決められた。
夫にもはや愛情も未練もないが、一人息子の怜と離れ離れになってしまったことだけが辛い。市役所の臨時職員の職を得て、苦しいながらもなんとか生活を続けるが、頭に浮かぶのは怜のことばかりだ。
中学に入った怜が真知子に連絡をとったことで、再び交流が持てるようになった。しかし怜から聞く実家での暮らしの様子は心配なことばかり。そんな時、宮城の親戚からこちらに住まないかと持ちかけられ……。
虐げられた母子の再起の物語であることは間違いない。だがそれだけではない。
物語が動くのは、母子で天文台に行った場面からだ。ひとつの星に見えて、実は二重星がふたつ重なっているということ座のダブル・ダブルスターを知る。さらに鯛の中にある魚の形をした骨「鯛の鯛」の話や、果物の果肉と果実の違いなどのエピソードを通して真知子と怜は、ひとつに見えてもふたつかそれ以上のものがある、ひとつのものの中にはふたつ以上の何かが入っていることがある、ということを体感として学んでいくのだ。
読みながら、自分の目に映るものがそれまでと違って見えた気がした。人にとって軸となるものは決してひとつではないし、辛い思い出も自分を作るひとつなのだと肯定できる気持ちになった。なんと優しい物語であることか。
登場人物が善悪にきっぱり分けられているのが気になる人も多いだろう。だが、これはわざとだ。ひとつに見えてやっぱりひとつでしかない存在として夫や姑は描かれているのかもしれない。あるいは、彼らの中にも別の何かがあるのかも、という視点で見てもいい。
小説は、さまざまな軸の存在を示してくれる。読者の中に軸を増やしてくれる。小説という名の星と連なって生きることの幸せを改めて実感した。









