高齢者に弁当を配達する大学生の総司は、カエと出会う。家族を失い、片方の目の視力を失い、貧しい生活を送るカエは、将来を約束していた人と死に別れる前日のことを語り始める。残酷な運命によって引き裂かれたその男性との話には、総司の人生をも変える、ある秘密が隠されていた。
驚きのミステリ×微笑みの成長小説! 切なさ溢れる衝撃の結末が待ち受ける『美人薄命 〈新装版〉』の読みどころを日下三蔵さんの解説でご紹介します。

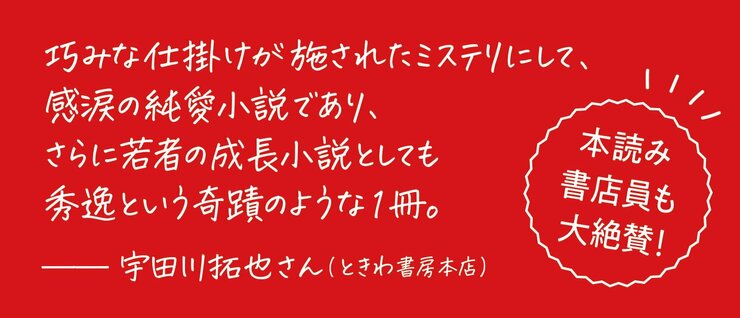
■『美人薄命 〈新装版〉』深水黎一郎 /日下三蔵[評]
深水黎一郎の二〇〇七年のデビュー作『ウルチモ・トルッコ』が改稿・改題のうえで『最後のトリック』として河出文庫に収められたのが一四年一〇月。イタリア語で「究極のトリック」を意味する原題をシンプルに日本語にしたこと、「読者全員が犯人」というキャッチコピーの強烈さが功を奏して同書はベストセラーとなった。いま筆者の手元には一五年二月発行の39刷があるが、長らく入手困難になっていた幻の名作とか新作書下し作品というわけでもない普通の文庫化作品が、短期間にこれだけ売れるというのは珍しい。
もちろんタイトルとキャッチコピーが良かっただけでベストセラーになるはずもない。後述するように内容が伴っていたからこそ、口コミの連鎖でどんどん売れていったわけである。
しかし桁外れに売れるということは、ふだんは推理小説を読まない人も手にとっているということになる。著者の作品が双葉文庫に入るのは初めてだし、『最後のトリック』で深水作品に初めて触れたという読者のために、著者の経歴とこれまでの作品について、まずは簡単にご紹介しておこう。
一九六三(昭和三十八)年生まれの深水黎一郎は、慶應義塾大学文学部卒。同大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学(仏文学専攻)。在学中に仏政府給費留学生としてフランスに留学し、ブルゴーニュ大学修士号取得、パリ大学DEA(博士課程専門研究課程)修了。四十歳を過ぎてからミステリ小説を執筆し、〇七年に『ウルチモ・トルッコ』で第三十六回メフィスト賞を受賞してデビュー。
著作リストは以下のとおり。
1 ウルチモ・トルッコ 07年4月 講談社ノベルス
→最後のトリック 14年10月 河出文庫
2 エコール・ド・パリ殺人事件 08年2月 講談社ノベルス
11年5月 講談社文庫
3 トスカの接吻 08年8月 講談社ノベルス
12年11月 講談社文庫
4 花窗玻璃 シャガールの黙示 09年9月 講談社ノベルス
→花窗玻璃 天使たちの殺意 15年10月 河出文庫
5 五声のリチェルカーレ 10年1月 創元推理文庫
6 ジークフリートの剣 10年9月 講談社
13年10月 講談社文庫
7 人間の尊厳と八〇〇メートル 11年9月 東京創元社
14年2月 創元推理文庫
8 言霊たちの夜 12年5月 講談社
→言霊たちの反乱 15年8月 講談社文庫
9 美人薄命 13年3月 双葉社
16年4月 双葉文庫 ※本書
10 世界で一つだけの殺し方 13年12月 南雲堂
11 テンペスタ 天然がぶり寄り娘と正義の七日間 14年4月 幻冬舎
12 大癋見警部の事件簿 14年9月 光文社
13 ミステリー・アリーナ 15年6月 原書房
1は「読者が犯人」という点で話題を呼んでいるようだが、同様の趣向で書かれた作品がこれまでになかった、というわけではない。辻真先の長篇デビュー作『仮題・中学殺人事件』(72年)を筆頭に、長篇作品だけでも七~八作は思い浮かぶ。そのうちのいくつかの作品については、作中でキャラクターにタイトルを伏せて言及させているから、作者もそれは承知のはずだ。つまり作者は先行作品の存在を踏まえたうえで、こんな手はどうですか、と新しいアイデアを提示しているのである。
推理小説が先人のアイデアに改良を加えて発展してきた歴史を振り返ってみると、深水黎一郎のスタイルは、王道中の王道ということができる。実際、『ウルチモ・トルッコ』では、同じ趣向の作品の中でもっとも納得できるトリックが使用されていた。さらに改稿を経た『最後のトリック』では、残っていたわずかな弱点が払拭されてトリックが補強されているのだ。
先行作品を踏まえるという点では、大癋見警部がミステリのさまざまな約束事を破壊していく連作の12もそうだ。これは明らかに東野圭吾が名探偵・天下一大五郎を起用して密室殺人や時刻表トリックを笑い飛ばしてみせた連作短篇集『名探偵の掟』(96年)への挑戦だろう。深水作品では叙述トリックや見立て殺人が俎上に載せられており、ミステリというジャンルそのものへの考察も、東野作品より深いレベルで行われている。傍若無人な大癋見警部のキャラクターには、ジョイス・ポーターが創造した名探偵(?)ドーヴァー警部が投影されているようにも見える。
究極の一冊ともいうべき作品が、現時点(16年3月現在)での最新作の13だ。これは多重解決ものに挑んだ傑作である。アントニー・バークリー『毒入りチョコレート事件』(29年)のように、ひとつの事件に対して複数の解決が提示される趣向のことだが、途中で提示される「偽の解決」のレベルが低ければ台無しになってしまう。つまり「真の解決」と比べても遜色ない解答をいくつも考えなければならない難しいスタイルなのだ。
国内でも、岡嶋二人『そして扉が閉ざされた』(87年)、貫井徳郎『プリズム』(99年)、霞流一『首断ち六地蔵』(02年)など数えるほどしか作例がない。ことに『プリズム』の完成度が高いので、これを超える作品は、まず出ないだろうと思っていたところに、重量級の13が現れた衝撃。現在、同書は第16回本格ミステリ大賞にノミネートされているが、充分に受賞に値するレベルの作品だと思う。
深水ミステリの特徴としては、人間の先入観を最大限に活用する、というテクニックも見逃せない。第64回日本推理作家協会賞の短編部門を受賞した7の表題作に顕著なように、作者は誰もが疑いを持たない死角のような箇所に的確に罠を仕掛けてくるのだ。
これを「ミステリ作家なら当たり前」というのは簡単だが、先入観が生む死角を発見するには、作者がまず先入観から解き放たれている必要がある訳で、これは容易なことではない。そして深水ミステリを読むと、われわれはいかにふだん、先入観や偏見に捉われて生活しているかということに気づかされるのである。
2~4、6、10は芸術に関わる事件で活躍する探偵・神泉寺瞬一郎の事件簿である。美術やオペラなどへの深い造詣に基づいてストーリーが構築されており、作者の高い教養がうかがえるシリーズだが、必要な知識は手際よく解説されていくので、薀蓄が鼻につくといった箇所はまったくない。誰もが自然に物語に引き込まれ、仕掛けられたどんでん返しに度肝を抜かれることになるはずである。
いずれもハイレベルな連作ではあるが、犯行方法の美しさと壮大さという点で4の『花窗玻璃』をベストに挙げておきたい。筆者が予選委員を務めていた第10回本格ミステリ大賞で強く最終候補に推薦した作品であり、他の委員からも一様に賞賛の声が上がっていたことを付け加えておこう。
12で主役を張った大癋見警部が、元々は芸術探偵シリーズのキャラクターだったり、神泉寺瞬一郎の伯父の海埜警部補が既に1で顔を見せていたりと、作品同士のリンクが緊密なのも深水作品の特徴である。古くは泡坂妻夫、近年では若竹七海、道尾秀介らも採用している趣向だ。もちろん個々の作品のレベルが高くなければ、こんな遊びをしてもたいした意味がない訳だが、深水ミステリは楽々と水準をクリアしているといっていい。
現時点でのベスト作品のひとつに挙げたい6の主人公も、3に登場している人物である。ワーグナーのオペラを下敷きにしたストーリーは、不穏な雰囲気に包まれたサスペンスフルな展開を示すものの、婚約者の死は列車事故によるものとしか思われない。だが、残りページもわずかになってから神泉寺瞬一郎が指摘する「真相」は、これまで見えていたものの意味をまったく反転させてしまうのである。
山田風太郎の『太陽黒点』(63年)は「90%が普通の小説、ラブストーリーで最後にひっくり返す」という趣向の長篇で風太郎ミステリの最高傑作に挙げる人も多い作品だが、『ジークフリートの剣』は、それに勝るとも劣らぬ傑作といえるだろう。
高い教養に裏打ちされたサスペンスフルなストーリーの中に、先行作品への敬意を払いつつ、読者の先入観を利用したトリックを仕掛ける手練れのミステリ作家
これまで述べてきた作品の特徴をまとめると、深水黎一郎という作家はこのように表現することが出来る。そして、その特徴のすべてを兼ね備えた逸品が、本書『美人薄命』なのである。(この作品は「小説推理」二〇一二年六月号から十一月号にかけて連載され、一三年三月に双葉社から単行本として刊行された)
大学生の礒田総司はフィールドワークの一環として独居老人に弁当を配達するボランティアに参加することになる。当初は単位のためにしぶしぶ参加した総司だったが、メンバーの中にかつて憧れていた同級生・沙織の姿を発見し、続けてみようと思うのだった。
総司は老人たちやボランティアのスタッフたちと関わるうちに、彼らが見た目からは想像もつかない一面を持っていることを何度も思い知らされる。片目の不自由な老婆の内海カエとは特に親しくなるが、常にユーモアを忘れないカエにも、意外な過去と秘密があったのだ……。
各章の冒頭や合間に、戦中戦後を生き抜いてきた内海カエの凄絶な半生が旧仮名遣いで綴られていく。1、2、4などで作中作を効果的に使ってきた作者であるから、本書のこの部分にも、もちろんトリックが仕掛けられているのだが、これを事前に見破るのは、よほど注意深い読者であっても難しいと思われる。しかし、本書が独創的なのは、仕掛けが分かった後で現代パートとどのように結びついてくるか、という点の工夫にある。こういう形で読者の先入観を利用した作品は、寡聞にして思いつかない。
作中で探偵役の人物も指摘するように、「美人薄命」というタイトルでありながら読んでみると老婆の話、というギャップも、各章のタイトルがローマと老婆をかけた駄洒落になっている目次も、すべてが読者に先入観を与えるための作者の計算なのだから恐れ入る。
あるいは『ジークフリートの剣』を先にお読みの方であれば、内海カエが同書の序章において、主人公とその恋人に不思議な予言を授ける占い師として登場していることをご記憶かもしれない。本書でもカエに予知能力があるらしいことは暗示されているが、この設定によって真相が明かされたあとの衝撃、哀しみが大きく増幅されている点も指摘しておきたい。
典型的な「今どきの若者」である礒田総司と、不自由な片目で倹しく暮らしてきた内海カエ。二人の微笑ましい交流を描いた前半部分は、ほとんどすべて伏線といっても過言ではなく、無駄なエピソードがまったくない。
中盤以降の意外な展開の連続に読者は「えっ」「まさか?」「そんなバカな!?」という叫びをあげ続けることになるだろうが、最後まで読んでみれば、人生にはつらいこともあるが、そんなに捨てたものではない、一日一日を大切に生きていこう、という気持ちになるはずだ。
つまり本書は超絶技巧のミステリであると同時に、まぎれもない青春小説、人間讃歌にもなっているのである。
ミステリ・ファンは言うに及ばず、ジャンルにこだわらずにとにかく面白い作品を探しているという読者にも、この『美人薄命』を強くお勧めしたい。そして深水黎一郎という作家の著作を、ぜひ追いかけてほしい。まだ今なら、あっという間に最新作に追いつくはずだ。そこには、これまで体験したことのなかった至高の読書体験が待っていることを保証します。





