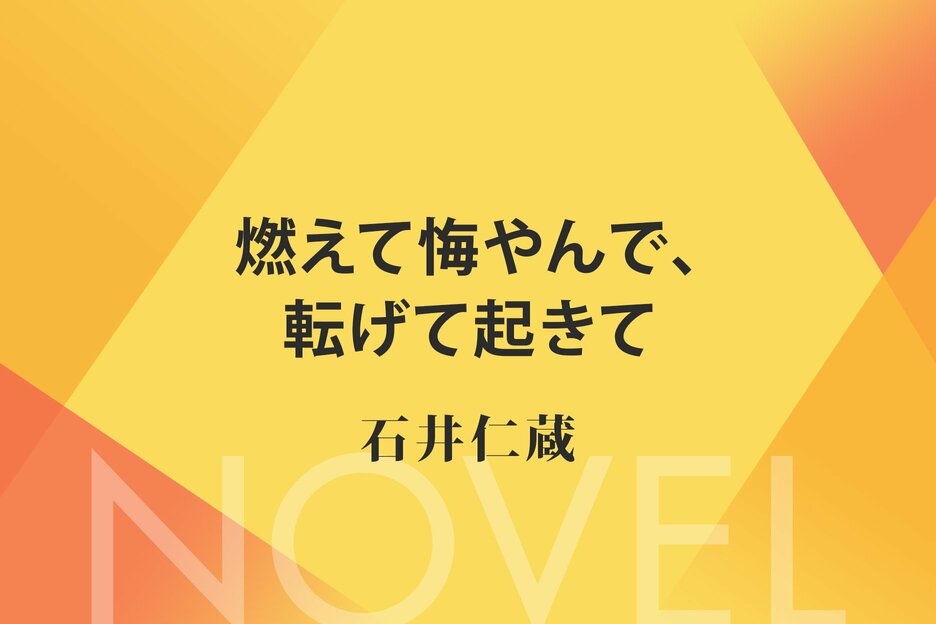風を切る。四百ccの愛車にまたがって市街地を抜け、バイパスをひた走る。エンジンから伝わる振動を全身に感じながら排気音を唸らせ、ちんたら進む自動車の列を追い抜く。ジャケットに打ち付ける十一月の風は冷たい。五十という自分の年齢が呪わしい。若い頃よりも脂肪がついた体はそのくせ、年々寒さに弱くなる。
バイクの魅力は解放感、というのは間違いないが、欠かせないのは緊張感だ。車に激突してお陀仏なんてのは御免被るが、ガードレールを突き破って崖から真っ逆さまの最期なら、病に冒されて苦しむよりはいくらかましに違いない。
いっそのこと死んじまうのも悪くないか、と破れかぶれな気分が頭をもたげる。
「会社としては、今回の件を重く受け止めざるを得ません」
育都アカデミー本社の小さな会議室で、安田校長は顔を曇らせながら言った。地区長の元村という男は彼の隣で不快感をあらわに、分厚い唇をひん曲げながら言葉を継いだ。
「子供が安心して勉強できる環境ってのは塾として当然のものでさ、あなたはその当然をぶち壊しにしたわけですよ太原さん。前々から似たようなことがあったとも聞いてるしね、会社のブランドイメージも損ねてるんだ。どうしてくれんのって話よ」
いつ見てもぺたっとしている灰色の髪にこけた頬の外見は、どこか骸骨を思わせる。前からそりの合わない男だった。事実確認をしたいんだけど、と元村は俺の行いについて蒸し返した。
夏期講習中の八月、俺は担当する生徒を叱った。中三の男子生徒だ。成績がよくないのに身が入っていないから、普段よりも少し強めに叱った。するとあろうことか、その生徒は俺の声を録音していて、ネット上にアップしやがったのだ。いわゆる炎上状態に陥って育都アカデミーの名前も俺の名前も明かされ、俺は会社を揺るがす大問題の中心人物という立場に据えられてしまった。
「生徒のためを思って言ってやったんですよ」
面倒事へのむかつきがぶり返す。「受からせるために一生懸命やってるんだから、言い方がきつくなるときもあるんです。昔の育都生だったらあんな程度でへこたれなかったんですけどね、ましてネットに上げるとかそんな、女々しい真似なんか」
「うちとしては終わりだわ太原さん」
元村が語調を強めて俺の言葉を遮った。一拍置いたあとで形だけは整えた姿勢を取り、「二十五年間、お疲れ様でした」とこれまた上っ面だけの丁寧な口調で頭を下げた。俺なりの言い分を並べたところで会社に迷惑を掛けた事実は消えないし、許しを乞おうとも思わない。すがりついてまで残ろうという気にはなれなかった。
お世話になりました、と口先だけの挨拶で俺は席を立った。
「自分を見つめ直す時間を、持ったらいいと思いますよ」
建物の玄関まで見送ってくれた安田校長は俺を責めるでも励ますでもなく、寂しげな調子で言った。彼に対しては申し訳ない気持ちだ。中高受験の上位クラスの担当がいなくなるのは校舎にとって大きな穴に違いなく、校長自身が俺の役割を代替するという。生徒のことをよろしくお願いします、と頭を下げたものの、正面から目線を合わせる胆力が俺にはなかった。
「ほいでこれからどうすんだや」
しばらくそっちに戻る、と連絡を入れた俺を、親父は持ち前の無愛想な顔で迎えた。クビになったとは言い出せず、会社の方針と合わなくてやめたと俺はいきさつをごまかした。大した蓄財もないままに五十を過ぎて職を失い、実家に戻って頭を冷やすというのは、お世辞にも賢明な人間の生き方とは言えない。重々わかっていたし、親父もくどくどしく説教を垂れるようなことはなかった。
「退職金はどんくれえなの」
「正社員じゃないから出ねえ」まして懲戒解雇だから出るわけもない。
「仕事の口なら、おらがあちこち声掛けてやっぺ」
「俺で探すわ」何の仕事を探すべきかも定まってはいないが。
「この辺も人が少なぐなってっけのう」
訥々とした会話を続けながら、夕食をつついた。白米とインスタントの味噌汁と、パック入りの惣菜だ。おふくろが肝臓を悪くして死んだのが六年前。それ以来独り暮らしを続ける親父は料理といえば肉や卵や野菜を炒めるのがせいぜいで、棚には買い置きのカップ麺が積まれていた。東京の俺の食生活も似たようなものだから偉そうなことは言えない。
無職となった独身男の帰省に愉快な要素は何もないが、老いた肉親の様子を見るという点では意義があるのかもしれない。後期高齢者の親父は衰えが目につき、腰が痛い、膝が痛いと口癖のように体のきしみを訴える。免許返納も考えさせたいところだが、いかんせん車が不可欠な田舎町だ。東京から新幹線で一時間半、ローカル線を一時間ほど乗り継ぐこの町の人口はご多分に漏れず減少の一途で、一時は十万に届いた住民の数も今では八万を切った。父とともに枯れゆくような町にいるあいだはせめて、運転の補助を請け負おうと思った。
「働くとしたらやっぱ、塾の仕事がいいんじゃねえのかね」
「最近はいろいろ難しくてさ。ちょっときつめに叱ったらクレームだよ」
人間が昔より弱くなってんだべさ、と親父はなぜか得意げに応じた。煙草を指に挟みながら日本酒のグラスを傾けた。
「言うこと聞かねえガキは、ペッチンってやってやりゃいいっぺよ」
腕を振った親父の節くれ立った指と、皺の多い手の甲が目に飛び込む。薄毛の遺伝子を俺に託した彼の頭にはいまや毛が一本もなく、たるんだ顎の皮が首との境目をなくしていた。思い出したように戸棚から錠剤を取り出す親父に、何の薬かと問うが、心臓がちょっとなと言葉少なに応えるだけで詳しくは教えてくれない。年を取った体は何かと入り用なんだと曖昧に呟き、錠剤を口に放り込む。酒のあとで服用するのはよくないのではとたしなめるも、大丈夫だわとうるさがるように言ってゴクリと飲み下した。
志気を失った老後というのは切ないものだ。一人息子の俺が、孫の顔を見せてやれるような人生を送っていれば、違う今があっただろうか。考えても詮ない。小さな庭の片隅では四十年近く前に建てた飼い犬の墓石がうら寂しく枯れ葉に囲まれていて、俺はふと在りし日を思い出す。そういえばタロベエと一緒に河川敷に出かけたよな、などと昔の話を広げてみせても、乾いた今が浮き彫りになるだけのような気がした。
自分も親父のように老いていくのだろうか。
そう思うとやるせなくなり、シフトペダルを上げて車を追い抜いた。
コンビニの駐車場にバイクを止め、ホットコーヒーを買う。店の前で飲んでいると、煙草を吸う作業着姿の男が目に映る。コンビニの脇の喫煙所など、東京ではめっきり見られなくなった。禁煙の煽りを受けた俺は十年前にやめたが、今は誰に気を遣う必要もない。ためしに吸ってみるかと店の入り口に引き返したところで、二人の男子小学生が飛び出してきた。ぶつかりそうになった直前、二人はひょいっと体を躱した。
「おい危ねえぞ!」
ぶつけた怒鳴り声に一瞬振り向き、何も言わずに走り去った。
見知らぬ子供をどやす趣味はない。塾の廊下を走る生徒を注意するようなつもりで、つい口走っていたのだ。己の習い性に呆れながら、足下に落ちた新品の消しゴムに気づく。薄いビニールに包まれた、ありふれた消しゴムだ。子供の一人が落としたものに違いない、と行き先を目で追うと、彼らは道路の向かいの建物へと入っていった。
県道の走る交差点のそばには二階建ての民家があった。石塀の奥には庭木が伸び、小綺麗な設えの家だった。消しゴムを地面に捨て置くのもなんとなく気が引けて、届けてやろうかと横断歩道を渡る。門の前に来ると、貼り付けられた看板に目が留まる。青い看板には白字で「きよい塾」と記され、塾名の下には「小中学校の補習 定期テスト対策 高校受験対策はお任せ!」の惹句。一見して普通の民家だが、個人経営の塾なのかもしれない。集団授業か、それとも個別指導だろうか。こういった塾のカリキュラムや教材はどういうものなのだろう。などといつの間にか考えていると、玄関の扉が開いた。
先ほどの男子の一人が顔を見せ、俺と目が合った瞬間にさっと引っ込んだ。追いかけてきたとでも思ったのだろう。苦笑しながら門の上に消しゴムを置き、去りかけたときにもう一度扉が開いた。
出てきたのは中年の女だった。ショートカットの女は四十そこそこと見えた。
「うちの生徒が、何かご迷惑をおかけしましたか」
不安げな表情でこちらを窺っていた。
「そんなんじゃありません。消しゴムを落としたようなので、届けに来ただけで」
「ああ、わざわざすみません!」
緊張を解いたように笑みを見せ、サンダルを履いて出てきた。消しゴムを受け取ると頭を下げ、そそくさと戻っていく。
「あのう」後ろ姿を見て、俺は気づけば彼女を呼び止めていた。
「この募集って、今もやってるんですか?」
看板の横の張り紙を指さした。そこには「講師急募!」の文字があった。
履歴書を書いたのは育都に入るとき以来、二十五年ぶりだ。
俺は高校までを地元で過ごし、大学進学を機に上京した。就職が迫った頃は折しも氷河期とされる時代で、就きたい仕事も見つけられずにいた俺は、何十もの会社から蹴られたあとでようやく内定を得た。大手の飲食チェーン店だった。ブラック企業なんて概念が広まるより前の時代で、ろくに休みもないまま十二時間以上働くような生活を続け、過労で倒れた。ベッドに横たわりながら退職を決め、飛び込んだのが学習塾の業界だ。
短いメールのやりとりを交わしてから、俺は面接を受けた。「きよい塾」の近所にある喫茶店だった。スーツは東京のマンションに置いてきたので、親父が十年以上前に着ていた背広を借りた。防虫剤のにおいが染みついた古くさい灰色の背広だ。野暮ったいうえにかなり窮屈だったものの、平服で出向くよりはいくらかましだろう。
「育都アカデミーって言ったら、大手ですよね。小中学生の指導ですか」
経営者の女性、清井志穂は履歴書から目線を上げた。白いブラウスに黒いチョッキの華奢な出で立ちで、あらためて見るとなかなかの美人だ。左手の薬指に指輪をはめているのを少し残念に思う。我ながら不埒者だ。
「はい。中学受験、高校受験をやってまして、ここ二十年は毎年、難関校対策のクラスを受け持ってて」
すごいですね、という賛辞は素直に受け取らせてもらう。社会的には大した経歴ではないかもしれないが、塾業界の現場で最前線に立っていた自負はあるし、田舎の個人塾での勤務などお安い御用だ。英国社の文系科目が専門だが理数を教えた経験もあると告げると、頼もしいです、と彼女はいかにも頼もしげに言った。
「人手が足りてなくて、太原さんのような方が来てくれたらすごくありがたいです」
「ほかの講師は?」
「今は私一人でやってます」
「旦那さんは?」
俺の問いに対し、清井は答えを迷うように間を置いた。九月に亡くなりました、と目を伏せて言った。授業の合間に頭痛を訴え、事務室で倒れた旦那はその翌日に息を引き取った。くも膜下出血だったそうだ。結婚指輪に落胆した先刻の自分がますます不届きに思われ、「女手一つで頑張ってるんですね」と労いの言葉を投げかけた。
勤務条件は先にメールで確認してあった。可能ならば週五日、夕方から夜に掛けての仕事で、対象は小中学生。給料は育都よりも遥かに少ないが、俺としてもずっと勤めていくつもりはない。今年度の終わりまでというくらいのもので、東京で職探しをするまでの腰掛けなのだ。
よろしくお願いします、と頭を垂れた俺に、清井は言った。
「育都をお辞めになったのはどうしてですか?」
顔を上げて見た彼女の表情は、笑みの気配を残しつつもいくらか強ばっているように思えた。
「事情がありまして、解雇されました」
夏の出来事から今日までのいきさつを、俺は包み隠さず話した。下手にごまかして事実を咎められるような事態は避けたかったのだ。
育都を辞めたあと、別の大手塾にいくつも応募してみたが、採用担当者は電話やメールで必ず例の件について問いただした。そのうえで寄越された通知は「不採用と決まりました」「採用を見送る形となりました」「採用は難しいと判断いたしました」。
「失礼ながら、私も」
清井は俺の話を聞くうちに神妙な顔つきに変わり、遠慮がちに口を開いた。「お名前をネットで検索させてもらいました。教員の不祥事のニュースもよく流れてきますし、お子さんをお預かりする立場としては、慎重でなくてはならないので」
性犯罪に手を染めた教師がどこかで捕まった、などという話は毎日のようにテレビで報道されている。もちろん俺は絶対にそんなことはしないし、下卑た誘惑に駆られた瞬間など一度とてない。だが、不祥事という単語でくくられたら俺も非道な連中と同じ部類に入れられてしまうのかと、いたたまれない気持ちになる。
「もし隠されるようなら、お断りするつもりでいたんです」
清井は悩ましげに首をかしげた。「けど、正直にお話しいただいたので、どうしようかと思ってて」
「音声を聞かれましたか?」
彼女はゆっくりと首を縦に動かした。元の投稿は削除されていたが、コピーされたものは今でもネット空間に漂っている。俺は居住まいを正して続けた。
「二度とあんな風な間違いはしません。大手の塾で上位のクラスを長年受け持って、驕っている部分もありましたけど、今はもうそんな身分でもないですし、時代に合わせた振る舞いをしていかなくちゃと思っていますから」
「身分とか時代とかっていう発想の仕方は」
彼女はテーブルの上で指を組み、苦笑気味に頬を緩めた。「違う気もします。状況がこうだからこうしなきゃ、みたいな考え方って、子供一人一人と向き合ってないように感じられちゃって。もしも体罰オーケーの時代なら、太原さんは体罰をするんですか?」
「体罰はやったことありませんよ、一回も」
「そうじゃなくて」
一人一人と向き合う。自分はいつだってそれを実践してきたなどと主張したところで、弁解じみた響きを帯びるようにも思い、俺は黙っておくことにした。
紅茶を飲み干したあとで息を吐き、わかりましたと彼女は言った。
「手が回らなくて実際困ってはいるんです。生徒も減っていってて、なんとかしなくちゃいけなくて。だからお願いしたいとは思っています。ただ、前の塾でのようなことをされるのは絶対に避けてほしいんですね。強い口調で脅すような指導はしないと、約束してもらえますか?」
強い口調というのはどの程度を指すのか、なんて言い方をするべきではないとは心得ている。約束します、と答えるだけだ。
「では、よろしくお願いいたします」
彼女の髪の毛先が、カップの縁に掛かった。丁重な態度に恐縮しながら深々とお辞儀を返し、かくして俺は「きよい塾」の一員となった。