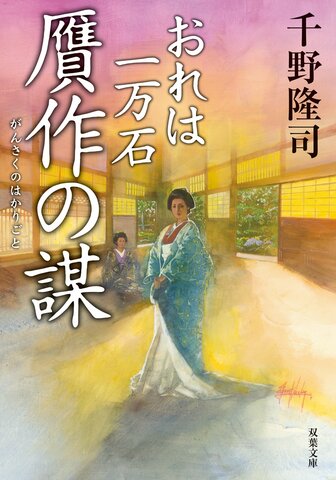一万石のギリギリ大名・高岡藩の世子の井上正紀は、さまざまな騒動に立ち向かいながら、藩の財政を立て直してきた。大坂定番だった藩主の正国が奏者番になり、江戸藩邸に戻ってくる。しかし奏者番の勤めに専念するため、引き続き正紀が、藩を治めることになった。そんなとき、奏者番就任の祝いとして貰った加藤文麗の絵が、正国の正室の和の目利きにより、偽物だと判明。和からこの一件の調査を頼まれた正紀だが、他にも調べなければならないことができた。米の不正な売買に、高岡河岸が利用されているらしいのだ。正紀の奔走が始まる。
一方、老中・松平信明の家臣の広瀬清四郎は、不正米の調査をしていた。かつて正紀と共闘したことのある清四郎だが、いくつかの事実が重なり、高岡藩にも疑いの目を向ける。そこに鹿島灘の海賊騒動や、正紀と縁の深い府中藩の継嗣問題が絡まり、事態は錯綜していくのであった。
贋作・不正米・海賊・継嗣問題。三題噺ならぬ四題噺というべきか。加藤文麗の贋作から幕を開けたストーリーが、主人公の行動と共に、大きく拡大していく。府中藩の内情など、いままでのシリーズで積み重ねてきた設定を上手に使いながら作者は、とんでもない悪巧みを創り上げる。清四郎の視点も入れながら、徐々に明らかになる犯罪の構図に、ページを捲る手が止まらないのだ。
そんな物語のクライマックスとして、正紀たちと海賊の戦いが控えている。船上でのチャンバラを、何度も経験している正紀だけに、海での戦も達者なもの。船の動きを見極めた斬り合いに、主人公の成長を感じた。
さらに正国の正室の和が、クローズアップされている点も見逃せない。狩野派に師事し、絵の蒐集を楽しんでいる和。藩の財政を助けるため、正紀の頼みに応えて絵を売ったことがあるが、そのことをいつまでもグチグチいっている。悪い人ではないが、現実が分かっていないと思われた和だが、本書では違った面を見せてくれた。あまり意識していなかった脇役が、鮮やかに屹立するのも、シリーズ物ならではの面白さなのだ。
本書のラストで正紀が、「この一件、落着とはならぬな」というように、一連の騒動は解決したものの、府中藩の火種は燻ぶったままだ。読者としても、気になるところだろう。だが安心してほしい。八月には第十弾が刊行されるのだ。物語の着地点はどこなのか。ワクワクしながら待ちたいのである。